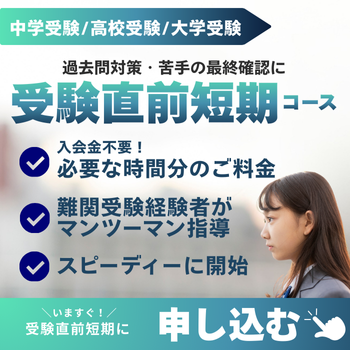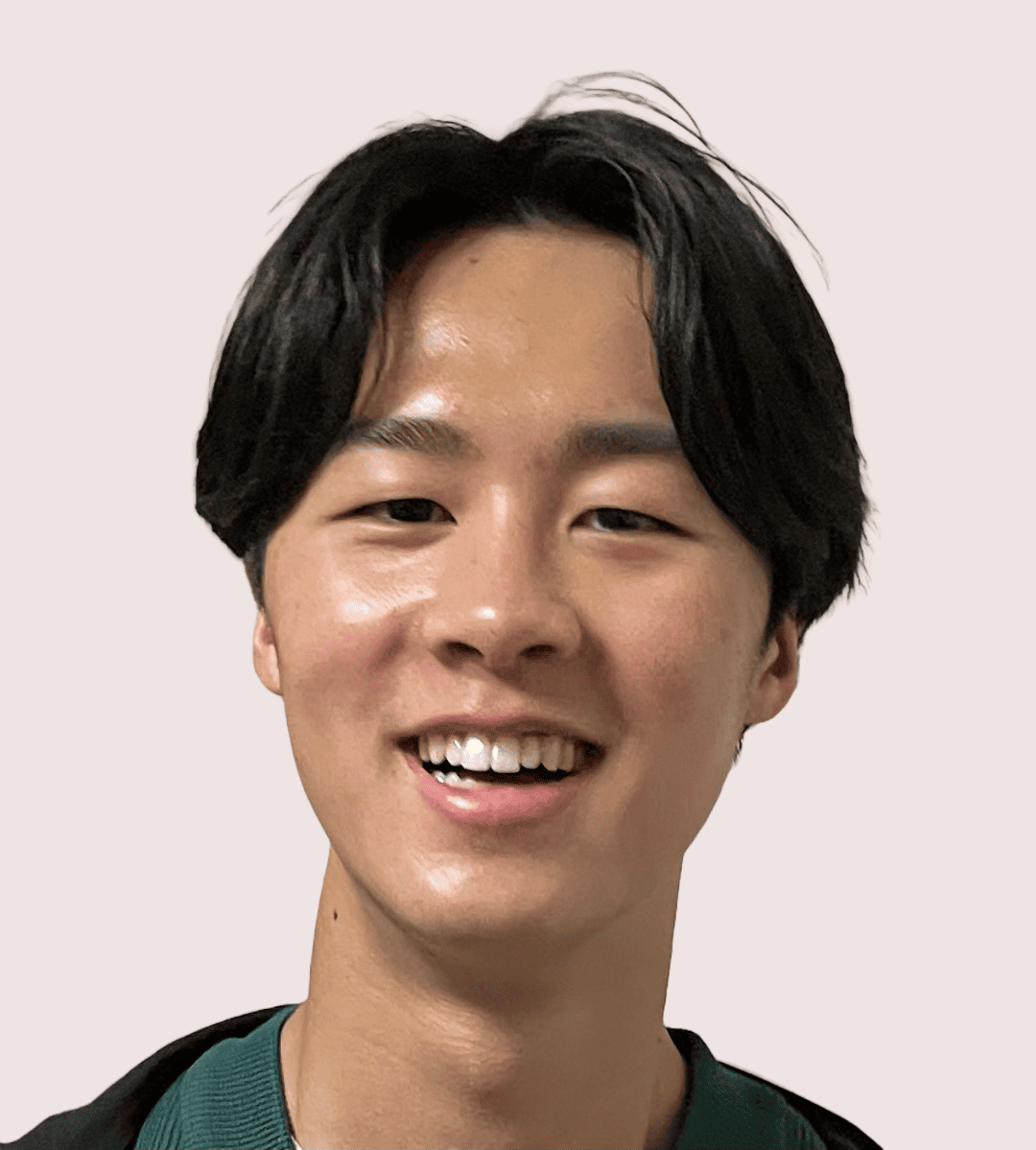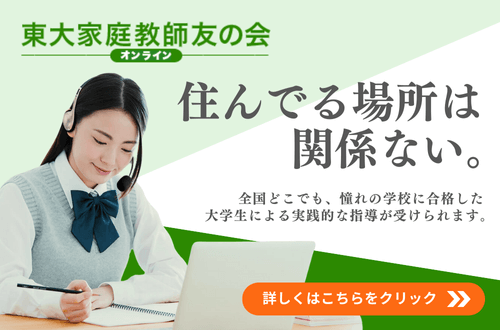![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
【2025年最新】東京大学入試概要
2025年2月に実施された入試情報に基づきます。最新の情報や詳細な入試要項は、必ず大学公式HPにてご確認ください。
学部別:倍率・偏差値
| 科類 | 倍率 | 偏差値 |
| 文科一類 | 約2.5倍 | 76 |
| 文科二類 | 約2.5倍 | 74 |
| 文科三類 | 約2.5倍 | 73 |
| 理科一類 | 約2.3倍 | 73 |
| 理科二類 | 約3.0倍 | 72 |
| 理科三類 | 約3.0倍 | 76 |
※倍率:東京大学令和7年度入学者選抜要項より
※偏差値:マナビジョンHP「東京大学の偏差値・共通テスト得点率(入試難易度)」より
学部別:科目・配点・時間
| 文科一類・二類・三類 | ||
| 国語 | 120点 | 150分 |
| 数学 | 80点 | 100分 |
| 地歴(注1) | 120点 | 150分 |
| 外国語 | 120点 | 120分 |
| 理科一類・二類・三類 | ||
| 国語 | 80点 | 100分 |
| 数学 | 120点 | 150分 |
| 理科(注2) | 120点 | 150分 |
| 外国語 | 120点 | 120分 |
| 面接※理科三類のみ | ||
(注1)世界史・日本史・地理から2科目選択
(注2)物理・化学・生物・地学から2科目選択
東大の過去問
過去問は、東京大学公式HPにて公開されています。詳しくは公式HPをご確認ください。
【2025年最新】科目別:東京大学二次試験の出題傾向・受験対策
| 解説を見たい科目をクリック | |
| 国語(理系) | 国語(文系)※準備中 |
| 数学(理系) | 数学(文系)※準備中 |
| 英語 | 世界史 |
| 日本史 ※準備中 | 地理 |
| 物理 | 化学 |
| 生物 | 地学 |
国語(理系)
国語(理系)の出題傾向
✓ 問題構成
東大理系国語の出題形式は、ここ数年においてほとんど変わっていません。
第一問現代文
(一)(二)(三):傍線部の理由や内容を2行で説明する問題
(四):文章全体の要旨を考慮して100字~120字程度で傍線部を説明する問題
(五):本文中に出てくる漢字の書き取り問題(3問)
第二問古文
(一):傍線部の現代語訳問題(3問)
(二)(三):傍線部の現代語訳または理由や内容を1~2行で説明する問題
第三問漢文
(一):傍線部の現代語訳問題(3問)
(二)(三):傍線部の現代語訳または理由や内容を1~2行で説明する問題
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
どの大問においても、題材となる文章のテーマや出典に偏りはありません。現代文は文理を問わず幅広いジャンルから出題され、古文漢文も様々な年代の様々な話が出題されます。また、内容についても大学入試としては標準的なレベルです。
一方で、解答欄が狭く限られているため、文章や設問の趣旨を見抜いてコンパクトに必要な情報をまとめる必要があります。これが東大国語を難しくしている点であると考えます。
国語(理系)の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
まず、評論用語や古文単語、漢文の用字・句法といった知識事項ですが、学校で配布される基礎的な単語帳、参考書に掲載されている内容をしっかりと覚えれば十分です。高度な知識は要求されないため、必要な基本知識を確実に身につけましょう。
次に記述に関しては、学校や塾の先生など第三者に添削を依頼すると良いでしょう。私も学校の先生に答案を見てもらい客観的な意見をいただいたことで、改善点を具体化することができました。
また、試験時間は100分で、順調に解き進めれば問題なく時間内に解き終えられる時間設定です。私は第一問を50分、第二問と第三問をそれぞれ20分で解き、残り10分で誤字脱字などを見直していました。
✓ 設問ごとの対策ポイント
・第一問:自分で練習する際は、時間を気にせず課題文をじっくりと読み込みましょう。一定の点数までは読解テクニックで伸ばすことができますが、そこから先は、テクニックだけに頼っていては点数が伸びづらいです。本文とたくさん向き合って、テクニックだけによらない実力をつけることが重要です。
・第二問と第三問:古文であれば品詞分解、漢文であれば句法の分析を日頃から怠らないようにしましょう。答案をまとめる練習として、現代語訳を見ながら答案を作成する勉強法も有効です。
国語(文系)
準備中
数学(理系)
数学(理系)の出題傾向
✓ 問題構成
150分間大問6個の構成で、分野は年によって様々です。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
近年の東京大学の数学では、ほとんどの分野から問題が出題されます。
計算量が多い問題が中心で、いわゆる難問や奇問は少ない傾向にありますが、整数問題を始めとする証明問題は難易度が高めです。
数学(理系)の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
大問一つにつき20分前後をかけるとして、全ての大問について大まかに以下の3つにわけて時間配分や解く順番を工夫するとよいです。
①すぐに解けそう(得意分野など)
②時間をかければ解けそう(計算量が多いなど)
③あまり解けなさそう(苦手分野、手がかりがつかめないなど)
私は①→③→②の順番で解いていましたが、人によって効率よく解ける順番は異なるかもしれません。過去問などを活用して、自分に合った解き方を模索すると良いでしょう。
時間配分を考えるときは、最後に自分の答案を見直す時間を設けることも忘れないようにしましょう。
理三以外であれば、他教科との兼ね合いを考慮しても60点~70点はとれると及第点と思われます。
✓ 設問ごとの対策ポイント
計算問題は確実に点数をとりましょう。時間をかければ解ける問題なので、他の受験生と差がつきにくいです。その分、落としてしまうと痛手になります。
証明問題や思考問題については、いかに部分点を得られるような、的を射つつ簡潔な答案を残せるかが鍵となります。日頃から先生や友人などの第三者に答案を見てもらって客観的な意見をもらうと、自分の解答の癖や陥りやすいミスに気づくことができるのでおすすめです。
また、得意分野があれば、それだけで気持ちが楽になります。自信を持てるくらいの演習を積んで、心の支えになる分野をつくりましょう。
数学(文系)
準備中
英語
英語の出題傾向
✓ 問題構成
基本的な問題構成は、以下の通りです。
問1(A)大意要約
(B)脱文挿入、語句整序
問2(A)自由英作文
(B)和文英訳
問3(A)(B)(C)リスニング
問4(A)英文正誤判定
(B)英文和訳
問5 長文読解
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
東京大学の英語試験では、長文読解、和訳、英作文、リスニングなど、多様な問題が出題されます。
問題文の単語や文法は大学入試として標準的なレベルであり、内容理解は難しくありません。しかし、あらゆる分野の対策が必要であり、120分という試験時間に対して問題数が多いため、テンポよく解答する必要があります。
以下に、出題されるリスニングについて特に詳しく述べます。
東京大学の英語リスニングでは、1つの音声が3分から5分程度と長く、訛りのある話者が話すことも多いです。また、共通テストとは異なり、ICプレイヤーではなく放送で音声が流れるため、試験を受ける教室や自分の座席位置によって聞こえ方が異なるようです。周囲の受験生の話を聞く限りでは、受験した教室が広いほど音声が聞き取りにくい傾向にあるようです。
こればかりは自分ではどうすることもできませんが、前もって知っておくと、当日多少条件が悪くても焦らずに済むでしょう。
英語の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
過去問を解いて、問題を解く順番や時間配分を決めておきましょう。試験開始後45分が経過するとリスニングが始まるので、前半45分と後半45分でどう取り組むのが自分にとって効率が良いか、色々試してみるとよいです。
✓ 設問ごとの対策ポイント
問1(A):要旨(筆者の主張)を記述するのか、要約(論理の流れ)を記述するのかを確認しましょう。問題文の指示が年によって微妙に異なるため注意が必要です。
問1(B)と4(A):マーク問題は最後に回し、時間がなければ適当に答えるくらいが良いでしょう。
問2(A)(B):内容や書き方を早く決定することがポイントです。また、普段の学習では第三者に見てもらいましょう。ChatGPTなどのAIを活用するのも有効です。
問3(A)(B)(C):問題の事前読み込みは必ず行いましょう。東大英語120点満点のうち30点分を占める(と言われている)部分です。点数を上げたいのであれば毎日シャドーイングを行いましょう。
問4(B):直訳すると不自然な日本語になることが多いです。自然な日本語に翻訳する練習を行うと力がつきます。
問5:小説や随筆が出題されます。学校で配布される副読本などで英語の物語に慣れておくと、後々役に立ちます。
世界史
世界史の出題傾向
✓ 問題構成
大問三つで構成されています。
第一問は12行・8行の論述2つ(2024年度入試より。1行30字程度。)、
第二問はおよそ2行から4行の小論述、
第三問は一問一答が10問ほど出題されます。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
全体として、教科書レベルの内容が深く理解できているかを見極めるような問題が出されます。
第一問は2023年度入試まで600字の大論述でしたが、2024年度入試から12行、8行(1行30字)の小問2つに変更されました。今後この形式が定着するかは不明ですが、どちらの形式にも対応できるようにしておくと無難でしょう。
また、第三問は比較的難易度が低めであることから、満点を狙うくらいで挑むとよいでしょう。
世界史の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
イギリスの帝国主義政策などは、過去に何度も出題されています。頻出分野は自信を持って答えられるようにすることが大切です。教科書によって重視されている内容がかなり違うので、教科書2冊以上を読み比べると、理解が深まります。
また、過去問で出題された分野の解答根拠が示されている教科書のページに付箋を貼って書き込みをすると、頻出分野が自然と見えてくるのでおすすめです。
教科書に更に図や表を加えたり、資料集をコピーして貼ったりして、自分だけの参考書として加工するのもよいです。当日のお守りのような存在にもなります。
✓ 設問ごとの対策ポイント
第一問は、問題文を注意深く読むことで出題者が求めている要素や文構成が見えてきます。記述は学校や塾の先生に添削してもらうのが望ましいですが、それが難しい場合は、複数の解答例を見比べて自分に足りない要素を洗い出すことが大切です。
第二問は主要な得点源であり、過去問や類題にどれだけ触れられたかが大きなポイントとなります。世界史が苦手な人は、解いた問題の答えを暗記し、第一問にも使えるフレーズとしてストックしていくのも有効です。
第三問は、先述の通り、比較的難易度が低く満点を狙っていきたいところです。なるべく短い時間で正確に答えることを心がけて演習しましょう。漢字のミスにも注意しましょう。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
日本史
準備中
地理
地理の出題傾向
✓ 問題構成
大問三つで構成されており、主に地図や統計の読み取り問題、特定地域の比較・分析問題などが出題されます。
大問の中には2~3問程度の設問があり、一つの設問にはおよそ4つの小問が設置されています。小問の内容は、2行から4行(1行30字)ほどの小論述、または短答形式での出題です。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
問題数が多いですが、共通テストレベルの基礎知識で解けるものも含まれています。特に短答形式のものは、点数がとりやすいので、落とすと周囲に差を付けられてしまう可能性が高いです。
各大問ごとの出題分野は年によって変動するため、出題分野の傾向は掴みにくいですが、第三問に限っては日本地誌が出題されることが多いです。特に、都市についての設問が多いため、過去問演習の際には復習に力を入れましょう。
地理の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
私大のように地名や史跡の名称が細かく問われることはほとんどありませんが、地形の成り立ちや都市の構造については簡潔に説明できるくらいまで理解しておくことが大切です。
また、地歴150分のうち、単純計算で地理にかけられる時間が75分とすると、小問1つにかけられる時間は3~4分ととても短いです。そのため、基礎知識のみで解ける定石問題を素早く解き、思考力を要する発展問題に時間を割けるように訓練していきましょう。
✓ 設問ごとの対策ポイント
地図や統計の読み取り問題は、記号や数値だけに着目するのではなく、背景となる気候、産業、文化などを意識するとよいです。文章にする前に一度簡単な表にまとめると思考が整理され、素早く解答が作れるのでおすすめです。
特定地域の比較・分析問題は、普段から自然条件→産業構造→生活様式などのように、因果的に説明する癖を付けておきましょう。因果関係がわかっていると、出題者の意図もとらえやすく、解答に盛り込むべき要素の取捨選択がしやすくなります。
物理
物理の出題傾向
✓ 問題構成
理科2科目を合わせて150分の時間設定です。
理科全体で大問6個、物理単体では大問3つの構成です。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
力学、電磁気と、熱力学または波動の組み合わせで出題されることが多いです。原子分野との関連など、複合問題として難解に見える問題が出題されることも多々あります。
年によって大問ごとの難易度はまちまちですので、簡単な問題や得意分野で得点を稼ぎ、残りを部分点狙いで対処するのが定石です。40点はとりたいところであり、十分に達成可能な難易度です。
物理の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
複合問題をはじめとして、条件や装置が入り組んでいて難しく見える問題も、読み解いてみれば基礎問題であることが多いです。入り組んだ問題設定に惑わされず、落ち着いて何を問われているかを見極めるようにしましょう。
また、大問の後ろに行くほど、時間はかかるが配点は高くないといったことも多いです。後半の計算が多いと感じたら、時間に余裕があっても一度切り上げて配点の高い問題でしっかり部分点がもらえるように時間を使うのも、一つの手です。
ただし、計算を早めに切り上げる場合にも、前後の設問と関係なく独立して解ける計算問題がないかは探すとよいでしょう(大問がローマ数字でさらに分けられている場合は特に、独立して解ける問題が見つかることがあります)。
✓ 設問ごとの対策ポイント
大問1は基本的な力学です。最も難易度が高いので、基本知識をしっかり頭に入れて、過去問や模試でできるだけたくさん演習を積むしかありません。
大問2は電磁気が多く出題されます。東京大学の電磁気は難易度が高くないので、得点源として考えるのが良いでしょう。微積分を用いた物理をかじっていると、さらに解きやすくなります。
大問3は熱力学か波動が多く出題されます。熱力学は、計算量は多いですが愚直に解けば点数がとれます。波動は、音波であれば力学の一種と考え、光波であれば電磁気の一種と考えることで苦手意識が薄れます。学習の段階で分野の関連を意識することで、スムーズに解けるようになります。
原子分野が出題される場合は、内容的には教科書レベルです。教科書がよく理解できていれば、重点的な対策は必要ないと感じます。
化学
化学の出題傾向
✓ 問題構成
例年、大問三つの構成です。
第一問が有機化学で、構造決定や高分子化合物の異性体をテーマにした問題、
第二問・第三問は、理論化学、無機化学で総合的な問題が多いです。
なお、2025年2月入試は形式が変わり、有機化学が第三問に来ていました。
計算問題は、過程を書かせる場合と答えのみの場合の両方があります。
記述問題では、実験結果からの考察や、適切な実験方法を考えて書くことが求められます。記述量のイメージは長くて2行(60字程度)です。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
有機化学では、メソ体やラセミ体、フィッシャーやニューマンといった高校の教科書の内容を超えて、問題文の誘導を読み込んで解答する問題が多いです。
理科の試験時間は2科目で150分なので、とにかく時間制約が厳しくなります。
計算問題は手が止まらない限りは解きましょう。計算に自信がなければ有効数字2桁でおおよその値を計算して解答するか、少しでも手が止まれば諦めて次の問題へ進むとよいです。
最後の問題は簡単な選択問題になっていることがあるので、必ず第三問の最終問題までひととおり解ける問題にあたって、残った時間で解ききれなかった計算に帰ってくるとよいでしょう。
化学の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
ただの暗記と計算では太刀打ちできません。2025年度は特に、自分の頭で考え、目の前の化学現象を考察する問題が目立ちました。
問題集などで見たことのあるトピックはまず出ないと考えておくとよいでしょう。化学に興味を持って、化学現象やそれに関連した実験をよく理解しておくことが、遠回りの様で最も近道です。
✓ 設問ごとの対策ポイント
時間制約が厳しいので、とにかくスピードが重要です。理論・無機分野の基本的な計算は有効数字三桁で速く正確に解けるようにしましょう。
有機化学は、教科書の範囲だけでなく、資料集のコラムや旧帝大・科学大の過去問に触れて、初見の問題への対処力をつけておくことをおすすめします。
初見問題への対処で重要な点は2つです。1つ目は焦らないことです。知らないものは知りません。焦って他の問題で計算ミスをしたりするともったいないので、知らないものは割り切って落ち着いて解答を進められるように、演習を重ねましょう。
2つ目は国語力です。化学とはいえ、問題文が年々長くなっているなという印象を受けます。急いで設問だけを先に見ずに、素直に頭から文章を丁寧に読んで、問題の設定をよく把握しながら解いていく練習をするとよいでしょう。
生物
生物の出題傾向
✓ 問題構成
例年、大問三つの構成です。
うち一問は必ず植物が出ます。そのほかは、動物や遺伝子の発現、発生、環境など大問ごとに大きなテーマはあるものの、分野をまたいだ総合問題になっていることが多いです。
解答用紙は横罫線のみ。「〇行から〇行で答えよ」「〇行以内で答えよ」「〇行程度で答えよ」などの指定があります。一行の目安は35字前後と言われますが、45字くらいまでの誤差は問題ありません。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
植物は確定で知識が問われるため、必ず押さえておきましょう。知識問題であっても選択問題は少なく、ほとんどが記述式です。
全体としては、実験結果からの原因考察が中心で、やはり時間制約が厳しいです。
問題が配られたら、まずざっと全体を見て、どの大問からどれくらいの時間をかけて解くかを素早く決めてから解き始めましょう。
また、問題を解く際は、問題文を一読で読み切ることが重要です。一度流し読みで最後まで見てから、また問題文のはじめに戻ってきて再度読む、ということをしていると間に合いません。何か書けそうであれば書くと良いですが、指定の行数分(例えば3行以上など)がなかなか書けそうにない場合は、思い切って飛ばして次の問題へ進んだ方が良いかもしれません。
生物の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
記述の練習は、必ず第三者に客観的な視点で採点してもらうようにしましょう。
全体として、国語よりも多くの文章を読まなければなりません。長いリード文を一読して要点を抜き出す力、条件を見落とさない注意力が必要です。
東大の問題は東大の過去問で練習するのがベストですが、10年前の過去問などは知識的に古くなってしまいます。各予備校の模試の過去問などを有効活用して演習を重ねましょう。
✓ 設問ごとの対策ポイント
どの問題においても総合的な知識が求められ、テーマを見抜くことすら難しいです。しかし、環境と生態系は独立して一問にされやすいので、いずれも固めておいて損はありません。
逆に、遺伝子頻度や組換え価の計算は、京都大学のような難しい問題は出題されません。確実に解けるように演習をしておきましょう。
地学
地学の出題傾向
✓ 問題構成
例他の理科科目と同じで、大問三つの構成です。
例年、大問一は宇宙分野、大問二は大気・海洋分野、大問三は固体地球、岩石・鉱物、地質・歴史分野です。
✓ 各問題の出題形式・頻出分野・難易度など
難易度に関していえば、もちろん他の大学の問題よりも難しいです。
しかし、物理・化学・地学で受験した筆者の経験としては、3科目の中では地学が最も点数がとりやすい科目です。
出題分野に偏りはなく、例年どの分野も満遍なく出題されている傾向です。
全体として論述形式の問題(解答用紙1~5行程度)と計算問題が多く、試験時間内に全て解き切るのはかなり難しいです。
大問一では主に計算問題や論述問題が出題されますが、近年では知識問題も増えてきています。対数の計算や微積分の知識が必要な問題も出題されたことがあり、数学の力が求められます。ケプラーの法則や視直径を使う問題は頻出です。
大問二も計算問題と論述問題が中心で、特に、初めて見るような状況設定の問題が多いです。エクマン輸送やフェーン現象は頻出です。
大問三も同じく計算問題と論述問題が中心です。地質図の読み取り問題や地震に関する問題、鉱物や示準化石についての知識問題が頻出です。
地学の受験対策
✓ 全体的な対策のポイント
論述問題が多いことに加え、計算問題は過程まで書かなければならないため、とにかく時間が足りなくなります。ひとつの問題に固執していると他の問題が解けなくなるため、大問一つにかける時間はあらかじめ決めておきましょう(例えば、大問一個25分など)。
特に大問一や大問三は時間が足りなくなるため、大問二から解き始めるのがおすすめです。
筆者は、計算問題が多い大問一を最後にし、大問二→大問三→大問一の順で解いていました。
なお、地学のみが載っている赤本は無いため、過去問対策の際は理系の全ての科目が掲載されている七カ年のものを買いましょう。可能であれば、古本屋などでより昔の赤本を購入して解くと良いです。
ただし、古い問題は近年の問題よりも時間の余裕がかなりある点に注意してください(したがって、古い問題の場合は時間の練習にはなりません)。
✓ 設問ごとの対策ポイント
論述対策として、普段の学習から、現象を理解し自分でも説明を書けるように練習しましょう。
大問三では、問題用紙に描かれている図を自分で解答用紙に写したり、一から図を描いて答える問題も出題されるため、図を描く練習も積んでおいた方がいいでしょう。
知識に関しては、共通テストの対策をきちんと行えば十分です。ただし、公式は意味までよく理解し、導出可能な公式は自分で導出できるくらいまで知識を深めておきましょう。
例えば、地殻の深さを求める公式は導出できます。地殻の公式は、それ自体が少し複雑なので、忘れてしまった時に導出できると便利でもあります。
【2025年最新】東京大学に受かるには?現役東大生からのアドバイス
文科一類合格/O.T.先輩
東京大学は二次試験に5科目が課されるので、受験生の皆さんの心理的負担は計り知れません。そんな中で、なかなか成績が上がらず悩んでしまうことも多いかと思います。うまくいかずに悩んだ時に考えてみてほしいのは、辛い出来事は、あなたの合格体験記をもっともっとドラマチックにするための要素だということです。
100人いれば100通りのサクセスストーリーがあります。ぜひ自分自身が受験の主人公になって、無我夢中で駆け抜けてください。ただし、勉強が辛くなった時は適度に息抜きをすることも大切です。時に迷い、悩みながらも前に進む自分を精一杯褒めてあげてくださいね。皆さんにも桜が咲きますように。心から応援しています。
理科一類合格/S.K.先輩
学校の教科書や、初めて使う参考書は定期的に見返してみましょう。ある程度演習が進んでからもう一度基本に立ち返ってみると、新しく気付けることが思いのほか多くありますよ。
また、模試の復習ノートをぜひ作ってみてください。入試本番の日に復習するための教材として、きっと大きな力を発揮してくれます。自分がどういう間違いをしたのか、何を見落としていたのか記録することの価値は、実際にノートを作ってみて初めてわかるはずです。
最後に、私立大学は、もし進学する気がなかったとしても、練習のつもりでいくつか受けてみるのがおすすめです。大学入試の雰囲気を掴んでおくことは、当日に落ち着いて試験を受けるためにも必要になります。確かに第一志望の入試は他の大学の試験とは感じ方が違うかもしれませんが、それでも事前に受験本番を経験しておくだけで、当日心に余裕が生まれます。
理科一類合格/T.Y.先輩
私は一年間宅浪をしました。その経験から、主に浪人生の方に向けてのアドバイスとなりますが、最も大切だと感じているのは「勉強を継続すること」です。
そんなの当然だと思うかもしれませんが、浪人中は(特に宅浪中は)、サボろうと思えばいつでもサボれてしまう上、先に大学生になった友達を見ると、つい遊びたくなってしまうものです。
もちろん、一年間毎日朝から晩まで勉強し続けるのは肉体的にも精神的にも辛いので、一日〇時間・週に〇日など、適度な休憩はむしろ設けるべきだと思います。しかし、何日も勉強をしないのは非常に良くありません。時間を空けすぎると、前回の勉強内容を忘れてしまったり、勉強に取り掛かるのが億劫になったりして、ますます休んでしまいがちです。
秋頃までは受験がまだ先のことに感じられるかもしれませんが、浪人を始めた時点で、受験当日までは1年を切っています。共通テストまでは10ヶ月ほどです。
受験本番までの勉強内容を逆算し、計画を立てて学習を進めましょう。計画的に勉強を継続すれば、合格は見えてくるはずです。
理科二類合格/S.R.先輩
東大といっても倍率は3倍程度です。しっかり準備をしてきたのであれば自信を持ちましょう。落ち着いていつも通りの力を出せれば、他の受験生が緊張で力を発揮できない中でも、問題なく合格できます。模試や過去問演習の段階で、一回一回に一喜一憂せず、毎回同じ精神状態を保つことを心がけましょう。
また、東大は天才じゃないと受からないような試験は作っていません。地道な努力と綿密な対策を重ねれば十分合格可能な試験です。
東大合格までに、どの人も大小差はあれど挫折を経験しています。気持ちが沈んだ時でも、ゴールは見失わず走り切ってください。
理科二類合格/Y.A.先輩
私は、女子・生物選択・塾無し、そのうえ毎年東大に5人受かるかどうかの公立校から受験をしました。なんとも不安になることが多かったのが正直なところです。
似たような状況の人は、有名進学校、有名東大専門塾の人たちと冠模試で相対して、私と同じく不安に思うことが多いかもしれません。私も、自分の勉強方法でいいのだろうか、そもそも東大を本当に目指せるんだろうか、そんなことも思いました。
しかし一番大切なのは、環境や現状より「絶対東大に行くんだ」という強い意志です。親や周囲に何と言われようと、自分がやり切ったといえるところまで、自分を信じて進んでください。
東大は、日本最高峰の大学である前に、皆さんの憧れの大学であってくれるはずです。とにかくモチベーション勝負です!どうか負けずに、頑張ってください。
また、東大入試は全教科での勝負です。どの教科も妥協しない気持ちが大事です。
具体的な勉強法は科目によって様々ですが、共通して言えるのは、勉強と教科を好きであること・探求したいと思うことが大事だということです。特に理系は、国語に苦手意識を持つ人が多い印象ですが、解けるのが楽しいと思えるまで勉強してみてください。その教科を好きな人に魅力をプレゼンしてもらうのも、やる気につながるのでおすすめです。
東大家庭教師友の会で東京大学受験対策!
東京大学在籍の家庭教師のご紹介
当会には現役東大生約9,700名が在籍しています。
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の東京大学受験対策のポイント
(1)東京大学に合格した先輩が指導
東京大学在籍の家庭教師が、東大受験対策のノウハウもとに指導いたします。実際に受験対策をした先輩だからこそ、自身の成功・失敗をふまえて、リアルで実用的な勉強法方法や学習計画をお伝えすることができます。
(2)基礎固めから過去問対策まで対応
当会では、カリキュラムや教材の指定はありません。基礎固めから過去問対策、苦手科目の集中的な対策など、東京大学合格に向けてそれぞれの生徒様に必要な学習計画・内容で指導いたします。
(3)指導のない日もオンライン自習室で自学&質問ができる
毎週月・木・金曜日に、オンライン自習室を開講!
指導のない日も集中して自学に取り組めます。東大生はじめ難関大生の教師が常駐しているため、質問対応も可能です。
オンライン指導も可能です