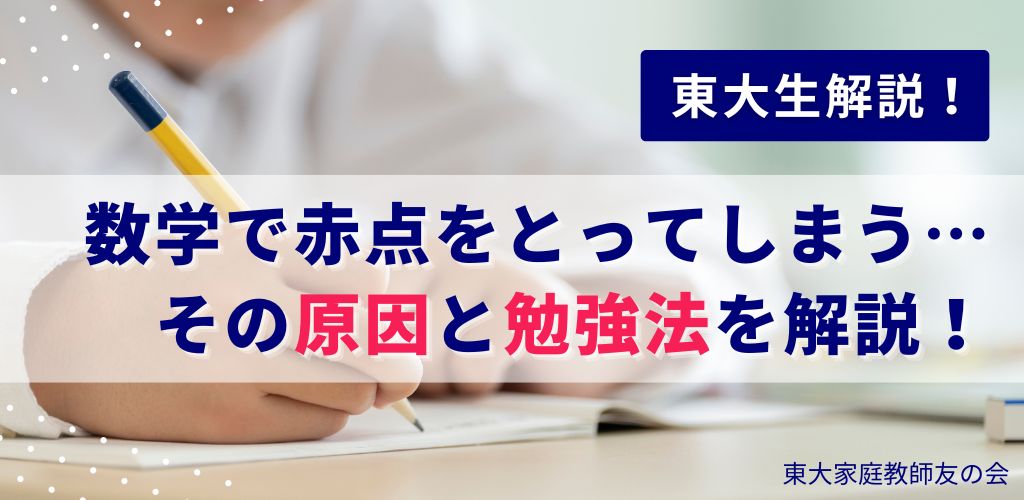![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 赤点は何点から?学校での基準の実例
赤点の基準に全国共通のルールはなく、学校によって異なります。
多くの場合、次のいずれかの方法で判定されます。
・絶対基準:あらかじめ決められた点数を下回ったら赤点
例:「60点未満は赤点」「50点未満は赤点」など
・相対基準:平均点に対して一定の割合を下回ったら赤点
例:「平均点の60%未満は赤点」「50%未満は赤点」など
実際には「60点未満」と定めている学校が多いですが、50点を基準にしている高校や、中学によっては赤点自体を設けていないケースもあります。詳しくは在籍している学校に確認してみましょう。
ちなみに赤点とは、学習指導要領に載っている正式な言葉ではなく、いわゆる「俗語」です。昔の通知表で赤点科目を赤い文字で記載していたことから、この呼び名が広まりました。
基準が学校によって異なることを確認したところで、高校・中学校での実際の赤点の扱いについて詳しく見ていきましょう。
①高校における赤点
高校生が定期テストで学校の基準点を下回った場合、その科目は赤点と判定されます。赤点になると単位が認定されず、放置すると進級や卒業に支障が出る場合があります。
高校では、赤点をとった生徒に対してさまざまな救済措置を用意しています。
・補習を受ける
・補習後にレポートを提出する
・再試験(追試)を受けて一定の点数を取る
このような課題をクリアすれば、単位が認められるケースがほとんどです。したがって、万が一赤点を取ってしまった場合には、学校の救済措置を確認し、確実に対応することが大切です。
②中学校における赤点
公立中学校には留年という仕組みがないため、赤点の基準も特に定められていません。定期テストで低い点数を取っても、進級や卒業に直接影響することはないのです。
ただし、定期テストの結果は通知表に反映され、内申点に大きく影響します。内申点が低くなると、高校入試の際に志望校の選択肢が狭まってしまうため注意が必要です。したがって、公立中学校に通う生徒であっても、赤点に相当するような点数を取らないよう心掛けることが大切です。
一方、私立中学校の場合は事情が異なります。ごく稀ではありますが、成績不良が続いて改善が見られない場合には留年を命じられるケースがあります。場合によっては公立中学校への転校を勧められることもあります。
このように、公立中学校では赤点そのものが進級に直結しません。一方で、私立中学校では高校と同じくらい厳しく扱われるケースも見られます。そのため、私立に通う生徒は日頃から赤点を徹底的に避ける姿勢が求められるのです。
2. 赤点になるとどうなる?影響とリスク
赤点を取ったからといって、すぐに留年するわけではありませんが「留年しないなら大丈夫」と考えるのは危険です。
ここからは、赤点をとることで生じる悪影響について、高校の場合と中学校の場合に分けてそれぞれ具体的に解説します。
①高校の場合
高校生が赤点をとってしまった場合、以下のような悪影響が考えられます。
(1)補習や追加課題を受けなければならない
(2)再試験(追試)を受けて一定の点数を取る必要がある
(3)評定が下がり、推薦入試に影響が出る
(4)奨学金の認定が受けづらくなる
(5)留年してしまうおそれがある
それぞれ詳しく説明します。
(1)補習や追加課題を受けなければならない
赤点を取ると、その科目の理解度に問題があると判断されます。高校では文部科学省が定めた単位を取得しなければ進級・卒業ができません。
単位の条件は「その科目の目標を十分に満たしていること」です。理解不足と見なされると、補習に参加したりレポートを提出したりと追加の課題を課されます。
課外活動やアルバイトに使える時間が減り、さらに新しい授業内容も並行して学習しなければならないため、負担が大きくなる生徒も少なくありません。
(2)再試験(追試)を受けて一定の点数を取る必要がある
多くの高校では、赤点を取った生徒に再試験(追試)が課されます。追試はテスト返却後、一定期間を空けて実施され、本試験と似た問題が出されるのが一般的です。
追試の前に補習を行う学校もあります。ただし、ここで再び赤点になると留年の危険が一気に高まります。そのため、追試を受ける場合には入念な準備が欠かせません。
(3)評定が下がり、推薦入試に影響が出る
赤点を取ると通知表の評定が下がる可能性が高まります。この評定は、将来の推薦入試や総合型選抜(AO入試)に直結する重要な要素です。多くの大学は「評定平均◯以上」といった基準を出願条件に設けています。条件を満たせないと、そもそも選考を受けられません。
評定平均は高1の1学期から高3の1学期までの全科目の平均で算出されます。例えば、ある科目で毎回「2」を取ってしまうと、全体の平均がじわじわ下がってしまうのです。
(4)奨学金の認定が受けづらくなる
2022年度の日本学生支援機構の調査によると、大学生の約55%が奨学金を利用しています。しかし、奨学金を受けるには成績基準を満たさなければなりません。たとえば、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金や無利子の第一種奨学金では、評定平均3.5以上が条件です。
赤点を取ると評定が下がり、この条件を満たせなくなるリスクがあります。希望する奨学金を受け取るためにも、赤点は避けたいところです。
(5)留年してしまうおそれがある
進級の可否は「成績」「出席日数」「提出物や生活態度」など総合的に判断されます。そのため、一度赤点を取っただけで即留年することはほとんどありません。
しかし、補習や追試に取り組む姿勢が見られなかったり、出席日数が不足していたりすると留年になる可能性があります。日本の高校では年齢主義が採用されており、同じ学年には同じ年齢の生徒が集まります。
そのため、留年すると居心地の悪さを感じたり、学校に通いにくくなってしまう生徒も少なくありません。中には「留年をきっかけに中途退学を選ぶ」というケースもあります。せっかく入った高校ですから、赤点を回避し、確実に単位を取得して卒業を目指すことが大切です。
②中学校の場合
中学校では、一部の私立を除けば留年はありません。そのため、定期テストで低い点数を取っても補習や再試験(追試)が課されることはほとんどありません。
ただし、定期テストの点数は通知表に反映され、内申点に大きく影響します。内申点は高校入試で重要な判断材料となるため、一定以上の点数を取ることが求められます。
公立高校(都道府県立など)の入試では、「内申点+入試の得点」で合否が決まります。入試では受験生が自分の学力に見合った高校を選ぶため、当日の得点差は大きくなりにくい傾向があります。ここで内申点が不足していると、不利な状況で試験に挑むことになってしまいます。
一方、私立高校の一般入試では、当日の得点が重視されます。その場合、内申点をあまり気にしなくても済みます。しかし、単願入試や「併願優遇」「併願推薦」といった制度を利用する場合は、やはり内申点が選考に使われます。
このように、中学生にとっても定期テストは重要です。しっかり点数を取り、内申点の低下を防ぐことが高校受験を有利に進める鍵となります。
3. 赤点を取ったときの対処法
ここからは、実際に赤点をとってしまった際の対処法について解説します。赤点をとってしまった場合の正しい対処法を知り、まずは目の前の単位を確実に取得することを考えましょう。
①生徒様ができる対処法
赤点を取ってしまった生徒は、まず単位を取得することを最優先に考える必要があります。そのためには、しばらく課外活動やアルバイトを控え、学習に集中することが大切です。
確実に単位を取るために取り組むべきことは次の通りです。
・補習を真剣に受ける
・課題が出た場合にも真剣に取り組む
・再試験では本番の問題を7割程度解ける状態に仕上げる
・難しい問題が多いときは教科書に戻って復習する
再試験は本試験とまったく同じ問題ではなく、類似問題が出題されるのが一般的です。そのため、解法や答えを丸暗記するのではなく、基本的な原理や解き方を理解しておくことが重要です。
赤点になる科目は多くの場合、もともと苦手意識が強い分野です。完璧を目指すのは難しいかもしれません。そこで、あらかじめ合格点を先生に確認し、確実に点が取れる問題を増やしていくことが現実的な対策となります。
②保護者様ができるサポート
生徒様が赤点をとってしまった場合、保護者様は冷静な対応を心掛けましょう。一番ショックを受けているのは、生徒様本人だという点を忘れてはいけません。大切なのは、落ち着いて挽回のためのサポートに徹する姿勢です。
喜ばれる可能性が高い行動
・テストに向けて努力していたこと自体を褒める
・一緒に学習スケジュールを立てる
・おやつや軽い夜食を用意する
・勉強に集中できる環境づくりに協力する(テレビの視聴を控える、きょうだいを静かにさせる等)
避けるべき行動
・点数が悪かったことを叱る
・スマートフォンの使用や動画の視聴、ゲームといった娯楽を完全に禁止する
・生徒様の人格を否定するような言葉をかける
・周りの子どもやきょうだいと比較して責める
もちろん、保護者様が我が子に期待する気持ちからこうした行動をとりたくなるのは自然なことです。しかし、これらは生徒様のモチベーションを下げるだけです。保護者様が慌てずにサポートしてあげれば、生徒様も落ち着いて学習に取り組めるはずです。
4. 赤点を取らないための学習法
赤点はできるだけ避けたいと思うのが自然な気持ちです。とくに一度経験してしまうと、生徒様も保護者様も「次は大丈夫だろうか」と不安になることでしょう。
そこで本章では、赤点を防ぐために日ごろから取り組んでおきたい勉強方法を解説します。普段から少しずつ準備しておけば、定期テスト前に慌てたり「もう無理だ」と諦めたりせずに済みます。
①生徒様が行うべきこと
生徒様にまず心掛けてほしいのは、「日頃の授業内容を大切にすること」です。定期テストと定期テストの間には、数か月の間隔があります。そのため、数か月前に学んだ内容をテスト直前の短期間で思い出すのは容易ではありません。
日々の学習では、次の点を意識して取り組んでみてください。
(1)1日・1週間・1か月ごとに学習内容を振り返る
(2)間違えた問題をそのままにしない
(3)インプットとアウトプットのバランスを取る
(4)学校の先生や塾講師・家庭教師を活用する
それぞれ詳しく解説します。
(1)1日・1週間・1か月ごとに学習内容を振り返る
授業で学んだことは、その日のうちに軽く振り返りましょう。毎日しっかり問題演習まで行うのは大変ですが、「何を学んだか」「どこが分かったか」を確認するだけでも効果があります。
すべての科目が難しければ、苦手科目だけでも十分です。大切なのは授業を受けっぱなしにしないことです。
(2)間違えた問題をそのままにしない
分からなかった問題は放置せず、その日のうちに解き直しましょう。授業で解説を聞いて「分かったつもり」になっても、自分で解けるとは限りません。
同じ問題を自力で解ける状態にしておけば、テスト前は思い出すだけで済みます。
(3)インプットとアウトプットのバランスを取る
普段から「覚える(インプット)」と「思い出して書く(アウトプット)」をセットで行うように心掛けましょう。
英単語や社会の勉強でありがちなのが、暗記ばかりに偏るケースです。単語帳に線を引いて覚えても、テストでは自分の力で思い出して答える必要があります。
(4)学校の先生や塾講師・家庭教師を活用する
分からないことがあれば、積極的に質問しましょう。「今さら聞くのは恥ずかしい」と思う生徒様もいますが、先生や講師は気にしていません。とくに英語や数学のように積み重ねが大切な科目は、疑問を放置すると後で大きなつまずきになります。
学校や塾で質問しにくいときは、家庭教師のように1対1で学べる環境もおすすめです。周囲を気にせず学べるため、苦手克服や赤点対策につながります。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
②保護者様にできること
赤点をとった場合と同じように、日ごろの学習でも保護者様にはサポート役をお願いします。ただし、テスト直前や直後のように細かくチェックしすぎると、保護者様も生徒様も疲れてしまいます。普段の学習は適度な距離感で見守ることが大切です。
たとえば、次のような関わり方がおすすめです。
・定期テスト前でなくても復習している様子が見られたら褒める
・勉強に集中しやすい環境を整える
・「勉強しなさい」と過度に声をかけすぎないよう注意する
・スマートフォンやゲーム、動画の利用時間は、落ち着いているときに話し合って決める
高校生が相手なら、細かく管理する必要はありません。
生徒様本人が「勉強しよう」と思ったときに、安心して机に向かえる環境を整えてあげれば十分です。
5. 赤点を取っても大丈夫!進級に備える対策と勉強法
赤点は一度とっただけで直ちに進級や卒業に影響するわけではありません。しかし、放置すれば、評定の低下につながり、将来の推薦入試や奨学金の審査にまで悪影響を及ぼす可能性があります。
赤点をとってしまったときは、補習や再試験(追試)に向けてしっかり対策し、確実に単位を取得することが大切です。同時に、日頃から授業の復習を丁寧に行い、わからない問題をそのままにしないことも重要です。必要に応じて、学校の先生や塾、家庭教師などの力を借りながら、赤点を未然に防ぐ習慣を身につけましょう。
▼当会では赤点の克服から、受験対策、中高一貫校の学習サポートまで対応しています。詳しくは下記ページをご覧ください。
あわせてチェック|赤点の関連記事
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。