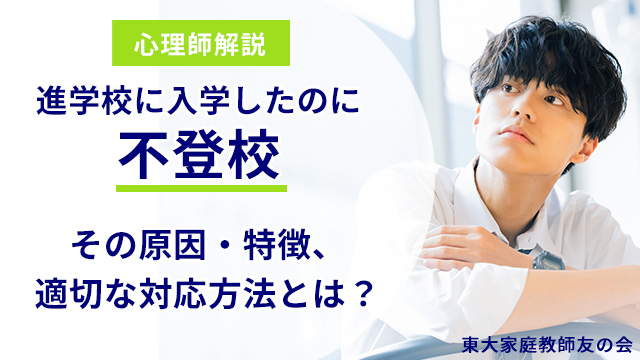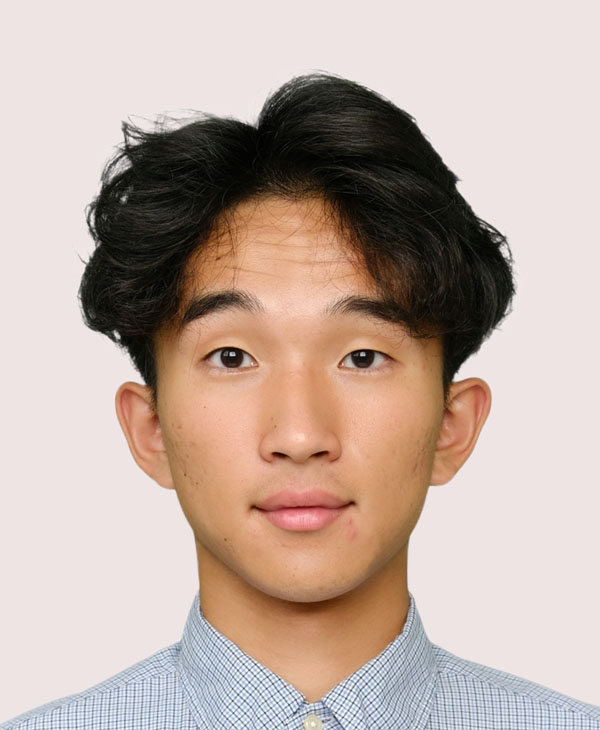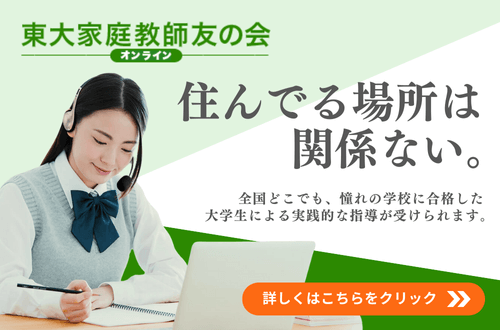![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業受付中!
1. 進学校の不登校で保護者様が抱える3つの悩み
進学校に通うお子様が不登校になってしまうと、多くの保護者様が強い不安を抱きます。
「大学受験はどうなるのだろう…」
「勉強が遅れてしまって取り返せないのでは…」
「どう声をかければいいのかわからない…」
こうした悩みは決して珍しいものではなく、多くの保護者様が同じように感じているものです。
ここでは、特によく寄せられる3つの悩みをご紹介します。
①大学受験が心配…このまま不登校が続いたら?
「せっかく進学校に入ったのに、大学受験はどうなるのだろう…」という不安は、多くの保護者様が最初に抱える悩みです。
進学校は大学進学を前提としたカリキュラムのため、欠席が続けば学習の遅れや受験準備に影響します。
また、「周りの同級生は勉強を進めているのに、うちの子だけ…」と比較して焦りを感じることもあります。
進学校では大学進学がゴールのように思われやすく、不登校=受験の失敗と短絡的に考えてしまいがちです。
②勉強しない子どもへの焦り
「家にいても勉強しない」「机に向かう時間が減った」──そんな姿を見ると、保護者様としてはつい「このまま落ちこぼれてしまうのでは」と不安になります。
特に進学校では、授業のスピードが速く、少し遅れるだけでも追いつくのが大変です。
そのため「なんとか勉強させなければ」と焦り、声を荒げたり強制したくなることもあるでしょう。
しかし、そうした焦りは子どもにとってプレッシャーとなり、不登校を長引かせてしまうことも少なくありません。
③親子関係の悪化…どう接すればいい?
不登校が続くと、家庭の雰囲気もぎくしゃくしやすくなります。
・「学校に行きなさい」と言っても反発される
・無理に話しかけると口をきいてくれない
・家の中で互いに気を使い、ストレスが溜まる
進学校に通う生徒様は「自分はできるはずなのにできない」という葛藤を抱えやすく、親の言葉に敏感になりがちです。そのため「どう声をかければいいのかわからない」というのも保護者様の大きな悩みの一つです。
この記事では、進学校の不登校の現状や原因を整理しながら、保護者様ができる適切な接し方やサポート方法について解説していきます。
不安を少しでも軽くし、今後の進路や受験への道を考えるうえでの参考にしていただければ幸いです。
2. 進学校に通う高校生の不登校割合
まずは、高校生全体、そして進学校にどれくらい不登校の生徒がいるのかを見ていきましょう。
①高校生の不登校者数
文部科学省の調査(注1)によると、高校生の不登校者数は2023年時点で68,770人にのぼり、前年度より8,195人(13.5%)増加しています。割合にすると全体の2.4%、つまり1学年に2~3人程度が不登校の状態にあることになります。
小中学生と比べると数字が少なく見えるかもしれませんが、高校生には「中途退学」という選択肢があるため、統計上は不登校者数が少なくなる傾向があります。実際には毎年約4万人が中途退学しているため、不登校で悩む高校生は数字以上に多いと考えられます。
▼高校生の不登校について、詳細は以下ページをご覧ください
②進学校の不登校者数
進学校に限定した正確なデータは公表されていませんが、アンケート調査では「勉強についていけず不登校になった」と答える高校生が一定数います。進学校は授業進度が速く、学習や人間関係の負担が大きいため、一般的な高校よりも不登校が生じやすい環境だといえるでしょう。
そのため「うちの子だけが特別なのでは…」と心配する必要はありません。同じように悩んでいる高校生は少なくないのです。
3. 進学校の高校生が不登校になる4つの原因

進学校に通う高校生が不登校になる背景には、さまざまな要因があります。
ここでは代表的な4つを紹介します。
①高校受験での疲弊と合格後の「燃え尽き症候群」
中学時代に必死で勉強し、やっと進学校に合格したものの、その直後に気持ちが切れてしまうケースがあります。 いわゆる「燃え尽き症候群」です。
厚生労働省(注2)によると、燃え尽き症候群とは「人一倍活発に仕事をしていた人が、なんらかのきっかけで、あたかも燃え尽きるように活力を失ったときに示す心身の疲労症状」とされています。
高校受験で目標を達成したことで緊張が解け、「もう頑張れない」と感じてしまうのです。
さらに進学校では授業スピードが速く、入学直後から新しい環境に適応しなければならないため、心身の疲労が一気に表面化し、進学校に入学したばかりの1年生が不登校になるケースもあります。
②「落ちこぼれたくない」同級生との比較によるプレッシャー
進学校には学力の高い生徒が集まるため、どうしても成績の競争が避けられません。
「友達は模試で好成績をとっているのに、自分だけ結果が出ない」
「親や先生の期待に応えられないかもしれない」
こうした比較や期待が大きなプレッシャーとなり、自己肯定感を下げてしまいます。
努力しても思うように成果が出ないと、「自分は劣っているのでは」という思い込みにつながり、学校に行くこと自体が苦しくなることがあります。
③ハードスケジュールや学習の遅れによる負担
進学校では、日々の予習・復習に加えて部活動やテスト、模試などが重なり、非常にハードな毎日を送ります。
十分な睡眠や休養が取れず生活リズムが乱れると、疲れが蓄積して学習の遅れにつながりやすくなります。
やがて「どうせ追いつけない」「もういいや」という気持ちが生まれ、登校意欲を失うケースも少なくありません。
④うつ病や適応障害など、心身の不調
不登校の背景には、うつ病や適応障害といった心身の不調が隠れていることもあります。
特に進学校の生徒様は「頑張りすぎてしまう」傾向があり、疲れやストレスをため込みやすいです。
その結果、気分の落ち込みや強い不安、頭痛・腹痛・不眠などの体調不良が続き、学校に行けなくなってしまうことがあります。
このような場合は、決して「怠け」や「甘え」と片付けず、医療機関や専門家の相談を検討することが大切です。早めに支援を受けることで改善につながるケースも多くあります。
4. 進学校で不登校になった高校生へのOK対応とNG対応
不登校のお子様を前にすると、保護者の方は「どう接するのが正解なのか」と悩むものです。
ここでは心理師の視点から、回復を後押しするOK対応と、逆効果になりやすいNG対応を紹介します。
【OK対応】①心と体を休ませ、気持ちを受け止める
不登校の生徒様は「学校に行けない自分」を責めてしまいがちです。まずは「休んでも大丈夫だよ」と伝え、安心できる環境を整えることが大切です。
また「学校に行く・行かない」だけでなく、休養や別の進路など学校以外にも選択肢があることを一緒に考えていけると安心につながります。たとえば、
「大学に行きたいなら通信制高校に編入する方法もあるよ」
「一度休んで浪人しても大丈夫だよ」
といった言葉をかけると、生徒様も「やり直せる道がある」と感じやすくなります。
その際は保護者様が「こうしなさい」と押しつけるのではなく、「こんな方法もあるよ。一緒に考えてみよう」と寄り添う姿勢を大切にしましょう。
【OK対応】②学習環境・生活リズムを整える
不登校が長引くと、生活リズムの乱れや勉強の遅れが不安を大きくします。まずは起床・就寝の時間を整えるなど、規則正しい生活習慣をサポートしましょう。
学習面では、スマートフォンや漫画などの誘惑を減らし、集中しやすい環境をつくることが大切です。
外に出にくい状況でも、オンライン学習や家庭教師といったサポートを取り入れれば、自宅から無理なく勉強を続けることができます。勉強以外の相談にも寄り添ってもらえるため、気持ちを整えながら少しずつ学習習慣を取り戻すきっかけになります。
![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業受付中!
【NG対応】①勉強の強制や偏差値へのこだわり
「勉強しなさい」と繰り返すのは逆効果です。生徒様本人は勉強の必要性を理解していても、心身がついていけないことが多いからです。強制されると反発や自己否定感が強まり、かえって勉強から遠ざかってしまいます。
代わりに「5分だけやってみよう」と少しずつ始める声かけや、「今日はやらなくてもいいよ」と余裕を持たせる工夫が効果的です。
心理学的に、やりかけの行動を続けたくなる効果(ツァイガルニク効果)や、禁止されると逆にやりたくなる効果(カリギュラ効果)を利用した方法です。
また、目先の偏差値にこだわるよりも、「どんな大学生活を送りたいか」「将来どんなことを学びたいか」といった将来のビジョンを一緒に考える方が意欲につながります。
偏差値の高さ自体がゴールではなく、その大学で得たい学びがあるかどうかが重要です。そうでなければ、せっかく進学しても理想とのギャップに悩むことになりかねません。
保護者様は、生徒様の希望や将来像を尊重しながら、無理のない進路選びをサポートしていきましょう。
【NG対応】②将来の不安をあおる
「このままでは大学に行けないよ」「将来困るよ」といった言葉は避けましょう。
保護者様としては「危機感を持ってほしい」「どうにかしてあげたい」と生徒様を思っての発言かもしれませんが、不登校の生徒様からすると、「責められている」と捉えてしまいます。
将来について話すときは、不安をあおるのではなく「まだ選択肢がある」「やり直せる方法もある」といった安心感を伝えることを意識しましょう。生徒様が前を向くためには、不安ではなく希望を示す言葉かけが大切です。
5. 進学校 不登校から大学受験へ:3つの選択肢

進学校に通う高校生が不登校になった場合でも、大学進学の道が閉ざされるわけではありません。
ここでは代表的な3つの選択肢をご紹介します。
①現在の高校で復帰を目指し、大学受験に臨む
不登校が続いていても、まずは現在の高校に少しずつ戻ることを目標にする方法です。
・まずは心と体を休ませる
・家庭教師や塾を利用して学習の遅れを補う
・授業や模試など、一部だけ登校して慣らしていく
こうしたサポートを組み合わせることで、無理のないペースで復帰でき、大学受験に向けて学力を取り戻すことが可能です。大切なのは「焦らず、一歩ずつ取り組むこと」です。
②通信制高校へ編入し、自分のペースで学ぶ
授業のペースについていけない、体調や精神的な理由で通学が難しい場合は、通信制高校への編入も選択肢になります。
・卒業すれば「高校卒業」の学歴取得、大学受験も可能
・自宅中心の学習スタイル
・必要に応じたスクーリング(登校授業)や面談でのサポート
進学校に通い続けることにこだわらず、自分のペースで学べる環境を整えることが、結果的に進路の可能性を広げることにつながります。
③高卒認定試験で大学受験資格を取得する
高校に復帰することや通信制高校への編入が難しい場合は、高卒認定試験(旧・大検)を受ける方法もあります。
・合格すれば大学受験資格が得られる
・出題内容は高校課程と同等で、自宅学習でも挑戦可能
・自分のペースで進められるため、体調や生活リズムに合わせた勉強が可能
高卒認定試験は「不登校だから大学進学はできない」という思い込みを取り除き、自分らしい方法で進学を目指せる選択肢のひとつです。
▼高卒認定試験の詳細は以下ページをご覧ください
保護者様は、生徒様と一緒に大学受験への選択肢を検討し、無理のない方法を選んでいけるようサポートしてあげましょう。
▼不登校の大学受験について、詳細は以下ページをご覧ください
6. 進学校の不登校生に家庭教師ができるサポート

進学校に通う不登校の高校生にとって、学習の遅れや大学受験への不安は大きなストレスです。家庭教師は、学校や塾とは異なり、生徒様の状況に合わせて柔軟にサポートできる点が特徴です。
ここでは代表的な3つのサポート方法を紹介します。
①一人ひとりのペースに合わせた学習計画の作成
不登校の生徒様は、授業のスピードに合わせて学習するのが難しい場合があります。家庭教師は、現在の学力や生活リズムを考慮して、無理のない学習計画を立てられます。
・苦手分野を重点的に復習するカリキュラム
・「1日30分からスタート」など少しずつ学習量を増やすステップ式の計画
・模試やテストに合わせた効率的な復習スケジュール
こうした個別プランにより、学習の遅れを取り戻しながら、自信を持って大学受験に臨むことができます。
②大学受験に向けた精神的なサポートと進路相談
不登校になると、勉強面だけでなく精神的な不安も大きくなります。家庭教師は、学習のサポートだけでなく、進路相談や精神的な支えにもなれます。
・勉強に行き詰まったときの声かけやモチベーション維持
・「今の学力でどの大学が目標になるか」を一緒に整理
・将来の夢や希望に合わせた学習計画の調整
学習と進路を一体でサポートすることで、漠然とした不安を減らし、前向きな気持ちを取り戻すことができます。
③「できた!」を積み重ねて自信を取り戻すサポート
不登校の生徒様は、勉強への自信を失っていることが少なくありません。家庭教師は、少しずつ「できた!」という経験を積ませることで、自信を取り戻すサポートができます。
・小さな課題をクリアして達成感を実感
・成績や理解度を可視化し、努力の成果を実感
・学習だけでなく、日常生活の目標設定や達成もサポート
「できた!」という経験を積むことで、「自分ならできる」という前向きな気持ちが芽生え、学校復帰や大学受験への意欲につながります。
東大家庭教師友の会では、年齢の近い大学生家庭教師が、学習だけでなく学校生活や進路の悩みにも寄り添いながらサポートします。
![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業受付中!
進学校の不登校は、新たな道を探すチャンス
進学校に通う生徒様が不登校になってしまうと、生徒様本人はもちろん、保護者様もどう対応すればよいかわからず、不安を感じることがあるでしょう。しかし、「不登校になったら終わり」でもなければ、「もう大学に行けない」というわけでもありません。
大切なのは、生徒様の状況に合った対応を見つけ、一歩ずつ前に進むことです。その過程で学んだ経験は、結果的に大学受験や将来の選択に大きく役立ちます。
ぜひ今回の内容を参考に、生徒様と一緒に少しずつ前へ進んであげてください。
大学受験の指導ができる家庭教師のご紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
オンラインでの指導も可能です
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る
進学校不登校生のサポートなら東大家庭教師友の会
あわせてチェック|不登校の関連記事