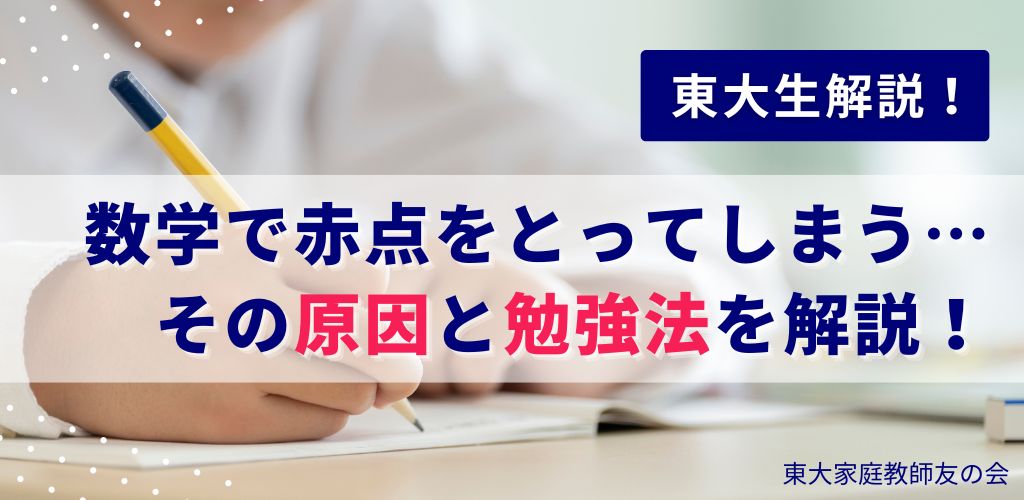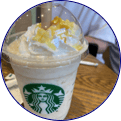1. 数学で赤点ばかり取ってしまう原因
数学で赤点ばかり取ってしまうとき、大切なのは「なぜそうなったのか」を冷静に分析することです。赤点には必ず原因があります。
ここでは、よくある3つの原因を整理してみましょう。
①基本事項の理解不足が大きな要因
定期テストは、授業内容の理解度を確認するものです。そのため、どの学校でも教科書にある例題レベルの基礎問題は必ず出題されます。
赤点を取ってしまうということは、この基礎的な問題を解けていないことを意味します。授業で学んだ基礎を理解できていないと、応用以前の段階でつまずいてしまい、得点につながりません。
②みんなが解ける問題を落としている
赤点は「平均点を基準に決まる」ことが多く、多くの学校では「平均点の半分以下」が目安になっています。
つまり、赤点を取るのは、難問ではなく、むしろ「誰もが解けている基本的な問題」を落としているケースが多いのです。クラスの大半が正解できる問題を間違えると、一気に平均点との差が開き、赤点になりやすくなります。
③質よりも「量」が足りない
「自分には数学のセンスがないから仕方ない」と思うかもしれませんが、実際には基礎問題は反復演習で解けるようになることがほとんどです。
とくに定期テストのように範囲が決まっている試験では、課題や宿題をサボらず、十分な量をこなしていれば赤点を避けられる可能性が高いです。
赤点の原因は、理解力以前に「演習量の不足」であることが少なくありません。
2. 数学で赤点を取った時の対処法
数学で赤点を取ってしまった場合、大切なのは「落ち込むこと」ではなく「どう立て直すか」を考えることです。
ここでは、赤点からの立て直し方と、保護者様の接し方について整理していきます。
①まずは解き直しで原因を把握する
試験後の問題用紙は、多くの場合そのまま持ち帰れます。解きっぱなしにしてしまうと、同じミスを繰り返しやすくなります。
まずは分からなかった問題や、途中で答えを出せなかった問題を 教科書や授業ノートを見ながらで構わないので必ず解き直す ようにしましょう。
・教科書やノートを見れば解けた → 復習不足が原因
・教科書やノートを見ても理解できない → 単元自体の理解不足
②問題集やワークで集中的に復習する
赤点になった分野は、できるだけ早いうちに克服しておく必要があります。数学は積み重ねの教科なので、苦手を放置すると次の単元でも理解が追いつかなくなり、実力テストや入試にも悪影響を及ぼします。
効果的なのは、 学校のワークや基本問題集を繰り返し解くこと です。ワークには基礎力を確認できる良問が多く、先生が試験範囲として指定することも少なくありません。追試がある場合は、まずは簡単な問題からでも確実に解けるように準備しておきましょう。
苦手分野は「数をこなす」ことで解法のパターンを自然に覚えられるため、復習は集中的に取り組むのがおすすめです。
③保護者の過干渉は逆効果
子どもの成績が悪いと、保護者様は「大丈夫だろうか」と心配になります。しかし、焦りから過度に口出ししたり手取り足取り指導したりすると、かえってモチベーションを下げ、自主性を奪ってしまうことがあります。
私自身も、赤点を取ったときに両親は口出しせず見守ってくれました。そのおかげで「自分でやらなければ」と考えるきっかけになり、今でも感謝しています。
もちろん、適度な声かけやサポートは必要ですが、基本は静かに見守る姿勢が大切です。保護者様がぐっと堪えて子どもの自主性を尊重することが、長期的には大きな成長につながります。
3. 数学で赤点回避するための勉強法
赤点を取ってしまっても、1回程度であれば進級や卒業に直結することはほとんどありません。大切なのは、そこで落ち込むのではなく、次の試験に向けてどう改善するかです。
ここでは、赤点を繰り返さないために意識すべきポイントを紹介します。
①数学の苦手意識を克服する
一度「自分は数学が苦手だ」と思い込んでしまうと、モチベーションが下がり、授業を真剣に聞かなくなったり、課題を後回しにしてしまいがちです。こうした状態になると、さらに成績が下がる「負のスパイラル」に陥ってしまいます。
保護者様は、ポジティブな声かけを心がけ、生徒が数学に前向きに取り組めるようにサポートしてあげることが大切です。
②「質問する」習慣を身につける
分からないことをそのままにしてしまうのは、数学の成績を伸ばす上で大きな障害になります。思春期の子どもは「質問するのは恥ずかしい」と感じがちですが、放置すれば理解不足が積み重なり、赤点の原因になってしまいます。
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」という言葉があるように、分からないところはその場で質問する習慣をつけさせましょう。
質問相手は先生だけでなく、塾の講師や数学が得意な友達でも構いません。むしろ友達の方が気軽に聞けて、親身に教えてくれることもあります。実際、私自身もクラスの友達に教えてもらうことで理解を深められた経験があります。
③コツコツ勉強する習慣をつける
赤点を取ってしまう生徒の多くは、そもそも「ノートをきちんと取る」「宿題をこなす」といった基本的な学習習慣が身についていません。
実際のところ、「しっかり勉強したのに赤点になった」というケースは少なく、大半は勉強不足や準備不足が原因です。
赤点回避のために特別な「ガリ勉」をする必要はありません。しかし、宿題を誠実にこなし、授業を集中して聞くなど、最低限の積み重ねは欠かせません。
保護者様も過干渉は避けつつ、コツコツ勉強する習慣を促すことが重要です。私自身も赤点を取った後の試験では授業を真面目に聞き、宿題を丁寧に取り組むようにしました。その結果、次の回では平均点に近い点数を取ることができ、問題なく進級できました。
4. 数学の赤点は誰でも努力で克服できる!
数学は「センスの有無」で決まる科目ではありません。確かに得意・不得意はありますが、基礎を理解し、解法のパターンを身につけることで誰でも克服できる科目です。
私自身も中学3年の時に赤点を取った経験がありますが、授業を真剣に聞き、宿題をきちんとこなすようにしたことで、少しずつ着実に成績を伸ばすことができました。
成績は一気に上がるものではなく、日々の積み重ねが大切です。焦らずにコツコツ努力を続けることで、赤点を回避し、安定して数学の力をつけていけるでしょう。
▼当会では、中高生の受験や、中高一貫校対策が可能です。ぜひあわせてご覧ください。
あわせてチェック|赤点の関連記事
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
東大家庭教師友の会をもっと知る