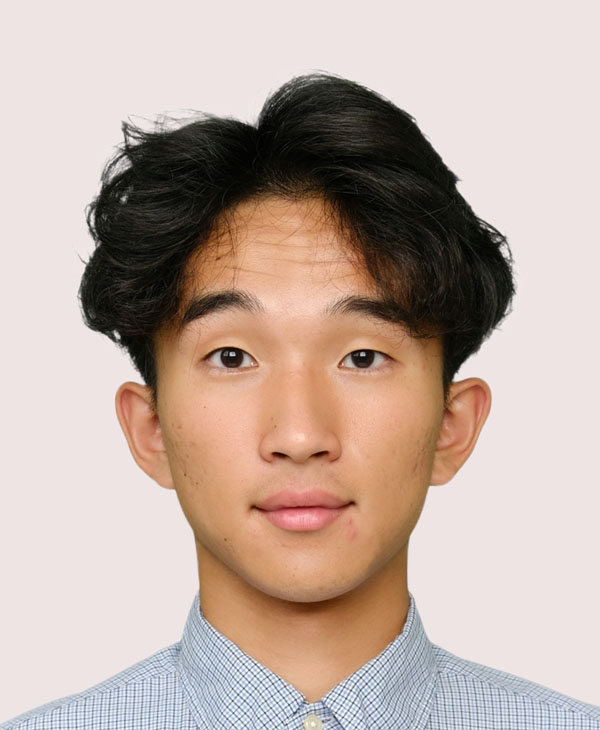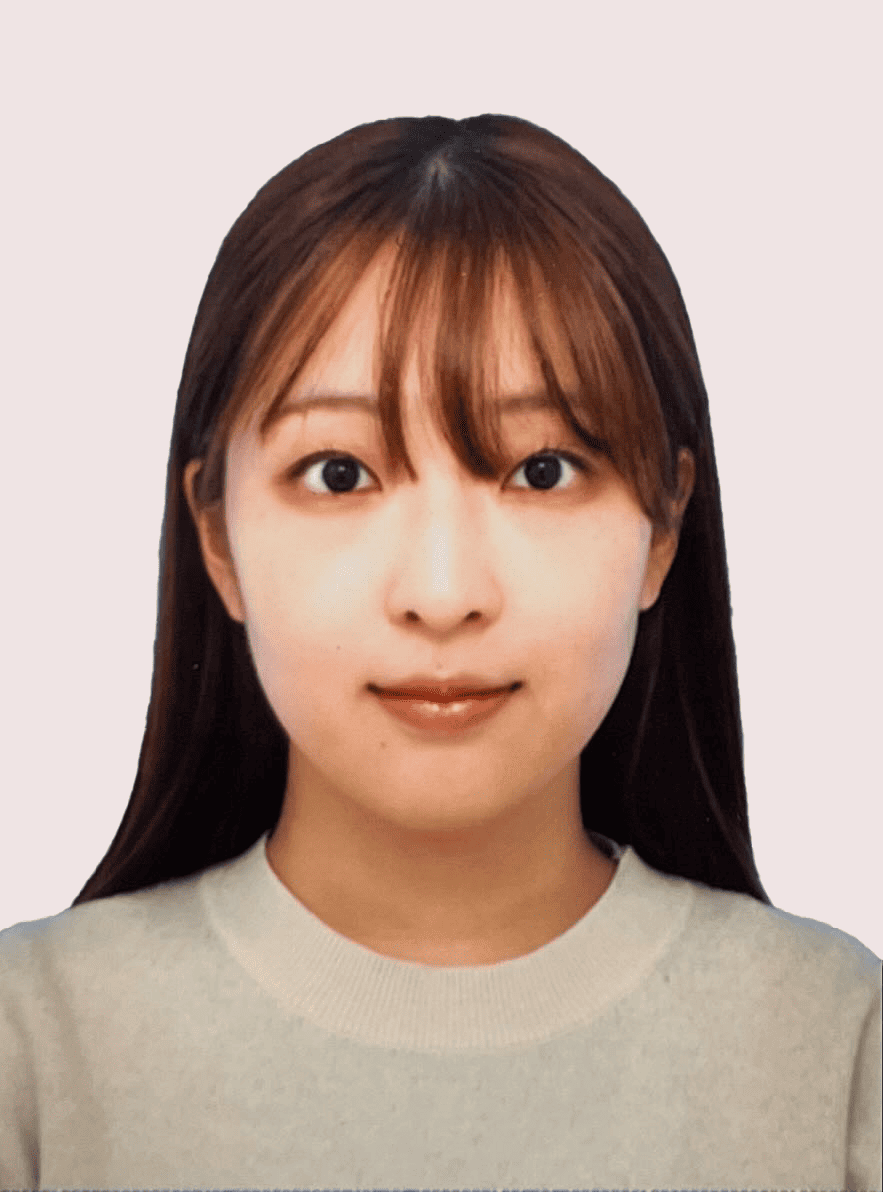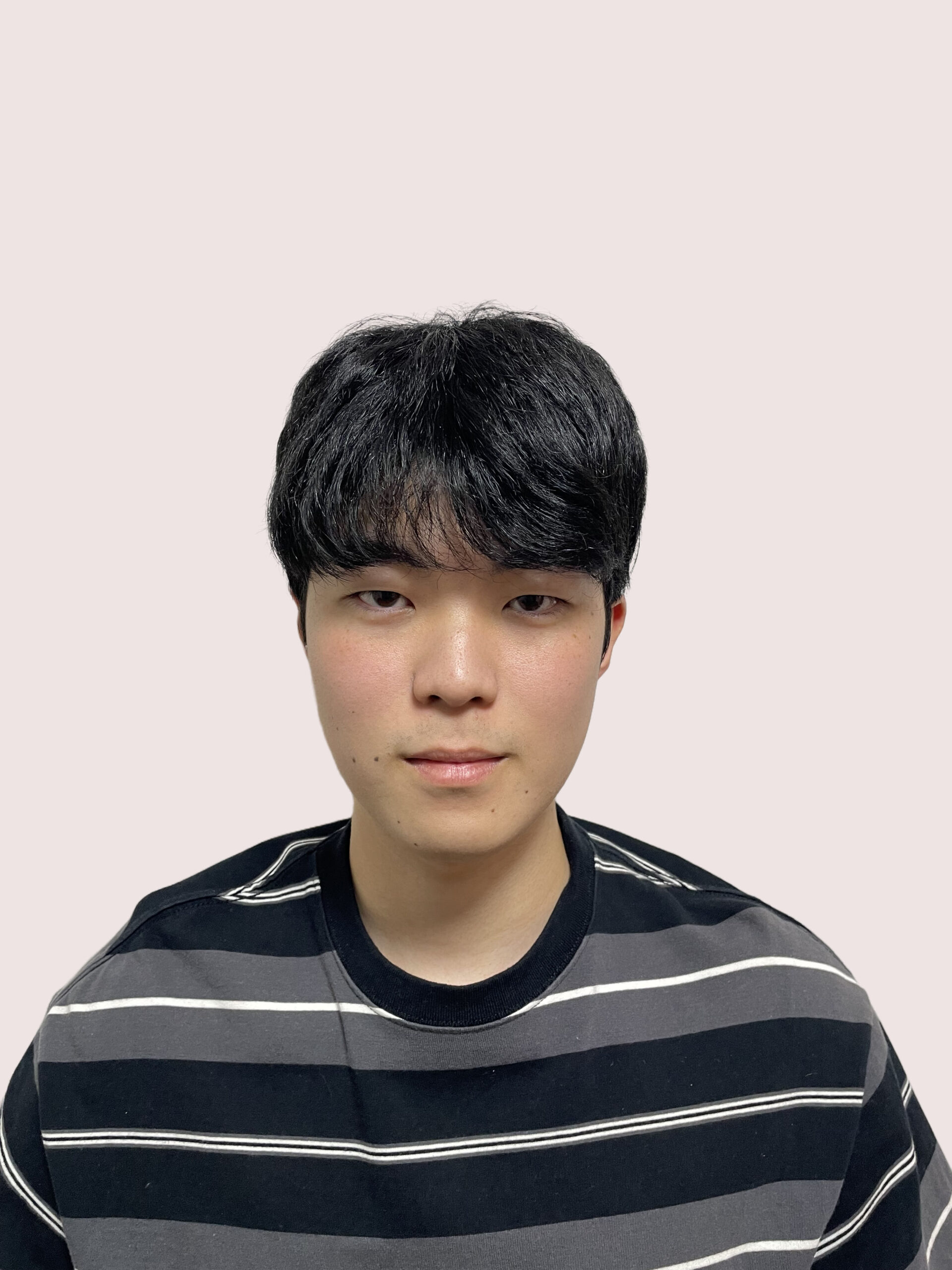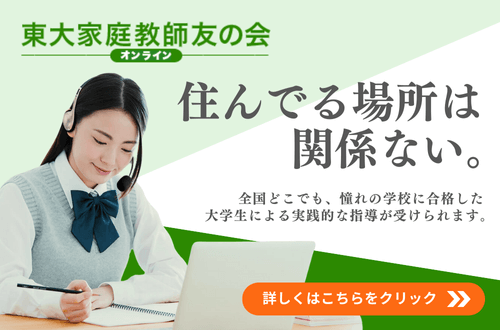![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 【共通テスト英語】リーディング&リスニングで9割達成する勉強法とおすすめ参考書

ここでは、単語編・文法編・問題演習編・リスニング編の4つに分けて、単語力・文法力をつけて効率的な問題演習をするための勉強法とおすすめの参考書を紹介します。
①単語編|共通テスト英語で必要な語彙数と覚え方
|
◉共通テスト英語で求められる単語4,000〜5,000語(英検2級レベル)を覚える ◉単語を見たらすぐに意味が言えるレベルまで覚える ◉単語は例文とセットで覚えて使い方も身につける |
英語の点数がなかなか伸びずに悩んでいる人は、まず単語の暗記と復習から始めるのがおすすめです。意味があいまいな単語をひとつひとつ確実に覚えていくだけでも、共通テスト英語の対策として大きな効果があります。
また、一度覚えたからといって安心せず、自分で復習の間隔を決めて、定期的に単語を見直すことが大切です。忘れかけたタイミングで復習することで、記憶がより定着し、長期的に使える語彙力が身につきます。
▶︎おすすめの暗記法:例文を丸ごと覚える
多くの単語帳には、覚えるべき単語の使用例として短い例文が掲載されています。一見すると遠回りに思えるかもしれませんが、例文ごと覚えることで、単語の正しい使い方や文中での役割、共に使われる前置詞や接続表現まで自然と身につけられます。
このように、単語だけでなくその用法までセットで覚えることで、実践的な英語力が着実に向上していきます。
◉おすすめ参考書
基本的には書店で手に取ってみて、一番自分が勉強できそうだと思った単語帳を選ぶのが良いでしょう。
私は学校から配布された「システム英単語」を使っていました。
各単語に短文の例文がついている上、その例文を読み上げてくれるCDがあるのでおすすめです。
②文法編|共通テスト英語で押さえるべき基礎と学習法
|
◉文法書を一冊選び、最初から最後まで一通り頭に入れる ◉例題を解くことよりも、文法全体の体系を理解するために、文法書を一周する |
使用する文法書は、高校卒業程度の英文法を網羅的に学べるものであれば、特定のものにこだわる必要はありません。まずは、文法書に記載された文法事項を一通り頭に入れることを目指しましょう。文法書に登場する主要な文構造が、すぐに日本語に訳せるレベルになれば十分です。
文法書には例題が豊富に掲載されていることが多いため、つい演習に意識が向き、最後まで読み切れないことがあります。しかし、共通テストでは個別の文法問題は出題されないため、例題をすべてこなすことの優先度はそれほど高くありません。
例題は、自分の理解を確認する手段として最小限活用し、あくまで全体の文法事項に一通り目を通すことを優先しましょう。
③問題演習編|共通テスト英語の解き方・順番
|
◉読解を助けるために、因果・対比・具体例などに使う自分なりの記号を決めておく ◉設問を先に読んでから本文を読み始め、本文は冒頭から飛ばさずにすべて読む ◉設問に答えながら読み進めることで、無駄な読み直しを減らす ◉集中力が続かない場合は、後半の大問から解くなど順番を工夫する |
問題演習に取り組む際、わからなかった単語を調べたり、文意が取れなかった原因を分析したりすることは、もちろん重要です。しかし、それらを意識していても思うように得点が伸びない場合は、以下の4つのポイントを意識してみましょう。
1.自分なりの記号を決める
逆説には三角、関係代名詞には四角など、自分なりの記号を決めて本文中に書き込むことで、内容の把握がしやすくなります。ただし、書き込みに気を取られすぎると本末転倒なので、本文を読みながら自然に手が動く範囲に絞って書き込むとよいでしょう。
2.設問を先に読む
まずは設問を読み、何が問われているのかを正確に把握しましょう。その際、設問の中にキーワードがあれば、それも見落とさずに確認しておくことが大切です。
続いて、本文は冒頭からすべて丁寧に読み進めます。焦って設問に関係のありそうな部分だけを拾い読みしようとすると、十分な英語力がない限り、かえって内容を取り違える原因になります。
3.設問に回答しながら読み進める
問題文を読み進める中で、明らかに設問の答えになりそうな箇所があれば、その都度設問に答えながら読み進めていきます。
ただし、無理に途中で答えを出す必要はありません。答えに迷った場合は、該当しそうな箇所に印をつけて、すぐに先へ進みましょう。このように目印を残しておくだけでも、後から読み直す時間を短縮でき、効率よく解答できます。
4.後半の大問から解き始める
共通テスト英語では、後半になるほど問題文の分量が増えていきます。そのため、試験後半に明らかに読解スピードが落ちる場合は、後半の大問から先に解く方法を検討してもよいでしょう。
私自身は、問題文の量と設問数が増え始める中盤あたりから解き始め、最後まで解き終えた後に最初の大問に戻って解く、という順序で取り組んでいました。この方法に変えたことで、明らかに解答スピードが向上したため、以後この手順を採用するようになりました。
ただし、この解き方には2つのデメリットがあります。
・マークを途中から始めることになるため、マークミスに一層注意が必要になる
・時間が足りなくなった場合、中盤の比較的易しい問題を落とすリスクがある
そのため、まずは実践形式の問題集などで一度試してみて、自分に合っているかどうかを確認することが大切です。もし解答時間に大きな変化がなければ、通常通り最初から順に解く方法をおすすめします。
◉おすすめ参考書
共通テスト形式の問題集は、各予備校から多数出版されています。これらの予想問題集に加え、センター試験の過去問の後半や、大学二次試験の英文なども対策用の教材として活用できます。
④リスニング編|毎日できる練習と復習手順
|
◉リスニングは毎日欠かさず、少しでも英語の音に触れる習慣をつける ◉同じ音源を繰り返し聞き、シャドーイングできるレベルまで定着させる |
リスニング対策でもっとも効果的なのは、リスニングを習慣化し、毎日継続することです。センター試験の過去問や練習問題に取り組むだけでなく、洋楽や英語ニュースなど、自分の興味のある音源も取り入れながら、継続的に耳を慣らしていきましょう。
問題演習を行う際、私は次のような手順でリスニング問題の復習をしていました。
1.問題を解き、答え合わせをする。間違った部分は何度も聞き直す
2.スクリプトの全文を読み、自分の考えていた話の筋とずれがないかを確認する
3.スクリプトを見ながらシャドーイングし、スクリプトを見なくても言えるようになるまで繰り返し聞く
また、試験直前に普段聞き慣れた音源を聞き直しておくことで、英語の音に耳が慣れた状態でリスニング試験に臨めます。
◉おすすめ参考書
センター試験の過去問や共通テストの予想問題に加えて、二次試験のリスニングも対策として使えます。また、洋楽やニュース、インタビューなどもリスニング力向上に有効です。
共通テストのリスニングでは、アメリカ人だけでなく、イギリス人やオーストラリア人の話す英語も出題されます。さまざまな訛りの英語に触れておくことで、当日動揺せずにリスニングを聞けるようになるでしょう。
![]() 家庭教師にご相談
家庭教師にご相談
体験授業も可能です!
2. 【共通テスト英語】リーディングの時間配分!3つのモデル例
共通テスト英語リーディングは大問8つ・80分構成で、時間配分が合否を大きく左右します。とくに、後半の長文や第8問に十分な時間を残せるかどうかが、高得点のカギです。まず、各大問の内容と押さえるべきポイントを整理しておきましょう。
| 大問 | 内容 | ポイント |
| 第1問 | パンフレット・案内文 | イラストや本文から日時や条件をすばやく見つける |
| 第2問 | ブログ記事 | 筆者の意見と事実を整理して読み分ける |
| 第3問 | 物語文 | できごとの順番と登場人物の行動を正しく追う |
| 第4問 | エッセイ・論説文 | 文と文のつながりを考えて自然な流れを選ぶ |
| 第5問 | 複数のメール | やり取りを比べて共通点や違いを読み取る |
| 第6問 | 物語+メール | 形式の違う資料をつなげて内容をまとめる |
| 第7問 | 説明文・記事 | 段落ごとの要点を押さえて根拠を見抜く |
| 第8問 | 複数意見+資料 | 立場を整理して資料と意見の関係を確認する |
時間配分モデル3つ
次に、目標や実力に合わせた3つの時間配分モデルを紹介します。
①標準型
多くの受験生におすすめの基本型です。
時間を均等に割り振って、最後まで解き切る感覚をつかむ時間配分になります。
| 大問 | 時間 |
| 第1問 | 6分 |
| 第2問 | 8分 |
| 第3問 | 10分 |
| 第4問 | 10分 |
| 第5問 | 10分 |
| 第6問 | 12分 |
| 第7問 | 12分 |
| 第8問 | 12分 |
②前半速処理型
英語がやや苦手、読むのが遅めで時間切れやケアレスミスが出やすい人向けです。
前半を高速処理して、後半の長文にしっかり時間を残す時間配分になっています。
| 大問 | 時間 |
| 第1問 | 4分 |
| 第2問 | 6分 |
| 第3問 | 6分 |
| 第4問 | 7分 |
| 第5問 | 10分 |
| 第6問 | 15分 |
| 第7問 | 15分 |
| 第8問 | 17分 |
③高得点挑戦型
読解力・速読力に自信があり、最難関大を狙う人向けになっています。
前半を効率的に突破して、後半の複雑な長文で得点を伸ばす時間配分です。
| 大問 | 時間 |
| 第1問 | 5分 |
| 第2問 | 7分 |
| 第3問 | 7分 |
| 第4問 | 7分 |
| 第5問 | 10分 |
| 第6問 | 14分 |
| 第7問 | 14分 |
| 第8問 | 16分 |
時間配分をこれから固めたい受験生は例1、英語がやや苦手/読むのが遅めで時間切れやケアレスミスが出やすい人は例2、最難関大狙いで前半を高速で処理できる読解力・速読力がある人は例3を目安に取り組んでみてください。
3. 【共通テスト英語】リーディング対策!時間切れになる原因と対処法

共通テストの英語は、全問が長文読解で構成される形式に変わったことで、「時間が足りない」と感じる受験生が年々増加しています。高得点、特に9割以上を目指すには、時間内にすべての問題を解き終えることが大前提。そのうえで、見直しの時間を確保することも重要です。
共通テストの英語が全問長文読解で構成されている以上、「時間内に解き終わらない最大の原因」は、長文を読むスピードが足りていないことだと考えられます。しかし「読むのが遅い」と言っても、その背景にはさまざまな理由があり、人によって原因は異なります。
ここでは、長文を読むスピードが遅くなる主な3つ原因と具体的な対策を紹介します。
原因①:単語力が足りない
ある程度の未知語があっても、長文を読んで設問に答えることは十分に可能です。しかし、知らない単語が増えるほど文脈をつかむのに時間がかかり、読むスピードが確実に落ちてしまいます。
また、「単語は覚えているはずなのに時間が足りない」と感じている人は、単語を思い出すのに時間がかかっている可能性があります。記憶があいまいな単語が多いと、そのたびに意味を思い出す作業が発生し、知らず識らずのうちにタイムロスが積み重なっていくのです。
高得点を狙うためには、単語の意味を「思い出す」レベルではなく、「見た瞬間に理解できる」レベルにまで定着させることが求められます。
▶︎対策:長文を立ち止まらずに読める単語力をつけましょう!
原因②:文法力が足りない
単語の意味がしっかりと定着していても、長文がうまく読めないというケースは少なくありません。その原因のひとつとして挙げられるのが、文法理解の不十分さです。
たとえ単語ひとつひとつの意味がすべて分かっていたとしても、文構造を正しく把握できなければ、文章全体の意味を正確に読み取ることはできません。
とはいえ、共通テストで出題される英文は、それほど複雑な構造ではありません。だからこそ、基本的な文法事項をしっかりと理解し、文の骨組みを素早く見抜けるようにしておくことが、時間内に読み切るための大きな武器となるのです。
▶︎対策:基本の文法事項をしっかりと身につけましょう!
原因③:長文読解に慣れていない
共通テストの英語は、すべての問題が長文読解で構成されています。さらに、問題が進むにつれて文章の分量も増えていくため、どうしても集中力が削がれ、後半になるほど読解スピードが落ちてしまいがちです。完全に疲れずに最後まで解き切るのは難しいかもしれませんが、疲れにくくする工夫は可能です。
たとえば、問題を解く順番を自分に合ったものに調整したり、文章の読み直しを最小限に抑えたりすることで、読解時の負担を軽減し、スタミナ切れを防げます。こうした小さな工夫の積み重ねが、最後まで安定したパフォーマンスを保つ鍵となるのです。
▶︎対策:長文読解の問題集を解き、自分なりの解き方を確立しましょう!
4. 【共通テスト英語】リスニング対策

リスニングの点数が思うように伸びず、途中で対策を諦めてしまう受験生は少なくありません。リスニングの点数を伸ばすことは簡単なことではありませんが、リスニングもリーディングと同じように、正しい方法で継続的に対策を重ねれば、確実に得点力は伸びていきます。
効率よくリスニングの点数を上げるためには、以下の2つの対策が効果的です。
対策①:問題の復習を大事にする
リスニング力を高めるには、毎日継続して耳を慣らすことが何より大切です。特に試験の1週間前からは、毎日リスニング問題に取り組む習慣をつけることで、本番での「聞きやすさ」に大きな違いが出てきます。
ただし、やみくもにリスニング問題を解くだけでは、十分な効果は得られません。演習後は、スクリプトを丁寧に読み、スクリプトを見なくても内容が自然に聞き取れるようになるまで、音源を繰り返し聞くことが重要です。
こうしたトレーニングを通して、最初は聞き取れなかった音やフレーズが徐々にクリアに聞こえるようになります。その過程で、自分の聞き取りの弱点や癖にも気づき、効率的にリスニング力を伸ばしていけるのです。
▶︎問題は何度も聞き直し、自分の苦手を探しましょう!
対策②:問題文の読み方を練習する
共通テストのリスニングでは、図や表と組み合わせた形式の問題が多く出題されます。そのため、こうした視覚情報をいかに効率よく読み取れるかが、得点を左右する大きなポイントとなります。
共通テスト英語のリスニングでは、設問ごとに問題冊子を読むための時間が設けられています。この時間を活用して、問題文や選択肢に素早く目を通し、回答のヒントになりそうなキーワードや数値をあらかじめチェックしておくことが大切です。
あらかじめ注目ポイントを把握しておくことで、音声が流れたときに内容をスムーズに理解でき、正確に答えを導きやすくなります。
なお、選択肢を読むタイミングやスピードには個人差があるため、問題演習を繰り返しながら自分に合ったリズムを身につけていくことが重要です。
▶︎問題演習を数多くこなし、回答の流れを掴みましょう!
5. 【共通テスト英語】2025年度の日程と出題範囲

2025年度の大学入学共通テスト英語の日程と出題範囲を正確に把握しておきましょう。日程と出題範囲を確認することで、試験日までのスケジュール管理や学習計画が立てられます。
2025年度の大学入学共通テスト英語の日程は、以下の通りです。
| 共通テスト英語 | 日程 |
| 外国語 「英語」リーディング |
2026年1月17日(土) 15:20~16:40 |
| 外国語 「英語」リスニング |
2026年1月17日(土) 17:20~18:20 |
※大学入学共通テストの追試験は2026年1月24日(土)及び 25 日(日)です
次に、大学入学共通テスト英語の出題範囲です。
| 出題科目 | 試験時間(配点) | 出題範囲 |
| 「英語」 リーディング |
80分 (100点) |
「英語コミュニケーションⅠ」 「英語コミュニケーションⅡ」 「論理・表現Ⅰ」 |
| 「英語」 リスニング |
60分 (100点) |
リーディングの問題形式
-
大問数や出題形式に大きな変更はありませんが、実用的な文章や複数の資料を比較する問題など、思考力や判断力を問う内容が強化されています。
-
全体の語数は約6,000語と増加しており、速読力や情報整理能力がより一層求められる内容となっています。
リスニングの問題形式
-
形式に大きな変更はありませんが、実際のコミュニケーションを想定した場面設定や、複数の話者によるディスカッションなど、実用的な英語力を評価する問題が出題される傾向があります。
6. 【共通テスト英語】リーディング&リスニングの過去問と平均点
共通テスト英語で得点力を伸ばすには、過去問と平均点のチェックが欠かせません。なぜなら、過去問を分析することで「出題傾向」や「時間配分の難しさ」、そして「どの問題で差がつくか」といった重要なポイントがみえてくるからです。また、平均点を確認すると、目標得点の基準も具体的に定まります。
英語の過去3年分の過去問(本試験)と平均点は、以下の通りです。
| 英語の過去問(本試験) | 平均点 |
| 2024年 英語(リーディング) 解答 |
57.69 |
| 2024年 英語(リスニング) 音声の内容 解答 |
61.31 |
| 2023年 英語(リーディング) 解答 |
51.54 |
| 2023年 英語(リスニング) 音声の内容 解答 |
67.24 |
| 2022年 英語(リーディング) 解答 |
53.81 |
| 2022年 英語(リスニング) 音声の内容 解答 |
62.35 |
引用元:大学入試センター
まずは1年分だけでも構わないので、実際の過去問にチャレンジして、自分の立ち位置を知ることが大切です。平均点を意識しながら、得点戦略を立てることが、共通テスト英語の攻略につながります。
7. 共通テスト英語のリーディング&リスニング対策を始めよう!
今回は、共通テスト英語のリーディング&リスニング対策を紹介しました。
要点をまとめると、以下のようになります。
①共通テスト英語では、速読力・文法力・語彙力・リスニング力の総合力が問われる
-
②単語・文法の基礎を固め、設問の読み方や解答順など実践的な工夫も重要
-
③リスニングは毎日継続し、復習とシャドーイングを徹底することで得点力が伸びる
今日から大学入学共通テストの英語対策をして、高得点を目指しましょう!
東大家庭教師友の会では共通テストの英語の対策に強い家庭教師を多数紹介しています。当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
大学受験英語の指導ができる家庭教師の紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
オンラインでの指導も可能です
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る
あわせてチェック|共通テスト対策の関連記事
共通テスト英語対策のお問い合わせはこちら