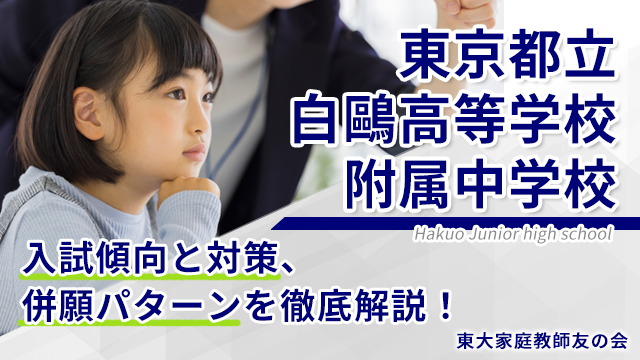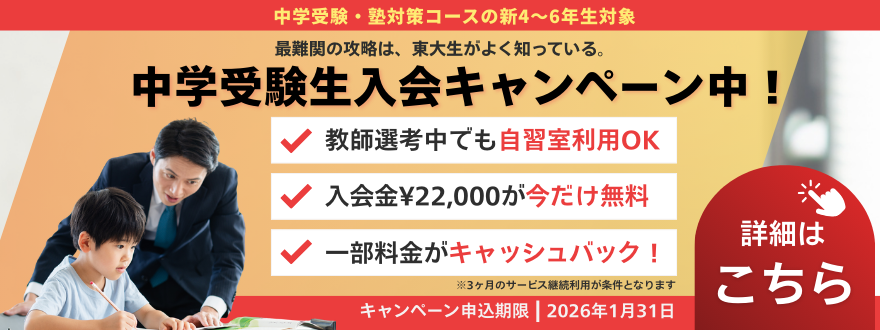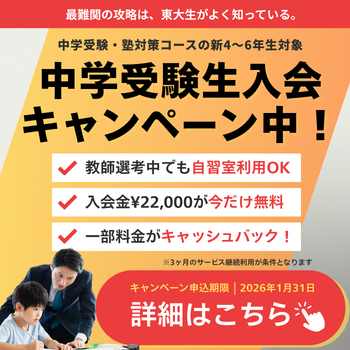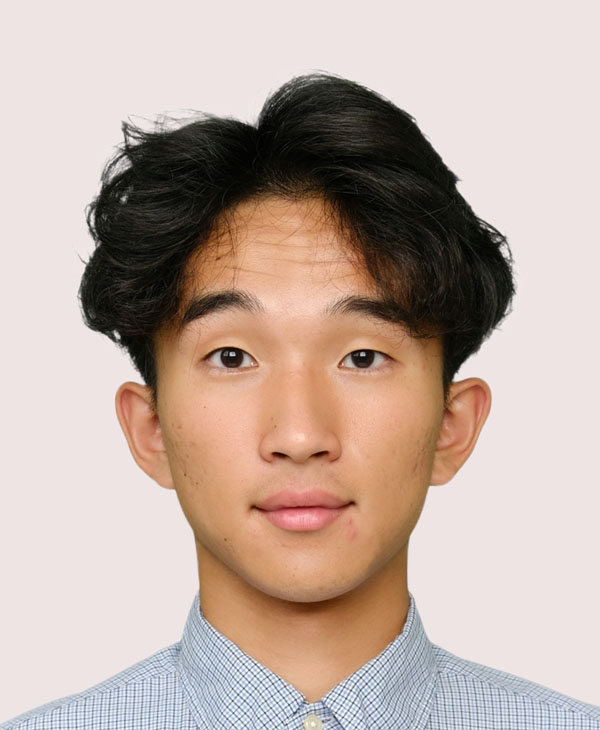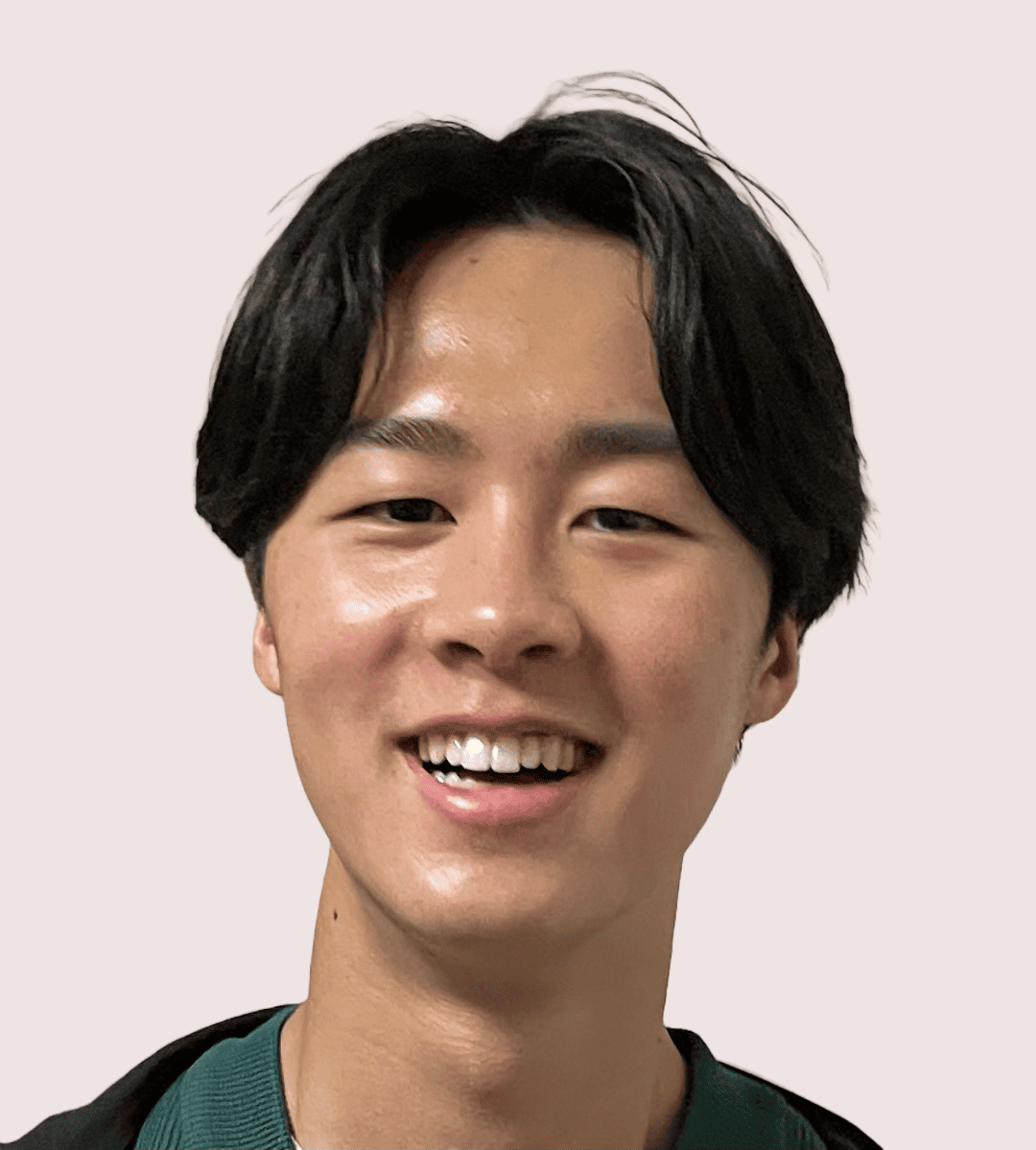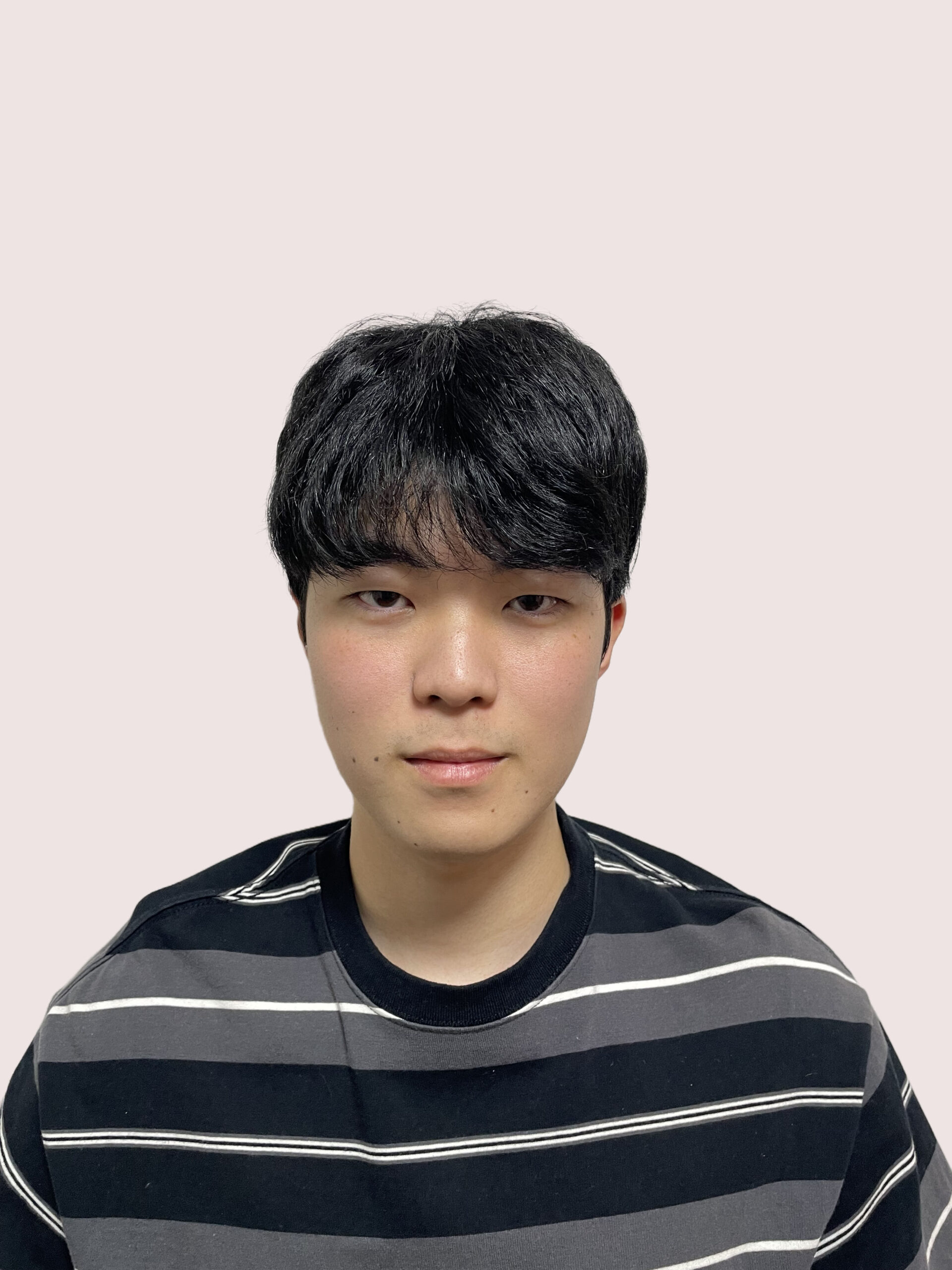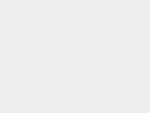![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 東京都立白鴎高等学校附属中学校の偏差値と基本情報

東京都立白鴎高等学校附属中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①東京都立白鴎高等学校附属中学校の偏差値
東京都立白鴎高等学校附属中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」と「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
| 2/3 一般 適性 |
男子 58 |
男子 65 |
東京都立白鴎高等学校附属中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受検する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②東京都立白鴎高等学校附属中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
2005年 |
|
所在地 |
東京都台東区元浅草三丁目12‑12 |
|
アクセス |
田原町駅 徒歩7分 |
| 校種 | 公立共学校(中高一貫校) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 |
・中3で海外研修旅行・TOKYO GLOBAL GATEWAY、オーストラリア短期留学など多数を実施 |
1888年に「東京府高等女学校」として誕生した白鴎高校。都立高校としては日比谷、戸山に次ぎ三番目に長い歴史があります。また白鴎高校附属中学校は、東京都内では初めての作られた公立中高一貫校です。
ここでは、白鴎高校・附属中学校の特色を、伝統文化教育、ダイバーシティ教育、学習・進路指導の3つの視点からご紹介します。
①地域性を活かした伝統文化教育
元浅草の立地を活かし、様々な伝統文化教育に力を入れています。中学での地域めぐりに始まり、音楽の授業での三味線演奏、4年生の「人間と社会」の科目では、地元の伝統行事に参加します。学校設定科目として「日本文化概論」という科目もあり、伝統文化を学ぶ独自のカリキュラムが展開されています。
和太鼓や長唄三味線といった珍しい部活動もあり、様々な場面で日本の伝統文化を取り入れた教育活動を行っています。
②世界で活躍する人材を育てるダイバーシティ教育
海外学校間交流推進校に指定されており、世界視野で考え行動できる人材の育成を目指しています。3年生でのアメリカ西海岸への研修旅行、5年生でのシンガポールを訪問などでは現地の同年代の生徒と文化交流を行います。
留学生の受け入れも盛んで、英語圏だけでなく、フランスや中国などからの留学生も受け入れています。
③中高一貫校の強みを活かした学習指導・進路指導
白鴎高校・附属中学校を代表する言葉として知られる「辞書は友達、予習は命」という言葉。中高一貫校の強みを活かし、予備校や塾に頼らず学校の学習で希望進路の実現させることを目標にしています。
キャリア教育は、中学1・2年生の職業講話や職業体験などを通じて「なりたい自分」をイメージすることから始まり、その実現のための具体的な取り組みにつなげていきます。
2. 東京都立白鴎高等学校附属中学校の入試傾向

白鴎高校附属中学校には、海外帰国・在京外国人生徒枠募集と特別枠募集、一般枠募集の3つの生徒募集枠があります。ここでは、それぞれの入試枠の概要や試験内容、2024年度の適性検査の特徴的だった問題・合否を分けた問題について説明します。
①入試日程
海外帰国・在京外国人生徒枠募集枠、特別枠については、応募資格等を募集要項で確認してください。
2025年度の試験日程は、
|
【海外帰国・在京外国人生徒枠募集】:1月24日(金) |
です。
②海外帰国・在京外国人生徒枠募集
海外帰国・在京外国人生徒枠募集は、作文(600点)と面接(400点)の総合1000点満点で合格候補者を決定します。
募集人数は男女合わせて30名で、2024年度の実質倍率は、男子が1.5倍、女子が1.3倍でした。
作文・面接ともに、英語か日本語、どちらか一方の言語を選択できます。
(1)作文
作文の試験は45分間で行われます。2024年度は「東京都中学生海外研修プログラム」に応募するとして、参加を希望する理由を501字~600字以内で作文に書く、という問題でした。その際、自分がこのプログラムに参加するにふさわしい理由と、プログラムに参加するまでの2年間の学校生活をどのように過ごしたいかに触れることが条件です。日本語・英語とも、作文の課題は同じです。
文字数などから、
|
第一段落:自分がプログラムに参加したい理由 |
という流れで書くのがよいでしょう。また、最後に、プログラムで学んだことをその後の学校生活や人生の中でどのように活かしていきたいかについて書けると、より高得点が狙えるかと思います。
(2)面接
面接も作文同様に、日本語・英語ともに問われる内容は一緒です。
白鴎高校附属中学校の海外帰国・在京外国人生徒枠の面接では、一般的に帰国生入試でよく問われる、志望理由や海外経験をどのように活かしていきたいかなどの質問に加えて、時事的な内容が問われる点が特徴です。
時事的な質問では、まず面接官が、あるテーマに関して説明する文章を読み上げます。その後、テーマに関連して、自分の考えを述べる問いを複数問われます。
例えば2022年度は、「移民」がテーマの説明を聞き、
|
・移民を受け入れるメリットは何だと思うか |
などが問われたようです。
自分の考えを問われるため、日頃から社会の動きに目を向け、何が論点で、それに対して生徒様がどのように考えるのかをご家庭でも話題に出すようにすることが、面接の対策にもつながります。
③特別枠募集
特別枠募集は、囲碁・将棋、邦楽、邦舞・演劇の分野に継続して取り組み、上級の資格や卓越した能力のある者を対象にした入試です。
報告書(200点満点)、面接(400点満点)、実技検査(400点満点)の合計1000点満点で合格者を決定します。
募集人数は男女合わせて6名以内です。2024年度は11名が受検し、4名が合格しています。
(1)報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表の成績を点数化したものです。
各評価の評定を、
|
評定3=20点 |
とし、それらの合計(360点満点)を200点満点に換算します。
(2)面接
面接では「志望動機や意欲等を総合的にみる」とあります。志望動機や入学後にしたいことなどのほかに、お稽古事などについても質問されることが予想されます。通常の面接練習に加えて、対策をしておきましょう。
(3)実技試験
囲碁・将棋:専門棋士との対局
邦楽分野、邦舞、演劇:出願時に提出するDVDにより専門家が判断
となっています。
➃一般枠募集
一般入学者は、小学校5・6年生の成績に基づく報告書と、試験日当日の適性検査の結果によって決定します。
配点は、報告書(250点満点)、適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(それぞれ試験時間は45分間、100点満点を250点満点に換算)の1000点満点です。
試験問題は、適性検査Ⅰ・Ⅱが都立中高一貫校の共通作成問題、適性検査Ⅲが白鴎高校附属中学校の独自作成問題です。
募集人数は男女各85名で、2024年度は男子が3.1倍、女子が4.9倍でした。
(1)報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表の成績を点数化したものです。
各評価の評定を、
|
評定3=20点 |
とし、それらの合計(360点満点)を250点満点に換算します。
(2)適性検査Ⅰ
適性検査Ⅰは、文章の内容を的確に読み取ったり、自分の考えを論理的で適切に表現したりする力をはかります。2024年度は例年同様、二つの文章をもとにした読解問題と作文の問題の形式でした。
ここでは、適性検査Ⅰの山場、〔問題3〕の作文について解説します。2つの文章の内容に触れながら、これから学校生活で仲間と過ごしていく上で言葉をどのように使っていきたいか、自分の考えを400~440字で書きます。
まず文章1、2のどちらの考え方を踏まえて書くのかを決めましょう。文章1は短歌を繰り返し心の中でつぶやくことで自分の気持ちを保つことができるという内容で、文章2は人々の気持ちを想像して勉強していくうちにすばらしい俳句が生まれるという内容でした。
意見や理由を書きやすかったり、経験などの具体的な内容と結びつけて考えられそうな文章を選びましょう。構成としては、
|
<内容1>:選んだ文章の筆者の主張と、そこからどのように言葉を使っていきたいかという自分の考えを述べる |
という総括型が最も書きやすいでしょう。問題に「これから学校生活で仲間と過ごしていく中で」とあるため、今後の中学校生活の中で仲間との関わる場面を具体的にイメージして書くことができるかが重要です。
作文では自分の経験や考えを具体的に示すことが求められます。日頃から自分の考えを持ち、それを文章として書く練習をしましょう。また、良い作文を書くためには、豊富な語彙力とそれを正しく運用する力が必要です。使いこなせる言葉の量を増やしていけるように、日頃から読書に親しんだりする姿勢は大切にしましょう。
(3)適性検査Ⅱ
適性検査Ⅱは、資料から情報を読み取ったり、課題に対して論理的に思考・考察する力をはかります。2024年度は、大問1が算数の規則性に関する問題、大問2が公共交通機関の利用を題材にした資料の読み取りと分析についての問題、大問3が摩擦についての実験や観察の問題でした。
ここでは、大問2の〔問題2〕を説明します。この問題はある町で「ふれあいタクシー」の取り組みが必要になった理由と、「ふれあいタクシー」導入の効果について、会話文と4つの図表から考えられることを説明する問題です。
この問題を解くためのポイントは、
|
・複数の資料から読み取れる内容を組み合わせて考えることができたか |
という2点です。
「ふれあいタクシーの必要性」は、資料から路線バスの平日一日あたりの運行本数が減ったことに加えて、人口の減少、75歳以上の高齢者が人口に占める割合の増加が読み取れることから、人口が減少し、路線バスの本数が減少したE町が、移動することに困っている人を対象にした交通手段を用意するため、などとまとめるとよいでしょう。
「ふれあいタクシーの効果」は、1か月に20回まで利用可能で、かつ一定額以上は町が利用料金を負担してくれるため、利用者の負担がそれほど大きくないことが読み取れると説明しやすくなるでしょう。実際に、E町の75歳以上の人の90%以上が利用していることから、75歳以上の多くが利用し、買い物や病院へ行けるようになったことをまとめます。
解答しなければならない内容を取りこぼすことがないように、まずは丁寧に問題文を読み込み、出題者が何を求めているのかを把握したうえで、論理的に考察し、的確に表現する力が必要になります。会話文や資料自体はそれほど複雑ではありませんが、数値の読み取りの要素が強くなっている傾向があるので気を付けて取り組んでいきたいですね。
(4)適性検査Ⅲ
適性検査Ⅲは、身近な課題に対して科学的・数理的な分析を行い、総合的に考察して判断・解決する力をはかります。大問1が、白鴎高校附属中学校の校舎と思われる校舎を題材にした問題で、これぞ独自作成問題と言えるような問題でした。大問2は料理を題材とした問題で、比較的頻出のパターンと言えます。
ここでは、大問1について解説しましょう。
|
〔問題1〕 |
|
〔問題2〕 |
|
〔問題3〕 |
問題2、3は比較的平易な問題で、必ず正解したい問題でした。基礎・基本が定着しているかどうかを確認する問題だったと言えそうです。
(5)出題形式の似ている学校は?
出題形式の似ている学校としては、国公立中学校をはじめとする適性検査・思考力型の入試問題を行っている学校が挙げられます。
また共栄学園中学校は、白鴎高校附属中学校と両国高校附属中学校の出題傾向を踏襲した「適性検査入試」を行っています。ですので、共栄学園中学校の過去問も、参考になることでしょう。
3. 東京都立白鴎高等学校附属中学校の受検対策

伝統校、そして進学校として人気のある白鴎高等学校附属中学校。合格に向けて、いつ・どんな対策をしたらいいのか、過去問にはどのように取り組むのかよいか、家庭で保護者様ができるサポートにはどのようなものがあるかなど、ここでは、具体的な受検対策方法について解説します。
①【時期別・教科別】いつ、何をするべき?
中学受検を意識するご家庭の増える小学校4年生から受検直前期まで、時期別・教科別にどのような点に注目して、何をしていけばよいのかをご紹介します。
(1)小学4年生
この時期はまず学習習慣を定着させ、都立一貫校の入試に必要な、思考力・分析力・表現力の土台となる4教科の学習にしっかり取り組み、苦手を作らないことが大切です。
<算数>
都立一貫校の入試でも出題される、周期算や植木算などの学習に取り組み、桁数の多い計算や小数・分数を含む計算も、素早く正確に解けるように練習しましょう。
<国語>
興味・関心を広げる意味でも、広く様々な本を読むようにしましょう。さらに、本の内容を簡潔にまとめられるようにしておくと、作文を書く際の練習にもつながります。
<理科・社会>
身近な事象に幅広く興味を持てるよう、様々な体験・経験ができるようにしましょう。科学館や博物館などに行って本物に触れる経験をするのも効果的です。
(2)小学5年生
都立中高一貫校受検に必要な「報告書」の対象になるのは5年生から。主要4科目に限らず、すべての科目で学校の学習活動に十分に取り組み、評定をとっておくことが大切です。
<算数>
基礎計算の正確さとスピードを鍛えるとともに、論理的に考える力や条件を整理する問題の解き方などを身に着けましょう。複雑な文章題では、式と答えだけでなく考え方もメモするように意識しましょう。
<国語>
知っている言葉だけではなく、使いこなせる言葉を増やせるよう、語彙の習得に努めましょう。
<理科・社会>
学習したことが身のまわりのこととどのようにつながっているのか、関連をみつけながら知識の定着を図りましょう。
(3)小学6年生(4月~6月)
<算数>
適性検査Ⅲの独自作成問題を意識し、条件を整理する問題や図やグラフを書く問題を中心に演習を重ねましょう。
<国語>
読解問題に力を入れましょう。筆者の主張や表現の意味することを記述させる問題は頻出です。答え合わせの際には、正解していても必ず根拠を確認しましょう。
<理科>
実験や観察の過程を説明したり、結果を分析・考察したりする問題の演習を行いましょう。重要なデータには印をつけるなど、速く・丁寧に解くためのコツを身に付けましょう。
<社会>
地図やグラフなどの、資料を使った問題の対策をしましょう。問題文や会話文から出題者の意図を読み取れるとよいです。
(4)小学六年生(7月~8月)
<算数>
頻出の条件の整理、場合の数などの問題の演習をしましょう。根気強さが求められるので、時間が十分にある夏こそ、じっくり向き合えるチャンスです。
<国語>
作文の対策に力を入れましょう。評論文では、読んだ文章のキーワードになる言葉を見つけたり、筆者の主張を要約したりする練習をすると効果的です。
<理科・社会>
複数の資料を総合的に活用する問題の対策を行いましょう。どの資料から何が分かるのか、情報を適切に分析し、記述式の問題でしっかり得点できるようにすることが大切です。
(5)小学六年生(9月~11月)
秋はいよいよ過去問に挑戦しましょう。過去問の解き方については、このあと詳しくお伝えします。
演習のあとは丸付けをするだけではなく、その問題の注目すべきポイントや別解など、自分の答案と解答・解説をよく見比べて、苦手や弱点などの気付いたことをメモし、学習を進めましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
受検直前期のこの時期は、出題形式の似ている他校の過去問なども活用しながら問題演習に取り組んで仕上げをしていきましょう。
埼玉や千葉などの学校も受検する場合は、本番に向けての体調やモチベーション管理の練習をしましょう。
②【過去問】いつやる?どうやる?
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的は2つあり、1つはは、出題形式を知ったり傾向を掴むため、もう1つは時間の感覚を掴むためです。入試本番では、決められた時間で少しでも多く点数を取る必要があります。
限られた時間でどの問題を優先し、どの問題を後回しにするのかを判断する力はもちろん、最後まで集中力を切らさないようにする訓練も必要です。ですから、過去問に取り組む時には、入試本番と同じスケジュールで解いてみましょう。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入試範囲の学習が一通り終わり、間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある6年生の秋(9月から11月)ごろから取り組むことをお勧めします。傾向が掴めて来たら、似た出題形式の学校の過去問などにも挑戦しましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第一志望なら5年分程度、併願校として受検する場合も、2・3年分は解きましょう。白鴎高校附属中学校の独自作成問題である適性検査Ⅲはできるだけすべて解くことをお勧めします。
過去問は何度も繰り返し解く必要ありません。できる問題を何度も繰り返し解くよりも、今できていないものを一つでも多くできるようにすることの方が、合格への近道だからです。その分、過去問演習で間違えた問題は時間をかけて復習し、解けるようにしましょう。
③【家庭でできる!】保護者様のサポートとは?
(1)日本の伝統文化に親しむ
白鴎高校・附属中学校では、日本の伝統文化の継承を掲げています。日本の伝統文化に親しむ姿勢を持つことは入学後の学習活動にも繋がってくるでしょう。
特別枠入試の対象になるようなお稽古事でなくとも、カルタやけん玉のような身近な昔遊びから興味関心を広げていきましょう。
(2)生徒様ご本人の成長に着目して、前向きな声掛けを
生徒様と向き合っていると、つい保護者様ご自身やご兄弟、他の生徒様と比較してしまいたくなってしまいますよね。ですが、生徒様一人ひとり、学習に集中できる環境や得意・不得意、やる気に火が着くタイミングは異なります。
他の人と比べたくなる気持ちをぐっと堪え、生徒様ご本人の変化に目を向けるようにしましょう。それが、多感な時期の生徒様の自尊心を守ることにもつながります。
生徒様が少しでも前向きな気持ちで自分から学習に向き合えるような、「向学心」を伸ばすよう心がけましょう。
(3)健康管理とメンタル面のサポートをする
心身ともに大きく成長する小学校高学年。多感な時期であるとともに、普段の学校生活に加えて受検勉強と、大人が想像する以上に忙しく、負担が大きいものです。大人の気が付かないところで不安を抱えていたり、プレッシャーと戦っていたりしています。
だからこそ、健康管理とメンタル面のサポートは、保護者様にしかできない、最も力を入れていただきたいサポートです。
受検本番はもちろん、生徒様が一日一日をよりよい状態で過ごせるように、食事や睡眠時間等のサポートに加え、生徒様がストレスを抱えたりした際に相談しやすい関係作りや、一人で心を落ち着かせたり、集中したりできるような環境づくりを行ってください。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 東京都立白鴎高等学校附属中学校志望を受ける際の併願パターン
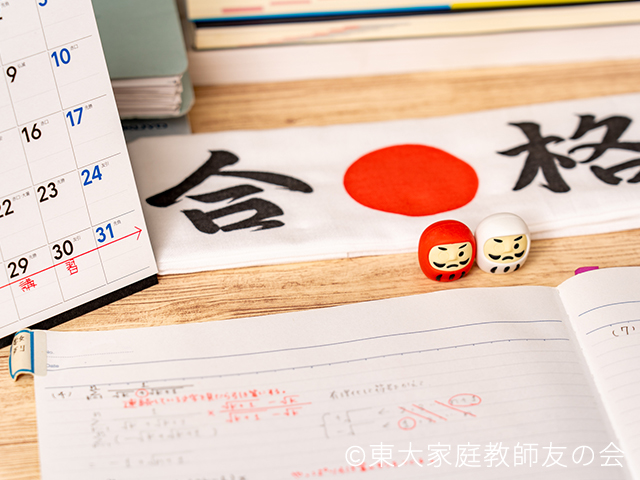
ここでは、ライターが出会った生徒様の併願校を参考に、白鴎高校附属中学校の一般募集枠の受検を検討するみなさんにおすすめの併願校をご紹介します。
立地の点からも、広尾学園小石川中学校や安田学園中学校、開智日本橋中学校を併願する生徒様が多い印象です。
なお、この併願校情報は2024年度の入試をもとに作成しています。2025年度の入試情報に関しては各校の募集要項を必ずご確認ください。
①同偏差値帯併願パターン
白鴎高校附属中学校と偏差値帯が近い学校を併願するパターンです。安田学園中学校や開智日本橋中学校は、適性検査型の入試も行っているため、白鴎高校附属中学校や両国高校附属中学校を受検する生徒様の併願が多いです。
(1)1月入試
|
・専修大学松戸中学校 |
(2)2月1日
|
・広尾学園小石川中学校 |
(3)2月2日
|
・城北中学校 |
(4)2月4日以降
|
・成城中学校 |
②適性検査・思考力型入試を重視した併願パターン
こちらは、都立中高一貫校を目指している受検生をメインのターゲットに行われる、適性検査型や思考力型、公立型などと呼ばれる入試を実施する学校を中心に併願するパターンです。
(1)1月入試
|
・昭和学院中学校 |
(2)2月1日
|
・宝仙学園理数インター中学校 |
(3)2月2日
|
・宝仙学園理数インター中学校 |
(4)2月4日以降
|
・順天中学校 |
5. 東京都立白鴎高等学校附属中学校の受験対策をはじめよう!
一般枠での入学者は他の都立中高一貫校と同様に、小学校5・6年生の成績に基づく報告書と、試験日当日の適性検査(IとⅡは都立中高一貫校の共通作成問題、Ⅲは独自作成問題の総合得点で決定します。作文の配点が比較的大きいため、しっかり準備をして試験に臨みましょう。
伝統文化の継承を掲げる学校ですので、生徒様が日本の伝統分野に興味や関心を持てるような工夫ができるとよいでしょう。特に保護者様には、生徒様ご本人の成長に目を向けた声掛けを行い、健康面とメンタル面での後押しをしていただければと思います。
東大家庭教師友の会では実際に東京都立白鷗高等学校附属中学校に合格した家庭教師による指導を受けることができます。無料体験授業もございますので、まずは一度ご相談ください!
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
白鷗中学の受験対策なら東大家庭教師友の会
他の学校の入試傾向・受験対策