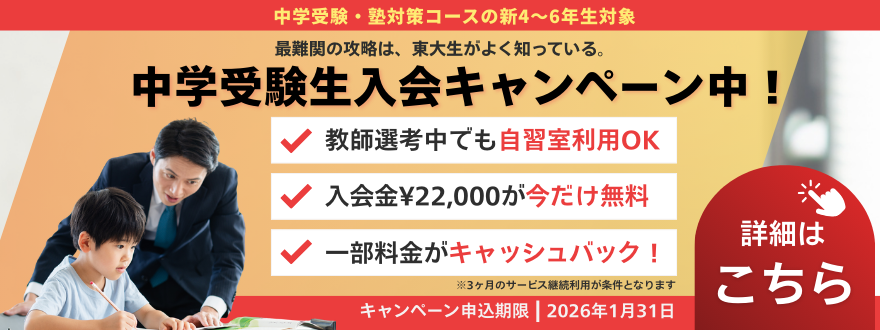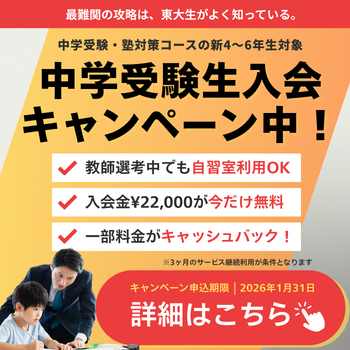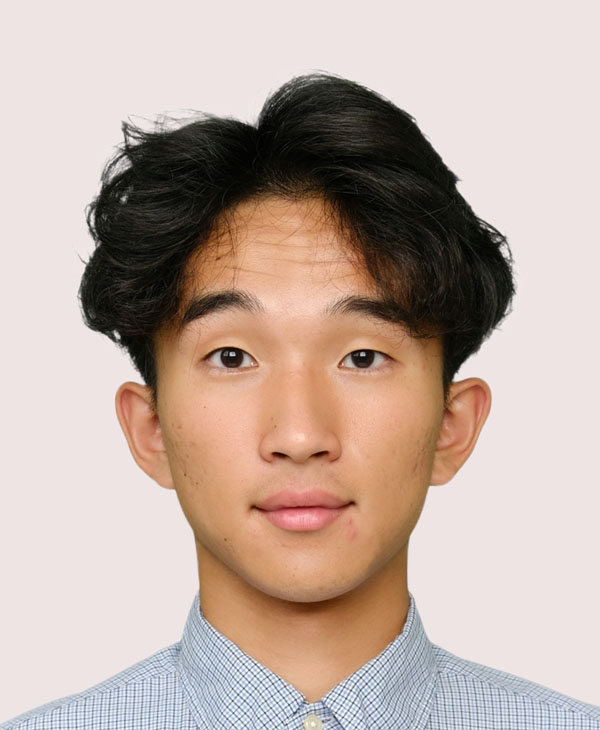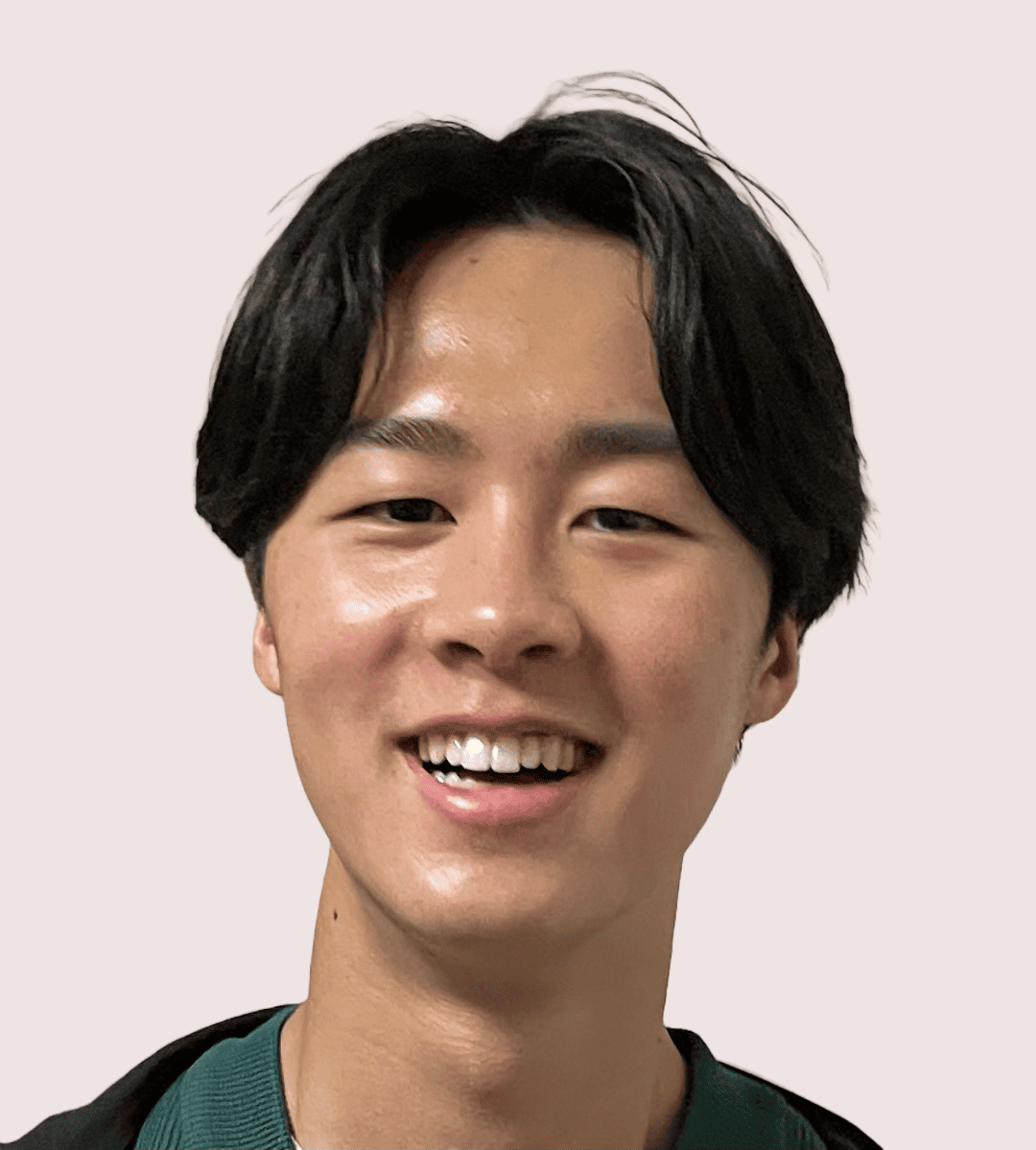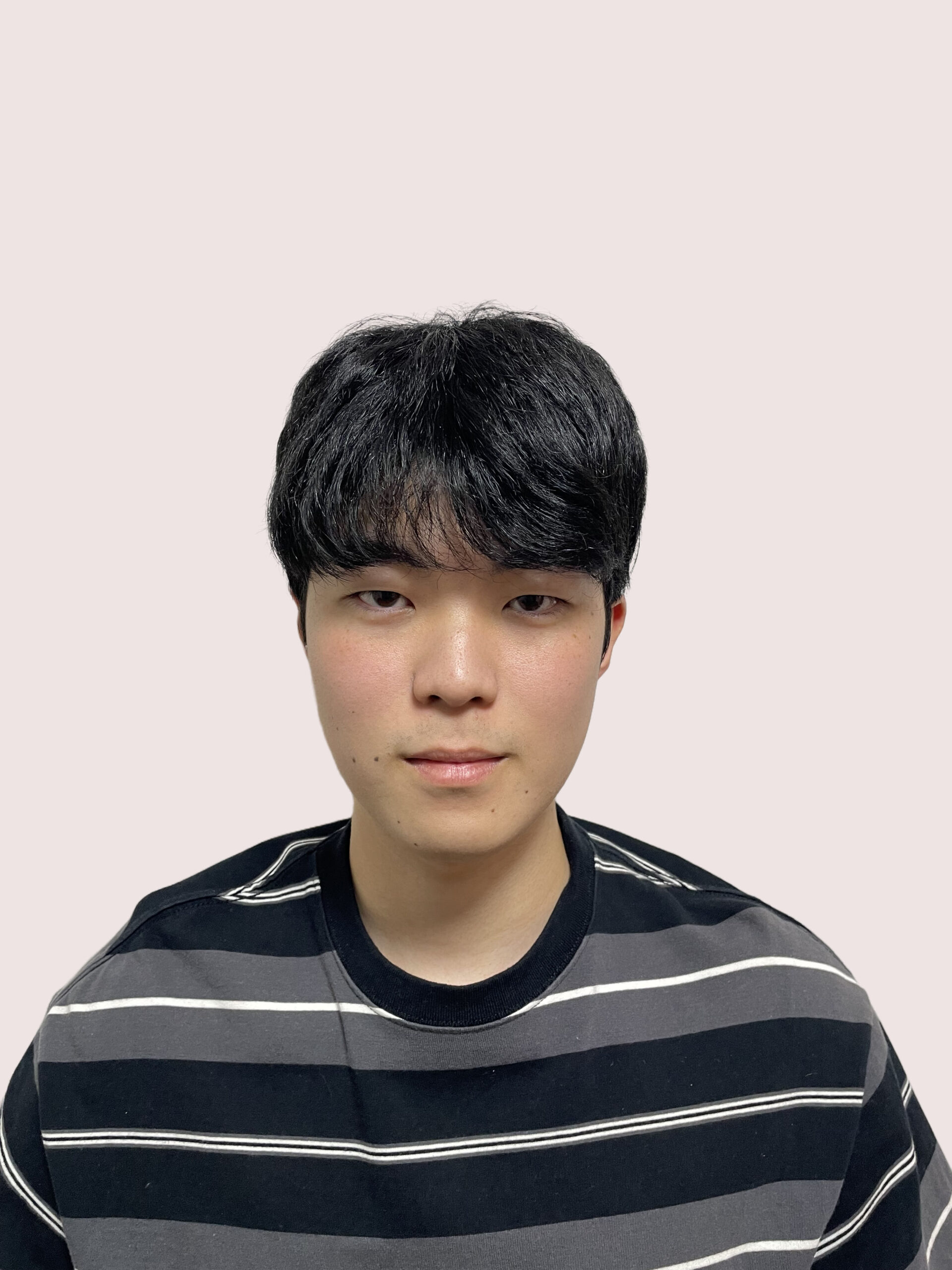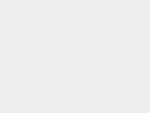![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の偏差値と基本情報
日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の偏差値と基本情報について紹介します。
①日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の偏差値
日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」と「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
|
2/1 |
男子 54 |
男子 64 |
|
2/2 |
男子 55 |
男子 66 |
|
2/3 |
男子 55 | 男子 68 |
日本学園中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受験する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1885年 |
|
所在地 |
東京都世田谷区松原2-7-34 |
|
アクセス |
京王線・井の頭線「明大前」駅から徒歩5分 |
| 校種 | 私立・男子校(2026年から男女共学) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | 農業体験、漁業体験、語学研修など、普段の生活では体験できない行事 |
| 部活動 | 運動部17、文化部13 |
1885年に創設された東京英語学校を前身とする伝統校、日本学園中学校。吉田茂元首相や日本画家の横山大観など優れた業績を残す多くの逸材を輩出してきました。
2026年には明治大学の系列校として共学となり、新しく明治大学付属世田谷中学校と名称が変わります。約7割の生徒様が明治大学に進学出来る体制に向けて計画を進めています。
2. 日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の入試傾向
日本学園中学校の入試概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|
対象入試 |
一般入試のみ |
|
選択科目 |
4科(算数・国語・理科・社会)もしくは2科(算数・国語)選択可能 |
|
試験時間 |
算数:50分 国語:50分 理科:30分 社会:30分 |
|
配点 |
算数:100点 国語:100点 理科:50点 社会:50点 |
|
合格基準 |
得点率65%程度(明治大学系列後に上昇) |
| 優遇措置 | なし |
| 出題傾向 | 記述問題が少なく、基本〜標準的な問題 |
ここからは日本学園中学校の入試傾向について、教科別に紹介します。
①算数
例年、大問6題の出題で、大問1番が計算問題、大問2番が小問集合、大問3番以降が、単元別の問題となっています。
頻出単元は、図形・速さ・規則性・食塩水です。全体としては、基本〜標準的な問題です。基礎をしっかりと定着させることが大切です。この形式は、第一回〜第三回までで変わりありません。
| 大問 |
出題傾向 |
|
【大問1】 |
基本〜標準的な問題 |
|
【大問2】 |
基本〜標準的な問題 |
|
【大問3】 |
「図形」:平面図形・立体図形(面積・体積・角度・相似) 「速さ」:旅人算・点の移動・水量グラフ 「規則性」:数・図形の規則性 「食塩水」:問題集でよく見る形式 |
②国語
例年、大問3題の出題で、大問1番が漢字の読み書き、大問2番が物語文、大問3番が説明文の形式です。
物語文・説明文共に、文章量が多いため、長い文章を読む集中力が必要です。設問は、語彙・抜き出し・正誤選択・接続詞などが出題されており、記述問題の出題は、あまりありません。しかし、実質記述問題と変わらない設問はあります。
| 大問 |
出題傾向 |
|
【大問1】 |
基本的な漢字の読み書き問題 |
|
【大問2】 |
文章量が多い、語彙・抜き出し・正誤選択・接続詞、実質記述問題 |
|
【大問3】 |
文章量が多い、語彙・抜き出し・正誤選択・接続詞、実質記述問題 |
全体としては、長文を読む集中力が必要であり、語句の意味を正確に理解し、指定された部分から根拠を見つけ出す力が求められます。
過去問で形式に慣れておきましょう。
③理科
例年、理科は大問4題で構成され、物理、化学、生物、地学がバランスよく出題されています。
設問形式は一見すると記号選択問題が多いように見えますが、実際には計算問題の答えを選択させる形式が一定数含まれており、見た目以上に難易度が高い試験となっています。
| 分野 |
出題傾向 |
|
物理 |
計算問題主体 てこ、電気、音、浮力、光が頻出 |
|
化学 |
計算問題主体 水溶液・気体に関するグラフ・表問題、中和計算が多い ※2024年度第1回も中和に関する水溶液の計算問題が出題 |
|
生物・地学 |
知識問題が多く出題 時事問題が出題されることもある |
➃社会
例年、社会は大問3題構成で、地理・歴史・公民がバランスよく出題されており、全体的に基本〜標準レベルの問題が中心です。しかし、2024年度第一回では、これまでにない記述問題が2題出題されました。一つは問題文に基づき説明する問題、もう一つは資料を読み取って答える問題でした。いずれも短い記述ではありましたが、対策をしていない生徒様にとっては難しく感じられた可能性があります。
このような記述問題は今後も出題される可能性があり、成城中学校や高輪中学校の過去問を参考に、記述問題への対応力を養うことが重要です。
| 分野 |
出題傾向 |
|
地理 |
地形・都道府県・都市、雨温図・統計・地形図が頻出 地図をベースにした学習が必要 |
|
歴史 |
時代ごとの有名人物・出来事の暗記が必須 年号暗記、できごとの順番、史料の確認が必要 |
|
公民 |
国会・日本国憲法が頻出 裁判制度、選挙制度、日本国憲法の条文・権利の学習が必要 |
⑤問題の形式等が似ている学校
全体的な傾向として、日本学園中学校の入試は京華中学校に似ています。特に、国語の穴埋め問題は京華中学校の問題が参考になります。
さらに、難易度が上がった場合に備えるなら、高輪中学校や明治大学付属中野中学校の問題も確認しておくと良いでしょう。これらの学校の問題はやや高いレベルですが、しっかりと対策をしておけば万全です。
3.日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の受験対策
日本学園中学校は、これまで一貫して基本から標準レベルの問題が中心に出題されており、その出題傾向に大きな変化は見られません。
全教科において、細かなミスが大きな失点につながりやすいため、どんな小さなミスも見逃さず、正確に解答することが求められます。
また、今後の入試では競争の激化や問題難化が予想されるため、基礎の徹底に加えて応用力を養うことも重要です。確実に得点できる力を身につけつつ、難化にも対応できる柔軟な準備を進めましょう。
| 教科 |
出題傾向 |
対策 |
|
算数 |
基本~標準問題が中心 図形・速さ・規則性・食塩水が頻出 |
・基礎を徹底させる ・「プラスワン」「ステップアップ」で応用力も身につける |
|
国語 |
抜き出し問題が多く、記述をベースとした問題が出題 | 根拠を見つける練習をする 長文読解に慣れるため読書習慣をつける |
|
理科 |
計算問題が中心 生物・地学は知識問題が多い |
計算問題は標準レベルを確実にできるようにする 知識問題は暗記を徹底させる |
|
社会 |
広範囲から基本~標準問題が出題 資料からの記述問題も出題 |
資料から解答を導く記述問題の練習をする |
①時期別・教科別対策
(1)小学4年生
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
・地理分野の学習を地図帳で確認しながら進める ・地形・都道府県・都市・雨温図・統計・地形図を学習する ・旅行を通じた地理の学習をする |
(2)小学5年生
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
・歴史を学び、全体的な流れを理解しながら暗記する ・できごとの時代と年号を確認し、反復学習をする ・地理の復習も時間を見つけて行う |
(3)小学6年生(4月~6月)
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
|
(4)小学6年生(7月~8月)
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
・過去問を3回分解き、記述問題対策を強化する ・ニュース・新聞を活用し、時事問題も確認する |
(5)小学6年生(9月~11月)
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
・過去問を解き、全般的な復習も行う ・「日本のすがた」(最新版)で統計を学習する ・「重大ニュース」を活用し、時事対策を強化する |
(6)小学6年生(12月~1月)
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
・全般的な復習をする ・地図帳・統計・年号暗記・時事問題を確認する ・記述問題への対策を強化する |
②日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方
日本学園中学校の入試では、過去問と似た問題が出題されるため、過去問の解き直しが重要です。
算数と理科は特に過去問と似た形式の問題が多く、解き直しを通じて解法の定着を図ることが得点につながります。国語と社会は出題形式に慣れることが重要で、解き直しに過度な時間を割く必要はありません。
| 教科 |
効果的な使い方 |
|
算数 |
頻出単元(図形、速さ、規則性、食塩水)を中心に解き直しを行い、ミスをなくす |
|
理科 |
計算問題は何度も解き、計算方法を確実に理解する |
|
国語・社会 |
過去問の形式に慣れ、問題の読み取り方を確認する |
(2)過去問はいつから解き始めればよいか
| 教科 |
時期 |
理由 |
|
算数 |
夏休み前から | 配点が高く、差がつきやすいため |
|
国語 |
夏休み前から | 配点が高く、差がつきやすいため |
|
理科 |
夏休みに入ってから | 試験範囲の学習が終わっていない場合がある |
|
社会 |
夏休みに入ってから | 試験範囲の学習が終わっていない場合がある |
(3)何年分を何周解けばよいか
| 教科 |
目標回数 |
解き直し | ポイント |
|
算数 |
10回~20回 | 3~4周 | 図形・速さ・規則性・食塩水に重点を置き、時間を測って素早く解く練習をする |
|
国語 |
10回~15回 | 2周 | 長文読解を速く正確に読み、設問に的確に答える訓練をする |
|
理科 |
10回~15回 | 3~4周 | 計算問題の反復練習と、周辺知識の理解・暗記を強化する |
|
社会 |
10回 | 2周 | 形式に慣れる。特に記述問題を意識し、間違えた内容の周辺知識を整理・暗記する |
③保護者様にできるサポート
(1)成績が下降してきたら…
成績が下がった場合は、基本に立ち返りましょう。難しい問題ばかりに取り組んでいると、基礎が疎かになり、土台が崩れてしまいます。
次のような取り組みをしてみましょう。
|
・小学四年生・五年生の基本単元に戻って復習する |
基本に立ち返ることで、成績は安定し、基礎力が向上します。
(2)計算力対策
計算力を高めることが、日本学園中学校の合格には重要です。日本学園中学校では、計算問題が頻出し、正確さとスピードが求められます。
以下の方法を試してみてください。
|
・毎日10問の四則演算問題を解く |
計算力を向上させることで、確実に得点が伸びます。
(3)書籍
読書は幅広いジャンルから選び、バランスを保つことが重要です。読書量が増えることで、読解力が向上し、国語の長文問題にも対応しやすくなります。
|
・物語文・説明文をバランス良く選ぶ |
さまざまなジャンルの本を読むことで、読解力が向上します。
(4)時事問題対策
時事問題は、保護者様が生徒様と一緒に考える姿勢が重要です。生徒はニュースを自分のこととして捉えにくいため、大人との会話を通じて理解を深められます。
|
・「円安ってどういうことかわかる?」と質問する |
保護者様との対話を通じて、生徒様は時事問題を理解できます。
(5)ケアレスミス対策
ケアレスミスは、正しい習慣づけで大幅に減らせます。ケアレスミスは、習慣から生じることが多く、正しい確認方法を身につければ防げます。
以下の方法を試してみてください。
|
・計算は筆算を大きく書く |
正確な計算と確認の習慣で、ケアレスミスを大幅に減らせます。
ご家庭でのサポートは、日々の学習の質を高め、入試本番に向けて力をつけていくうえで、大きな支えとなります。
とはいえ、受験期は不安や迷いがつきものです。
「このままで大丈夫?」「どこまでサポートすればいいの?」と悩む場面もあるかもしれません。
そんなときは、受験に詳しい家庭教師に相談してみるのも一つの方法です。
保護者様の不安を軽減しながら、生徒様に合った学習サポートで、合格に向けた準備を無理なく進めていけます。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)を受験する際の併願パターン
日本学園中学校を受験する際の併願パターンを紹介します。
①1月
|
・城西川越中学校 |
1月は「練習」として受験するのに適した学校として、城西川越中学校、城北埼玉中学校、西武学園文理中学校が挙げられます。これらの学校で合格を手にすることで、精神的な安定を得られるでしょう。
②2月1日
|
・午前:日本学園中学校(1次) |
午前は日本学園中学校(1次)の受験をおすすめします。
午後は、東洋大学京北中学校(2次)が第1候補です。もし安全を確保したい場合は、東京電機大学中学校(2次)も良い選択です。また、京華中学校(特別選抜・1次)も抑え校として有力です。2日目以降の戦略に備えつつ、無理をしないようにしましょう。
③2月2日
|
・午前:東洋大学京北中学校(3次)・獨協中学校(3次) |
午前は東洋大学京北中学校(3次)か獨協中学校(3次)を選びましょう。
午後は日本大学豊山中学校(2次)が優先ですが、無理をしないために穎明館中学校(3次)も選択肢に。1日の午後入試で疲労が予想されるため、体調管理を優先してください。
④2月3日
|
・午前:日本大学豊山中学校(3次) |
この日は日本大学豊山中学校を受験するのが良いでしょう。ただし、午前・午後の連続受験は体力的に厳しい可能性があります。どちらか一方に絞り、日本学園中学校(2次)に向けて体力を温存するのも戦略です。
⑤2月4日
|
・日本学園中学校(2次) |
この日は日本学園中学校(2次)の受験をおすすめします。
さらに2月5日には日本学園中学校(3次)も控えています。最後まで諦めずに挑みましょう。
【参考文献】
・日本学園中学校
・日本学園中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・京華中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・高輪中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・明治大学付属中野中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
5. 日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)の受験対策をはじめよう!
日本学園中学校は、2026年から明治大学の系列校となり、「明治大学付属世田谷中学校」として共学校に生まれ変わります。進学実績も大きく変わり、約7割の生徒様が明治大学へ進学できる見込みです。この影響で受験の人気は急上昇しています。
現時点では、入試問題は基本~標準レベルが中心ですが、今後は競争の激化により、合格ラインが上昇したり、問題が難化する可能性も考えられます。確かな基礎と応用力を兼ね備えた学習で、合格に一歩近づきましょう。
「どんな勉強をすればいい?」「今のやり方で間に合う?」と不安を感じたときは、受験に詳しい家庭教師に相談してみるのがおすすめです。
生徒様一人ひとりの理解度や性格に合わせた学習サポートで、日本学園中学校(明治大学付属世田谷中学校)合格に向けた準備をしっかり進めていきましょう。
まずは、家庭教師の無料体験授業からお気軽にご相談ください。
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
日本学園中(明治大学付属世田谷中)合格をサポート
他の学校の入試傾向・受験対策




.jpg)