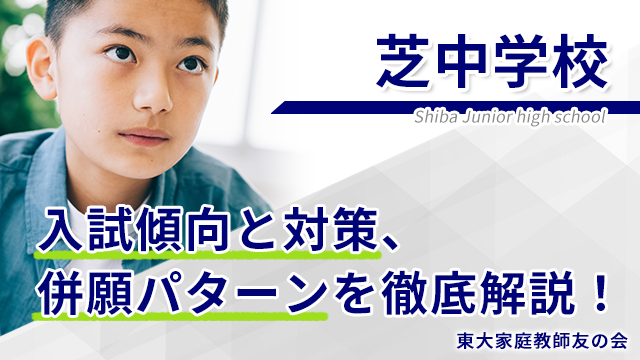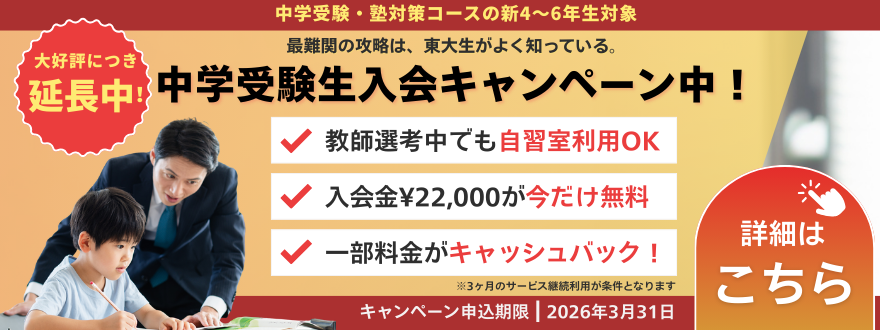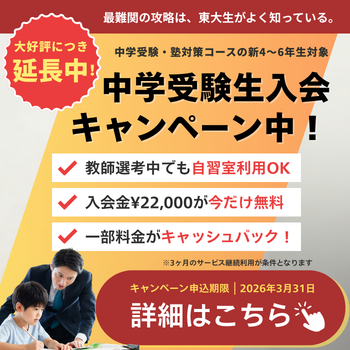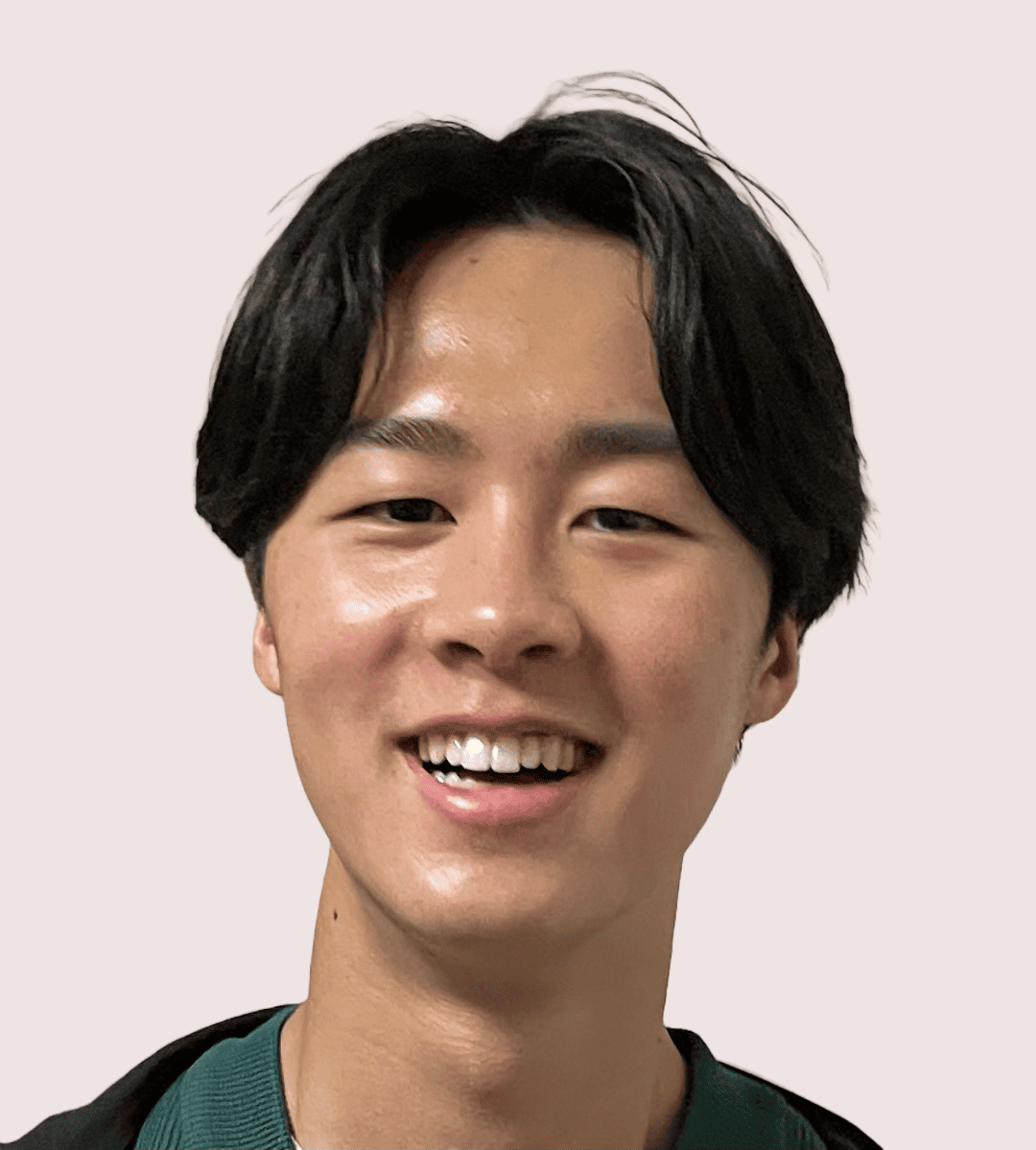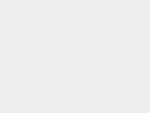![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 芝中学校の偏差値と基本情報

芝中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①芝中学校の偏差値
芝中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
SAPIX小学部 (合格率80%偏差値) |
|
2/1 |
男子 58 |
男子 70 |
- |
|
2/4 |
男子 63 |
男子 73 |
男子 58 |
芝中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受験する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②芝中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1906年 |
|
所在地 |
東京都港区芝公園3‑5‑37 |
|
アクセス |
地下鉄日比谷線「神谷町駅」徒歩5分 |
| 校種 | 私立男子校(中高一貫) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・理科室多数、臨海寮での実習行事あり ・中2~ネイティブ常勤、GTEC必修、オンライン英会話導入 ・宿題少なめで課内学習重視 ・仏教に根ざした人格育成 |
東京の中心部に立地している芝中学校。
自由な雰囲気の中、生徒様がのびのびと学校生活を送れる環境、かつ、伝統的進学校であることが人気の要因です。部活動も盛んで、文化祭は大人気!私の子供は鉄道のシミュレーターにはまっていました。
仏教系の学校であることから、仏教に関する学校行事が多く、近くにある増上寺に参拝し、お話を伺う機会もあります。穏やかな生徒様が多いのは、仏教の教えから来るのかもしれません。
勉強面に関しましては、数学に力を入れている印象です。先生のオリジナルプリントで授業を行う事もあり、生徒様に興味を持っていただけるような工夫を凝らしています。その他、海外研修として、カナダ・ニュージーランド・ベトナムの3つが用意されていまして、特にベトナム研修は定員を大きく上回る状況と聞いています。
2. 芝中学校の入試傾向

試験科目は、算数・国語・理科・社会の4科目です。
試験時間は各々50分・50分・40分・40分、配点は100点・100点・75点・75点となっています。
これは、第1回・第2回共通です。
ちなみに学校側でのお話として、第1回・第2回を両方受験する場合、第2回に5点以上20点以下の加点があります。
試験問題としては、算数で最も差がつきやすく、幅広く網羅していないと合格点には達しません。
国語は、設問の大半が記述問題で、制限時間内に解き切るには、かなりの実力が必要です。
理科は、計算問題や理解を伴う問題が多いため、単なる暗記では歯が立ちません。
社会は時事問題を含めた幅広い知識が必要で、課題文の要約問題があるのが特徴です。
①算数
大問8〜10問で構成されており、あらゆる単元から出題されています。問題は難易度順に並んでいるとは限りません。
特に出題される単元は、図形・速さ・場合の数・比と割合・規則性・数の性質・仕事算・図形です。
大問1番では小問2つの計算問題が出題されます。ここの計算問題をしっかり得点する事が重要です。
大問2番以降は、先ほどお話しした単元を中心として出されます。
どの問題も標準的なレベルを中心に出題されていて、難問はあまり出題されません。問題文自体は長くなく、複雑さもそこまでではありませんので、日頃から問題集でしっかり演習、解き直しをすることが肝心です。
特徴的な単元としては、比と割合・速さの問題です。
比と割合では、食塩水の問題と損益の問題がほぼ同程度出題されています。
どちらが出題されても、しっかりと得点したい単元です。
速さの問題では、旅人算か水量に関する問題が、グラフと共に出題されています。
2024年度第一回では、大問8番で、点の移動に関する問題が出題されました。
状況を理解しづらい問題でしたが、グラフを手掛かりに紐解く問題でした。
このレベルの問題が解けるかどうかが合否の分かれ目になってきます。
グラフの読み取りを演習することが大切です。
②国語
例年、大問1・2番で漢字や語彙の問題が出題され、大問3・4番で説明文・物語文が出題されています。
芝中学校の特徴としましては、記述問題が大半を占める事が挙げられます。
字数は30字程度〜60字程度の問題が多いですが、100字位の問題も出題されます。
記述問題は、文中から答えとなるポイントを見つけて、まず下書きとして箇条書きをしましょう。記述をする際には、主語を明確にし、一つ一つの文章が長くなり過ぎないように注意して書くようにしましょう。
2024年度第1回でも、説明文・物語文の各々最後の設問で、全体理解を問う80字以上100字以内の記述問題が出題されました。全体の内容理解を問うこれらの問題が合否を分けますので、日頃から要旨を書く練習をしてください。
③理科
例年、大問5題の出題で、物理・化学・生物・地学がバランス良く出題されています。
大問1番は小問集合です。小問と言っても、一問一答式の問題は少なく、しっかり理解していないと解けない問題が多く出題されます。
大問2番以降は、物理・化学・生物・地学それぞれのカテゴリー毎で出題されます。
物理では、「ばね」「てこ」と言った定番の計算単元も出題されますが、理解を問う問題や、ややマイナーな単元が出題される事もあります。
2024年度第1回では、電熱線の計算問題が出題されました。いわゆるマイナーな単元にあたりますが、電気単元として見るとよく出題されていますし、電熱線自体も2021年度第2回で出題されていました。この事から、過去問をしっかり取り組んでいた生徒様と、そうでなかった生徒様とで差がついたものと思われます。過去問を解くのも必要ですが、特に解き直しをしっかり行ってください。
化学では、難関校でよく出題される化学反応に関する計算問題と実験問題が合わさった問題が頻出です。記述問題やグラフ作成問題が出題されることもあり、総合的な力を試される問題となっています。過去問を演習することが最も重要でしょう。
生物は、暗記を中心とした問題が出題されますが、時折考察問題を基にした計算問題も出題されています。計算レベルは高くないですが、考察問題の対策としては、生物分野の理解も欠かせません。暗記一辺倒にならないように学習してください。
地学は、満遍なく出題されているものの、天体分野の頻度がやや多いです。特に、惑星・星・月の運動に関する理解を軸とした問題が頻出です。これらの単元は、不得意な生徒様が多いですから、時間をかけてじっくり学習しましょう。
④社会
例年、大問4問の出題で、地理、歴史、公民・時事問題が満遍なく出題されます。
大問1番は、地理の出題です。地形・雨温図・人口・工業・統計の問題が頻出です。
地形は細かい部分まで問われていますから(例えば、鹿島灘)、とにかく地図帳でよく場所を確認する必要があります。また、統計は毎年複数出題されていまして、統計対策は必須です。過去問を見ると、繰り返し出題されている農作物もありますから(例えば、キウイ・レタス・ほうれん草など)、過去問を中心に学習をするようにしてください。
大問2番は歴史からの出題です。時代問わず、広く出題されていまして、全般的に学習を進める必要があります。また、年号も出題されていて、特に江戸時代以降の年号が頻出です。芝中学校特有の問題としては、芝周辺の歴史についての設問です。増上寺や愛宕神社、また芝周辺に本社を置く企業名も出題されたことがあります。今後もこのような問題はあり得ますので、対策するのが宜しいでしょう。
大問3番は公民・時事問題です。国会・憲法・国際機関など重要単元については、全般的に暗記を行いましょう。
芝中学校は、時事問題についてもよく出題されていまして、ノーベル賞・社会保障・税金・貨幣・オリンピックなど幅広く出題されています。改正民法やインボイス制度の話も設問に出てきていますので、新聞・ニュースで見識を深める必要があるでしょう。
2024年度第1回でも、大問3番で時事問題が出されました。今回は、合計特殊出生率・社会保障・税関係の問題が出題されました。これらは、過去問によく出てくる話題でしたから、過去問をしっかり解いている生徒様は対策されていたでしょう。
大問4番は、文章題となっていまして、地理・歴史・公民・時事問題問わず設問となっています。最後の設問が特徴的で、課題文に関する100字程度の記述問題となっています。要旨を答える問題が多く、はっきり言ってしまえば、国語の問題です。国語の対策をすることで、対処できる問題となっています。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
算数が比較的満遍なく出題される点や、国語の記述問題が多い点を考えますと、本郷中学校・桐朋中学校・城北中学校が似ていると思われます。芝中学校の過去問が解き終わった場合に、ご参考にされると宜しいかと思います。
3. 芝中学校の受験対策
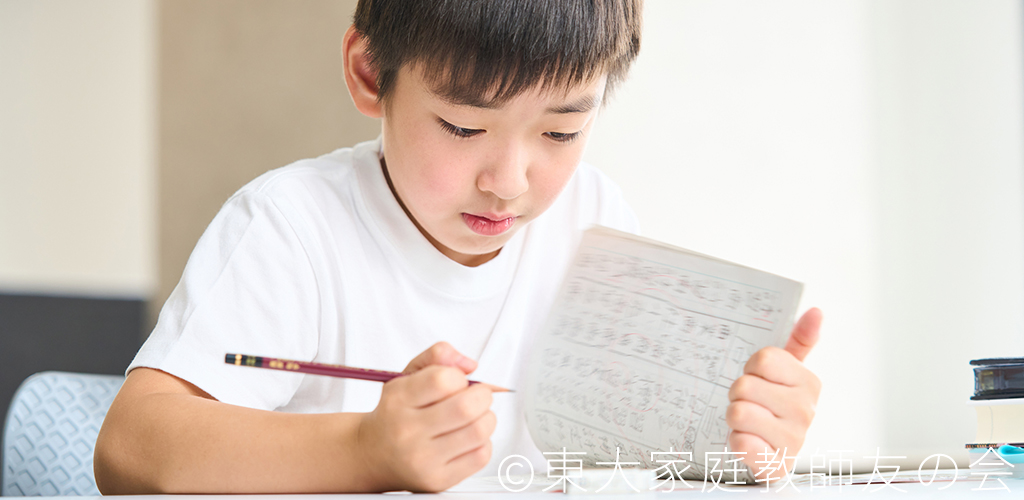
芝中学校は算数で差がつきますので、算数の強化を第一に考えましょう。幅広く標準的な問題が出題されますので、苦手単元を作らないことが大切です。幅広く抑えた上で、図形・速さ・数に関する単元など頻出項目の底上げを図っていきましょう。差が大きくつくわけではないですが、平均点が低く難しい科目が国語です。
問題の大半が記述問題で、試験時間の中で数多くの記述問題を纏め上げていくには、相当な実力が必要です。
日々の読書による読解力だけでなく、書く力をつけるべく、以下にお話しする対策を行っていきましょう。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学4年生
【算数】
塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。
塾に通われてない生徒様は「予習シリーズ」に沿って進めていくと良いでしょう。
芝中学校は、満遍なく出題されますので、苦手単元を作らない事が大切です。
また、計算力も必須です。芝中学校では、大問1番に必ず計算問題が出題されています。
速く、正確に計算ができるようにトレーニングをしてください。
【国語】
カリキュラム・予習シリーズをもとに行いますが、文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにしてください。
文章を読んでから、要旨を50~100字で書いていくのが、読解力向上に良いでしょう。
少しの時間でも良いので、毎日の読書も欠かさず行いたい所です。
【理科】
生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。
ですが、暗記だけでは芝中学校の問題には対応できません。
芝中学校の入試問題に対応するには、身の回りの現象理解がとても大切です。
これは生徒様だけに任せるのは大変かもしれません。是非、保護者様も生徒様と一緒に考察してください。
【社会】
地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。
また、今の時期から統計の暗記も始めていくと良いでしょう。
ご旅行に行かれるのも大変重要です。2023年度第2回では温泉地の問題が出題されました。
また、新幹線に関する問題も時折出題されています。
ご旅行の思い出は記憶に残りやすいですから、地理に関する会話をしながら行かれると良いかと思います。
(2)小学5年生
【算数】
小学四年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにしてください。
少し時間が経ってしまうと、できなくなってしまう事も多いです。
単元を絞らずに、全体的に強化していきましょう。
【国語】
物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。
生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、引き続き、要旨を100字程度で書く練習をしましょう。
正誤選択問題では、しっかりと文章に戻って、正しいかどうかの判断をするようにしてください。
読書は継続的に行い、漢字・語彙も忘れずに行ってください。
【理科】
物理・化学の計算問題が始まります。よく出題されていますので、しっかり復習をし、標準的な問題は解けるようにして行きましょう。
引き続き、単なる暗記ではなく、何故こういった現象が起きるのか、考えてみましょう。
わからない事は、調べつつ、理解を深めてください。
【社会】
歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、暗記を行ってください。年号暗記も忘れずに行ってください。特に江戸時代以降が重要です。
ニュース・新聞を見て多くの事を知っていただきたい時期です。わからないことは、生徒様と一緒に調べてあげてください。
(3)小学6年生(4月〜6月)
【算数】
前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。
過去問の問題を一度解いてみてください。解ける問題もあると思いますので、その中で弱い単元を中心に復習をしていくと良いでしょう。
また、「プラスワン」(東京出版)で復習をしていくと効果的です。
【国語】
過去問を一度解いてみましょう。記述問題がとても多いですから、まずは慣れていく必要があります。
記述問題は、傍線部の近くだけで解答が作成できるわけではありません。本文全体を読んだ上で、設問を解いていくようにしましょう。ポイントを箇条書きした上で纏めていくと宜しいかと思います。
【理科】
引き続き、身の回りの事柄への理解を深めつつ、計算問題の力をつけて行きましょう。
計算問題が苦手な生徒様は特に力を入れて復習してください。
過去問は、一回分だけでも解いてみると、夏休みが有効活用できると思います。
【社会】
公民が始まります。基本的事項は押さえつつ、地理・歴史の復習も取り入れて行くと、今後楽になります。
「日本のすがた」(最新版)で統計の確認を始めましょう。
(4)小学6年生(7月〜8月)
【算数】
過去問を3〜5回分解いていきましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。
「プラスワン」の解き直しをしつつ、余裕があれば「ステップアップ」(東京出版)も解いてみましょう。
秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。とにかく基礎固めをしっかり行いましょう。
【国語】
過去問を3回分は解きましょう。読書も継続してください。
語彙・漢字については、この夏休みで固めていきましょう。
【理科】
過去問を3〜5回分解きましょう。弱い単元について復習をしてください。生物を中心に暗記も行いましょう。
計算問題については、少し難しい問題にも対応できるようにしていきましょう。
【社会】
過去問を3~5回分行いましょう。過去問を通して弱点を見つけ、補強して行きましょう。
スポーツの時事問題なども出題されていますので、ジャンル問わず、時事を補強していきましょう。
大問4番の要約問題に対処できる様にしていきましょう。
(5)小学6年生(9月~11月)
【算数】
過去問中心になりますが、特に解き直しに力を入れてください。
「プラスワン」「ステップアップ」の解き直しも重要ですから、時間を取って行ってください。
【国語】
過去問を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行ってください。
過去問の解き直しも行いましょう。
この時期でも、読書は継続していただき、様々なジャンルに触れましょう。
【理科】
やはり過去問を中心に行っていきます。同時に解き直しも忘れずに行ってください。
今まで学んできた現象理解が身についているか、確認をしてください。
【社会】
過去問中心です。大手塾から出版されている「重大ニュース」を使用して、時事対策を万全にしていきましょう。
地理・歴史の復習も忘れずに行いましょう。特に、地理では、地形や場所を細かく地図帳で確認して、歴史では、幅広く内容の暗記と年号暗記をしてください。
(6)小学6年生(12月~1月)
【算数】
過去問の解き直し、教材の解き直しを行いましょう。
この時期でも、過去問演習は効果的ですから、遡って行ってください。
基本〜標準的な問題で取りこぼしが無いように、復習しましょう。
【国語】
時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。
漢字・語彙の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
【理科】
今まで習ってきた内容や、過去問の内容で、理解しきれていない所は無いか、確認してください。
計算問題も、標準的な問題や有名問題での取りこぼしが無いように復習をしてください。
【社会】
全体の暗記は勿論ですが、芝中学校周辺の歴史について知識をつけていく時期です。周辺の大企業についても問われたことがありますから、現在の状況についても見識を深めてください。統計は、過去問に出てきたものは特に注意して復習をしてください。
②芝中学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方
出題形式は比較的一定しており、過去問を解くことが最も効果的と言えるでしょう。
しかし、出題形式が一定だからといって、問題が簡単なわけではありません。
算数は最も差がつきやすい科目ですので、特に力を入れましょう。
(2)いつから解き始めればよいか
算数・国語・理科は夏休み前に一度解き始めましょう。一方、社会は統計・時事問題・要約問題など課題はあるものの、上記の3科目と比べれば対策はしやすく、点差もつきにくい科目です。夏休みから始めれば良いでしょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、最低10回分、できれば20回分解いておきたい所です。
過去問と似た問題が出題されることもありますので、できるだけ多くの過去問に当たっていただきたいです。
まずは時間を測って解き、その後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しをしましょう。
国語は、ほぼ全てが記述問題ですから、制限時間内に解くには素早く解答を纏める必要があります。
慣れるために、最低10回分、できれば15回分解くと良いでしょう。
解き直しは2周できれば良いと考えます。
理科は、過去問を解くことで、理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直すことができます。
そのため、最低10回分、できれば20回分解くと良いかと思います。
解き直しについては、計算問題の解き直しを中心に3~4周行いましょう。
社会は、過去問を解き始めるのは夏休みで良いのですが、解く回数は最低10回分、できれば15回分解きたい所です。
統計を中心に、同じ問題が出題されることもありますので、より多くの問題に当たっておいた方が良いでしょう。
解き直しは、3~4周行えると良いでしょう。
③保護者様にできるサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題ができなくなっている可能性が高いです。塾などで難しい問題ばかり行っていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。保護者様には、基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされる事をおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、対応してください。
また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげてください。
(2)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的な事でも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにしてください。
例えば、
|
「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」 |
と言った質問から、生徒様と一緒に会話をし、一緒に調べることは重要です。税制や民法改正なども出題されていますから、保護者様の方でもアンテナを張っていただければと思います。
(3)理科の対策
芝中学校の理科は、これまで説明している通り、理解を問う問題が多く出題されています。
保護者様としましては、身近な事柄について、生徒様と会話をしながら理解をさせてください。
例えば、
|
「洗濯物を干すと乾くのは何故だろうね?」 |
など、日常当たり前の事をしっかりと調べることは、理科の対策にとても重要です。
ご家庭だけでは難しいと感じた場合は、家庭教師のサポートを取り入れるのもおすすめです。
生徒様の性格や理解度に合わせて、無理なく学習を進められます。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 芝中学校を受ける際の併願パターン

①1月
|
大宮開成中学・西武学園文理中学校・栄東中学校 |
1月は練習として、大宮開成中学・西武学園文理中学校・栄東中学校が挙げられます。
しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
|
午前:芝中学校(1次) 午後:世田谷学園中学校(算数選抜)・東京農業大学第一高等学校中等部(1次)・東京都市大学附属中学校(I類・2次) |
午前入試は芝中学校(1次)で決まりです。
午後入試は、算数に自信がお有りでしたら、世田谷学園中学校(算数選抜)が良いと思います。
そうでなければ、東京農業大学第一高等学校中等部(1次)が良いと思われます。
抑え校として考えるならば、東京都市大学附属中学校(I類・2次)が良いでしょう。
③2月2日
|
午前:城北中学校(2次)・世田谷学園中学校(2次) |
2日午前の入試は、城北中学校(2次)がおすすめです。
もしくは抑え校として、世田谷学園中学校(2次)も良いでしょう。
④2月3日
|
午前:東京都市大学附属中学校(Ⅰ類・3次)・成城中学校(2次) 午後:暁星中学校(2次) |
3日午前は、東京都市大学附属中学校(Ⅰ類・3次)・成城中学校(2次)、午後は暁星中学校(2次)が良いでしょう。
2日午後を受けずに、3日に午前・午後両方受験するのが良いと考えます。
3日でしっかり合格を勝ち取り、4日の芝中学校(2次)に向かうのが戦略的に正しいやり方でしょう。生徒様の疲れ具合を見ながらお考えください。
⑤2月4日
|
芝中学校(2次) |
4日は芝中学校(2次)を受験しましょう。
3日までに抑え校に合格し、思い切って勝負していきましょう。
【参考文献】
芝中学校(https://www.shiba.ac.jp/)
芝中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
本郷中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
桐朋中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
城北中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
5.芝中学校の受験対策をはじめよう!
芝中学校の入試問題は、算数で大きく差がつきます。問題の難易度は高くありませんが、幅広く標準的な問題が解ける力をつけなくてはなりませんので、そう簡単ではありません。あまり難問ばかり行わずに、基礎~標準問題が解ける力を徹底的に磨いてください。
読解力・記述力も重要です。国語はほとんどが記述問題で、社会でも文章の要約問題が出題されます。本を読み、要約練習を積むことで力がついていきます。要約を書く際は、まず書きたいポイントを箇条書きにし、一文が長くなりすぎないよう意識しましょう。
もし「家庭だけでは十分な対策ができるか不安」と感じられる場合は、家庭教師のサポートを活用するのもおすすめです。生徒様の理解度や性格に合わせた柔軟な指導により、苦手分野の克服や記述力の向上をサポートいたします。
生徒様一人ひとりに寄り添った指導で、芝中学校合格を目指しましょう。ご相談だけでもOKです。お気軽にお問い合せください。
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
家庭教師が芝中学校合格へのサポートをいたします
他の学校の入試傾向・受験対策