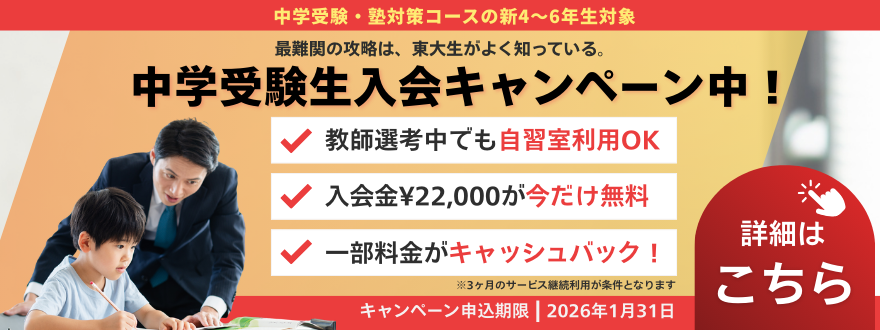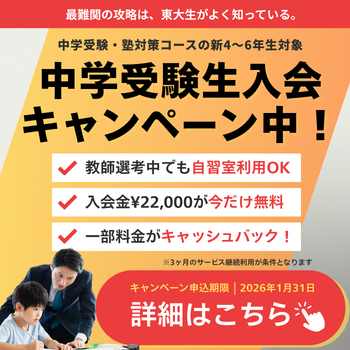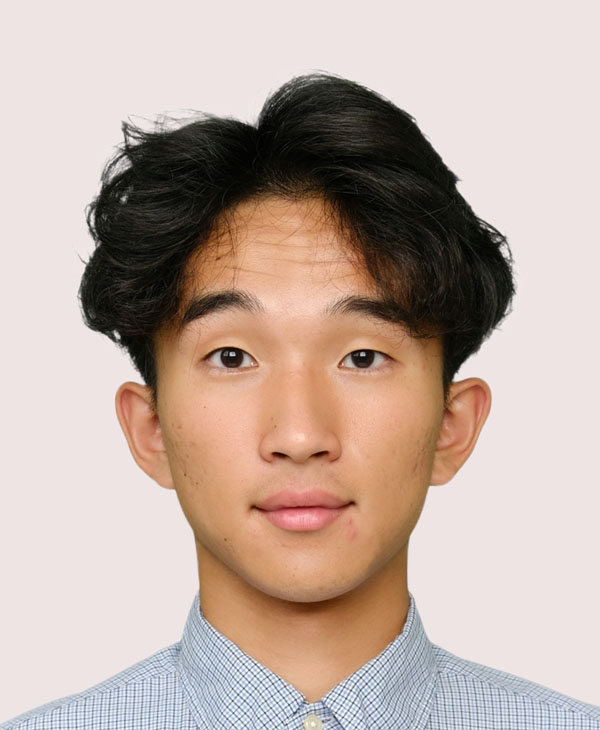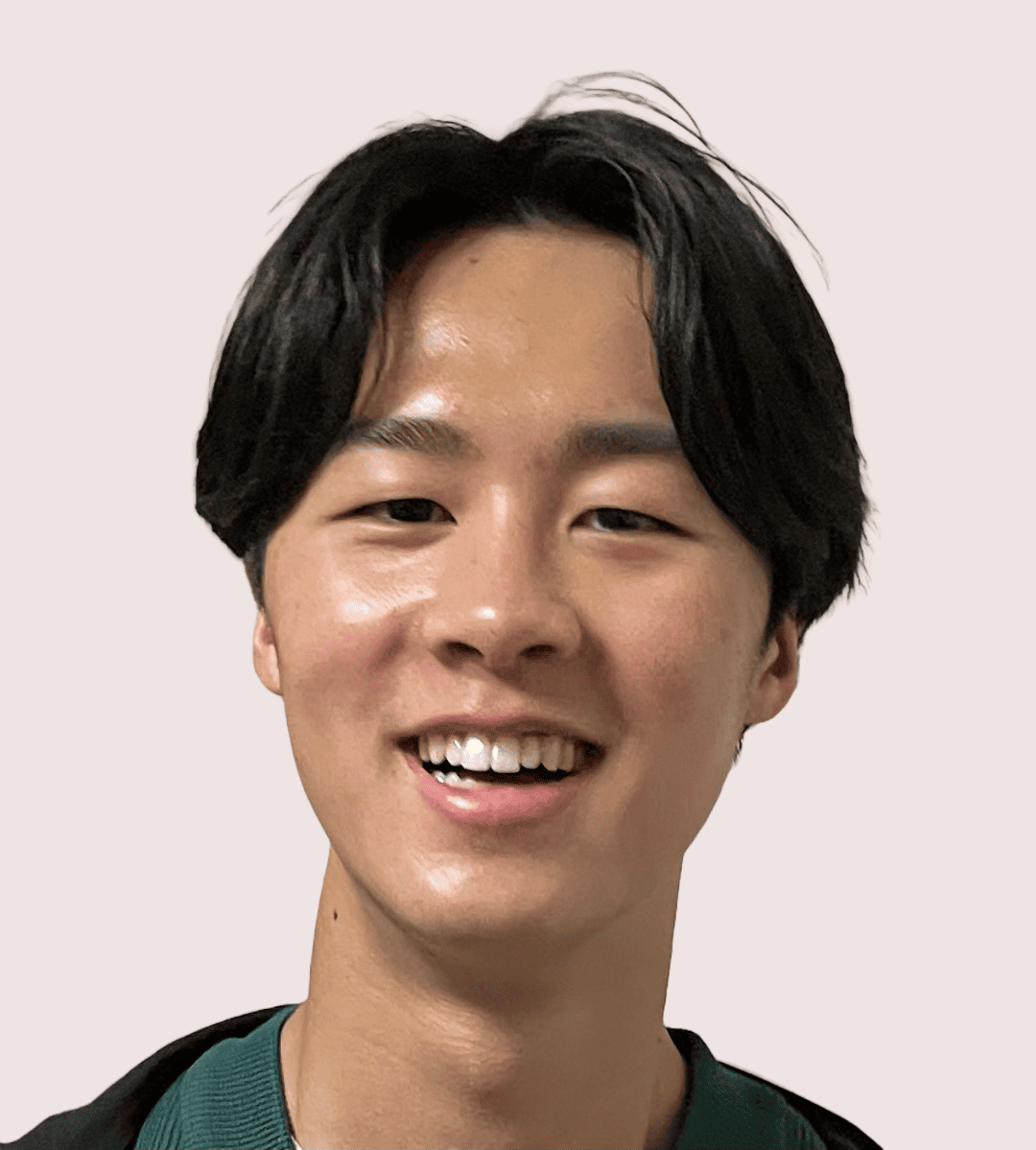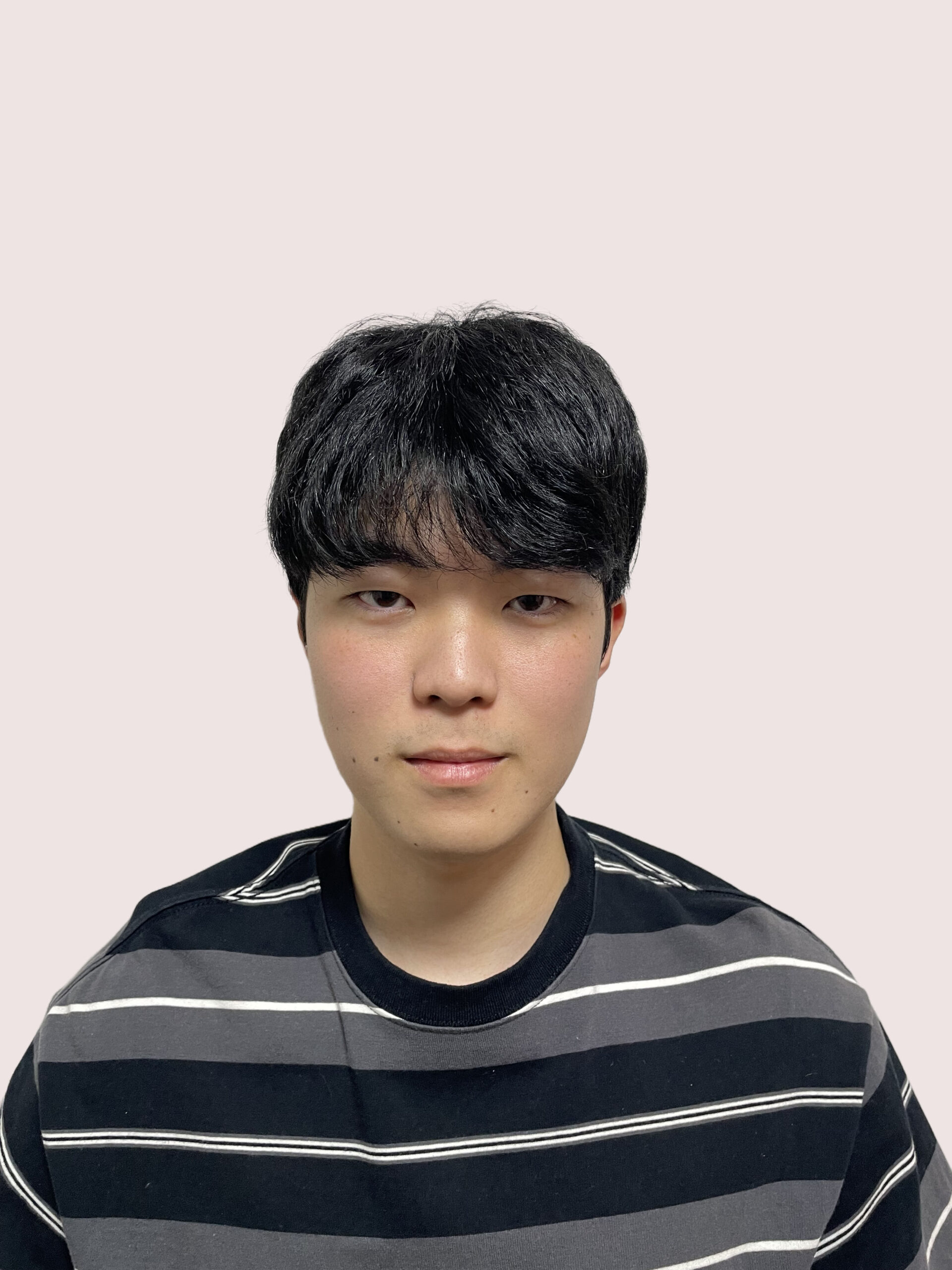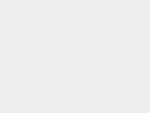![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 芝浦工業大学附属中学校の偏差値と基本情報
芝浦工業大学附属中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①芝浦工業大学附属中学校の偏差値
芝浦工業大学附属中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
|
2/1 4科 |
男子 55 |
男子 68 |
|
2/2 4科 |
男子 57 |
男子 69 |
|
2/2 |
- |
男子 68 |
|
2/2 |
- |
男子 68 |
芝浦工業大学附属中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受験する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②芝浦工業大学附属中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1982年 |
|
所在地 |
東京都江東区豊洲6‑2‑7 |
|
アクセス |
東京メトロ有楽町線「豊洲駅」6a/6b出口より徒歩約7分 |
| 校種 | 私立男女共学校(中高一貫) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・授業の振り返りとアウトプットで自律的な学習力を育成 ・IT・GC・総合探究を通じて、社会課題解決力とプロジェクト遂行力を養成 ・実験・工作体験で理工系への興味を引き出す特別プログラム ・大学教員による講座・研究室訪問・先取り授業などで高大一貫の実践教育を実施 |
1922年に前進の学校が設立され、2017年に現在の名称へと変更、2021年に共学化されました。芝浦工業大学系列であることから、理工系教育を重視。
芝浦工業大学の協力によって、ロボットを一人一台作成したり、デザイン工学について学んだりと、ここでしか味わうことができない最先端の教育を学べます。
国際教育にも力を入れており、中学3年生時には、約2週間という長期にわたる全員参加型の海外教育旅行があります。
芝浦工業大学系列ではありますが、内部進学率は50%弱で、残りの生徒様は、多くの方が理工系の難関大学へと進学されます。
2. 芝浦工業大学附属中学校の入試傾向
| 科目/試験時間/配点 | |
| 第1回・第2回入試 |
算数/60分/120点 国語/60分/120点 理科/50分/100点 |
| 言語・探求入試 |
言語技術と探求/40分/100点 算数/30分/100点 |
| 英語入試 |
英語/40分/100点 算数/30分/100点 |
第1回・第2回入試の試験科目は、算数・国語・理科の3科目で、試験時間・配点は上記の通りです。理工系の学校ですから、算数・理科の計算問題の対策が重要になるのは勿論ですが、言語運用能力も多分に問われます。尚、2026年度より社会が試験科目に追加されますので、最新の入試情報は学校公式HPで確認するようにしてください。
言語・探求入試の「言語技術と探求」という科目は、適性検査Ⅰ(言語)に近い科目で、主要科目の国語に似ています。ただし、理工系に関する論理的思考力を見る問題で、生徒様の考えを問う記述問題も出題されています。そのほか英語入試があり、試験科目は英語と算数です。
①算数
例年、大問5題の出題で、各問題の概要は以下の通りです。
| 内容と対策 | |
| 大問1番 |
・その場で放送を聞いて問題に答える放送問題。 ・例年約5分間の内容で、基本〜標準的な問題が2題出題される。 ・対策としては、聞き漏れがないようメモを取りながら、しっかり集中して取り組む。 |
| 大問2番 |
・計算問題を含めた小問集合。 |
| 大問3番 |
・やや難易度が高い小問集合。 |
| 大問4・5番 |
・単元別の問題で、図形・速さ・数の問題が頻出。
【図形】 ・平面図形・立体図形どちらも出題。 ・平面図形では相似・面積の問題、立体図形では切断・体積・表面積が頻出。
【速さ】 ・旅人算・点の移動・水量グラフの問題が頻出。 ・グラフを読み取る問題も出題されるため、しっかりと演習し対策する。
【数】 ・規則性・場合の数が頻出。 ・2024年度第1回でも、規則性の問題が出題された。 ・数の問題は具体的に書き出すと理解が進むため、面倒がらず手を動かし対策する。 |
尚、言語・探求入試での算数は大問3題の出題で、大問1番が「計算問題や小問集合」、大問2・3番が「思考力を試す問題」となっています。
複雑な図形問題や、長い文章題が出題されることが多く、やや難しい問題です。過去問で演習しつつ、ほかの学校の算数選抜入試の問題も演習していくと良いでしょう。
②国語
例年、大問6題の出題で、大問1番で放送問題、大問2番で物語文、大問3番で説明文、大問4番で詩や短歌・俳句、大問5番で語彙、大問6番で漢字という構成です。制限時間内に解き終えるにはスピードが必要です。
| 内容と対策 | |
| 大問1番 |
・例年約5分の内容の放送問題。 ・まず2~3分の文章が読まれ、その後設問という流れで行われる。 ・設問は細かい所を聞かれるため、最大限の集中力でメモを取りながら答えていく。 |
| 大問2・3番 |
・大問2番は物語文、大問3番は説明文からの出題。 ・記述・正誤選択・抜き出し・接続詞・語彙・文法など、総合的な出題。 ・問題文自体は短めだが、テキパキ解くことが必要不可欠。 ・一度読んで文章の内容を理解できるようにする。 |
| 大問4番 |
・詩・短歌・俳句から出題。 ・特徴的な問題として、100字程度の記述問題がある。 |
| 大問5番 |
・語彙問題から出題。 ・与えられたことわざ・慣用句を使用して作文する問題が出題される。 ・インプットして知識を蓄えるだけでなく、日々の生活の中で実際に使ってみることも意識する。 |
| 大問6番 | ・漢字問題。 |
大問4番は、詩・短歌・俳句から出題されます。2024年度第1回での大問4番は、「カエル達が人間に話しかけるとしたらどんなことを話かけるか」という設問でした。詩の読解をベースに作文する問題で、この形式に慣れていないと中々書くのは難しいでしょう。普段から日記を書いて文章を書く練習をしつつ、詩の対策が必要です。
「わかる国語」(旺文社)などの総合的な文法書を一冊用意していただき、詩に関しての知識を蓄えつつ、過去問やほかの学校の問題を解くと良いでしょう。
③理科
例年大問7〜8題の出題で、物理・化学・生物・地学が出題されますが、物理・化学の出題割合が高めです。この傾向は回数によりません。
| 内容と対策 | |
| 理科 |
【放送問題】 ・例年5分程度で、基本的な内容。 ・最大限の集中力で、必要なメモをしっかりと取りながら対処する。
【物理・化学】 ・知識問題・理解問題・計算問題と満遍なく出題される。
【生物・地学】 ・考察問題が中心で、知識問題と理解問題が半々。 ・導入文が長いケースもあるが、問われている内容は基本〜標準的な問題。 ・基礎固めをしっかり行う。 |
物理・科学分野では知識問題・理解問題・計算問題と満遍なく出題される傾向にあります。2024年度第一回では、物理分野でばねと電気、化学分野では化学反応式と溶解度に関する問題が出題されました。
やや難しい問題もありましたが、基本〜標準的な問題が大半でしたので、対応できた生徒様とそうでない生徒様では差がついたと思われます。過去問で似た論点の問題が出題されていますので、過去問の演習・解き直しに時間を掛けることが大切です。
④言語技術と探求
| 内容と対策 | |
| 言語技術と探求 |
・適性検査Ⅰ(言語)や国語に近い科目で、理工系の文章や資料が出題される。 ・文章・資料から読み取れることを答える問題や、問題点の解決策を問う問題など出題される。 ・論理的思考力と課題解決力双方が問われる試験問題となっている。 |
2024年度でも文章・資料を参考に生徒様のアイデア・解決策を問う問題が2題出題されました。それぞれ字数が200字程度必要で、タフな問題でした。日頃から文章を読み大意を掴む練習や、生徒様自身が考えて創造していく訓練が必要となってきます。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
|
東京都市大学附属中学校 |
難易度は高めではありますが、東京都市大学附属中学校は、比較的似ていると思われます。詩や俳句が出題されていることも参考になるでしょう。
3. 芝浦工業大学附属中学校の受験対策
芝浦工業大学附属中学校は理工系の学校であることから、算数と理科の計算問題が中心の学校です。しかし、算数の解法を書く欄があったり、国語の記述問題があることや、言語技術と探求という試験科目を考えますと、言語運用能力も相当程度必要となる学校です。
①時期別・科目別対策内容
(1)小学4年生
| 科目 | 対策 |
| 算数 |
・塾のカリキュラム、もしくは「予習シリーズ」に沿って進めていく。 ・計算力も必須のため、速く・正確に計算ができるよう毎日トレーニングを行う。 |
| 国語 |
・カリキュラム・予習シリーズをもとに対策する。 ・文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにする。 |
| 理科 |
・生物・地学を中心とした暗記単元が始まるため、今のうちにしっかりと暗記する。 ・現象理解のためには、図鑑や理科事典で調べたり、科学館に行ったりするのも有効。 |
| 言語技術と探求 |
・国語での対策をしつつ、ものづくりに興味を持つことが大切。 ・パソコン・ロボットなど実際に手で触れて考察したり、生徒様なりの研究をしたりすると良い。 ・自由研究に取り組むのも有効。 ・企業のHPを見て、興味を持ったものを研究するのもおすすめ。 |
国語で文章が難しいと感じる場合の対策としては、文章を読んでから要旨を50字程度で書くと良いでしょう。少しの時間でも良いので、毎日の読書も欠かさず行うようにしましょう。
読書量を増やすことで、速く、正確に読めるようになります。日記を書いて文章を書けるように練習することも大切です。保護者様で添削されると良いでしょう。また、詩の対策として「ウイニングステップ小学四年生物語と詩」(日能研ブックス)といった問題集で詩に慣れるのも良いでしょう。
(2)小学5年生
| 科目 | 対策 |
| 算数 |
・引き続き、カリキュラム通りに対策する。 ・小学4年生の内容、及び小学5年生で習う内容も適宜復習する。 |
| 国語 |
・物語文・説明文共に、客観的に読む訓練をする。 ・読書も継続的に行い、理工系の文章も読んでいくと言語技術と探求にもプラスになる。 ・漢字・語彙・日記も忘れずに行う。 ・「わかる国語」などの文法書を使い、詩・短歌・俳句の表現技法・季節などをよく学習する。 |
| 理科 |
・物理・化学の計算問題が始まるため、やや難しい問題も解けるようにしていく。 ・単なる暗記ではなく、何故身近な現象が起きるのかを考える(現象理解)。 |
| 言語技術と探求 |
・大人が読む新聞を手に取ると良い。 ・自由研究を行うことで、論理的文章を書く練習にもなる。 |
国語の対策では、客観的に読む訓練として、要旨を80字程度で書く練習を引き続き行いましょう。書きたいポイントを箇条書きにしてから、記述するのがおすすめです。
理科の現象理解のためには、図鑑や理科事典を使用しながら納得するまで調べてください。全学年同様、科学館に行くのも良いでしょう。
言語技術と探求への対策としては、新聞の理工系のページから知識を吸収しつつ、わからないことは調べるようにしましょう。
(3)小学6年生(4月〜6月)
| 科目 | 対策 |
| 算数 |
・前学年までの復習をしっかり行いながら、全体的なレベルを上げていく。 ・特に図形・速さ・数の問題に不安がある場合は、この時期に克服しておく。 |
| 国語 |
・標準的な文章で、設問の解き方を確認する。 ・日記を書くほか、新聞の題材を要約したり、その題材についての生徒様なりの考えを書く練習したりすることで作文問題への対策をする。 |
| 理科 |
・身の回りの事柄への理解を深めつつ、計算問題の力をつける。 ・物理・化学共に計算問題は似た問題が出題されるため、何度も解き直して対応できるようにする。 |
| 言語技術と探求 |
・新聞や企業HPからの題材を研究する。 ・ものづくりに関するドキュメンタリー番組を見るのもおすすめ。 |
(4)小学6年生(7月〜8月)
| 科目 | 対策 |
| 算数 |
・過去問を3〜5回分解く。 ・苦手単元があれば、夏休み中に克服しておく。 ・「ステップアップ」(東京出版)にも取り掛かると良い。 ・秋以降は過去問など演習に時間を取られるため、まとまった時間が取れる最後のチャンス。 |
| 国語 |
・過去問を3回分は解いて、形式に慣れておく。 ・記述問題は、主語を書くことを意識する。 |
| 理科 |
・過去問を3〜5回分解く。 ・理解不足のところは基本に戻って理解し、知識問題はこの夏休みに定着させる。 |
| 言語技術と探求 |
・過去問がほとんど掲載されていないため、海城中学校や麻布中学校の社会にある資料問題や公立一貫校の適性検査Ⅰの問題を解いてみるのも良い。 |
(5)小学6年生(9月~11月)
| 科目 | 対策 |
| 算数 |
・過去問中心に、特に解き直しに力を入れる。 ・言語・探求入試を受験される生徒様は、巣鴨中学校や高輪中学校の算数選抜入試の問題も演習してみる。 |
| 国語 |
・過去問を中心に進め、漢字・語彙の強化も忘れずに行う。 |
| 理科 |
・過去問を中心に行い、解き直しも忘れずに行う。 |
| 言語技術と探求 |
・1週間に1題程度、作文問題に触れておく。 |
(6)小学6年生(12月~1月)
| 科目 | 対策 |
| 算数 |
・過去問の解き直し、図形・速さ・数の問題を含めた全般的な定着を行う。 |
| 国語 |
・時間配分・設問形式を忘れないため、1週間~2週間に1度は過去問に触れる。 ・日々の読書も継続する。 |
| 理科 |
・今まで習ってきた内容や過去問で、理解しきれていないところはないか、確認する。 ・物理・化学の計算問題は似た問題が出題されるため、しっかりと定着させる。 |
| 言語技術と探求 |
・今までの復習を行い、時間があれば引き続き演習も行う。 |
②芝浦工業大学附属中学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方
| 算数・理科 |
・比較的似た傾向の問題が出題されるため、なるべくさかのぼって行う。 ・解き直しもしっかり行う。 |
| 国語 |
・詩・短歌・俳句についての問題が出題されているため、10回分程度はさかのぼって行う。 ・過去問だけでは演習量が少ない場合は、慶応義塾中等部や青山学院中等部の問題も使用する。 |
| 言語技術と探求 |
・過去問がほとんどないが、麻布中学校・海城中学校の社会にある資料問題が参考になる。 ・公立一貫校の適性検査Ⅰの問題にも取り組むと良い。 |
(2)いつから解き始めればよいか
| 算数・理科 |
【夏休み前から】 早めに解き始めた方が、夏休みを有効活用できる。 |
| 国語 |
【夏休みに入ってから】 |
| 言語技術と探求 |
【夏休み入ってから】 麻布中学校・海城中学校の社会にある資料問題を参考にする。 |
(3)何年分を何周解けばよいか
| 算数 |
【最低10回分、できれば20回分解く】 ・図形・速さ・数の問題といった頻出単元があり、素早く正確に解く練習も必要。 ・時間を測って解いた後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しを行う。 |
| 国語 |
【10回分解く】 ・通常の文章だけではなく詩・俳句・短歌など特別な形式の問題もあるため、10回分解く。 ・2周解き直しができれば良い。 |
| 理科 |
【最低10回分、できれば20回分解く】 ・過去問を解くことで理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直す。 ・計算問題については、練習が必要。 |
| 言語技術と探求 |
【10題~20題程度解く】 ・10題~20題解くとポイントがわかり、慣れることができる。 |
③保護者様にできるサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
生徒様の成績が下降してきたら、基本的な問題、例えば小学4年生・5年生の単元に立ち戻った復習を生徒様に促すことをおすすめします。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的なところがおろそかになり、土台が崩れ成績が下降することがあるためです。
「少し前の単元に戻ってやってみようか。」「ゆっくり基本からやり直してみよう。」などと声をかけ、生徒様を責めずに対応してみてください。試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様をも見守ることが大切です。
尚、復習とは「間違えた問題をできるまで解き直しを行うこと」を言います。できるまで行うことがポイントです。
また、一度解けたとしても、また暫く経ってから解き直すことも必要です。保護者様でしっかりと管理していただくと良いでしょう。
(2)計算力対策
計算力対策としては、毎日10問程度、四則演算の計算問題を解くよう生徒様に促しましょう。
芝浦工業大学附属中学校は、計算問題は必ず出題されるため、計算力が鍵を握ります。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。正確さが身についてから、スピードを身につけるようにすることが大切です。
(3)放送問題対策
放送問題対策としては、過去問を繰り返していただきたいですが、それでも対策は不十分だと思われます。
芝浦工業大学附属中学校特有の問題である放送問題。問題自体は基本〜標準的な問題ですが、問題文がなく、聞くだけで理解をすると言うのは難しさを伴うためです。
そこで保護者様にしていただきたいのが、問題を作って過去問のように読み上げることです。
生徒様と一緒に過去問を聞いた上でレベル感を実感し、実践すると良いと思います。問題作成が難しければ、問題集の基本〜標準レベルの問題文を読み上げていただくと良いでしょう。
(4)ケアレスミス対策
計算間違いをなくすには、まずゆっくり正確に計算を行うことから始めます。
頭で計算(暗算)せずに、筆算をしっかりしましょう。計算は大きく行いましょう。また、計算の都度、確認をすると良いと思います。
次に、見間違い・勘違いへの対策を行います。文章の数字や人物には丸をつけるなど、目立つようにしましょう。また、何を答えるべきなのか、設問で聞かれていることにも印をつけると良いでしょう。
答えを出したら、もう一度問題文を確認し、生徒様自身の解答も、もう一度確認です。
計算間違い・見間違い・勘違いなどは全てケアレスミスと言われます。このように徹底することで、今までのミスが格段に減ると思われます。保護者様も、ぜひ生徒様の横でチェックしていただけると良いと思います。
日々の学習において、保護者様ができるサポートはたくさんありますが、ご家庭だけでは対応が難しい場面もあるかもしれません。
そんなときは、家庭教師のサポートを活用するのも一つの方法です。生徒様一人ひとりの状況に合わせて、柔軟に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 芝浦工業大学附属中学校を受ける際の併願パターン
①1月
|
・埼玉栄中学校 ・大宮開成中学校 ・西武学園文理中学校 |
1月は練習として、埼玉栄中学校・大宮開成中学校・西武学園文理中学校が挙げられます。
しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
②2月1日
|
【午前】
安田学園中学校(2次) |
午前は芝浦工業大学附属中学校(1次)で決まりです。午後は国学院大学久我山中学校(ST・1次)が良いでしょう。もしくは、安田学園中学校(2次)で抑えておくのも良いと思います。
③2月2日
|
【午前】
安田学園中学校(4次) |
午前は、芝浦工業大学附属中学校(2次)で決まりです。午後は、芝浦工業大学附属中学校(言語・探求、英語)がありますので、受験される方は決まりです。
但し、特殊な試験となりますので、安田学園中学校(4次)を受験して抑えておくことも考えましょう。1日に午前・午後受験されると思いますから、生徒様の疲労を考慮して、午後の受験を回避することも視野に入れておくと良いでしょう。
④2月3日
|
【午前】 法政大学中学校(2次)
帝京大学中学校(3次) |
3日午前は、安田学園中学校(5次)が良いでしょう。2日までで抑えている生徒様は法政大学中学校(2次)が良いと思われます。
午後は、国学院大学久我山中学校(T・2次)、もしくは帝京大学中学校(3次)が候補です。生徒様の疲れ具合など考慮の上、お考えください。
⑤2月4日
|
・東京農業大学第一高等学校中等部(4次) ・東洋大学京北中学校(4次) |
4日は抑え校が合格していれば東京農業大学第一高等学校中等部(4次)、合格されていなければ東洋大学京北中学校(4次)が良いでしょう。
5.芝浦工業大学附属中学校の受験対策をはじめよう!
芝浦工業大学附属中学校は系列大学との連携授業により、ロポットを作成したりデザイン工学を学んだりと最先端の工学技術を体験できる貴重な学校です。
入試問題は、算数・国語・理科の3科目。理数系重視の学校ではありますが、意外にも国語が鍵となる学校です。
毎日の読書による読解力の向上だけでなく、論理的な文章を書ける様にするために日記や要約を書くことをおすすめします。
もちろん算数と理科もしっかりとした対策が必要です。算数は、図形・速さ・数の問題に力を入れ、理科は物理・化学の計算問題を中心に学習しましょう。
「どこから始めればいいか分からない」「家庭だけでは不安…」という場合は、家庭教師のサポートを活用するのもおすすめです。
ご相談からでもOKです!お気軽にお問い合せください。
【参考文献】
芝浦工業大学附属中学校
芝浦工業大学附属中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
東京都市大学附属中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
麻布中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
海城中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
慶応義塾中等部2025年度版10年間過去問声の教育社
青山学院中等部2025年度版10年間過去問声の教育社
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
芝浦工業大学附属中の受験対策なら東大家庭教師友の会
他の学校の入試傾向・受験対策