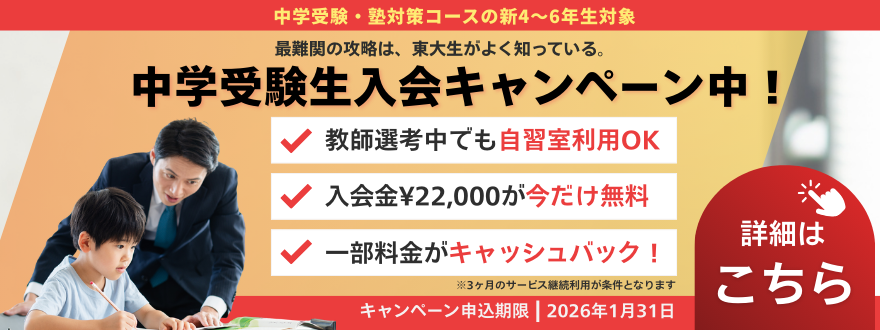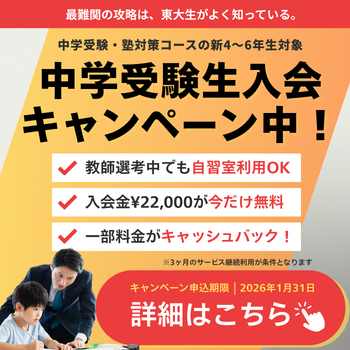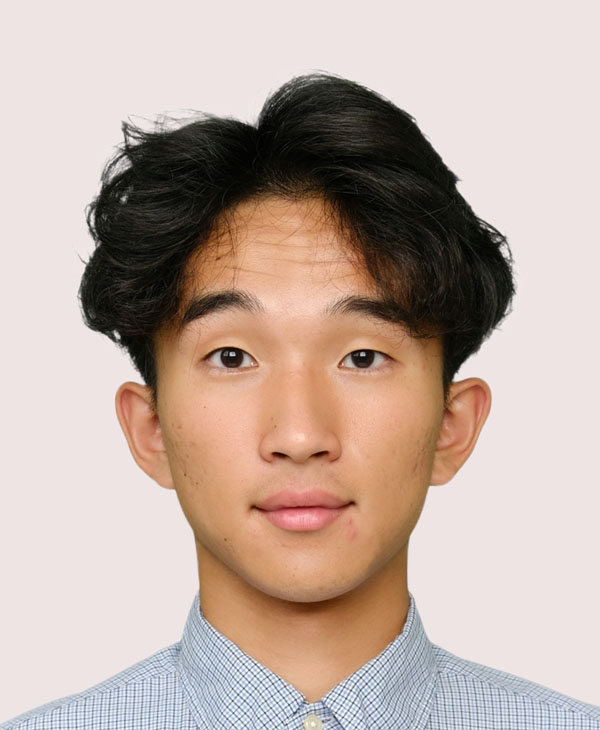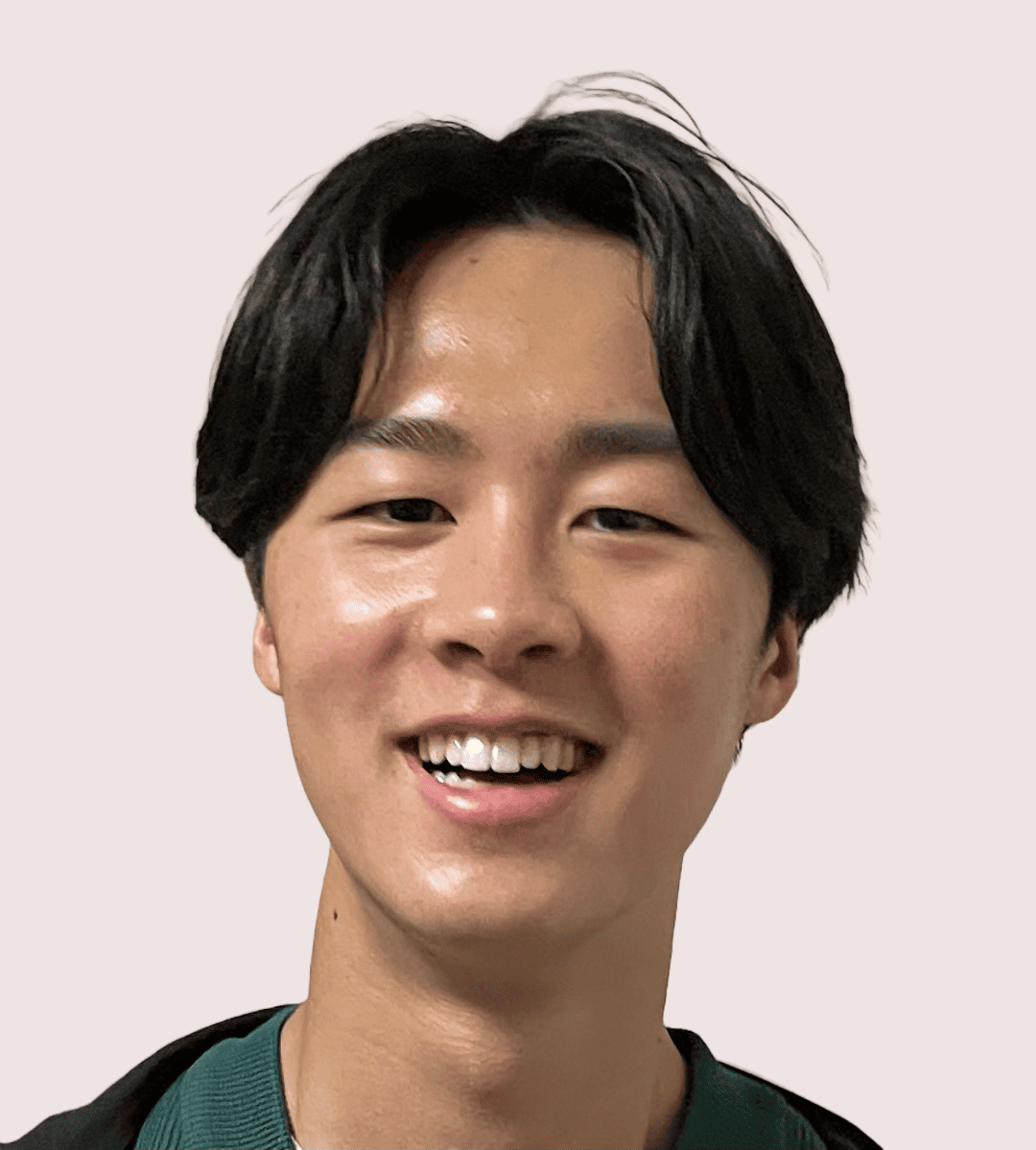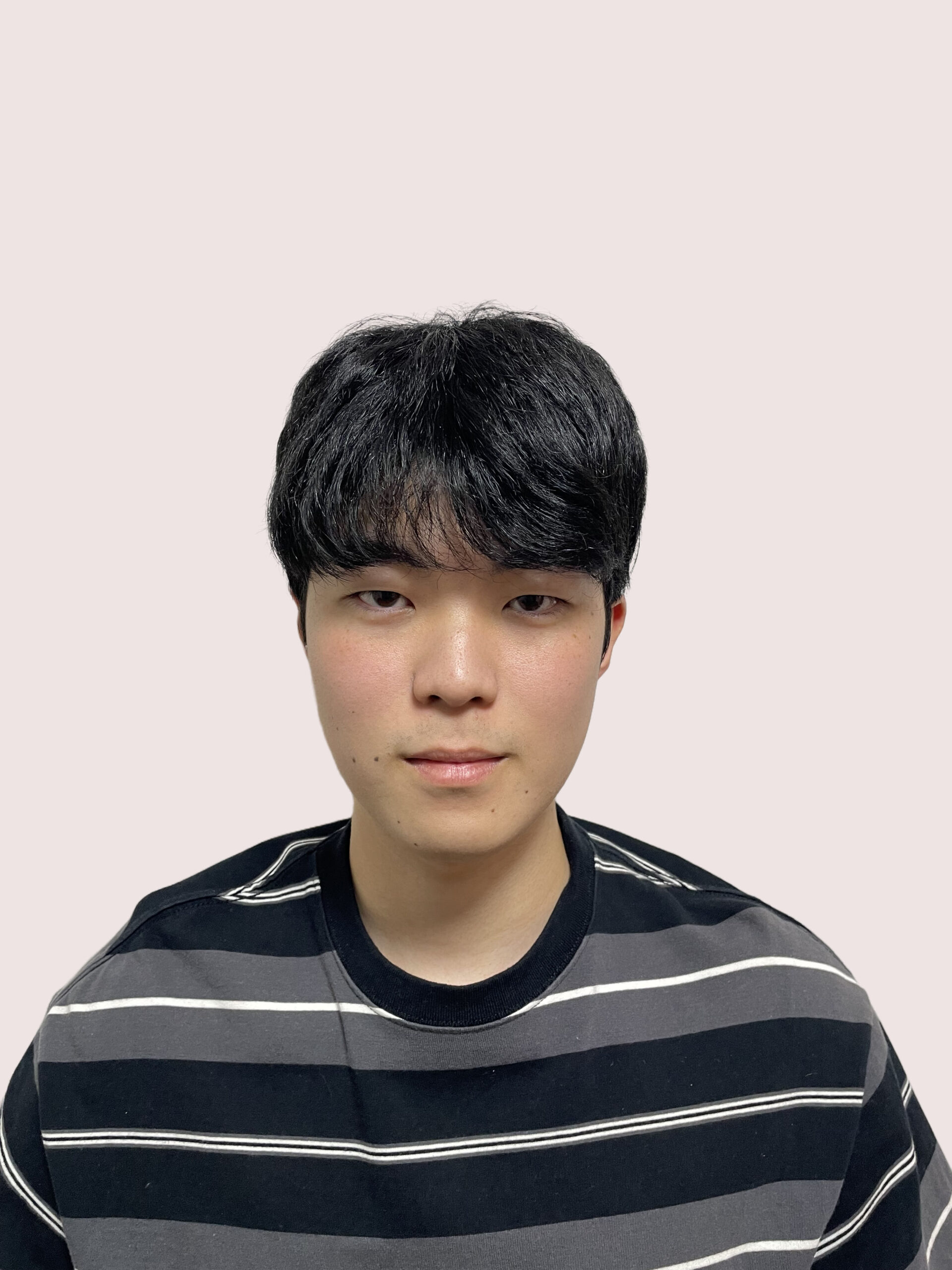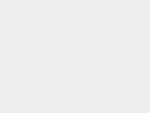![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 桐光学園中学校の偏差値と基本情報

桐光学園中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①桐光学園中学校の偏差値
桐光学園中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
|
2/1 |
男子 48 女子 42 |
男子 59 女子 54 |
|
2/2 |
男子 50 女子 43 |
男子 62 女子 55 |
|
2/3 |
男子 50 女子 43 |
男子 61 女子 54 |
|
2/3 |
-
|
男子 55 女子 50
|
| 2/3 第3回B T&M 4科 |
-
|
男子 55 女子 50
|
桐光学園中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受験する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②桐光学園中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1982年 |
|
所在地 |
神奈川県川崎市麻生区栗木3‑12‑1 |
|
アクセス |
小田急多摩線「栗平駅」徒歩約12分 |
| 校種 | 私立男女別学校(中高一貫) |
| コース | 中3から成績に応じて「SAコース」「Aコース」に分かれる |
| 特徴的な教育 | ・ホームルームや教科授業は男子・女子別に編成 ・大学の専門家や教授を招いた「大学訪問授業」を中高生全学年対象に実施 ・担任と副担任による二人体制で中高一貫を通じてきめ細かな進路・生活支援 ・カナダのホームステイ研修や、ハーバード・ケンブリッジ生との英語ディスカッションを含むエンパワーメント・プログラム、イートン校サマースクールなど、多彩な国際教育機会 |
川崎市の麻生区にある桐光学園中学校。最寄り駅は小田急多摩線の栗平駅です。広い敷地に充実した施設が魅力的な学校ですが、2028年の高校創立50周年に向けて、校舎の新設等が計画されており、今後ますます注目度が高まりそうな学校の一つと言えるでしょう。
桐光学園高等学校に内部進学したのち、国公立大学をはじめ難関大学への進学数も多く、「入学したから伸びる学校」「高校入試で入学するより中学校から入学した方がお得」とも言われています。
ここでは、桐光学園中学校の大きな特徴である「男女別学教育」と「クラブ活動」「講習制度」の三つについてご紹介します。
①男女別学校
桐光学園の最大の特徴は、何といっても「男女別学」であることでしょう。普段、ホームルーム活動を行ったり授業を受けるクラスは男女別で、性別に紐づく社会的な期待や役割、「こうあるべき」といった考え方に左右されず、個々の能力や興味関心に応じて、のびのびと過ごせます。その一方で、委員会活動や学校行事、一部の部活動などでは、男女が協力して活動を行う場も多く準備されており、まさに、「別学校と共学校のいいとこどり」ができる学校です。
②充実したクラブ活動
桐光学園中学校には、運動系・文化系合わせて50ものクラブがあり、活発に活動を行っています。
特に文化系の部活動では、折り紙研究部や航空研究部、電子工学部、技術工作部、エルガリ(スイスの楽器)同好会など、他の学校ではあまり見られないようなクラブも多くあります。
桐光学園中学校では、各部活に専用の活動場所が用意されている点も魅力の一つです。「体育館の割り当ての関係で、今日は部活ができない……」などということがなく、のびのびと活動できます。
③選べる講習制度
桐光学園中学校には、自分の興味関心に合わせて選べる「ユニーク講習」と「通常講習」の2つの講習と、「大学訪問授業」があります。
(1)ユニーク講習
桐光学園中学校には、知的好奇心や探究心を喚起し、学ぶことの楽しさを実感してもらうために、教科の学習を離れて学べる「ユニーク講習」を開講しています。江の島や箱根などを巡るフィールドワークや、陶芸、楽器体験、天体観測など多くの講座があり、全学年・男女問わず、ともに学べるものになっています。
(2)通常講習
また、放課後や夏休み・冬休み中に、生徒が自らの意志で選択する、学習サポートのための講習もあります。中学生には「指名講習」という、実力テストの成績上位者を対象としたハイレベルな内容を扱う講習もあり、生徒の一つのモチベーションになっています。
高校も含めると、年間で約600もの講座があり、自分のレベルや希望に合わせたオリジナルのカリキュラムを組んで学べます。
(3)大学訪問授業
桐光学園の名物とも言えるのが、土曜日の4限の時間に行われる「大学訪問授業」です。さまざまな分野で活躍する大学の先生たちをお招きして、知の最先端のお話を伺えます。
大学訪問授業の内容は書籍として刊行されており、中学校や高校の入試問題として、毎年複数の学校で出題されています。
2. 桐光学園中学校の入試傾向

2025年度入試は、2025年1月5日に行われる帰国生入試と、2月1日から3日にかけて行われる一般入試、2月3日に行われる英検3級以上(またはそれと同等の資格)を持つ人を対象にした英語資格入試と、小学校時代に一生懸命になったものがあり、桐光学園入学後もそれをさらに伸ばしていきたいという人を対象にしたT&M(talent&motivation)入試が行われます。
ここでは、各入試の概要と、各入試科目の出題の傾向、合否を分けた問題や特徴的だった問題をピックアップしてご紹介します。
①入試の特徴
ここでは、各入試の入試概要等についてお伝えします。
(1)一般入試(第1回・第2回・第3回A)
第1回、第2回、第3回A入試は、4教科受験です。算数・国語は試験時間50分で150点満点、理科・社会は試験時間40分間で100点満点の試験です。いずれも、8時30分集合で、合格発表は当日の21時です。
倍率は、男子:2.1~2.5倍程度、女子が1.6倍程度となっています。
(2)第3回B入試
2月3日午前に、第3回A入試と同時に行われるのが第3回B入試です。国語・数学と面接で行われます。なお、試験問題は第3回A入試の国語・算数の問題と同じです。
倍率は男子が2.8倍、女子が1.1倍となっています。
(3)帰国生入試
帰国生入試は、国語・算数・英語から2科目を選択して行う筆記試験と、面接が行われます。
募集人数は男女ともに若干名となっていますが、2024年度は男子が26名、女子が11名合格しています。倍率は男子が1.8倍、女子が1.6倍でした。
いずれの入試も、女子に比べて男子のほうが倍率が高くなっていることが分かります。
②算数
算数の問題は、例年、大問5題で構成されています。大問1は基本的な小問集合問題、大問2は応用的な小問集合問題となっていますが、大問3以降の問題は様々な単元から出題されています。特に、角度や面積、長さを求めるような問題や辺や面積の比や相似に関する問題など、図形に関連する分野の出題率が高いです。
問題のレベルとしては、各単元の標準的なレベルの問題が大半ですが、中には、複数の単元の内容が関連するような問題が出題されることもあります。2024年度第一回の問題では、大問3の「調べ」の問題にどの程度粘り強く取り組めたかが合否を分けたと言えるでしょう。35人が横一列に並んで座っていて、2つのルールに従い、立ったり座ったりを繰り返します。
問1は2秒後なので、問題の例を参考に考えると、すぐ答えを出せるでしょう。しかしながら、問3のように、17秒後となると、35人の動きを一人ひとり書き出して答えを求めることもできますが、なかなかに大変な作業でしょう。
問2で、2の累乗の秒数ごとに2人が立ち上がる時間がやってくることに気が付ければ、その1秒後に立っている人数は、いずれも4人であることが分かります。
このような規則性を利用した調べの問題は、他校ではあまり見かけない、特徴的な問題だと言えるのではないでしょうか。
ぱっと規則性が思い浮かばなくとも、ある程度書き出す時間があれば、解けた問題であるとも言えます。特に大問1や大問2などの小問集合はできるだけ早く処理し、大問3以降の後半の問いにいかに時間をかけられるかがポイントです。
③国語
桐光学園中学校の国語の問題は、例年、以下の形で出題されます。
|
大問1:漢字の書き取り |
大問1の漢字は、小学校で習う漢字から出題されているので、漢字検定5級レベルまでの漢字が書ければ十分に対応できます。
文学的文章・説明的文章はともに、比較的新しく出版された本から出題されているような傾向が見られます。ですので、2025年度入試に向けては、2023年の秋ごろ~2024年の夏ごろまでに出版された本の中で話題になった本や入試で出題されやすそうだなと思うものには、簡単にでも目を通しておくとよいでしょう。
文学的文章では、場面や状況の把握や登場人物の心情やその理由、表現の特徴などがよく問われており、説明的文章では、筆者の考えなどに加え、会話形式で本文の要旨を問うような問題も出題されています。
昨年度入試の特徴的な問題として、第1回の大問2の問6「———線5「るり子は大げさに~川を覗き込んだ」とありますが、その理由について、わかりやすく説明しなさい。」という問題について説明します。
この問題は、主人公の心情を説明する記述問題ですが、傍線部分が六三字と長く、「頭をふる」「ため息をつく」「フェンスにからだを寄せる」「川を覗き込む」という4つの一連の動作について記述しなければならない点、「わかりやすく説明しなさい」と条件が付けられている点、字数制限が設けられておらず、罫線もない大きな解答欄しか用意されていないという点が特徴で、どの程度具体的に書けばよいのか、悩む受験生が多いのではないでしょうか。
桐光学園中学校では、このような記述問題が例年出題されています。配点も12~16点程度と大きいので、ここで高得点をとれるかどうかが合否を分けると言えるでしょう。
このような問題に対応するためには、傍線部を丁寧に読み取り、複数の要素に分ける練習をすることが大切です。そして、その要素1つ1つに対応するように登場人物の心情をおさえ、文章としてつなげて書く練習をすることが必要です。
「わかりやすく」「ていねいに」など、問いの文言は多少変わりますが、大きな解答欄の場合、60~70字程度で文章をまとめられるように練習しておくとよいでしょう。
➃理科
理科は、地学・化学・生物・物理の大問4題で、各分野からまんべんなく出題されています。
2024年度の第1回は以下の構成でした。
|
大問1:地学分野の小問集合 |
地学分野は、天体や天気、流れる水のはたらきなどから多く出題されているほか、環境問題などと関連させた出題も見られます。化学分野では、物質の反応や水溶液の性質など、比較的オーソドックスな中学入試の問題が出題される印象です。生物分野に関しては、動物や植物のからだのつくりに関する問題がよく見られます。
2024年度の第1回の問題では、桐光学園の周辺の里山や裏山、ビオトープなどに生息する生き物に関する出題が特徴的です。まず、問題文が長く、どのような情報を与えられているのか・何を問われているのかを整理することに時間がかかった受験生も多かったことでしょう。具体的な生き物や植物の名前が多く挙げられているものの、それほどメジャーな生き物でもなかったため、不安を感じたのではないでしょうか。
問3の(2)では、ホトケドジョウの数を計算することが求められています。条件から、全体の生息数に占める印をつけた個体の割合と、あとから捕まえた数に占める印のついた個体の割合が同じであるとみなして計算していきます。理科的な知識だけではなく、算数的な計算の力も求められている問題です。
桐光学園の理科の問題では、身近な現象や生物環境に関する問題が出題されることが多くあります。学校の周りに生息している生き物の名前や特徴などをある程度知っていると、より問題を具体化して考えるでしょう。桐光学園のSNSでは、学校周辺の生物環境についてよく投稿されているので、定期的に確認してみるのも試験対策に繋がるかもしれません。
⑤社会
社会の問題は、大問3題で構成されています。記号で選択する問題と、空欄に適する語句を答える問題が多く出題されますが、数行程度の記述問題も出題されています。
2024年度の第1回は、以下の出題でした。
|
大問1:2023年5月に開催された、G7広島サミットに関する問題 |
地理・歴史・公民ともに、幅広い分野から出題されることに加え、地図や資料を活用した問題も多く見られます。
地理分野は、日本の自然や気候、農林水産業の特徴や、人口、生活、文化などの内容が出題されています。歴史に関しては、特定の時代というよりも、あるテーマに関しての総合的な問題がよく見られます。公民分野は、時事的な事柄が取り上げられることが多く、経済や国際関係、条約、環境問題などが出題されています。
2024年度の第1回の問題で特徴的だったのは、G7広島サミットを軸にした複合問題でしょう。G7に関連する国の場所や地名、各国の首相や大統領の顔、開催地である広島の歴史やジェンダーギャップに関するグラフの読み取り問題など、様々な知識が求められました。特に問7番の、【核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン】と2つの新聞記事を読み、一部の被爆者やNGOがなぜ「広島ビジョン」を批判しているのかを説明する問題は、多くの受験生が苦戦したものと思われます。『「核なき世界」の理想と現実』が何を指しているのか、その内容が過不足なく伝わるように意識しながら理由を丁寧に書かなければならなかった点が、難易度が高かったと言えるでしょう。
社会ではまず、質問事項が多岐にわたるため、不得意分野を作らないことが重要です。また、先ほど取り上げた大問1では、日本三景や「明治日本の産業革命遺産」など、学校や塾での学習でもなかなか触れないような内容に関連させて出題される場合もよく見られますので、ただ知識を覚えるだけでは歯が立たないような問題もあると言えるでしょう。日頃からあらゆることに関心を持って、気になることは調べるように意識付けしておくと、効果的に試験対策ができます。
3. 桐光学園中学校の受験対策
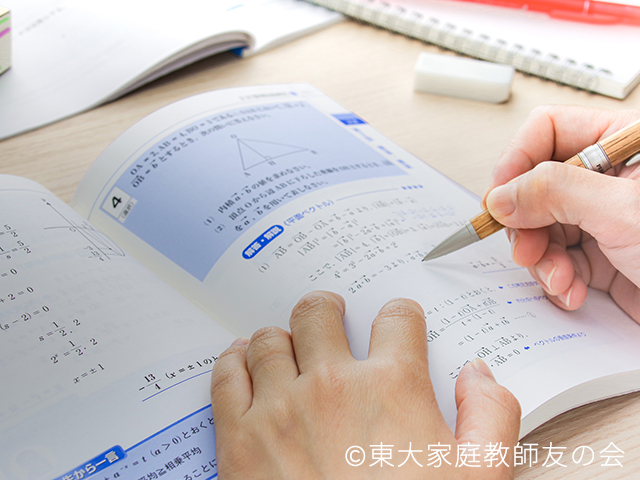
桐光学園中学校の受験対策を紹介します。
①時期別・教科別対策方法
ここでは、本格的に受験を意識し始める小学校4年生から受験直前までの受験対策を紹介します。
(1)小学4年生
まずは、様々な学校を知って、自分の志望校・受験校を探していく時期でしょう。
この時期は、学習習慣を身につけさせることが重要です。習い事などと並行して塾に通ったり、家庭での学習を続けている段階の生徒様も多いのではないでしょうか。
最低限、学校や塾の宿題などのやるべきことをしっかりこなす時間を確保するとともに、中学受験の土台として、算数については基礎計算の正確さとスピードを養い、国語に関しては様々な種類の本に親しむ機会を作りましょう。
(2)小学5年生
5年生から本格的に受験勉強を始めるご家庭も少なくないため、模試の偏差値がぐっと下がったりしてしまい、気持ちのコントロールが難しい5年生。この1年を頑張り切れるかどうかが、最終的な合格を左右するのではないでしょうか。5年生では、伸ばすのに時間のかかる能力や、直前期には取り組むのが難しいようなものをやっておくことがおすすめです。
【算数】:基礎計算の正確さやスピードはもちろん、論理的に考える力を伸ばしたいのがこの時期。論理的思考を伸ばすドリルなどに楽しみながら取り組むことをお勧めします。
【国語】:語彙の学習に力を入れたいのが、5年生の1年間。慣用句や四字熟語、故事成語などに積極的に触れる機会を作りましょう。
【理科】・社会:まだまだ、必要な知識を入れる段階の理科や社会。塾や学校で習ったことを丁寧に復習し、確実に自分の力にしていきましょう。
(3)小学6年生(4月~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校が具体化してくるのも、この時期なのではないでしょうか。
【算数】:時間を意識して解けるように、このころから準備を始めていきましょう。中学受験に特有のつるかめ算や旅人算、面積図などはこの時期あたりまでに使いこなせているとよいですね。もちろん、それらを使わなくとも、答えを導き出すことはできますが、知っているとぐっと解く時間を短縮できますし、計算ミスを防げます。
【国語】:漢検5級範囲までの漢字は、確実に読み書きできるようにしましょう。また、読解の記号選択式の問題は、根拠を持って答えを導き出せるようにしましょう。
【理科】:苦手分野をつくらないように、幅広く基礎固めに取り組んでいきたい時期です。受験勉強のスタートが遅かった生徒様も、この時期までに一問一答形式の知識を問う問題はしっかり解けるようにしましょう。
【社会】:地理分野をしっかり固めておきたい時期です。理科と同様に、一問一答形式の問題にはしっかり答えられると良いですね。
(4)小学6年生(7月~8月)
「夏は受験の天王山」と言われるほどのこの季節。体調管理と生活リズムを整えることに注意しながら過ごしたいですね。
【算数】:中学受験の定石と呼ばれるような問題の解き方はこの時期までにマスターしておくことをお勧めします。
【国語】:桐光学園中学校の近年の大問1・2の出題傾向から考えると、昨年~夏休みの時期あたりまでに話題になった本は軽くでも目を通しておくと良いでしょう。
【理科】:この時点で、知識を問うような問題には確実に答えられるようにしましょう。
【社会】:歴史分野の総復習に力を入れたいのがこの時期。時代ごとにどんなことがあったのか、という横のつながりはもちろん、「文化」「政治」など、ジャンルごとの縦の歴史のつながりについても整理しましょう。
(5)小学6年生(9~11月)
志望校合格に向け何をしなければならないのか、ゴールから逆算して考えるのがこの時期です。冬が近づいてきたら、過去問にもチャレンジしましょう。
【算数】:過去問でよく出題される分野の問題を中心に、苦手な分野を潰していきましょう。
【国語】:力が身に着くまでに時間のかかる科目なので、読解や記述系の問題は、この時期に重点的に取り組みましょう。
【理科】:夏に固めた基礎を活かして、実験や観察に関する問題に取り組んでいきましょう。
【社会】:過去問の傾向も意識しながら、より実践的な内容に取り組めるよう、地図やグラフを用いた問題を中心に演習しましょう。
(6)小学6年生(12~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、新しいことをしたり、覚えたりというよりは、どの科目もこれまでしてきたことを振り返り、抜け漏れているところがないかどうか確認し、見つけ次第復習する期間です。
②桐光学園中学校の過去問対策
ここでは、入試本番に向けての過去問の効果的な使い方や、過去問にチャレンジする時期などについてお伝えします。桐光学園のホームページでは、過去5年分のすべての入試問題と解答をダウンロードできるので、有効に活用してください。
(1)過去問の効果的な使い方
過去問を解く目的は、2つあると考えています。
1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。過去問を解いて間違ったところは、今の時点で復習が必要なポイントということです。残りの時間で、間違えた問題の知識を確認したり、類題に取り組むことで、同じような問題が出た際には解けるように、準備しておきましょう。桐光学園中学校の場合、入試回ごとの合格最低点を公開していますので、その情報と照らし合わせてみるとよいでしょう。
2つ目は、時間的な感覚を掴むためです。入試は、決められた時間内に合格点をとる必要があります。ですので、過去問に取り組む時には、時間の感覚を身につけるために、入試本番のスケジュール通りに問題を解いてみることをお勧めします。
(2)過去問はいつから解き始めればよいか
過去問は、ある受験校が固まり、間違えた分野の問題に取り組む時間的・精神的な余裕がある、6年生の11月~12月ごろ以降に解き始めるのがおすすめです。併願校として受験するのであれば、直前でも構いません。
年末から年明け以降、試験日が徐々に近づいてくると、過去問が売り切れてしまっていて手に入らない、ということもあり得ますので、冊子として持っておきたい場合には、余裕を持って準備しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばよい?
第1志望の場合は3~5年分、併願校として受験する場合にも、2,3年分は過去問を解いておきましょう。6年以上前の問題に関しては、学習指導要領が現行のものとは違っていたり、傾向が現在と異なることがあるので、解かなくても心配はありません。
過去問は、1周すれば十分です。1回で解けた問題は、ケアレスミスなどがない限り、何度やっても解けるからです。もうすでにできていることに時間を割くよりも、できないことをできるようにすることのほうが大切です。1度解いて間違った問題は時間をかけて復習し、解けるまで何度でもチャレンジしましょう。
③保護者様にできるサポート内容
(1)生徒様に合った学習環境、リラックスできる環境を整える
学習のスタイルは生徒様によって違います。1人でじっくり取り組みたい生徒様もいれば、誰かと一緒のほうが安心して、集中できる生徒様もいますし、集中できる環境が保護者様とお子様で違う、ということも十分にありえることです。
生徒様がどのような環境なら集中して取り組めるのかをよく見極め、それに合った学習環境を準備できるようにしましょう。
また、生徒様が気持ちをリセットしたりほっと安心できるような、1人になれる空間や時間を作ることも大切です。
(2)生徒様ご本人の成長に目を向ける
点数や順位と向き合わなくてはならないのが中学受験。どうしても、ご兄弟やお友達、保護者様ご自身と生徒様を比較してしまいがちですよね。ですが、その気持ちをぐっとこらえて、生徒様ご本人の成長に目を向けましょう。
模試の結果なども、以前の生徒様との変化を比べて、伸びている点や良かった点に目を向けた声掛けができると、生徒様の自己肯定感を伸ばしていくことに繋がり、結果として前向きに学習に向かう姿勢にもなっていくことでしょう。
ご家庭でのサポートは、日々の学習の質を高め、入試本番に向けた確かな力を育むうえで大きな支えとなります。
とはいえ、受験期は不安や悩みが尽きない時期でもあります。
「このままで大丈夫かな?」「どこまでサポートすればいいの?」と迷う場面もあるでしょう。
そんなときは、中学受験に詳しい家庭教師のサポートを活用するのも一つの方法です。
保護者様の不安を軽減しながら、生徒様に合った学習サポートで、合格に向けた準備をスムーズに進めることができます。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 桐光学園中学校を受験する場合の併願パターン

桐光学園中学校を受験する場合の併願パターンとして、男子受験生、女子受験生、帰国生に分けてご紹介します。
①男子受験生の場合
|
・東京都市大学等々力中学校 |
共学校が比較的人気の併願校です。特に、サッカー、野球、バスケットボールなどのスポーツ系の部活動を頑張りたいと思っている生徒様は、法政第二中学校や桐蔭学園中等教育学校を併願していることが多いように感じます。
男子校であれば、
|
・東京都市大学付属中学校 |
②女子受験生の場合
女子受験生の場合には、併願校にも女子校を選んでいる生徒様が多く、
|
・洗足学園中学校 |
共学校を併願先としている場合には、男子受験生と同様に
|
・桐蔭学園中等教育学校 |
③帰国生の場合
帰国生の場合は、併願先として
|
・慶應義塾湘南藤沢中学校 |
英語教育に力を入れていて、先進的な学びに取り組んでいる学校が選ばれているような印象ですが、女子生徒の場合は、カリタス女子や洗足学園など、キリスト教系の女子校を併願先にしている場合も多いようです。
【参考文献】
・声の教育者「桐光学園中学校2025年度用スーパー過去問」
・桐光学園中学校・高等学校ホームページ https://www.toko.ed.jp/high/notice/current.html
5.桐光学園中学校の受験対策をはじめよう!
本記事では、桐光学園中学校の入試概要や4教科の対策、併願パターン、過去問の活用法などを解説しました。
国語・算数は標準的なレベルですが、国語の読解量や算数の調べる問題など、粘り強く取り組む力も求められます。
理科・社会では、時事問題や身近な事象を含む幅広い出題が特徴です。日頃から関心を持ち、過去問で形式に慣れておきましょう。
受験期は保護者様のサポートも重要です。学習面だけでなく、心身のケアも含めて、親子で合格を目指していきましょう。
「このままで大丈夫?」「何から始めればいい?」と迷ったら、中学受験に詳しい家庭教師への相談がおすすめです。
一人ひとりに合った指導で、桐光学園中学校合格をしっかりサポートします。
まずは、家庭教師の無料体験授業からお気軽にご相談ください。
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
家庭教師が桐光学園中学校合格へのサポートをいたします
他の学校の入試傾向・受験対策