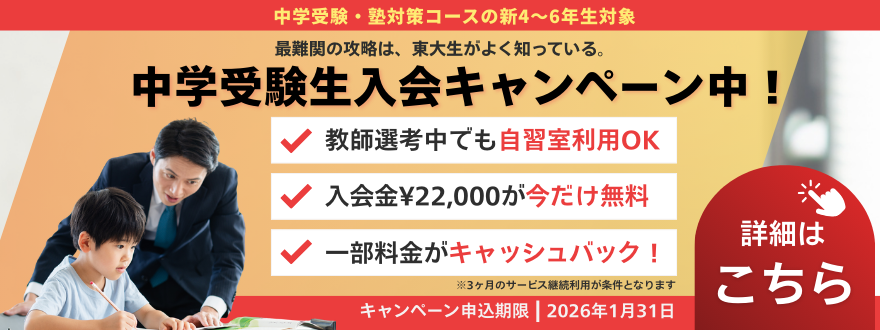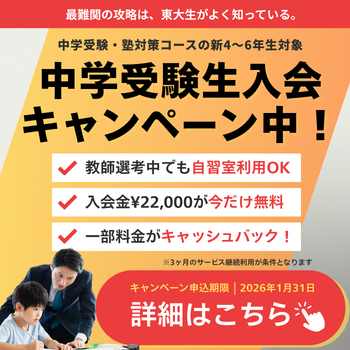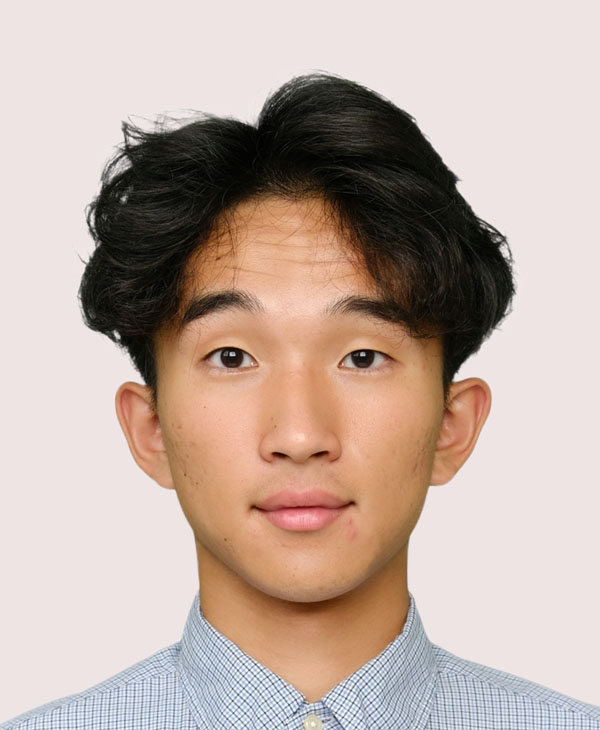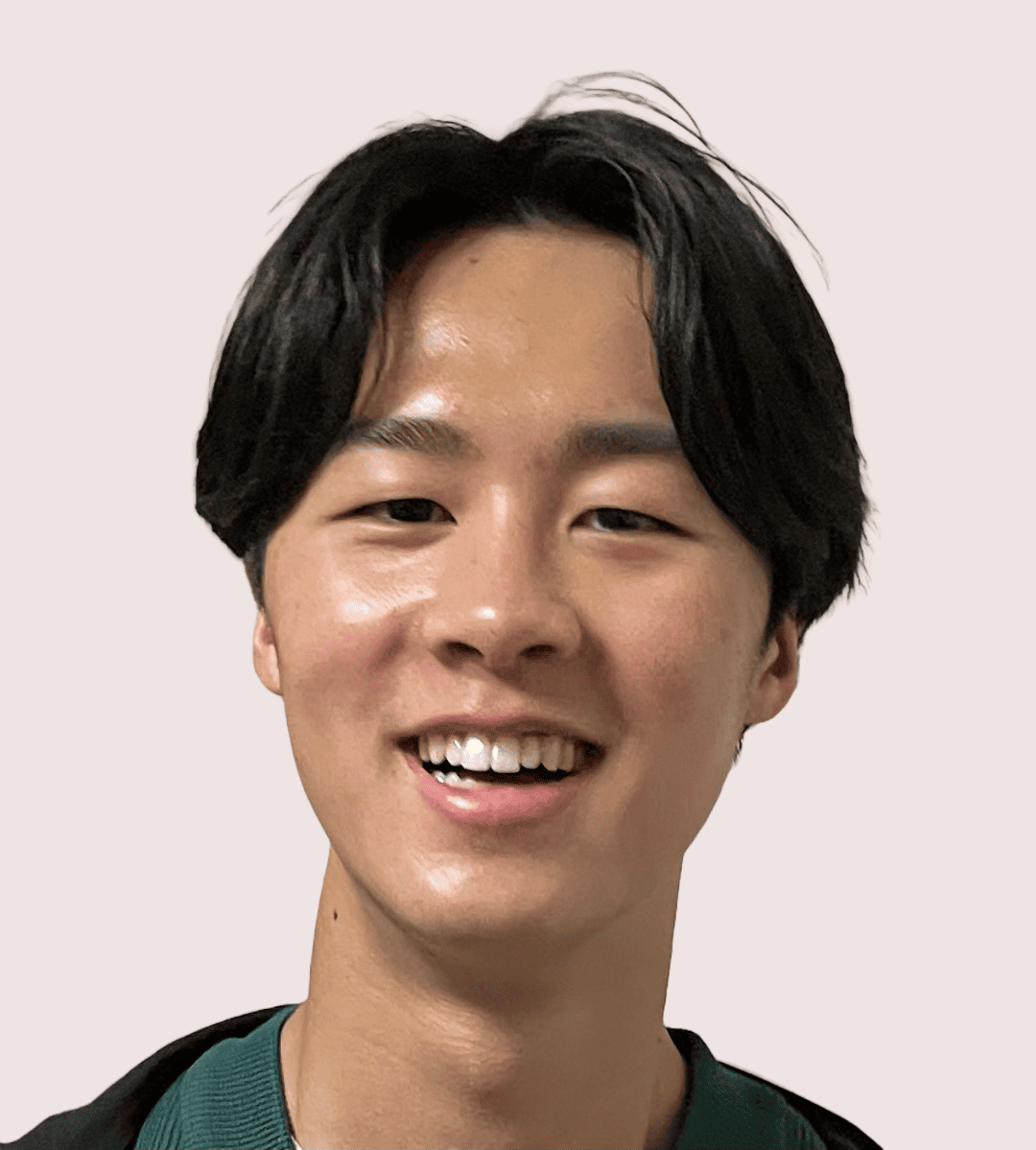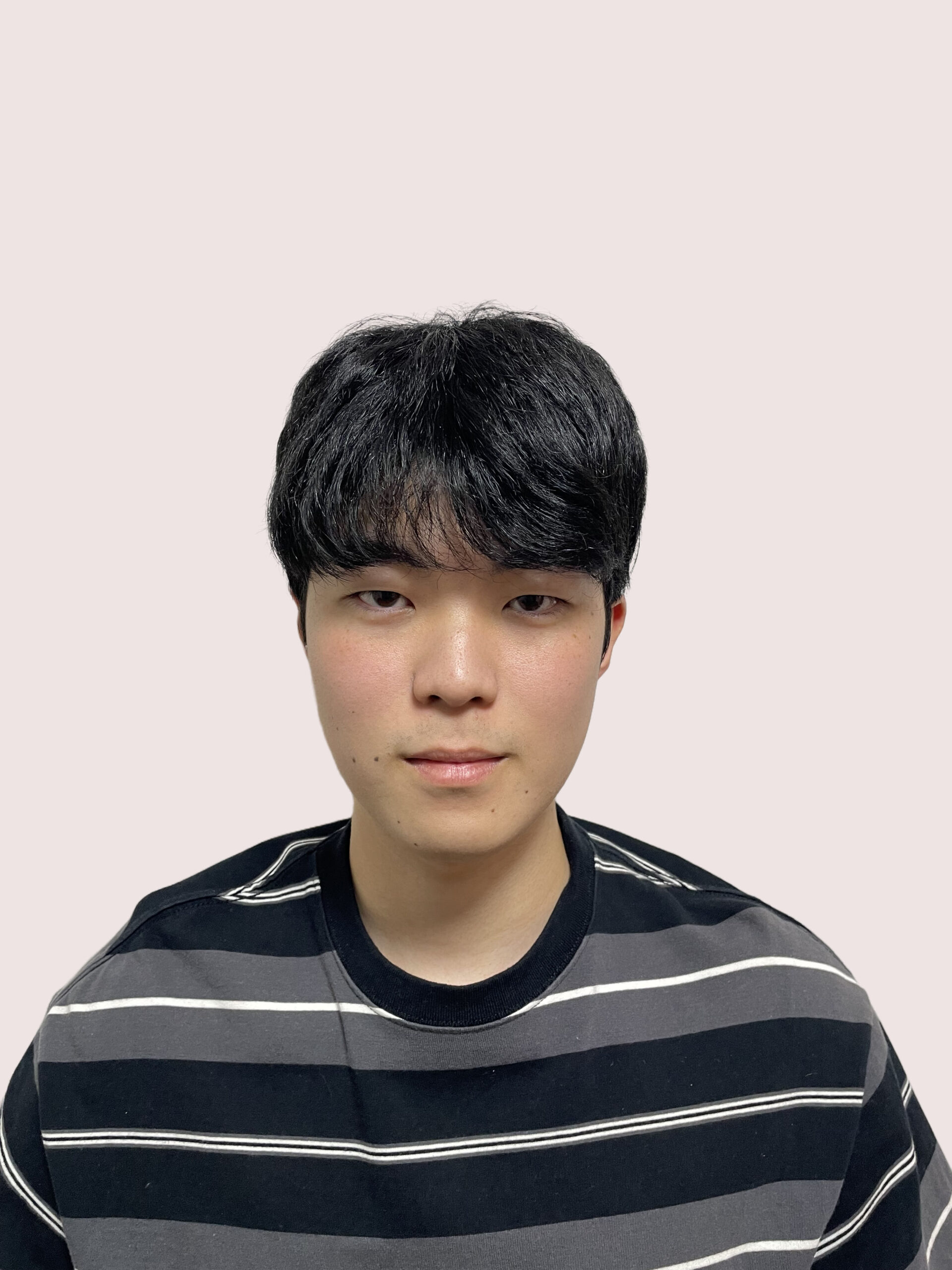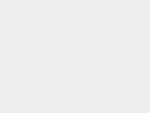![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 東京都立武蔵高等学校附属中学校の偏差値と基本情報
東京都立武蔵高等学校附属中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①東京都立武蔵高等学校附属中学校の偏差値
東京都立武蔵高等学校附属中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」と「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
| 2/3 一般 適性 |
男子 62 女子 62 |
男子 69 |
②東京都立武蔵高等学校附属中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
2008年 |
|
所在地 |
|
|
アクセス |
JR中央線・西武多摩川線「武蔵境駅」北口より徒歩約10分 |
| 校種 | 東京都立の中高一貫校 |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | 習熟度別・少人数授業 45分7時間授業 中高合同行事 地球学 |
| 部活動 | 運動部9、文化部12 |
「自主自律」と「文武両道」の精神を大切にする、東京都立武蔵高等学校・附属中学校。
高校では制服がなく、自主性を尊重する自由な校風も魅力のひとつです。都立中高一貫校の中でも、比較的自由度が高い学校として知られています。
武蔵の特色ある教育活動として、次の3つのポイントをご紹介します。
①豊かな知性と感性を磨く武蔵の授業
東京都立武蔵高等学校・附属中学校では、確かな学力を育むための充実した指導体制が整っています。その理由は、習熟度や学習段階に応じた柔軟な授業編成にあります。
たとえば、国語・数学・英語では習熟度別・少人数制の授業を展開し、理解を深めやすい環境が整えられています。さらに、中学理科ではチームティーチングの形式を採用し、実験や観察を積極的に取り入れることで、体験的に学べる授業を実施しています 。
また、中高一貫の強みを活かし、中学段階から高校内容の先取り学習を行い、高校2年までは全員が主要5科目を履修。高校3年次に文系・理系に分かれるカリキュラムを採用しており、進路に応じた学びへとつなげます 。長期休業中の講習や記述対策講座など、受験対策のフォローも万全です。
このように、東京都立武蔵高等学校・附属中学校では、一貫した学びと多様な指導法により、生徒一人ひとりの学力を着実に伸ばしていきます。
②独自の探究授業「地球学」
東京都立武蔵高等学校・附属中学校では、「地球規模の視点から物事を見る」ことをテーマに、教科の枠を超えた探究活動を展開しています。
また、文献調査、実験・観察、インタビューといった多様な調査手法に加え、グループワークを通じた課題研究にも取り組みます。
人類が直面するさまざまな課題について、自ら問いを立て、解決策を見いだす力を育成。こうした探究的な学びを通して、国際社会で活躍できるリーダーの資質を養っています。
③生徒様が主体の様々な学校行事
「三大行事」として知られる音楽祭(6月)、体育祭(9月)、文化祭(9月)は、中高合同で生徒様が主体となって企画・運営する学校行事です。どの行事も毎年大いに盛り上がり、生徒様の創造力や団結力が発揮される貴重な機会となっています。
また、これらの三大行事に加え、地球学発表会、校外学習、球技大会、修学旅行など、学年ごとに多彩なイベントが年間を通して実施されます。本番だけでなく、企画・準備の過程から楽しめることも大きな魅力で、仲間との絆を深める貴重な時間となっています。
2. 東京都立武蔵高等学校・附属中学校の入試傾向
武蔵高校附属中学校の入試は、一般枠募集のみで行われます。合格者は、小学校での学習状況を記した「報告書」と「適性検査」の総合得点によって決定されます。
ここでは、気になる倍率をはじめとした「入試の概要」「報告書の得点換算方法」「2024年度入試で特徴的だった問題」「合否の分かれ目となった設問」について解説します。
①入試の概要
武蔵高校附属中学校の入試の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|
募集人数 |
男子80名 |
|
配点(1,600点満点) |
報告書:400点 |
|
試験時間 |
適性検査Ⅰ:45分 |
| 2024年度倍率 |
男子:2.5倍 |
| 問題の構成 |
|
②報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の「各教科の学習の記録」の評定を点数化します。
| 項目 | 内容 |
|
対象学年 |
小学5年生 |
|
対象教科 |
国語・社会・算数・理科・音楽・図工・家庭・体育・外国語(英語) |
|
評定の点数化 |
評定3:25点 |
| 1学年あたりの満点 |
225点(9教科 × 最大25点) |
| 2年間の合計満点 |
|
| 換算後の点数 |
400点満点に換算 |
③適性検査Ⅰ
東京都立武蔵高等学校附属中学校の適性検査Ⅰ〔問題3〕では、文章の内容を的確に読み取ったうえで、自分の考えを論理的かつ具体的に表現する力が求められます。2024年度も2つの文章を比較しながら、文章の主張を踏まえた上で、「今後の学校生活で言葉をどう使いたいか」を400~440字の作文としてまとめる問題が出題されました。
2つの文章は以下の通りです。
| 内容 | |
|
文章1 |
短歌を繰り返し心の中でつぶやくことで、自分の気持ちを保つことができる内容 |
|
文章2 |
他者の気持ちを想像しながら学んでいくことで、すばらしい俳句が生まれる内容 |
※ どちらを選んでも採点には影響なし
自分が書きやすい方を選択して、作文にまとめます。作文のおすすめ構成は、三段落構成の双括型です。
| 段落 | 内容 |
|
第1段落 |
選んだ文章の筆者の主張と、それに基づいて自分が言葉をどう使いたいかを述べる |
|
第2段落 |
そう考える理由を、自分の体験などを通して具体的に述べる |
|
第3段落 |
|
作成した作文が以下の観点で評価されます。
| 評価される観点 | 内容 |
|
読解力 |
文章の内容を的確に把握し、自分の考えに反映できているか |
|
論理性 |
自分の考えが論理的に展開されているか |
|
具体性 |
自分の体験や具体例を交えて述べているか |
| 表現力 |
適切な言葉遣いや語彙を用いて表現できている |
| 形式面 |
原稿用紙の使い方や段落構成が明確であるか |
適性検査Ⅰ〔問題3〕では、他者との関わりを意識した「言葉の使い方」について、自分の考えを根拠とともに書けるかどうかが鍵になります。日頃から読書や作文の練習を通して語彙力を増やし、自分の考えを具体的に表現する習慣を身につけましょう。
➃適性検査Ⅱ
東京都立武蔵高等学校附属中学校の適性検査Ⅱでは、資料から情報を読み取り、課題に対して論理的に思考・判断する力が問われます。2024年度は以下の3つの大問が出題されました。
| 大問 |
内容 |
出題意図 |
|
大問1 |
得点板の数字をマグネットシートで作る条件整理問題 |
与えられた条件の下で柔軟に考え、論理的に処理する力を問う |
|
大問2 |
貨幣の歴史・小判の価値の変化・銀行設立の背景を扱う独自作成問題 |
資料読解力・数値計算力・時代背景の理解力・記述力が求められる |
| 大問3 |
摩擦に関する実験結果から物体の性質を考察する問題 |
実験結果から因果関係を導き、説明する科学的思考力を問う |
本校独自作成の大問2では、「貨幣の歴史」や「銀行の設立」といった時事的な題材が中心となっており、2024年の新紙幣発行も背景にあります。問題は3問構成で、以下のような出題でした。
| 問題 |
出題形式 |
ポイント |
|
〔問題1〕 |
【鎌倉時代における土地の価値の表し方の変化】 |
地域ごとの貨幣普及の違いを根拠に簡潔にまとめる力を問う |
|
〔問題2〕 |
【江戸時代の小判に含まれる金の量と価値の変化】 |
資料をもとに数値を算出し、因果関係を説明する力を問う |
| 〔問題3〕 |
【銀行設立数の増加とその背景】 |
資料と会話文を読み取り、背景と理由を整理して書く力を問う |
2024年度の入試では、新紙幣発行やお金にまつわる時事的話題が取り上げられました。これは武蔵高校附属中学校に限らず、多くの学校で共通した傾向です。こうした時事問題に対応するために、以下のような習慣がおすすめです。
|
・新聞やニュースを日常的にチェックする ・時事ニュースに関連する歴史や背景も意識して調べる ・数値の読み取りや割合計算など、基礎的な算数の力を磨く |
⑤適性検査Ⅲ
東京都立武蔵高等学校附属中学校の適性検査Ⅲは、すべて独自作成問題で構成されており、算数・理科を融合した思考力・論理力重視の出題が特徴です。2024年度は以下の3つの大問が出題されました。
| 大問 |
内容 |
|
大問1 |
図形の移動や長さ、数列に関する問題 |
|
大問2 |
ジュース製造や蒸発を題材にした算理融合問題 |
| 大問3 |
図形デザインを題材とした面積と配置に関する論理問題 |
この中でも、図形分野が頻出である大問1に注目して解説します。
問題は3問構成で、以下のような出題でした。
| 問題 |
出題形式 |
ポイント |
|
〔問題1〕 |
【五角形の回転と頂点の動き】 五角形を直線上で回転させ、頂点の動きを予測する問題 |
空間認識と回転の規則を丁寧に追う力を問う |
|
〔問題2〕 |
【傘の開閉の規則性】 会話文をもとに傘の開閉パターンを読み取り、128人目の傘の状態を判断 |
数列の増加と開閉の交互変化に気づく力を問う |
| 〔問題3〕 |
【円の中に小円を敷き詰める問題】 |
計算に基づいて論理的に成立しない根拠を説明する力を問う |
上記の問題に対応するために、以下の対策をしましょう。
|
・回転や数列のパターンを日常的に扱い、視覚的・論理的に処理する練習を積む ・理科的知識(蒸発など)と算数的思考(面積、割合、規則性)を組み合わせる演習をする ・答えの導出だけでなく、「どう説明するか」に重点を置いた記述練習をする |
⑥出題形式の似ている学校
出題形式が似ている学校としては、適性検査型や思考力型の入試問題を採用している中学校が挙げられます。中でも聖徳学園中学校の「適性検査型(三科型)」は、武蔵高校附属中学校の入試問題を参考に作成されており、問題演習に適しています。過去問を活用して、出題傾向や記述力を鍛えましょう。
また、都立中高一貫校の中でも理数教育に特化している「都立小石川中等教育学校」の適性検査Ⅲもおすすめです。この問題は算数と理科の融合問題が中心なので、条件を整理しながら論理的に思考する力を養うのに適しています。
3.東京都立武蔵高等学校・附属中学校の受験対策
武蔵高校附属中学校の合格に向けては、時期に応じた学習計画と、過去問の効果的な活用が重要です。また、家庭での保護者様のサポートもお子さまの学習意欲を高める大きな力になります。
ここでは、実践的な対策法を詳しく解説します。
①時期・教科別受験対策
(1)小学4年生
この時期は、まず学習習慣をしっかりと定着させることが最も重要です。あわせて、都立中高一貫校の入試で求められる思考力・分析力・表現力の土台となる4教科(国語・算数・理科・社会)の学習に幅広く取り組み、苦手分野を作らないようにしましょう。
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 社会 |
|
(2)小学5年生
都立中高一貫校の受験では、5年生から学校の「報告書(内申書)」が選考の対象になります。
とくに武蔵高校附属中学校では、総合得点に占める報告書の割合が25%と高く、他の学校に比べて学校での学習活動が重視される傾向があります。そのため、主要4科目に限らず、すべての教科にバランスよく取り組むことが大切です。また、5年生の後半以降は、適性検査を意識した対策も徐々に始めていきましょう。
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 社会 |
|
(3)小学6年生(4月~6月)
いよいよ勝負の6年生。受験対策が本格化する時期ですが、これまで通り学校の学習にも手を抜かず、日々の授業を大切にすることが重要です。
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 |
|
| 社会 |
|
(4)小学6年生(7月~8月)
「受験の天王山」とも言われる夏。特に夏休み中は生活リズムを整え、目標を持って計画的に学習を進めましょう。
| 算数 |
|
| 国語 |
|
| 理科 社会 |
|
(5)小学6年生(9月~11月)
秋は、実はスランプに陥る生徒様が多い時期。モチベーションを維持する工夫が欠かせませんが、過去問に本格的に取り組み始める重要なタイミングでもあります。
大切なのは演習後の振り返りの質です。単に丸付けをして終わりにせず、その問題で問われているポイントや自分の答案と解答・解説との違いを確認しながら、自分の弱点や課題に気づきましょう。気づいたことは必ずメモに残し、次の学習につなげてください。
(6)小学6年生(12月~1月)
受験直前期となるこの時期は、過去問の復習に加え、出題形式が類似している他校の過去問も活用しながら、実戦的な問題演習で仕上げをする段階です。
また、1月入試にチャレンジする場合は、学力面だけでなく、本番に向けた体調管理やモチベーションのペース配分も含めて事前に練習しておきましょう。
②過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方
過去問を解く目的は2つあります。
|
・問題の出題形式を知る ・時間の感覚を掴む |
(2)過去問はいつから解き始めればよいか
過去問に取り組むのは、6年生の秋(9月〜11月ごろ)から始めるのが効果的です。
この時期は、入試範囲の学習が一通り終わり、間違えた問題を見直す時間的・精神的な余裕があるため、過去問演習に集中しやすいからです。
秋から過去問に取り組むことで、自分の苦手分野を把握し、間違えた問題をもう一度解き直す時間を確保できます。さらに、他校の過去問から似たタイプの問題を選んで練習することで、応用力や実戦力を高めることもできます。しっかりと計画を立てて取り組みましょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
第一志望として受験する場合は、過去5年分程度を目安に解きましょう。
併願校として受ける場合でも、2〜3年分は必ず取り組むべきです。
とくに武蔵高校附属中学校の適性検査Ⅱの大問2と適性検査Ⅲは、独自作成が導入されてからの全ての問題に取り組んでおくと安心です。
過去問は、できなかった問題の解き直しに時間をかけ、できるまで挑戦しましょう。
③保護者様にできるサポート
(1)物事を多角的に見る視点を身に着けさせる
適性検査では、物事を多角的にとらえ、情報を的確に分析・判断する力が重要になります。
1つの事柄をさまざまな視点から考え、自分の考えを整理して言語化する力が求められるからです。
適性検査では、「あるできごとについて、異なる立場で考え、自分の意見を述べなさい」といった記述問題が出題されることがあります。
そのため、日常生活の中で生徒様自身が気になったニュースや身近なできごとについて、「どう思う?」「他の見方はあるかな?」など、意見を言葉にする習慣が効果的です。
こうしたアウトプットの経験が、中学入学後に始まる探究学習においても、自ら問いを立て課題を解決する力の土台になります。日々の対話を通じてその力を育てていきましょう。
(2)生徒様ご本人の成長に着目して、前向きな声掛けをする
中学受験期には、他の子と比較するのではなく、生徒様ご本人の小さな変化や成長に目を向けることが大切です。生徒様一人ひとり、学習に集中できる環境や得意・不得意、やる気が出るタイミングは異なります。他のごきょうだいや周囲の子と比べてしまうと、生徒様の自尊心が傷ついたり、学習意欲が下がったりする原因になることがあります。
たとえば、模試の結果を見たときには、「なんでこんな点数なの?」という声かけよりも、「ここが前より良くなったね」「見直しが丁寧にできているね」と本人の努力や変化に目を向けた言葉をかけることで、生徒様は前向きな気持ちで学習に向かいやすくなります。中学受験を、親子の信頼や絆を深める機会として前向きに過ごしていけるとよいですね。
(3)健康管理とメンタルサポートをする
受験期には、保護者による健康面と精神面の両面からの支えがとても重要です。
小学校高学年は思春期に差しかかり、心も体も不安定になりやすい時期です。それに加え、学校生活と受験勉強の両立で、子どもたちは大人が思っている以上に忙しく、知らないところでプレッシャーや不安を感じていることがあります。そのため、受験本番だけでなく、そこに向かう日々の中でも、生徒様がベストなコンディションで学習に取り組めるような環境づくりが欠かせません。
具体的には、栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠時間を整えることはもちろん、ストレスや不安を抱えたときに安心して相談できる関係性づくりが大切です。また、必要に応じて生徒様が一人で心を落ち着かせたり集中できたりする時間や空間をつくることも、メンタルの安定につながります。健康面と心の面、両方をサポートしてあげましょう。
ご家庭でのサポートは、日々の学習の質を高め、入試に向けて実力をしっかりと育てる支えになります。
とはいえ、受験期には「このままで大丈夫?」「どこまでサポートすればいいの?」といった不安や悩みがつきものです。
そんなときは、受験に詳しい家庭教師に相談してみるのも一つの方法です。
保護者様の不安を軽減しながら、生徒様に合った学習サポートで、合格に向けた準備をスムーズに進めることができます。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 東京都立武蔵高等学校・附属中学校を受験する際の併願パターン
ここでは、ライターが過去に出会った武蔵高校附属中学校を志望する生徒様の併願校の傾向をもとに、おすすめの併願校をご紹介します。
武蔵高校附属中学校を目指すご家庭の併願戦略は多様で、とくに「偏差値帯」「校風」「出題形式」の3つの観点から学校選びをされるケースが多く見られます。加えて、他の都立中高一貫校を志望する場合と比べて、大学附属校を併願校に選ぶ傾向が強いのも特徴です。
なお、以下の情報は2024年度入試をもとに作成しています。2025年度の最新情報については、各校の公式募集要項をご確認ください。
それでは、それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。
①同偏差値帯併願パターン
武蔵高校附属中学校と同程度の偏差値帯にある中学校を併願校として選ぶパターンです。
学力面でのバランスを重視しながら、学習環境や大学進学実績にも注目して学校選びをするご家庭におすすめの併願スタイルです。
とくに、将来の進路まで見据えた中長期的な視点から、一定以上の学力水準を維持したいご家庭に適しています。
(1)1月入試
|
・栄東中学校 |
(2)2月1日
|
・国学院久我山中学校 |
(3)2月2日
|
・明治大学明治中学校 |
(4)2月4日以降
|
・頌栄女子中学校 |
②校風重視併願パターン
こちらは、武蔵高校附属中学校の自主性や自律性を重んじる校風に魅力を感じている方におすすめの併願パターンです。
学力面での偏差値帯は①のパターンと比べて上下の幅がありますが、生徒様主体で行事や活動を進める学校を中心に選定しています。
校風や教育方針の共通点を重視して併願校を検討したいご家庭に適した選び方です。
(1)1月入試
|
・渋谷教育学園幕張中学校 |
(2)2月1日
|
・中央大学附属中学校 |
(3)2月2日
|
・明治学院中学校 |
(4)2月4日以降
|
・中央大学附属中学校 |
③出題形式重視併願パターン
こちらは、都立中高一貫校を志望する受験生を主な対象とした、いわゆる「適性検査型」「思考力型」「公立型」入試を実施している学校を中心に併願するパターンです。
とくに聖徳学園中学校の適性検査型(三科型)は、2023年度入試において121名もの武蔵高校附属中学校受験生が併願している実績があり、人気の高い併願校のひとつとなっています。
(1)1月入試
|
・昭和学院中学校 |
(2)2月1日
|
・聖徳学園中学校 |
(3)2月2日
|
・目黒日本大学中学校 |
(4)2月4日以降
|
・順天中学校 |
5. 東京都立武蔵高等学校・附属中学校の受験対策をはじめよう!
東京都立武蔵高等学校・附属中学校は、「自主自律」と「文武両道」を重んじる、自由な校風が魅力の都立中高一貫校です。
入試は一般募集のみで、調査書と適性検査の総合得点により合否が決まります。中でも調査書の比重が25%と高く、日々の学習態度や授業への取り組みが重要です。
適性検査では、共通問題に加えて武蔵独自の出題もあり、時事的な話題を扱った問題や、論理的思考を求められる記述問題が特徴です。そのため、日頃からニュースや社会の動きに関心を持ち、自分の考えを言葉にする力を養っておくことが大切です。
もし「どこから対策すればいいかわからない」「もっと効率よく勉強したい」と感じたら、家庭教師の無料体験授業を活用してみるのもおすすめです。
生徒様に合わせた指導で、無理なく合格を目指せます。ご相談からでもOK!お気軽にお問い合わせください。
【参考文献】
・声の教育社「東京都立武蔵高等学校附属中学校2025年度用スーパー過去問」
・都立武蔵高等学校・附属中学校ホームページ
・都立中との併願について|聖徳学園中学・高等学校
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
武蔵高校附属中学校の受験対策なら東大家庭教師友の会
他の学校の入試傾向・受験対策