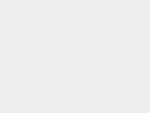1.東京学芸大学附属小金井中学校の偏差値と基本情報
東京学芸大学附属小金井中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①東京学芸大学附属小金井中学校の偏差値
東京学芸大学附属小金井中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」と「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
| 2/3 一般 4科 |
男子 49 |
男子 54 |
②東京学芸大学附属小金井中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1947年 |
|
所在地 |
東京都小金井市貫井北町4丁目1−1 |
|
アクセス |
JR中央線「国分寺駅」より徒歩約15分 |
| 校種 | 国立・共学校(中学校) |
| コース | 中学校単独校(高校は別募集) |
| 特徴的な教育 | ・教育実習や教育研究の場としての役割を持ち、東京学芸大学と連携した教育活動を実施 ・自主・自立の精神を重んじ、体験・活動を重視した学習 ・制服は定められておらず、生徒自身が中学生らしい品位ある服装を自主的に選択 ・修学旅行やスポーツフェスティバルなど、主体的に取り組む学校行事が充実 |
東京学芸大学附属小金井中学校は、東京都小金井市にある国立中学校です。東京学芸大学の附属校としても運営されています。
理数系及び英語の教育に力を注いでおり、「学びあい」を通して問い学び探求を「深める」学習をテーマとしています。また、各学年で一回行われる修学旅行も特徴的です。修学旅行の本来の意味である「学を修める」ことに重きを置いており、事前学習、事後学習に半年かけて取り組みます。
最も多い進学先は東京学芸大学附属高校ですが、私立高校に進学する生徒様もおり、進学先は多岐にわたります。
2.東京学芸大学附属小金井中学校の入試傾向
東京学芸大学附属小金井中学校の入試は、国語、算数、理科、社会の筆記試験と面接が行われます。
筆記試験の問題の構成やスタイルは基本的にはオーソドックスですが、一部特徴的な問題が出題されることがあります。以下では、過去問の特徴的と対策方法を解説します。
①国語
(1)出題傾向
大問1では例年リスニング問題が出題されます。
年度によっては、数問にわたってリスニング問題が出題される場合もあります。解答方式は、選択肢問題や記述問題など様々な形式が用いられます。
近年は、日本の人口・高齢化がテーマの文章が出題されました。
(2)対策のポイント
問題文は一度しか読まれません。読解力以外に聞いた言葉を瞬時に理解し、要点をメモする能力が必要になります。日ごろからニュースやラジオを聴く機会を増やし、保護者と一緒に内容を確認することが大切です。
また問題の特性上、決まった時間をこの問いに費やさなければならないため時間配分が難しくなります。そのため、普段から時間配分を意識しながら問題を解く訓練が大切になります。
②算数
(1)出題傾向
前半に計算問題を出題し後半に文章題を出題するオーソドックスな形式で、問題数は少なめです。
後半の文章題は、問題文を正確に読み取ることができれば、基礎計算で解ける問題です。しかし、読解の難易度が高く読み取るのに時間がかかります。
(2)対策のポイント
前半の計算問題で、計算ミス等のケアレスミスをしないことが大切です。また、後半の文章題は、問題文をしっかり読まなければいけません。
前半に時間をかけず正確に解き、読解が必要な後半に時間を残す時間配分が必要です。過去問は複数年分を解き、時間配分の感覚を身に着けるようにしましょう。
③理科
(1)出題傾向
基礎知識が中心の問題構成ではあるものの、中盤から終盤にかけてところどころ時間がかかる問題や頭をひねる問題が見られます。
近年では、植物の呼吸(酸素・二酸化炭素の出入り)の実験についての図解を用いた問題が出題されました。基礎知識のみの習得ではなく、実験や図の理解などの応用力も必要な問題でした。
(2)対策のポイント
図解の実験問題では、問題文を読み込む必要があるため、他の問題に比べ時間がかかります。また、理科の基礎的な知識に加えて、問題文の要点を把握すること、図の違いが何を表しているかを読み取る力が求められます。実験の内容は小学校の授業で行うものと似ているため、授業で行った実験の復習をすることで対策しましょう。
また、本番の試験では一度この問題を飛ばして、後で解くのも有効です。他の問題を解いた後、ゆとりをもって問題に取り組みましょう。
④社会
(1)出題傾向
例年、小問中心で終盤まで進行し記述問題が2題前後出題されるようなオーソドックスな問題形式です。記述問題については時事問題について問う問題や、生活に必要な知識などを問う問題も出題されます。
また、日本地図を用いた問題が2022年から3年間連続で出題されています。例えば、文化庁の庁舎移転先を地図から選ぶ問題、近年人口が減少している道府県を地図から選ぶ問題、G7サミットの開催地を地図から選ぶ問題などが出題されました。
(2)対策ポイント
日本地図の問題は、各県ごとに番号が振られている日本地図が用意されており、その図を用いて回答していく形式です。事前知識として、各都道府県の場所と名称を把握している必要があります。トイレやお風呂に日本地図を貼り、日常的に目にすることで、都道府県の位置を自然と覚えられます。
⑤出題傾向の似ている学校
東京学芸大学附属小金井中学校の問題は比較的オーソドックスな問題が多いです。出題傾向の似ている学校としては、城北中学校、世田谷学園などがあげられます。
3.東京学芸大学附属小金井中学校の受験対策
全体を通して、学習時間を決めて、自由時間もきちんと設けられるようにするのがおすすめです。こうすることで、生徒様のやる気を保ち、メリハリをつけながら学習に取り組むことができます。
時期別の受験対策
①5年生
学習習慣を身につけましょう。目安として1日あたり3~4時間程度の学習時間を確保できるとよいでしょう。
②6年生(4月~8月)
5時間以上の学習時間を確保しましょう。また、受験校についても本格的に絞り込みをしていくとよいでしょう。夏休みに突入したら、1日に9時間程度は勉強するようにしましょう。
③6年生(9月~12月)
この時期から週に1~2本程度、過去問に取り組むようにしましょう。過去問は新しいものから取り組み、どの問題を間違えたのか整理するようにしましょう。過去問の効果的な使い方は以下で詳しく解説いたします。
過去問の効果的な使い方
ここでは過去問の効果的な使い方を解説いたします。
過去問に取り組む目的は大きく分けて3つあります。
1つ目は、問題の難易度や傾向をつかむことです。
そのためには、過去問を解いた後の復習が大切になります。解けなかった問題や、どのような問題が出ていたかをしっかり確認するようにしましょう。直近5年分の過去問は受験直前期に集中的に取り組むのが効果的です。
2つ目は、試験の際の時間配分を身に着けることです。
試験では知識だけでなく、決められた時間で問題を解ききることが大切になります。そのため、過去問を解く際は本番と同じスケジュールで取り組むことをおすすめいたします。
3つ目は、予備知識や基礎知識の定着の確認です。
東京学芸大学附属小金井中学校の社会の入試問題では、3年連続で都道府県の位置を予備知識を必要とする問題が出題されています。このような問題で間違えてしまった場合は、間違えた原因が予備知識の不足であったのかを確認するようにしましょう。
保護者様からできるサポートについて
1つ目は勉強が嫌いにならないようにすることです。
成果報酬型にし、「テストでよい点を取れたから外食に行こう」など、頑張ったご褒美をあげてもよいでしょう。最初のきっかけはどうであれ、勉強が嫌にならないように工夫してみましょう。
2つ目は点数が悪くても叱るのではなく勉強方法を生徒様に合ったものに変えること、
3つ目は人と比較しないことです。
受験は確かに人との競争です。しかし、人と1回の模試の点数で競い合うよりも、生徒様に合った学習スタイルで内容をどれだけ吸収し、いかに本番発揮するかどうかの方が重要です。
模試でうまくいかなかったとしても、叱るのではなく、本番失敗しないように学習に取り組むことのできる環境づくりを優先しましょう。
4.東京学芸大学附属小金井中学校を受ける際の併願パターン
東京学芸大学附属小金井中学校の入試は、2/3に実施されます。したがって1月に試験が実施される栄東中学校を受験し、試験に慣れておくとよいでしょう。
また、直前である2/1に入試が実施される獨協中学校や日本大学豊山中学校を併願することも、試験に慣れるためにはよいでしょう。
5.東京学芸大学附属小金井中学校の受験対策をはじめよう!
東京学芸大学附属小金井中学校の入試では、国語、算数、理科、社会の筆記試験と面接が行われます。
筆記試験の問題は比較的オーソドックスなものが多く、基礎的な知識の定着具合を確かめる問題が多く出題されます。問題数は少ない傾向があるため、ケアレスミスを減らすことが大切です。また、読解力が必要な文章問題が出題されるため、時間配分には気をつけましょう。
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら