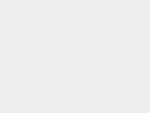1. 法政大学第二中学校の偏差値と基本情報

法政大学第二中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①法政大学第二中学校の偏差値
法政大学第二中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」と「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
| 2/2 第1回 4科 |
男子 57 |
男子 69 |
| 2/4 第2回 4科 |
男子 57 |
男子 69 |
法政大学第二中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受験する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②法政大学第二中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1939年 |
|
所在地 |
神奈川県川崎市中原区木月大町6‑1 |
|
アクセス |
JR南武線・武蔵小杉駅西口 徒歩約12分 |
| 校種 | 私立共学校(中高一貫校) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・研究・実験・プレゼン等を取り入れ、大学進学に必要な能力を育成 ・英語・数学は分割授業で、英語が外国人講師による指導強化 ・調査・実験・討論・発表型授業を通じたアクティブ・ラーニング実践 |
法政大学第二中学校は、法政大学の附属中学校ということももちろんですが、神奈川屈指のスポーツ強豪校としても知られ、大変人気のある学校です。また、最寄り駅は武蔵小杉駅と、神奈川県各所からも東京都内からもアクセスがよく、広範囲から生徒が通ってきています。
元々は男子校でしたが、2016年に共学化が始まり、2024年度入試では入学者の募集人数も、男女同数のずつ募集になりました。
①中学校から大学までの10年一貫教育
法政大学では、中学校から大学までの「10年一貫教育」を掲げており、生活上の問題がなく、かつ学校の定める成績の水準に到達できていれば、全員が法政大学第二高校へ進学できます。学校ホームページによると、毎年、ほぼすべての生徒が内部進学に必要な成績水準に到達できているようです。
さらに、普段の定期テストなどの成績や生活態度が一定の基準に達成しており、法政大学の指定する外部英語試験、法政大学の各付属高校に通う生徒が受験する「基礎的思考力確認テスト」で基準となる成績を修められた希望者は、全員、法政大学へ進学できます。また、法政大学への進学の権利を持ったまま、他の国公私立大学を受験することも可能です。大学付属学校の場合、他の国公私立大学の受験を希望する場合には内部進学の権利を失う場合が多いので、ありがたい制度ですね。
②学習を定着させる取り組み
法政大学第二中学校では、大学付属校である強みを活かして、受験のための学習に囚われない様々な教育活動を行っています。
中学1年生、2年生の間は、学びの基礎・基本を育てる期間と考え、1クラス30名以下の少人数編成で授業を行っています。
特に、毎日の積み重ねや反復が重要だと言われている英語や数学では、1週間に2、3時間程度、クラスの人数をさらに半分にした、15人前後の単位で授業を行い、生徒一人ひとりの学習状況をしっかり把握し、それぞれに合った取り組みができます。
また、「実際に体験すること」を重視した授業も行っています。例えば理科では、中学校3年間を通して週に2時間、実験を伴う授業を行うなど、中高一貫で余裕のあるからこその独自のカリキュラムで授業が行われています。
③中学の学びの集大成「総合」
法政大学第二中学校で、3年間の学びの集大成と位置付けられているのが、3年生の「総合」の時間です。グループごとにテーマを決め、1年間を通じた探究学習を行います。広島への研修旅行や、教科横断的な探究学習での学びも踏まえながら、中間発表を行い、さらに年度末には、学習の成果をプレゼンテーション大会で発表します。
まさに、協働的で探究的な学びといえるこうした場があることで、仲間とのコミュニケーション能力も高まります。
2. 法政大学第二中学校の入試傾向

ここでは、各入試の試験日程や募集人数、昨年度の倍率などの入試概要についてお伝えします。
帰国生入試は、国語・算数(各50分・各100点)の2科目と、保護者同伴の面接の結果で総合的に判断します。昨年度の倍率は、男子が1.6倍、女子が1.9倍でした。面接の内容等は公表されていません。
一般入試は第一回が2月2日、第二回が2月4日に行われます。試験科目は、国語・算数が試験時間各50分で各100点満点、理科・社会は試験時間各40分間で各75点満点の、合計350点満点で行われます。
いずれの日程も、試験当日は8時15分集合で、合格発表は当日の22時にWeb(校内掲示は翌日10時から)で行われます。
2024年度入試では、募集人数が第一回では男女各70名、第二回では男女各35名と、男女の募集人数の比率が同じになりました。
男子の倍率は、第一回が4.5倍、第二回が6.9倍に対して、女子の倍率は第一回が3.0倍、第二回が3.5倍でした。2023年度入試と比較し、男子の倍率は高く、女子の倍率は低くなっていることから、募集人数の男女均等化が倍率に多少影響したのかもしれません。
①学校としての出題傾向
全体的には中学入試の標準的な問題が多く、基礎・基本がしっかり固まっている生徒を獲得したいという学校側の意図がはっきりと見て取れます。その一方で課題文は全教科共通して比較的長く、しっかり問題を読み込む忍耐力は必要だと言えそうです。
近年は資料を見て読み取れることを記述したり、自分の意見を述べたりする問題が出題されるなど、記述問題の分量も増えつつあり、その傾向は今後も続くのではないかと予想されます。
②算数
算数の問題は、例年、大問6題で構成されています。答えのみを解答用紙に書く形式です。
|
大問1:基本的な計算問題
|
の問題です。
2024年度入試の第一回、大問6のような立体図形の面積や体積を求める問題は、法政大学第二中学校では頻出の問題と言えます。
水を入れた直方体の容器について、問1では水の高さから中に入っている水の体積を求めます。問題自体は単純ですが、水の高さが分数であることから、正確な計算力が求められます。
問2では、ある一辺だけが地面に接するように、かつ面が地面と45度になるように直方体を傾けたときの地面から水面までの高さを、さらに問3では、ある頂点だけが地面に接するようにして、直方体を傾けていき、辺の比を使いながら体積を求めます。
問題には図が書かれてはいるものの、高さや体積を求める部分がどの部分なのか、イメージ化できるかどうかが問題を解くうえで大きな鍵になるでしょう。この問題であれば、辺EA、ZY、WⅩを延長して交わる点(仮に、Оとします)を頂点とする三角錐OWEZから、三角錐OXAYを引いた部分が、求める水の体積になります。三桁×二桁分の二桁の分数のように、正確さが求められる計算を何度も行う必要があり、計算の正確さと粘り強さが必要です。
大問5・6で最後の問題までしっかり解き、他の受験生と差をつけるためには、図形を正確に把握する力が必要です。また、大問1・2の標準的なレベルの問題で、いかに失点しないかが大切です。
③国語
法政大学第二中学校の国語の問題は、例年
|
大問1:漢字・同意語・品詞
|
の構成です。
大問1は、漢字の読み取り・書き取り、品詞の識別などの知識が問われます。大問2の論説文は、2024年は第一回で高橋源一郎、第二回で森達也の文章が出題されています。例年、文章量は3000~5000文字程度で、人文・社会科学系の文章がよく選ばれています。多くは記号の選択問題ですが、記述問題も出題されています。
大問3の物語文は、重松清や益田ミリなど、中学受験生にとってはお馴染みの作家の作品が出題されており、文章量は多いですが、内容としては読みやすいと言えるでしょう。問題は、場面の把握や登場人物の心情を読み取る問題が中心です。
2024年度入試の特徴的な問題として、第一回の大問3の問八「傍線部⑦「星野先生の宿題に、きみなら、どんなふうに答える」とあるが、あなたはここでの「星野先生の宿題」に対してどのように答えますか。次の条件に従って説明しなさい」という問題について説明します。
この問題は「1、星野先生の宿題が、どのような内容でどのような意図があるのか明確になるように説明すること」「2、1を踏まえて自分ならどのように答えるか説明すること(ただし、本文中に書かれたことは書かないこと)」「3、字数は八十字以上百字以内」という3点が条件として与えられています。
回答としては、星野先生の宿題には「希望」にあふれた理想的な地球の姿を子どもたちに考えてほしいという意図があった、という内容に加え、「希望」のある地球とはどのようなもので、そのためにどのようなメッセージを送るのがよいか、自分の考えを具体的に書く、という大きく二段階の構成で書けるとよいでしょう。
後者に関しては、星野先生の意図に合ったことが書ければよいので、実際に自分ができるか/やりたいかも重要ですが、回答を書ききる、問題を解き終えることに重点を置きましょう。
これまでの法政大学第二中学校の記述問題は六十字から八十字程度であることが多かったため、それに比べて記述の分量が多く、「自分の具体例を挙げる」という点に戸惑った受験生も多かったのではないでしょうか。2024年度の第一回入試では、大問2の問八でも字数は八十字以上百二十字以内で、筆者の主張をふまえつつ自分自身の具体例を挙げて説明するという問題が出題されており、比較的分量の多い記述問題が2題出題されています。
まずは記述問題にしっかり取り組めるように、ある程度スピード感を持って文章を読む必要があります。そのうえで条件に従い、1つ目の条件で指示されていることを的確に説明する力が必要です。日頃から意味段落ごとに文章を要約するなどの練習をしておくとよいでしょう。
➃理科
理科は大問5題構成で、地学・化学・生物・物理の各分野からまんべんなく出題される傾向があります。2024年度の第一回は、
|
大問1:外来種に関する問題
|
という構成でした。
地学分野は、天体や天気、地形や地層の問題がよく出題されます。化学分野では、水溶液や気体の性質に関する問題が多く、物理分野では力学や電気回路からの出題が目立ちます。生物分野では、植物の分類や季節と植物に関する内容、ヒトの消化酵素や血液の循環などは必ずチェックしておきたい分野です。さらに大問5のように、科学の歴史や環境問題が題材になることもあります。問題のレベルとしては中学入試の標準的なレベルの問題がほとんどなので、落ち着いて解けるように準備しておきましょう。
2024年度の第一回では、大問1~4をいかにミスなくこなし、さらに大問5でどの程度正解できたかで受験生に差がついたと言えそうです。
この問題は、近年、地質年代の新たな区分として「人新世(じんしんせい)」という時代を設けることが検討されており、国際地質科学連合が作業部会を設置し、検討を進めているが、「人新世」が新たな地質年代として正式に求められるようになるまでには、まだ検討の余地がある、ということを説明した文章の空欄にあてはまる語句を、記号で選択する問題でした。そもそもこの話題について触れたことのない受験生も多く、多くが戸惑いを感じたのではないでしょうか。
社会で解説した問題と同様にこの問題も、そもそもこの話題について知っているかどうかが大きなポイントとなるでしょう。かといって、テレビのニュース等で大きく取り上げられた話題でもないことから、対策が難しいとも言えます。学校や地域の図書館などで、小・中学生向けの科学情報雑誌などに目を通すようにすると、様々な話題に触れられるため、より科学に対して親しみが持てます。
⑤社会
社会の問題は、大問5題で構成されています。記号で選択する問題に加え、語句を答える問題、並び替え問題、記述で答える問題と、問題の出題形式はバラエティーに富んでいると言えます。 2024年度の第一回は、
|
大問1:日本の世界遺産に関する問題
|
が出題されました。
地理・歴史・公民ともに、幅広い事柄を問う出題になっていることが多く、細かい専門的な内容を問うような問題はあまり出題されません。
地理分野は、各地の自然や気候、農林水産業、生活や文化に関する問題が必ず出題されています。歴史分野は説明文や史料をもとに、空欄を補充したり関連する事柄について問う問題が多く出題されています。記述問題は歴史分野から出題されることが多いため、ある出来事に関して、表面的な理解だけではなく。その因果関係を理解できているかどうかが問われていると言えるでしょう。公民分野は、憲法に関連した出題が多くみられる点が特徴です。環境問題や、時事的な内容を題材にした問題が出題されることもあります。
2024年度の第一回の問題で特徴的だったのは、大問3の問題です。原始から現代までの人間と犬との関わりをテーマにして書かれた課題文を読み、関連する事柄について答える問題です。課題文の空欄に当てはまる語を答える問題、一問一答形式の語句を答える問題、記号選択式の問題のほか、銅鐸に描かれた文様を見て何をしている図かを答えたり、戦時中にハチ公像が回収された原因を記述で答えるなど、一つの大問の中で様々な出題形式が見られました。
どの問題も標準的なレベルの問題ではありますが、問12の、1957年に世界で初めて宇宙に飛び立った犬「ライカ」について述べ、世界で初めて人工衛星の打ち上げに成功した国を答える問題は、難易度が高かったと言えるでしょう。まったく知識がなかったとしても、傍線部の前の部分に「東西冷戦の時代」とあるので、(あ)ソ連か(い)アメリカの2択までは選択肢を絞ってほしい問題です。
2024年度の第一回では、2023年5月に行われた「G7広島サミット」に関連させ、核軍縮に関する問題が出題されていたように、時事問題に関連させた出題が見られる傾向があります。ですので、日頃からニュース番組を見たり新聞を読んだりして、社会の動きによくアンテナを張っておくことも効果的な試験対策と言えるでしょう。
3. 法政大学第二中学校の受験対策

ここでは、法政大学第二中学校を受験するにあたり、
「どのような時期に、何をしたらいいのか?」
「過去問はいつ頃、どのように取り組むのがよい?」
「ご家庭ではどんなサポートができる?」
といった、具体的な受験対策に関する疑問にお答えしていきたいと思います。
①時期別・教科別対策方法
ここでは、本格的に中学受験に向けて準備を始める生徒様の多い、小学校4年生から受験直前までの、時期別の受験対策方法をご紹介します。
(1)小学4年生
受験勉強の本格的なスタートにあたるこの時期は、学習習慣を身に着けさせることが重要です。まだ、習い事などと並行して塾に通ったり、塾に通わずに学習している生徒様も多いのではないでしょうか。最低限、学校や塾の宿題などのやるべきことをしっかりこなす時間を確保するとともに、中学受験の土台として、算数については基礎計算の正確さとスピードを鍛え、国語に関しては様々な種類の本に親しむ機会を作りましょう。
また、法政大学第二中学校の入試の理科・社会では、時事的な内容に触れながら様々な知識について問うような問題が出題されています。図鑑や百科事典などにたくさん触れて、教養としての知識を身につけたり、興味や関心を広げていくようにしましょう。
(2)小学5年生
気持ちのコントロールが難しい5年生。この1年を頑張りきれるかどうかが、最終的な合格を左右するのではないでしょうか。5年生では、伸ばすのに時間のかかる力や、直前期には取り組むのが難しいようなものをやっておくことがおすすめです。
算数:工夫して計算する力を身につけたいのがこの時期。分数の処理や計算の手順など、基礎計算のスピードと正確さ、両方を身につけられるように練習していきましょう。
国語:語彙の学習に力を入れたいのが5年生の1年間。慣用句や四字熟語、故事成語などに積極的に触れる機会を作るとともに、法政大学第二中学校では品詞などの問題も出題されるため、口語文法に関する学習を先取りしておくと安心です。
理科・社会:まだまだ、必要な知識を入れる段階の理科や社会。塾や学校で習ったことを丁寧に復習し、確実に自分の力にしていきましょう。
(3)小学6年生(4月~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校を具体的に絞っていくのもこの時期でしょう。
算数:時間を意識して解けるように、このころから準備を始めていきましょう。中学受験に特有で、法政大学第二中学校でも頻出のつるかめ算や旅人算などはこの時期あたりまでに使いこなせているとよいですね。
国語:漢検5級範囲までの漢字は、確実に読み書きできるようにしましょう。また、読解の記号選択式の問題は、根拠を持って答えを導き出せるようにしましょう。
理科:苦手分野をつくらないように、幅広く基礎固めに取り組んでいきたい時期です。受験勉強のスタートが遅かった生徒様も、この時期までに一問一答形式の知識を問う問題はしっかり解けるようにしましょう。
社会:地理分野をしっかり固めておきたい時期です。理科と同様に、一問一答形式の問題にも対応できるようにしておきましょう。
(4)小学6年生(7月~8月)
「夏は受験の天王山」と言われるほどのこの季節。体調管理と生活リズムを整えることに注意しながら過ごしたいですね。
算数:中学受験の定石と呼ばれるような問題の解き方はこの時期までにマスターしておくことをお勧めします。特に立体図形の頻出パターンの問題に関しては、この時点で問題を読んだだけで解法が思い浮かぶようにしておきたいですね。
国語:記述問題の対策に力を入れたい時期。特に2024年度入試では、自分の経験や意見をもとにして書くような問題が出題されているので、似たような形式で、百字程度で意見を述べる練習をするとよいでしょう。
理科:この時点で、知識を問うような問題には確実に正解できるようにしておきましょう。
社会:学校の学習の進度も意識しながらですが、歴史分野の総復習に力を入れたいのがこの時期です。時代ごとにどんなことがあったのか、という横のつながりはもちろん、「文化」や「政治」など、ジャンルごとの縦の歴史のつながりについても整理しましょう。
(5)小学6年生(9~11月)
志望校合格に向け何をしなければならないのか、ゴールから逆算して考えるのがこの時期です。冬が近づいてきたら、過去問にもチャレンジしましょう。
算数:過去問でよく出題される分野の問題を中心に、苦手な分野を潰していきましょう。
国語:力が身に着くまでに時間のかかる科目なので、読解や記述系の問題は、この時期に重点的に取り組みましょう。
理科:夏に固めた基礎を活かして、実験や観察に関する問題に取り組んでいきましょう。
社会:過去問の傾向も意識しながら、より実践的な内容に取り組めるよう、地図やグラフを用いた問題を中心に演習しましょう。
(6)小学6年生(12~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、新しいことをしたり、覚えたりというよりは、どの科目もこれまでしてきたことを振り返り、抜け漏れているところがないかどうか確認し、見つけ次第復習する期間です。
②法政大学第二中学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方
私は、過去問を解く目的は2つあると考えています。1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。過去問を解いて間違ったところは、今の時点で復習が必要なポイントということです。残りの時間で、間違えた問題の知識を確認したり、類題に取り組むことで、同じような問題が出た際には解けるように、準備しておきましょう。
2つ目は、時間的な感覚を掴むためです。入試は、決められた時間内に合格点をとる必要があります。ですので、過去問に取り組む時には、時間の感覚を身につけるために、入試本番のスケジュール通りに問題を解いてみることをお勧めします。
(2)過去問はいつから解き始めればよいか
基本的には、過去問に挑戦するのは、受験校が固まり、間違えた分野の問題に取り組む時間的・精神的な余裕がある、6年生の11月~12月ごろをお勧めしています。ですが、法政大学第二中学校を第一志望としているのであれば、ほとんどの問題は中学入試の標準的なレベルの問題ですので、6年生の9~11月、少し早い時期に、基礎の完成度のチェックも兼ねて挑戦してみることをお勧めします。過去問を解いて解けなかった問題は、まだ基礎が不十分なところと考え、直前期に向けてしっかり克服してきましょう。
併願校として受験するのであれば、直前でも構いません。年末から年明け以降、試験日が徐々に近づいてくると過去問が売り切れてしまっていて手に入らない、ということもあり得ますので、冊子として持っておきたい場合には、余裕を持って準備しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばよい?
第一志望の場合は3~5年分、併願校として受験する場合にも、2、3年分は過去問を解いておきましょう。6年以上前の問題に関しては、学習指導要領が現行のものとは違っていたり、傾向が現在と異なることがあるので、解かなくても心配はありません。
過去問は、一周すれば十分です。1回で解けた問題は、ケアレスミスなどがない限り、何度やっても解けるからです。もうすでにできていることに時間を割くよりも、できないことをできるようにすることのほうが大切です。一度解いて間違った問題は時間をかけて復習し、解けるまで何度でもチャレンジしましょう。
(4)どのくらいできたら安心?
年度によって傾向の変化等もありますので、一概にいうことはできませんが、2024年度入試の合格最低点が、
第一回…男子:227点、女子:218点
第二回…男子:223点、女子:218点
ですので、男女ともに、過去問が240点以上であれば、自信を持って試験に臨めるのではないでしょうか。
③保護者様にできるサポート内容
(1)興味・関心を広げるきっかけを設ける
これまでもお伝えした通り、法政大学第二中学校の理科・社会の問題では、「知っていれば周りの受験生と差をつけられる」というような問題が出題されます。配点も決して小さくはありません。こういった問題に対応するためには、様々なことに興味関心を持ち、教養的な知識を蓄えておくことが必要です。
ですので、博物館や科学館などに一緒に行く、図鑑や百科事典、学習マンガを読むなど、生徒様が楽しみながら自然と興味・関心が広がり、教養が身に着くようにしましょう。
(2)「自分の意見」を持つ練習をする
2024年度の国語の問題では、自分の経験などをもとにしながら、筆者や登場人物の考えに対して意見を述べるような問題が出題されています。
ニュースに対して、「これはどう思う?」と、自分の考えを言葉にすることを促したり、「似たようなできごとはある?」といったように、具体的な自分の経験を引き出す練習を日頃からしておくと、中学受験はもちろん、入学後の探求的な学習のなかでも役立ちます。
(3)生徒様に合った学習環境、リラックスできる環境を整える
どのような環境で学習するのがあっているのかは、生徒様によって違います。静かな環境でじっくり取り組みたい生徒様もいれば、音楽を聴きながらのほうがはかどるという生徒様もいますし、集中できる環境が保護者様と生徒様で違うということも十分にありえることです。
ですので、生徒様がどのような環境なら心地よく学習に取り組めるのかをよく見極め、それに合った学習環境を準備できるようにしましょう。また、生徒様が気持ちをリセットしたりほっと安心できるような、一人になれる空間や時間を作ることも大切です。
4. 法政大学第二中学校を受験する場合の併願パターン
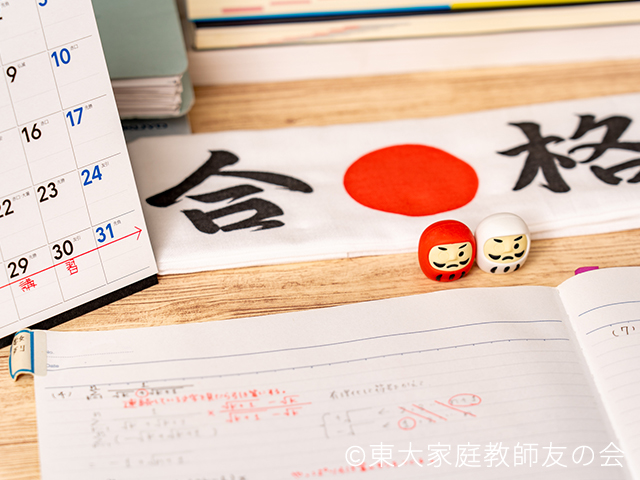
法政大学第二中学校の試験日は、2月2日と4日なので、1日にどの学校を受験するかが併願校を決める上で重要なポイントになると言えるでしょう。
ここでは、将来的に法政大学への進学を希望している場合の併願先、他の大学附属校の併願先、大学附属校以外の併願先に分けて、これまでライターが関わった受験生がどのような学校を併願していたのか、その一例をご紹介します。
やはり、法政大学第二中学校の受験を考えている生徒さんは、大学の附属校と併願している場合が多いように感じます。
どの学校を受験するにせよ、後悔のないような学校選びをするとともに、しっかりと戦略を立てて受験本番に臨みたいですね。
①将来的に法政大学への進学を希望している場合
法政大学の付属中にこだわるのであれば、1日、3日、5日は法政中学校を、2日.4日は法政大学第二中学校を受験するという方法があるでしょう。また、女子生徒様であれば、2015年から法政大学と連携協定を結んでいる三輪田学園中学校を受験するというパターンも考えられます。
②大学付属校を志望している場合
大学の付属中学校への受験を希望している場合は、アクセスの面でも、2月1日午前または2月2日午後に中央大学附属横浜中学校や青山学院横浜英和中学校を受験する生徒様が多い印象です。
また、2月1日に東京農業大学第一中学校を受験する生徒も見受けられます。加えて、男女ともに桜美林中学校や成城学園中学校を受験する生徒さんも少なくない印象です。
③大学付属校以外の併願先
特に男子の生徒様で、「運動系の部活動でスポーツを頑張りたい!」という場合には、桐蔭学園中等教育学校や桐光学園中学校との併願も多い印象があります。
女子の生徒様ですと、香蘭女学校中等科、品川女子学院中等部、頌栄女子学院中学校などとの併願が多い印象です。
5. 法政大学第二中学校の受験対策をはじめよう!
関東各地からのアクセスも良く、法政大学の付属校としてもスポーツの強豪校としても、神奈川屈指の人気を誇る、法政大学第二中学校。
この記事では、法政大学第二中学校の大学付属中学校の内部進学に関する情報や基礎・基本の定着を重視し、少人数で授業が行われることをご紹介したほか、入試の概要、一般入試4教科の入試対策や併願パターン、過去問の効果的な使い方などについて解説しました。
入試問題はどの教科も、中学入試の標準的なレベルの問題が中心なので、いかに失点を少なくするかが重要になってきます。また、近年では「知っているか」で差がつくような時事問題や、自分の意見を述べる記述問題等も出題されているので、普段から様々な出来事や物事に関心を持って、それらに対する自分の考えを述べる練習をすることで、合格に大きく近づけるでしょう。
保護者様は、生徒様の健康面・メンタル面のケアに充分に気配慮するとともに、幅広い話題に触れるきっかけを作っていくようにサポートしてあげられるとよいでしょう。保護者様も生徒様とご一緒に、合格に向けて準備を進めていってください。
【参考文献】
声の教育者「法政大学第二中学校2025年度用スーパー過去問」
法政大学第二中学校・高等学校ホームページ
法政大学第二中学校・高等学校デジタルパンフレット
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら