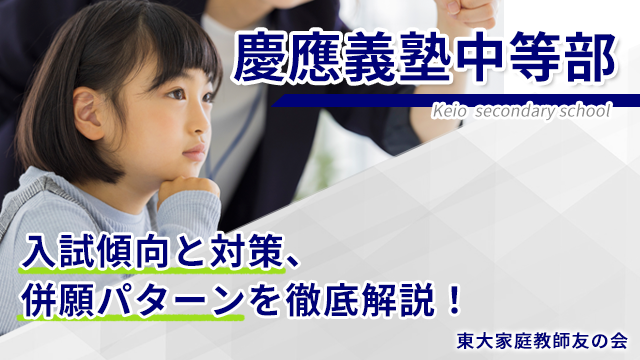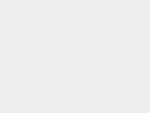1. 慶應義塾中等部の偏差値と基本情報

慶應義塾中等部の偏差値と基本情報について紹介します。
①慶應義塾中等部の偏差値
慶應義塾中等部の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
SAPIX小学部 (合格率80%偏差値) |
|
2/3 |
男子 65 |
男子 74 |
男子 58 |
②慶應義塾中等部の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1947年 |
|
所在地 |
東京都港区三田2‑17‑10 |
|
アクセス |
JR「田町」駅・都営三田線「三田」駅より 徒歩約10分 |
| 校種 | 私立共学校 |
| コース | - |
| 特徴的な教育 | ・校則は最小限で、教室に教壇なし、教員を「さん」付けで呼ぶなど上下関係の垣根を排除 ・「半学半教」の精神で、教員と生徒が共に学ぶ文化 ・質の高い授業 |
1947年に設立された慶應大学付属の共学校。規律は存在しますが、校則は設けられていないなど、自由な校風が特徴です。生徒様一人ひとりが自ら考え、自ら判断し、自ら行動することで、自らが責任を持つ自立した人物になれるように、敢えて自由にし、生徒様に主体性を持たせています。
スポーツも盛んで、野球の早慶戦観戦は大きな伝統行事です。弓術・テニス・器楽など全国レベルの部活もあります。
2. 慶應義塾中等部の入試傾向
慶應義塾中等部の試験は1次試験が算数・国語・理科・社会の4科目の試験です。
試験時間は、算数45分・国語45分・理科25分・社会25分、配点は各々100点・100点・50点・50点です。
1次試験合格後の2次試験は体育実技・保護者様同伴の面接です。
1次試験問題は、全体的にスピード・正確性・幅広い知識が問われる問題です。
幅広い知識と言うのは、塾で習うレベルの知識では、全く物足りません。日常生活の中で、多くのことに興味を持つ・体験することがとても重要です。
①算数
例年、大問6〜7題の出題で、計算・小問集合など含めて、大変広範囲に出題されています。問題量が多いですから、スピードが求められますし、また当然ながら正確性も必須です。問題は基本〜標準的な問題が多いですが、中にはやや難しい問題や複雑な問題が含まれています。
2024年度では、大問6番が図形に関する場合の数の問題で、やや難しい問題でした。場合分けをしながら数え上げるタイプの問題で、時間がかかる問題でしたから、6番(2)の問題は捨ててもよい問題でした。ここに時間を掛けすぎて、しかも不正解となった場合、かなり痛いダメージになりました。問題の取捨選択が肝心です。
と言いつつも、やはりやや難しい問題が解けるレベルまでは引き上げておきたいですから、頻出かつ難しめの問題が出やすい図形・速さ・数の問題には力を入れて学習をして下さい。
②国語
例年、大問5題の出題です。知識問題のみの問題が大問4・5番と2題分あります。
大問5番は漢字で、15題の書き取り問題が出題されます。難しい漢字も出題されますので、高難度の漢字も含めて対策する必要があります。
もう1題の知識問題である大問4番は、四字熟語・ことわざ・慣用句など、定番のものもありますが、細かい文法を問う問題や、社会の時事的な内容に関する知識問題もあります。
残りの大問3題は文章題で、説明文・物語文・随筆文・短歌・俳句など幅広く出題されます。大問1・2番は一般的な文章題が出題され、2題を通して記述問題は設問1題、しかも字数は少なめです。ですので、ほぼ全てが記号問題と言える状況で、文章理解・語彙・表現技法・文学史などが問われています。大問3番が厄介な形式が多く、俳句・和歌は近年の頻出単元です。
2024年度第3問では、文章自体は随筆文の形式でしたが、漢詩の表現技法や、季語・季節を問う問題があり、結果的に俳句の知識が無いと解けない問題でした。対策をしていない生徒様には厳しい入試問題でした。「わかる国語」(旺文社)などの総合的な文法書を一冊用意して頂き、短歌・俳句を始めとした対策が必要だと考えられます。
③理科
例年、大問4〜5題の出題で、物理・化学・生物・地学が満遍なく出題されています。但し、2021年度は物理が出題されず、化学が2題出題されました。
物理・化学は計算問題も出題されますが、どちらかと言うと理解を伴う問題や知識問題が多く出題されます。2024年度では、化学でプラスチックに関する細かい性質が問われる問題、物理が電気回路・コイルに関するしっかりとした理解が必要な問題でした。どちらも、かなり難しい内容で、それぞれの内容を深く理解していないと対応できない問題でした。
生物・地学は、観察問題・考察問題をベースにした問題が出題され、理解が必要な問題が出題されます。しかし、知識問題が多く出題される部分もあり、かなり細かい知識が要求されます。
全科目的に、とにかく広く深く理解・暗記が必要です。塾の教材だけでは対応できないことが多いですから、生徒様自身で、テキストの内容を深く追求していく、図鑑・理科事典を読むなどの対応を取る必要があります。また、科学館や博物館などに興味を持って、足繫く通うこと自体が理科の対策になっていきます。ニュース・新聞記事・科学ドキュメンタリーなどで理科に関する題材を見聞きすることも大切です。
➃社会
例年、大問4〜5題の出題で、地理・歴史・公民・時事・常識問題が出題されています。理科と同様に、広範囲に深い知識が要求されていますが、相違点として、記述問題が複数題出題され、字数も多い時は80字程度必要なことがあります。資料が与えられることもあります。背景知識があった上で記述する力が必要となります。
地理・歴史・公民それぞれ標準的な知識は勿論必要ですが、原点回帰がポイントとなってきます。地理であれば、地図帳・地形図・統計、歴史であれば、写真・絵・史料、公民であれば、憲法の条文・グラフ・資料など、テキストでは十分に網羅されていない事柄を知っていかなくてはなりません。旅行で色々な場所に行くことも大変重要ですし、工場見学やミュージアムといった近場のレジャーも、社会の対策になるでしょう。
時事・常識問題についてですが、時事問題では、ここ10年程度の内容は知っておく必要があります。常識問題としては、例えば、2024年度大問3番で、為替レートに関する問題が丸々一問出題され、差がついたと思われます。苦手単元を無くしながら、実生活との結びつきを理解する必要があります。ニュース・新聞記事・社会ドキュメンタリーなどの内容を見聞きし、十分に深めていくことが大切です。福沢諭吉先生についての見識も深めておきましょう。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
全体的な傾向としては、同じ慶應大学系列の男子校である慶應義塾普通部と似ています。慶應義塾湘南藤沢中等部も参考になるとは思われますが、慶應義塾普通部の方が演習にはよいでしょう。
3. 慶應義塾中等部の受験対策

慶應義塾中等部の入試問題は基本~標準的な問題が中心ですが、それぞれの科目で対応が非常に難しい点があります。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学4年生
算数は、塾のカリキュラムに沿って行っていきましょう。
塾に通われてない生徒様は「予習シリーズ」に沿って進めていくとよいでしょう。
慶應義塾中等部は、満遍なく出題されますので、苦手単元を作らないことが大切です。
また、計算力も必須です。慶應義塾中等部では、必ず計算問題が出題されます。
速く、正確に計算ができるように毎日トレーニングをして下さい。
国語は、慶応義塾中等部の試験問題に記述問題はほとんど出題されません。文章を読んでから、要旨を50字程度で書いていくことが、読解力向上にはよいでしょう。
毎日の読書は欠かさず行いましょう。その際に、いわゆる世界的に、そして日本的に有名な文学作品は必ず読むようにしていきましょう。国語の文学史の問題で問われる可能性がありますし、本文を抜粋して作品を選ばせる問題も出題されています。
また、短歌・俳句の対策も必要です。まずは詩の表現技法を定着させ、できれば詩集も読むとよいでしょう。「ウイニングステップ小学四年生物語と詩」(日能研ブックス)といった問題集で詩に慣れるのもよいでしょう。
理科は、生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記をしましょう。
この分野での暗記問題は多いのですが、塾や学校のテキスト・教科書で出てきたものを深く掘り下げて調べるとよいでしょう。身の回りの現象理解が必要な問題も出題されます。図鑑や理科事典を使用したり、植物園・動物園・科学館・ミュージアムなどに行ってみたりすると、興味の範囲が広がっていくでしょう。
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。
地形図の読み取りが良く出題されます。地形図の読み取りや地図記号を今のうちに理解・暗記をしましょう。統計知識も今のうちに少しずつ入れていきましょう。
ご旅行に行かれるのも大変重要です。旅行の思い出がそのまま地理の勉強にもなります。旅行とまで行かなくても、工場見学やミュージアムなど社会科見学に行くことも大変重要です。
また、ニュース・新聞を見る習慣付けをしていけるとよいでしょう。気になった内容について、調べることも必要です。
(2)小学5年生
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学四年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにして下さい。
少し時間が経ってしまうと、できなくなってしまうことも多いです。
全体的に基本〜標準的な問題をしっかり解けるようにしていきましょう。
図形・速さ・数の問題は難しい問題までできるようにしておきましょう。
国語は、物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。
生徒様自身の意見ではなく、筆者の意見を読み取れるよう、引き続き、要旨を80字程度で書く練習をしましょう。
読書は幅広く文学作品を中心に継続的に読んで下さい。漢字・語彙・文法は細かな内容が出題されます。ことわざ・慣用句も含めて、復習もしっかりと行いましょう。
理科は、物理・化学の計算問題が始まります。慶應義塾中等部は、それほど計算問題は出題されませんが、標準的な問題は解けるようにして行きましょう。
引き続き、暗記事項を覚えつつ、深めていきましょう。物理・化学の現象理解は必須です。何故そうなるのか、また他の実験をしてみたらどうなるのか、という視点で図鑑や理科事典を調べてみるとよいでしょう。
社会は、歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、暗記を行って下さい。年号暗記も忘れずに行って下さい。
主なできごとが何時代なのか、判断できるまで反復して下さい。写真・図・史料といった資料の内容も忘れずに理解・記憶をして下さい。
引き続き、旅行や近場の社会科見学もよいですし、ニュース・新聞から知らないことを調べてみて下さい。また、世の中の仕組みを生徒様に伝えていくことも必要です。例えば、銀行や保険の仕組みや、円安・円高、都会と地方の違いなど、保護者様にとっては当たり前のことが生徒様には当たり前ではありません。世の中の常識(60歳になったら還暦のお祝いをする、など)についても伝えていくようにして下さい。
(3)小学6年生(4月~6月)
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。
特に、図形・速さ・数の問題に不安がある場合は、この時期に克服したい所です。
全体的な復習として、「プラスワン」(東京出版)に取り掛かるとよいでしょう。
過去問にも一度取り掛かってみましょう。
国語は、標準的な文章で、設問の解き方を確認して下さい。
引き続き、読書・漢字・語彙・文法は必須です。
過去問にも取り掛かるとよいでしょう。
理科は、知識の復習をしっかり行い、全単元的に理解を徹底します。
暇さえあれば、図鑑や理科事典を読む位の気持ちでいて頂きたいです。
社会は、公民が始まります。覚えるべき単語は勿論ですが、日本国憲法の条文やグラフ・資料は欠かさず目を通し、理解をして下さい。
地理・歴史の復習は勿論ですが、時事問題にも取り掛かりましょう。ここ10年ほどの時事問題について理解・暗記をしていきましょう。
(4)小学6年生(7月~8月)
算数は、過去問を3〜5回分解いていきましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服していきましょう。
「プラスワン」を1周させ、解き直しもしていきましょう。余裕があれば「ステップアップ」(東京出版)にも取り組み始めるとよいでしょう。
秋以降は、過去問など演習に時間を取られますので、まとまった時間が取れる最後のチャンスです。
国語も、過去問を3回分は解いて、形式に慣れましょう。
読書を継続しながら、漢字・語彙・文法を固めていきましょう。「中学受験国語の必須語彙2800」(エール出版社)のレベルはマスターしたい所です。短歌・俳句の知識を増やしていきましょう。有名な人物と短歌・俳句が結びつくようにすることと、表現技法・季語を理解していきましょう。
理科も、過去問を3回分解きましょう。過去問で弱点を把握し、理解不足の所は、基本に戻って理解をしていきましょう。夏休みは科学館で実験教室なども開かれています。お時間が無い中ではありますが、参加してみるとよい
社会も、過去問を3回分行いましょう。過去問を通して弱点を見つけ、補強して行きましょう。地理・歴史・公民の総復習です。
福沢諭吉先生についての見識を深めていきましょう。「朝日ジュニア学習年間」(朝日新聞出版)・「現代用語の基礎知識学習版」(自由国民社)で時事知識を深めていきましょう。
(5)小学6年生(9月~11月)
算数は、過去問中心になりますが、特に解き直しに力を入れて下さい。
「プラスワン」「ステップアップ」の解き直しをして下さい。特に、図形・速さ・数の問題を中心に解くことをおすすめします。
国語は、過去問を中心に進めますが、漢字・語彙・文法・俳句の強化も忘れずに行なって下さい。
過去問の解き直しも行いましょう。
理科も、やはり過去問を中心に行っていきます。
過去問で出てきた内容については、暗記だけでなく、理解ができているか、保護者様で確認して頂くとよいと思います。
解き直しも忘れずに行って下さい。
社会も、過去問は解きますが、それと同時に、全般的な復習も忘れずに行って下さい。
この時期から「日本のすがた」(最新版)を利用した統計の勉強、及び大手塾が出版している「重大ニュース」を読み、更に時事問題を強化していきましょう。
(6)小学六年生(12月~1月)
算数は、過去問の解き直し、図形・速さ・数の問題を含めた全般的な定着を行いましょう。
この時期でも、過去問演習は効果的ですから、遡って行って下さい。
基本〜標準的な問題で取りこぼしが無いように、「プラスワン」「ステップアップ」を復習しましょう。
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。
漢字・語彙・文法の最終チェックも忘れずに行い、日々の読書も継続してください。
理科は、今まで学んできた内容や、過去問の内容で、理解しきれていない所は無いか、確認して下さい。
計算問題は、最低限の有名問題はできる様にしておきましょう。
社会も、理科同様に、今まで学んできた内容の最終確認です。
記述問題が出題されますから、理解も含めて確認して下さい。
②慶應義塾中等部の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
算数・国語・理科・社会どれも、形式に慣れる必要があるでしょう。
特に算数は、時間との戦い、また、捨てる問題をどうするか、という観点からも十分に演習を積んだ方がよいでしょう。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と国語については、夏休み前から解き始めるとよいでしょう。
この2科目は配点が高い科目です。早めに解き始めた方がよいでしょう。
一方、理科と社会は夏休みに入ってから始めればよいと考えます。
あまり早く始めても、試験範囲の学習が終わっていない場合もありますので、焦らず夏休みに集中して行っていきましょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
算数は、図形・速さ・数の問題といった、よく出る単元がありますし、素早く正確に解く練習も必要です。
従って、最低10回分、できれば20回分解いておきたい所です。
時間を測って解き、その後、間違えた問題を中心に3~4周は解き直しをしましょう。
国語は、通常の文章だけではなく、俳句・短歌など特別な形式の問題もあります。
従いまして、10回分解くとよいでしょう。2周解き直しができればよいと考えます。
理科は、過去問を解くことで、理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直すようにしましょう。
そのため10回分解くとよいかと思います。
解き直しについては、2周行えばよいでしょう。
社会は、出題形式に慣れる意味で、10回分行いましょう。
解き直しは2周でよいと思われますが、過去問で間違えた問題から、弱い所を見つけ出し、その強化に時間を掛ける様にして下さい。
③保護者様にできるサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題ができなくなっている可能性が高いです。
塾などで難しい問題ばかり行なっていると、基本的な所が疎かになり、土台が崩れていきます。
すると、成績が下降して行きます。ですので、保護者様には、是非基本的な問題、例えば小学四年生・五年生の単元に立ち戻って、再度復習をされることをおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声掛けし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、対応して下さい。また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげて下さい。
(2)計算力対策
慶應義塾中等部は、計算力が鍵を握ります。計算問題は必ず出題されていますし、スピードが必要な試験です。
毎日10問程度、四則演算の計算問題を解くとよいでしょう。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。
正確さが身についてから、スピードの順番でお願いします。
(3)理科の対策
慶應義塾中等部の理科は、現象理解を問う問題が出題されております。
保護者様としましては、身近な内容から生徒様と会話をし、一緒に調べて理解を促すようにして頂けると宜しいかと思います。
例えば、
|
「洗濯物を干すと乾くのは何故だろうね?」 「シャボン玉の仕組みを一緒に考えてみようか」 「地震が起きる仕組みを一緒に調べてみようか」 「月の形が毎日少しずつ違ってくるのはどうしてなんだろう。」
|
など、日頃目にする、耳にする内容を理解することは、理科の対策にとても重要です。
是非、生徒様とご一緒に取り組んでみて下さい。
(4)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的なことでも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。
ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにして下さい。
例えば、
|
「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」 |
と言った質問から、生徒様と一緒に会話をし、一緒に調べることは重要です。
是非、取り組んで頂ければと思います。
(5)ケアレスミス対策
計算間違い・見間違い・勘違いなど全てケアレスミスと言われます。
しかし、そのミスは放っておいて直るのでしょうか。また、優秀な生徒様は何故ケアレスミスが少ないのでしょうか。
計算間違いを無くすには、まず(2)でお話したように、ゆっくり、正確に計算を行うことから始めます。
そして、頭で計算(暗算)せずに、筆算をしっかりしましょう。計算は大きく行いましょう。また、計算の都度、確認をするとよいと思います。
次に、見間違い・勘違いについてです。
文章の数字や人物には丸をつけるなど、目立つようにしましょう。また、何を答えるべきなのか、設問で聞かれていることにも印をつけます。
答えを出したら、もう一度問題文を確認し、生徒様自身の解答も、もう一度確認です。
このように、徹底することで、今までのミスが格段に減ると思われます。保護者様も、是非、生徒様の横でチェックして頂けるとよいかと思います。
4. 慶應義塾中等部を受ける際の併願パターン

①1月受験校
|
・栄東中学校・東邦大学附属東邦中学校・市川中学校・渋谷教育学園幕張中学校 |
1月は練習として、栄東中学校・東邦大学付属東邦中学校・市川中学校が挙げられます。
この中で、しっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。
渋谷教育学園幕張中学校は、受験してもよいのですが、もし不合格ですと、生徒様は相当に落ち込む可能性があります。生徒様の性格を踏まえてご検討下さい。
②2月1日
|
午前:広尾学園中学校(一般・1次)・渋谷教育学園渋谷中学校(1次) |
午前入試は広尾学園中学校(一般・1次)がよいでしょう。慶應義塾中等部の抑え校として最適だと思われます。
渋谷教育学園渋谷中学校(1次)もありますが、抑え校にはなりませんので、別に抑え校を考えましょう。
午後入試には広尾学園中学校(一般・2次)がありますが、レベルが高くなります。
東京農業大学第一高等学校中等部(2次)で抑える手もあるでしょう。
尚、1日午前ですが、その他に、男子校では慶應義塾普通部、女子校では桜蔭中学校が候補に挙がるでしょう。
③2月2日
|
午前:慶應義塾湘南藤沢中等部・渋谷教育学園渋谷中学校(2次)・明治大学付属明治中学校(1次) |
午前は慶應義塾湘南藤沢中等部があります。場所は離れますが、何が何でも慶應義塾の共学校ということでしたら、宜しいかと思います。
その他には渋谷教育学園渋谷中学校(2次)がよいでしょう。抑え校として明治大学付属明治中学校(1次)も候補です。
午後は広尾学園中学校(医進サイエンス)がありますが、レベルが高いですので、無理はしなくてもよいと思います。
次の日に慶應義塾中等部がありますから、休養に充てた方がよいでしょう。
④2月3日
|
慶應義塾中等部 |
3日は慶應義塾中等部で決まりです。
⑤2月4日
|
・中央大学附属中学校(2次)・慶應義塾湘南藤沢中等部 |
抑え校として、中央大学附属中学校(2次)がよいでしょう。
但し、ここまでで抑えられている場合は、特に受験しなくてもよいでしょう。
尚、慶應義塾湘南藤沢中等部の2次試験がありますので、1次試験に合格されている方は、体育実技と面接があります。
次の日の5日には、慶應義塾中等部の2次試験があります。最後まで気を抜かずに頑張って下さい。
5. 慶應義塾中等部の受験対策をはじめよう!
算数では、高度な思考力問題は少ないものの、試験時間が短く、スピードと正確性が要求されます。幅広い範囲を網羅しつつ、問題量を多くこなして、捨て問題を見分けられる目利きが必要です。図形・速さ・数の問題は少し難しめの問題までできるようにしておきましょう。
国語は、知識問題対策が重要ですので、詳しい文法書を一冊仕上げましょう。俳句・短歌はよく出題されているので、注意して下さい。
理科や社会の学習では、単なる暗記にとどまらず、幅広い分野を理解することが求められる。日々のニュースや新聞、書籍に目を通し、科学館や博物館なども活用しながら、知識を深めていく姿勢が重要です。
【参考文献】
・慶應義塾中等部ホームページ
・慶應義塾中等部2025年度版10年間過去問声の教育社
・慶応義塾普通部2025年度版10年間過去問声の教育社
・慶応義塾湘南藤沢中等部2025年度版10年間過去問声の教育社
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
慶應義塾中等部・高等部出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら