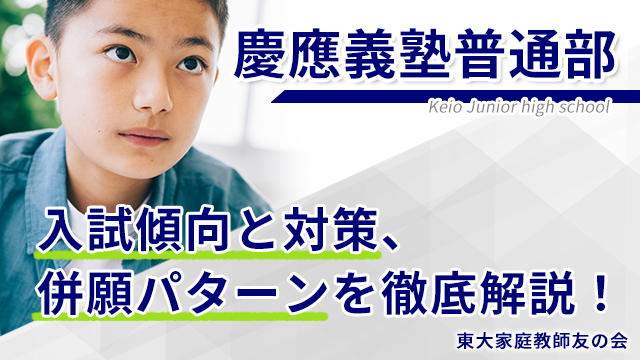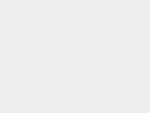1. 慶應義塾普通部の偏差値と基本情報

慶應義塾普通部の偏差値と基本情報について紹介します。
①慶應義塾普通部の偏差値
慶應義塾普通部の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
SAPIX小学部 (合格率80%偏差値) |
|
2/1 |
男子 65 |
男子 73 |
男子 58 |
②慶應義塾普通部の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1898年 |
|
所在地 |
神奈川県横浜市港北区日吉本町1‑45‑1 |
|
アクセス |
東急東横線・目黒線・横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」から徒歩約5分 |
| 校種 | 私立男子校(中高一貫校) |
| コース | ー |
| 特徴的な教育 | ・全校行事「労作展」では文化・学術作品を手作りで発表 ・中1は24名クラス、中2以上は分割授業で英語など少人数制導入 ・中3から土曜にユニークな選択講座 |
慶應義塾普通部は、東急東横線の日吉駅を挟んで、慶應義塾大学日吉キャンパスや慶應義塾高等学校の反対側に位置しています。
各界で活躍する著名人の出身校としても知られ、人気のある学校の一つです。
ここでは、慶應義塾普通部の是非ともご紹介したい魅力を、3点に絞ってお伝えします。
①「生涯学習力」を育てるカリキュラム
各教科の基礎・基本を確実に身に着けることを大切にしながらも、時には中学校の学習指導要領を越えた高度な内容にも触れ、学問の本質を学んでいきます。知識だけではなく、思考力や情報リテラシー、問題解決能力などの「学び方を学ぶ」ことを重視し、生涯を通して自立して学ぶ姿勢である「生涯学習力」を育成します。
その1つとして、土曜日には選択授業の時間が設けられ、教科の枠に囚われない様々な講座が行われています。外部の施設を施設を訪問したり、最先端の研究を行っている方のお話を伺うなど、まさに「学びの本質」に触れるきっかけになっています。
②一貫教育と歴史を活かした「縦・横の繋がり」
学校の長い歴史と卒業生の人脈を活かして、様々な分野で活躍する卒業生を招き、普通部時代の思い出や、学びがどのように今に活きているのかを話していただく「目路はるか教室」を行っています。また、慶應義塾大学の学生や社会人のOBがコーチとして部活動の指導にあたる部活
動も多くあり、「縦の繋がり」が強い点も一つの特徴です。
慶應義塾中等部や湘南藤沢中等部と定期に試合をを行う部活動があるなど、一貫教育校同士の「横の繋がり」もあります。
③「労作教育」を後押しする内部進学制度
「労作教育」は、時間を惜しまずに思う存分に自分の興味・関心のあることに向かって向き合い続けるなかで、自ら考え、主体的な選択ができるようにする教育のことで、慶應義塾普通部の根幹とも言える考え方です。
普通部では、中学校としての全課程を終え、普通部長(校長)からの推薦を得ることで、慶應義塾の一貫教育校である、慶應義塾高等学校、慶應義塾志木高等学校、慶應義塾湘南藤沢高等学校(ただし、中高一貫校のため、推薦を受けられる人数には制限があります)、慶應義塾ニューヨーク学院のいずれかを選択して進学することができます。
充実した環境の中で高校受験を気にせずに自分の興味のあることに没頭することができる点は、大学の附属校に進学する大きな利点ですね。 また、各高等学校卒業後は、慶應義塾大学のいずれかの学部に進学することができます。
2. 慶應義塾普通部の入試傾向

2025年度の入試は2月1日(土)に行われます。試験内容は国語、算数、社会、理科の4科目の筆記試験と受験生本人のみの面接、体育実技です。
入試問題は、一問一答のような単純な知識だけでは歯が立たないような、複数の分野の知識を組み合わせれ図表を読み取ったり、生活の中で知識を活かすような問題など、一筋縄では解けないような問題が出題されます。ですので、過去問などである程度演習を多くこなし、知識の応用力を高めていくことが必要でしょう。
ここでは、入試の概要や各科目の出題傾向、2024年度入試で「差がついた問題」や「特徴的だった問題」とその対策についてお伝えします。
①慶應義塾普通部の入試の概要
国語と算数は試験時間が各40分で各100点満点、社会と理科が試験時間30分で各100点満点の試験です。
2024年度入試では、募集人数約180名に対して応募者569名、受験者526名で、倍率は2.7倍でした。ここ数年は倍率が2.7~2.9倍程度となっています。
面接の形式や質問内容等については、公式には公表されていません。また、体育実技に関しても詳細は公表されていませんが、年度によって内容が変わるものの、柔軟体操のあとに簡単な運動を行うとしています。
②算数
2024年度入試では大問9題構成と、2023年度に比べて1題多く、
|
大問1:四則計算と逆算 大問2:相似に関する平面図形の問題 大問3:相当算 大問4:点の移動をともなう平面図形の問題 大問5:場合の数 大問6:速さと比 大問7:整数の性質 大問8:相似や長さに関する立体図形の問題 大問9:角度に関する平面図形 |
という構成でした。
図形の問題が四分の一以上を占めていて、特に力を入れて対策を行っていきたい分野です。辺の長さや角度、相似や面積、立体図形の展開図や表面積、体積など、様々な出題パターンが見られます。
速さに関する問題では、2023年度まで4年連続で旅人算が出題されていたので、注意しておきましょう。
割合と比の分野では、還元算や相当算と比の性質が数年おきに出題されています。2023年・2024年と2年連続で還元算・相当算からの出題が続いたので、2025年度は比の性質の問題が出題される可能性があります。2021年度から1年おきに出題されている和差算や分配算も要注意です。
難問・奇問が出題されることはほとんどなく、標準から応用レベルの問題がほとんどを占めます。また、問題数が多いため、スピードと正確さが求められていると言えるでしょう。短時間で多くの問題をこなす練習が必要です。
ここでは、頻出の図形に関する問題として、大問4を取り上げて解説します。
台形ABCDにおいて、点P、Qが頂点Aから同時に出発し、台形の辺上をDまで動きます。Pは毎秒3㎝、Qは毎秒1㎝で動くとき、P、Qを結んだ直線が台形の面積をはじめて2等分するのは、PとQが頂点Aを出発してから何秒後かを求めます。
与えられた辺の長さの条件から、台形ABCDの面積の半分は18.75㎠です。動きの速い点Pが点Cと一致するのは出発してから5秒後で、点Qが点Aから5㎝の距離にあるときです。このときの三角形BPQの面積は12.5㎠と、台形ABCDの面積の半分よりも小さいため、PQが台形ABCDの面積を二等分するのは、点PがCD上にあるときだと分かります。このとき、PD+AQはAB+CDの半分になるため7.5㎝となり、これは点P、Qが頂点Aを出発してから6.25秒後と求めることができます。
PQが作る図形が三角形の場合と台形の場合、2つの場合を確認する必要があること、少数第二位までの計算をしなければならないことから、想定以上に時間がかかった受験生が多かったと予想されます。
2024年度は大問4のほかにも、大問2・8・9で図形に関する問題が出題されました。このような図形の問題を解くためには、与えられた情報を丁寧に整理し、図に書き込むなどしながら問題を解いていくようにしましょう。特に、図に書き込んだ数値が長さなのか比なのかを分かりやすくするために、比の場合には数値を囲むなど、自分なりのルールを作っておくとよいです。
大問4であれば、直感的にPQによってできる図形が台形になるときだと分かった受験生も少なくなかったと思いますので、余分な時間を使わなくてもいいように、効率よく解いていきましょう。
③国語
国語の問題は例年、大問3題で構成されています。 2024年度入試では、
|
大問1:小説(津村記久子『ディス・イズ・ザ・ディ』より、約4300字) 大問2:随筆(奥山由之『windows』より、約3300字) 大問3:漢字の書き取り |
の構成でした。読解問題が全体の80%近くを占めています。出典は近年、小説・物語文と随筆が続いています。文章量は大問1、2合わせておよそ6500字~8000字程度と、それほど長くはありません。
読解の問題の中で文中における表現の意味や慣用句、ことばのきまり、四字熟語などに関する問題が出題されることもありますし、主題や内容、情景描写、心情の読み取り、空欄補充など、バラエティーに富んだ問題が出題されます。読解力を試すような問題が多い点が特徴だと言えるでしょう。
大問3は知識を問う問題で、漢字の書き取りが多いものの、熟字訓などが問われることや、パズルのような問題が出題されることもあります。
2024年度入試で受験生に差がついた問題として、大問2の問五について説明します。
課題文は、東京の窓をテーマにした写真集の序文で、すりガラスの窓の写真を撮り続けてきた筆者が、日本の窓にすりガラスが多い理由を複数の視点から説明し、「窓」について考察しているものです。
問五は「傍線部④「西洋建築と日本建築は構造的に大きく異なっており」とありますが、それぞれの建築において、窓はどのような目的意識をもって作られたのであるのか、六十字以内で説明しなさい」というものでした。
この問題は、内と外を明確に分ける、組積造の西洋建築では、「窓」は外から風邪や光を取り入れる目的で窓が開けられた一方で、壁のない軸組み構造の日本建築では、必要に応じて空間を閉じたり仕切ったりする目的で「窓」が設けられたということを、指定字数以内で、西洋と日本を対照的に書けているかがポイントになります。難易度としてはそれほど高くありませんが、だからこそ、確実に点数を取っておきたい問題です。
この問題においても写真集の序文という変わった出典であったように、一般的な中学入試の素材文とは少し違った形式の文章を出題することも少なくありません。中学入試でよく取り上げられる筆者や作品を読むことももちろん大切ですが、日頃から様々な話題や種類の文章に触れておくことが慶應義塾普通部の国語の問題を制するうえでは必要になってくるでしょう。
➃理科
理科は大問4題構成で、やや生物分野からの出題が多いと言えるでしょう。
2024年度は、
|
大問1(物理):電熱線の発熱についての問題 大問2(地学):太陽の動きと影についての問題 大問3(総合的な問題):キャンプについての問題 大問4(生物):カブトムシとシロアリについての問題 |
という構成でした。 生物は、動物についての出題が8年続いています。
植物に関しては、2020年以降1年おきに出題されており、昨年度出題されているため、2025年度は出題の可能性は低そうです。
物理、化学、地学に関しては、幅広い分野から出題されており、どの分野に関してもよく学習しておく必要があるでしょう。
小学校の学習範囲を超えるような内容は出題されませんが、図表を用いた問題や実験・観察に基づく問題、2024年度の大問3のように、複数の分野を融合した総合的な問題があり、知識があるだけでは解くことができないものも多いです。
回答の形式も、あてはまるものを複数選ぶ問題、記述形式の問題など、注意深く問題を読む必要があります。
ここでは、2024年度の問題から大問3を取り上げて説明します。
この問題は、キャンプに行き、たき火でカレーを作るという設定です。中でも、差がついた問題だったと考えられる問1、2、4、8についてみていきましょう。
問1はたき火をするときに火がつきやすい木の種類を選ぶ問題です。針葉樹は空気や油分が多く含まれるため、火がつきやすいという特徴から答えを導き出します。植物の分類から、落葉広葉樹ではないイチョウとスギの二択までは絞りたい問題です。
問2は、どのように薪を組み合わせればよいか、適切な図を選択する問題でした。薪が燃えるためには、より空気に触れやすいように組む必要があります。この問題では鍋に火力が伝わるようにしたいので、山型に組むのが正解と言えるでしょう。
問4はカレーを作るときのタマネギの切り方としてふさわしいものを二つ答える問題です。日常的に料理をする受験生にとっては簡単な問題だったと言えるでしょう。完成時に形を残すためにはくし切りに、甘みを引き出すためにはみじん切りが適切です。他教科の知識や日常の知恵とも言える問題ですが、こうした問題もしっかり根拠を持って答えたいですね。
問8は、火を消すのに効果がないものをすべて選ぶ問題です。ものを燃やし続けるためには、燃えるもの、酸素、一定以上の温度の3つの条件を揃える必要があります。3つの条件を、それぞれの選択肢に当てはめてみましょう。
このように、知っている知識を整理しながら複合的に使って問題を解いていく必要があるのが慶應義塾普通部の理科の問題です。この問題であれば、おうちでお手伝いをした経験や、実験の手順・注意を思い出すことも、答えを導く手助けになったでしょう。学んだことを実社会とどのように結びつけられているかが問われていると言えますね。
さらに問4のように、適切なものを二つ選んだり、問8のように効果がないものをすべて選ぶという問題の指示を読み違えてしまった受験生もいたはずです。そういった点でも、大問4は合否を分けた問題だったと考えられます。
⑤社会
社会の問題は、大問6題で構成されています。選択肢の中から記号を選択して答える問題と用語を答える問題がほとんどですが、一行程度の記述問題も出題されることもあります。漢字で書くことを指定される場合もあるので、用語は漢字で覚えましょう。
2024年度は、
|
大問1(公民):貧困問題に関する問題 大問2(地理):自然災害を伝承する石碑に関する問題 大問3(地理):北海道と北東北に関する問題 大問4(歴史):近世の人物とできごとに関する問題 大問5(総合的な問題):福沢諭吉に関連した問題 大問6(歴史):お正月の歌を題材にした問題 |
が出題されました。
地理と歴史の分野からの出題がそれぞれ40%近くを占めており、公民的な内容の問題が比較的少ない点が特徴です。 地理分野は、地図とグラフの読み取りの練習は欠かせません。各地方の特色や人口・生活・文化、農林水産業に関わる分野が頻出です。
歴史分野は史料や地図なども用いながら、一つのテーマに沿って出題されています。原始から現代まで、幅広い時代についての知識が問われますが、中世以降の時代がメインになることが多いです。
公民分野は、三権分立に関する問題が頻出です。また、数年おきに憲法に関する問題も出題されています。
2024年度の入試で特徴的だった問題として、ここでは大問3の問4と問6を取り上げます。
大問3は北海道と、青森・岩手・秋田の北東北三県に関する問題で、問4は「Cの岬(襟裳岬)付近は昆布の産地です。明治時代以降、徐々に昆布が採れなくなってしまいましたが、約50年前からあることを行いはじめ、現在では昆布が育つ豊かな海が復活しています。豊かな海を復活させるために行ったことを説明しなさい。」という問題でした。
襟裳岬の近海は、江戸時代から昆布の産地として知られていましたが、その後の北海道の開拓と近代化の影響で周辺の森林が伐採されたことで荒れ、土が海に流れ出てしまったことで、昆布が育たなくなってしまいました。そこで漁師らが植林活動を行い、森を再生させたことで、良質な昆布が採れる豊かな海に回復したという歴史があります。
記述問題とはいえ、簡潔に書く必要があるため、「植林し森林を再生させた」程度の分量で書けるとよいでしょう。こうした問題に対応するためには、地理の知識だけではなく、北海道・北東北地域の歴史的な知識も必要だと言えます。
問6は、地図上に引かれた直線の断面として正しいものを記号で答える問題です。断面をたどると、西側は山岳地帯で、苫小牧市付近の平野を通り、高く険しい日高山脈を越えて十勝平野が広がります。よって、それにあてはまるアが正解です。
十勝平野は比較的知名度があるため、東側が平野になっていないイを消すことは難しくなかったことでしょう。しかし、十勝平野の広がりや日高山脈の位置や標高、苫小牧付近の平野が断面のどのあたりにあたるのかなど、詳細で正確な知識が求められ、苦戦した受験生が多かった問題だったと考えられます。
慶應義塾普通部の社会の問題では、広く深い知識に加えて、知っている情報を史料や図表、地図などの見える形で具体化して考えられるかどうかで得点に大きく差がつきます。
3. 慶應義塾普通部の受験対策

ここでは、慶應義塾普通部の受験に向けて、
「いつ、どんなことをしていったらいいのか?」
「過去問はいつ頃、どのように取り組むのがよいのか?」
「保護者様がご家庭でできるサポートとは?」
といった、具体的な受験対策に関する疑問について、お伝えしていきます。
①時期別・教科別対策方法
ここでは、小学校4年生から受験直前までの、時期別・教科別の受験対策方法をご紹介します。
(1)小学4年生
この時期は、中学受験を多少意識していても、受験をするか決めきれていなかったり、学校について情報収集している段階のご家庭も多いことでしょう。ですが、学習も少しずつ難しくなっていき、学校でも学力差が顕著になってくる時期でもあるので、受験する/しないや志望校にかからわず、自律した学習習慣を身に着けさせる時期です。
学校や塾の宿題などのやるべきことをしっかりこなす時間を確保するとともに、興味関心を広げられるよう、様々な分野の図鑑や百科事典などをみたり、博物館や科学館などに行ってみましょう。
(2)小学5年生
本格的に中学受験を意識して学習する生徒様の増える5年生。一方で、気持ちのコントロールが難しい時期でもあります。この1年を頑張りきれるかどうかが、最終的に中学受験の結果を左右するのではないでしょうか。
5年生では、小学校の学習範囲の基礎・基本を固めるとともに、育成に時間のかかる読解力や批判的思考力などを意識した問題など、直前期には取り組むのが難しいようなものをやっておくことがおすすめです。
算数:基礎計算のスピードと正確さを意識しましょう。中学受験に頻出のつるかめ算や旅人算、面積図の利用の仕方などは、5年生のうちに使いこなせるようにしておきましょう。
国語:語彙の学習と読解力を強化したいのがこの1年間。慣用句や四字熟語、故事成語などに積極的に触れる機会を作りましょう。はじめは穴埋めや一問一答形式の問題で、その言葉自体を覚えているかどうかを確認し、その段階がある程度進んだら、今度は文章の中での使い方を確認するなど、自分の語彙として運用する練習をしていくとよいです。
また、慶應義塾普通部の入試の出題傾向から考えると、一般的な本だけではなく、実用的な文章も含めて様々な文章に触れる機会を持つようにしましょう。
理科・社会:必要な知識を入れる段階の理科や社会。塾や学校で習ったことを丁寧に復習するとともに、資料集などの細かいところにも繰り返し目を通して、知識の取りこぼしがないようにしましょう。
(3)小学6年生(4月~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校を具体的に絞っていくのもこの時期でしょう。
算数:時間を意識して解けるように、このころから準備を始めていきましょう。また、慶應義塾普通部の数学の問題は、中学入試の定番のような問題の出題が多いので、入試の定石と言われるような問題には、この時期までに問題を見ただけで解法がイメージできるようにしましょう。
国語:ある程度長さのある文章をスピードを意識して読むことができるように、読解問題を解くときには、時間を測る習慣をつけるとよいです。また、漢検4級範囲までの漢字は、確実に読み書きできるようにしましょう。
理科:苦手分野をつくらないよう、幅広く基礎固めに取り組んでいきたい時期です。また、日常の出来事と関連付けたような問題や、様々な分野を組み合わせた総合的な問題にも徐々にチャレンジしていきましょう。
社会:慶應義塾普通部で頻出の地理分野について、地図やグラフ、歴史的な出来事などと関連付けながら、より深い知識を身につけていきましょう。
(4)小学6年生(7月~8月)
「夏は受験の天王山」と言われるほどのこの季節。体調管理と生活リズムを整えることに注意しながら過ごしたいですね。
算数:頻出の図形の問題に力を入れて、様々なパターンの問題にチャレンジしましょう。
国語:読解問題の練習に取り組んでいきましょう。特に選択式の問題については、正解、不正解の根拠も明確に説明できるように、本文に線を引いたり、印をつけながら読むことを勧めます。
理科:実験や観察をもとにした問題の出題が多いので、実験の手順や器具の使い方などについて、普段より時間がとれる夏休みに確認しておいてください。
社会:出題の約40%を占める歴史に力を入れていきましょう。古代から現代までの流れを掴むとともに、用語は漢字で正確に書けるようにしましょう。
(5)小学6年生(9月~11月)
志望校合格に向け何をしなければならないのか、ゴールから逆算して考えるのがこの時期です。秋以降は、過去問にもチャレンジしましょう。
算数:過去問に挑戦し、できなかった問題は徹底的に復習をしましょう。標準的な問題が多いぶん、ミスをなくしていくことが大切です。
国語:記述問題や空欄補充の問題を意識して練習しましょう。
理科:手間のかかる問題が多いので、過去問など解く際は、時間をかけてでも解く問題とそうでない問題のより分けができるようにしていきましょう。
社会:時事的な事柄やそれに関連した問題に対応できるよう、ニュースや新聞などを見て、世界できごとや経済の動きを掴んでおきましょう。
(6)小学6年生(12月~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、新しいことをしたり、覚えたりというよりは、どの科目もこれまでしてきたことを振り返り、抜け漏れているところがないかどうか確認し、見つけ次第復習する期間です。
体育実技の試験に向けて、リフレッシュも兼ねて身体を動かしたり、実践的な面接の練習にも取り組みたいですね。
②慶應義塾普通部の過去問対策方法
(1)過去問の効果的な使い方
過去問を解く目的は大きく2つあると考えています。1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。つまり、自分の弱点を知るために過去問を利用するのです。間違えたところは、決してそのままにはせず、解説をしっかり読んで何を間違えたのかを整理し、教科書や参考書を読み直したり、似たような問題を練習して、再度その問題に挑戦してみましょう。
過去問を解く目的の2つ目は、時間的な感覚を掴むためです。入試は、決められた時間内に問題を最後までやりきり、かつ合格点をとらなくてはいけません。過去問に取り組む時には、時間の感覚を身につけるために、時間通りに問題を解くだけでなく、できれば入試本番と同じスケジュールで問題を解いてみることをお勧めします。
(2)いつから解き始めればよいか
基本的には、過去問に挑戦するのは、受験校が固まり、間違えた分野の問題に取り組む時間的・精神的な余裕がある、6年生の11月~12月ごろをお勧めしています。ですが、慶應義塾普通部を志望しているのであれば、少し早めの9月~11月ごろに挑戦してみることをお勧めします。
実際に問題を解いてみることで、秋以降の応用的な問題の対策や基礎基本の抜け漏れを補う学習をどのようにしていくか、早めに計画を立てるためです。過去問を解いて解けなかった問題は、まだ基礎が不十分なところと考え、直前期に向けてしっかり克服してきましょう。
併願校として受験する場合でも、試験日直前は過去問が売り切れてしまっていて手に入らない、ということもあり得ますので、冊子として持っておきたい場合には、余裕を持って準備しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
慶應義塾普通部を受験する場合、基本的には3~5年分程度解いておくとようでしょう。それ以上前の問題についても、例えば理科・社会のさまざまな分野にまたがっている問題や、算数の図形問題など、頻出の分野に関しては、対応力をつけたり、演習量を増やして確実に点数に繋げていくためにも、8年分程度チャレンジしてみてもよいでしょう。ただし、年数が経過しているものについては、学習指導要領が改定され、出題範囲が今と異なることがあるので注意が必要です。
過去問を解く回数については、一周すれば十分だと考えています。一回で解けた問題は、ケアレスミスなどがない限り、何度やっても同じように解けるからです。もうすでに解けた問題にさらに時間を使うよりも、今できないことをできるようにすることのほうが、合格への近道になります。過去問は一周で構いませんが、一度解いて間違えた問題は、解説をよく読んで間違えた理由を確認し、解けるまで何度でもチャレンジしましょう。
③保護者様にできるサポート内容
(1)直前期も一緒に体を動かす時間を作る
慶應義塾普通部では、午後に体育実技の試験があります。
実技の出来栄え自体は合否にはさほど影響せず、安全に配慮して行動できるかや指示に従い動くことができるか、一生懸命に取り組もうとする姿勢が見られるかや体を動かす習慣がついているかといったことが見られているようです。
運動する習慣が身に着いているかどうかは専門家が見ればすぐにわかるものですし、受験勉強の合間にリフレッシュも兼ねて、親子で体を動かす時間を設けるとよいのではないでしょうか。
(2)面接試験の練習をする
慶應義塾普通部の面接試験は、生徒様のみで行われます。面接で話す内容はもちろん、入室からの立ち振る舞い等も重要ですので、本番で全力を出し切れるよう、一緒に面接練習をするなどして、自分の考えを言葉にするサポートや、面接時の作法を身につけさせましょう。
(3)生徒様に合った学習環境、リラックスできる環境を整える
どのような環境で学習するのが適しているのかは、生徒様によって違います。整理整頓された机の上で静かに取り組みたい生徒様もいれば、音楽を聴いたり、ねそべったりしながらのほうが、学習がはかどるという生徒様もいます。ですから、集中して学習に取り組める環境が保護者様と生徒様で違うということもよくあることなのです。
ですので、生徒様がどのような環境なら心地よく学習に取り組めるのかを見極め、それに合った環境を準備できるようにしましょう。また、生徒様が気持ちをリセットしたりほっと安心できるような、一人になれる空間や時間を作るように手助けすることも重要なサポートの一つです。
4. 慶應義塾普通部を受ける際の併願パターン

①1月
千葉・埼玉などの私立中学校の入試が行われる1月は、2月入試に向けた練習も兼ねて受験する生徒様がほとんどです。
受験校としては、
|
・栄東中学校 ・市川中学校 ・渋谷教育学園幕張中学校 ・立教新座中学校 |
が多い印象です。複数の学校を受験して場慣れしておくことも大事ですが、前哨戦とはいえ、受験には体力や時間を要します。生徒様の性格等も鑑みて、受験する学校を決めていきましょう。
②2月2日
この日は慶應義塾湘南藤沢中等部の試験が行われますので、普通部を志望している生徒様の多くは、そちらを受験しています。また、午前は慶應義塾湘南藤沢中等部を受験し、午後は別の学校を受験しに行くというパターンもあります。
|
【午前】 ・慶應義塾湘南藤沢中等部 ・栄光学園中学校 ・青山学院中等部 ・聖光学院中学校 ・法政大学第二中学校 【午後】 ・中央大学附属横浜中学校 |
などが併願校として考えられます。
③2月3日
3日は慶應義塾中等部の入試があります。中等部以外の学校だと、
|
・浅野中学校 ・逗子開成中学校 |
の2校との併願が多いです。
また、暁星中学校なども選択肢に入りうるかと思います。
➃2月4日・5日
(4日)
4日は、慶應義塾湘南藤沢中等部の二次試験が行われます。
|
・聖光学院中学校 ・サレジオ学院中学校 ・東京都市大学付属中学校 ・法政大学第二中学校 |
などが併願校としてよく挙げられます。
(5日)
慶應義塾中等部の二次試験が行われる5日。中等部以外の併願先としては、
|
・広尾学園中学校 ・逗子開成中学校 ・本郷中学校 ・立教池袋中学校 |
などが挙げられます。
5. 慶應義塾普通部の受験対策をはじめよう!
慶應義塾普通部は、慶應義塾の設置する中等教育を行う学校の中では唯一の男子校であり、かつもっとも古い歴史を持つ学校です。内部進学できるという利点を活かした、時間を惜しまずに自分が興味・関心のあることに向き合い続ける中で主体性を育む「労作教育」の考え方を軸に、各教科の基礎・基本を確実に身につけることを大切にしながらも、生涯にわたって学習する力を育てていきます。
入試問題は、算数は比較的オーソドックスな問題が多いものの、そのほかの科目に関しては、複数の資料が提示されたり、様々な分野が融合されたり、実生活の中での活用について問うなど、一筋縄では解けないような問題や、深い知識が問われるような問題が出題されます。ですので、過去問などである程度演習を多くこなし、知識の応用力を高めていくことが必要でしょう。
筆記試験に加えて、午後には体育実技と面接の二次試験があります。保護者様におかれましては、生徒様の健康面・メンタル面のケアに加えて、実技試験に向けて一緒に体を動かす機会を定期的に設けたり、面接練習をしたりしておくことで、精神的にも生徒様の支えになることができるはずです。
合否に関わらず、2月入試の初日である1日に納得のいく挑戦ができたかどうかは、その後の生徒様の精神状態にも大きく関わってくることと思います。是非、生徒様・保護者様ご一緒に、併願校選びも念入りに行っていってください。
【参考文献】
・慶應義塾普通部公式サイト
・慶應義塾普通部デジタルパンフレット
・声の教育者「慶應義塾普通部2025年度用スーパー過去問」
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら