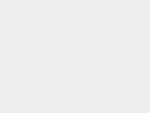![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 東京都立小石川中等教育学校の偏差値と基本情報

東京都立小石川中等教育学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①東京都立小石川中等教育学校の偏差値
東京都立小石川中等教育学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
SAPIX小学部 (合格率80%偏差値) |
|
2/3 |
男子 65 |
男子 74 |
男子 60 |
②東京都立小石川中等教育学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1918年 |
|
所在地 |
東京都文京区本駒込2‑29‑29 |
|
アクセス |
都営三田線「千石駅」徒歩約3分 |
| 校種 | 公立共学校(中高一貫校) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・自ら志を立て、道を切り拓き、新しい文化を創る力を育成 ・「小石川教養主義」「理数教育(SSH)」「国際理解教育」に力点 ・週1–2時間の課題研究を中学1年から高校3年まで継続し、探究力・表現力・論理力を育む ・全国SSH指定校(第1–4期)。実験室が複数、理科実験・先取り授業多数 |
大正7年に「東京府立第五中学校」として誕生した小石川中等教育学校。「立志・開拓・創作」の三つを建学の精神に据えて様々な教育活動を行っており、その結果多くの卒業生が現役で難関大学への進学を果たしています。また、卒業生には政治家や小説家など多くの著名人が名を連ねています。
ここでは、小石川中等教育学校の三つの「教育の柱」をご紹介します。
①小石川のスピリット「小石川教養主義」
小石川中等教育学校では、6年間を通じて文系・理系などのクラス分けをせず、全員が全科目を学習し広く深い教養を身に着けます。
また、6年間「小石川フィロソフィー」と呼ばれる課題研究に取り組み、発達段階に応じて課題発見力・継続的実践力・創造的思考力の3つの力を育みます。
②理数教育
創設時から理化学教育の振興に力を入れ、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)にも指定されています。
特に理科教育においては、各分野の実践室と専門教員を配置しているほか、授業の7割で実験や実習をする方針を戦前から守り、大学や企業、研究施設と連携し、国際社会でリーダーとして活躍できる「課題発見力」「継続的実践力」「創造的思考力」を兼ね備えた科学技術人材の育成を目標に掲げています。
③国際理解教育
令和4年度から7年度までの3年間、「東京グローバル人材育成指針」に基づき精神的な取り組みを行う学校として認定されており、世界の多様な価値観を理解し国際的な舞台で活躍できる人材の育成に力を入れています。
海外の同世代と交流を持ったり、自分の課題研究の成果を英語で発信できるようにするなど、語学力だけでなく異なる文化や考え方に触れ、多様性を受け入れる体験をしていきます。中学3年生でのオ-ストラリア、高校2年生のシンガポールやマレーシアへの海外研修は、それまでに身に着けた「国際力」を試す絶好の機会になっています。
2. 東京都立小石川中等教育学校の入試傾向
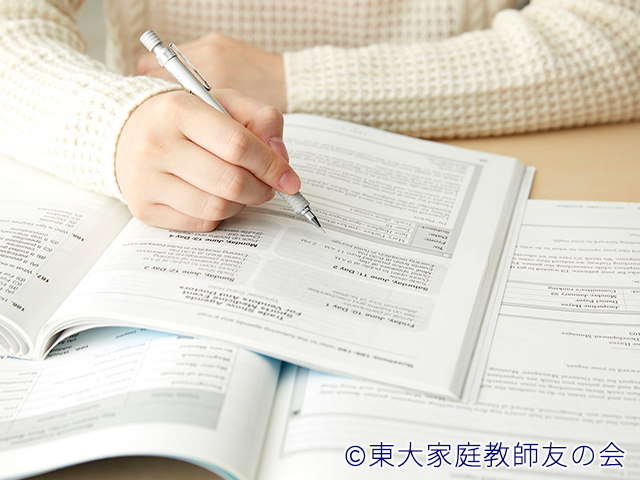
小石川中等教育学校の入試は、特別枠募集と一般枠募集の2種類があり、特別枠入試が2月1日、一般枠入試が2月3日に実施されます。
ここでは、入試の概要や、小学校での学校生活の様子について記載された報告書の点数の換算方法、各試験の内容等についてお伝えするとともに、2024年度入試の適性検査で特徴的だった問題や合否を分けた問題について解説します。
①入試の特徴
特別枠募集は、「自然科学分野の全国的なコンクール等に入賞し、入学後もその能力の伸長に努めることができる者」という応募要件を満たした上で、報告書(100点満点)と面接(25分程度、500点満点)、作文(45分、400点満点)の総合成績により合格者を決定します。2024年度入試では、募集人数5名に対して3名が受検し、2名が合格しています。
一般入試は、報告書と適性検査によって合否が決まります。報告書(200点満点)、適性検査Ⅰ(45分、200点満点)、適性検査Ⅱ(45分、200点満点)、適性検査Ⅲ(45分、200点満点)の800点満点です。2024年度入試の倍率は3.9倍でした。
小石川中等教育学校では適性検査ⅠとⅡ(ただし、大問2は独自作成問題に差し替え)は、都立中高一貫校の共同作成問題を使用していますが、適性検査Ⅲについては理数系の独自作成問題です。問題は中学受検の中でも特に難関と言われており、都立の中高一貫校で重視される「思考力・表現力・分析力」はもちろんのこと、その土台となる4教科の学力が十分に身についていることが大前提です。
②報告書の換算方法
報告書は、小学校5・6年生の通知表にある「学習の記録」を点数化したものです。
各評価の評定を、
評定3=25点
評定2=20点
評定1=5点
とし、その合計点を、特別枠の場合には四分の一にして100点満点、一般枠の場合は二分の一にして200点満点で計算します。
③適性検査Ⅰ
適性検査Ⅰは例年同様、読解問題と作文の問題という形式でしたが、読解問題に関しては文章量が大きく増えました。
文章1の出典は東直子『生きていくための呪文』で、春の短歌から生まれる心情について筆者が述べた文章です。文章2は藤田真一『俳句のきた道芭蕉・蕪村・一茶』からで、江戸時代の俳諧について、松尾芭蕉が述べた言葉を説明したものでした。
ここでは、適性検査Ⅰの山場とも言える問題3の作文について解説します。文章1、2で読み取った内容に触れながら、これから学校生活で仲間と過ごしていく上で、言葉をどのように使っていきたいか、自分の考えを400~440字で書きます。
まずは文章1、2のどちらの考え方を踏まえて書くのかを決める必要があります。文章1は、短歌を繰り返し心の中でつぶやくことで、自分の気持ちを保てるという内容で、文章2は、人々の気持ちを想像して勉強していくうちに、すばらしい俳句が生まれるという内容でした。自分が意見や理由を書きやすかったり、経験などの具体的な内容と結びつけやすいほうを選ぶとよいでしょう。
段落についての条件はありませんでしたが、文字数から考えても、
段落1:選んだ文章の筆者の主張と、そこからどのように言葉を使っていきたいかという自分の考えを述べる。
段落2:そう考える理由を、これまでの体験などを踏まえて具体的に書く。
段落3:文の結びとして、これからどのように言葉を使っていきたいかをもう一度簡単に繰り返して書く。
という、三段落構成の総括型が最も書きやすいでしょう。「これから学校生活で仲間と過ごしていく中で」と問題にあるので、中学校生活の中で仲間との関わる場面を具体的に想定して書けているかが採点する上での大きなポイントになります。
さらに条件としても挙げられているように、原稿用紙を正しく使えるかどうかや、適切な言葉遣いができるかどうかも見られています。
作文では毎年、自分の経験や考えを具体的に示すことが求められます。日頃から様々な事柄に対して自分の考えを書く練習をしましょう。良い作文を書くためには、豊富な語彙力とそれを正しく運用していく力が必要です。将来を見据え、小学生のうちに使いこなせる言葉の量を増やしていけるように、日頃から読書に親しんだりする姿勢は大切にしていきましょう。
④適性検査Ⅱ
2024年度の適性検査Ⅱは、大問1がデジタル数字を題材にした算数の規則性に関する問題、大問2が独自作成問題で、世界の森林面積をテーマに資料を分析しながら環境問題について考える社会系の問題、大問3が理科分野からの出題で、摩擦についての実験や観察の問題でした。
資料や会話文が多く提示されており、限られた時間の中で、正確に情報を処理する能力が試されていると言えます。
ここでは、小石川中等教育学校の独自作成問題である大問2の中から、[問題2]を取り上げます。この問題は、これまでの会話文や問題、資料等を参考に「世界の森林面積を増加させるにはどうしたらよいか」「世界の森林面積を減少させないためにはどうしたらよいか」について、世界の国々はどのような協力をすればよいと思うか、自分の考えを目的ごとに151~210字で書くという問題でした。2024年度は、小問の数が減ったことから、その分記述の量が増えたと考えられます。大問1と3が標準的なレベルであったため、この問題が受検生に差をつけた1問になったと言えます。
この問題を解くためのポイントは、
・与えられた情報をもとに、筋道立てて考え、それを文章で説明できたか
・「世界の国々がどのように協力すればよいか」という、国家間の協力の視点で書けたか
の2点です。
記述する文字数は増えたものの、2つの目的それぞれについて触れて書く必要があるため、むしろ指定字数に収めることに苦労した受検生は多かったことでしょう。どちらの目的についても、根拠となる事柄を簡潔に示しつつ、国家間で連携して行う取り組みであることを示すことが必要で、丁寧に取り組みたい問題です。
⑤適性検査Ⅲ
適性検査Ⅲは、小石川中等教育学校の独自作成問題です。大問1は音をテーマにした、理科の物理分野の問題、大問2は規則性をもとにグループ分けをする問題で、実験に対する考察や、規則性に従って考える力をはかろうとする出題の意図が感じられます。
ここでは、例年の傾向とやや異なる出題が見られた大問1の[問題2]について解説します。
図5の3びきのアマガエルがなく様子を観察した結果から、アマガエルは他のアマガエルと声が重ならないように鳴いていることがわかります。(1)はその理由について自分の考えを述べる問題、(2)はアマガエルたちが鳴くタイミングをどのように判断しているのか、自分の考えと理由を述べる問題、(3)は、鳴いたアマガエルの位置を把握するためには、どのような工夫をすればよいか説明する問題で、(3)では説明に図を用いてもよいとされています。
(1)は、会話文中の「アマガエルが鳴くのはオスのアマガエルがメスのアマガエルを呼ぶため」という部分がヒントになります。同じタイミングで鳴くと自分の鳴き声がメスに届かない可能性がありますよね。この問題は必ず正解しておきたい問題です。
(2)は図5から、アマガエルたちが少しずつタイミングをずらして鳴いていることが分かります。したがって、近くのオスが鳴く声を聞いたあとに鳴いていると考えられます。感覚的に理解できたとしても、理由をどのように言語化すればよいか悩んだ受検生が多かったのではないでしょうか。
(3)は例年、ある実験の方法を説明し、その実験の予想される結果を述べる問題が出題されていましたが、2024年度は調査方法を説明と、例年と異なるタイプの出題でした。アマガエルに鳴き声を測定する装置とGPSを着ける、鳴き声に反応して近くのライトが光る仕掛けを用いるなど、回答の幅は広い問題ではありますが、発想力が求められる難易度の高い問題だったと言えます。
柔軟に物事を捉えてアイディアを出す力だけではなく、イメージしたものを、具体的に言語化できるかどうかという点についても見られている問題です。
また、適性検査Ⅲでは例年、条件をもとにして書き出して数え上げる問題が出題されます。短い時間の中での根気強さが求められますが、条件を正確に読み取り、丁寧に書き出すことで、確実に点数につなげられる問題です。過去問なども利用して類題に多く取り組み、得点源にしましょう。
⑥出題形式の似ている学校
出題形式の似ている学校としては、適性検査・思考力型の問題を出題している学校が挙げられます。
都内の公立中高一貫校でも、全て独自作成問題で出題している千代田区立九段中等教育学校や、実施する学校が独自に作成している各校の適性検査Ⅲの問題などは参考になるでしょう。
そういった学校の過去問なども参考にしながら演習を進めましょう。
3. 東京都立小石川中等教育学校の受検対策

ここでは、小石川中等教育学校を受検するにあたり、
「いつ、何をしたらいいの?」
「過去問の取り組み方は?」
「家庭でのサポートの方法は?」
といった、保護者様が気になる受検対策方法をお伝えします。
①時期・教科別受験対策
ここでは、小学校4年生から受検直前まで、時期別・教科別の受検対策方法をご紹介します。理数教育に力を入れている学校ですから、算数や理科を得意科目にできるよう意識して準備しましょう。
(1)小学4年生
この時期には、学習習慣を身に着けることが何より重要です。自分から学習に向かう「向学心」を育みましょう。また、教養としての知識を身に付けたり、興味や関心を広げられるようにしましょう。
算数:基礎的な計算力を身に着けるととに、私立中入試でも都立中入試でもよく出題される、周期算や植木算などの学習に取り組みましょう。
国語:ある程度長さのある文章で、内容を正しく読み取れるようになることを意識しましょう。
理科・社会:身近な事象に幅広く興味を持てるよう、体験・経験を重視して楽しく教養を身に着けられるようにしましょう。
(2)小学5年生
都立の中高一貫校受検に必要な「報告書」の対象になるのは、5年生の学校生活の様子からです。特に小石川中等教育学校は、総合成績に対して報告書の占める割合が25%と比較的高いため、油断は禁物です。すべての科目において、学校の学習活動にも十分に取り組み、評定をとっておくことが大切です。都立中高一貫校の適性検査で求められる思考力や表現力、分析力は、しっかりとした基礎基本の上に育っていくものです。習ったことは確実に身に着けていけるように意識しましょう。
算数:基礎計算の正確さとスピードを鍛えるとともに、論理的に考える力や条件を整理する問題の解き方などを身に着けましょう。
国語:語彙を増やすことに力を入れましょう。特に小石川中等教育学校では、適性検査Ⅰの作文の得点が合否を大きく左右します。正しい書き言葉や文法を意識して文章を書きましょう。
理科・社会:学校や塾で習ったことを丁寧に復習し、知識を問う問題に関しては確実に答えられるようにしましょう。
(3)小学6年生(4~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校を具体的に絞っていくのもこの時期でしょう。
算数:文章題を中心に問題を正確に読み取り、どのような方法をとれば正解にたどり着けるのかを考える力を身に着けましょう。
国語:読解問題、特に記述式の問題の練習をしましょう。筆者の主張や表現の意味することがらを記述させるような問題は頻出ですので、確実に得点できるよう、答え合わせの際には、正解していたとしても必ず根拠を確認しましょう。
理科:実験や観察の結果を分析したり、考察したりする問題の対策を進めましょう。示された数値が何を表しているのか理解したり、データを分析する過程で、どのデータを組み合わせるのかを理解できるように意識するとよいです。
社会:時事的な問題に対応できるよう、新聞やニュース番組を見るように心がけましょう。また、それに対して自分がどう思うかを誰かと話したり、文章として書いてみることも作文や記述問題の力につながります。
(4)小学6年生(7~8月)
「夏は受験の天王山」とも言われる季節。特に夏休み中は、体調管理と生活リズムを整えて過ごしたいですね。
算数:初見の問題への対応力を身に着けたい時期です。特に頻出の条件の整理、場合の数などの問題では、短い時間で丁寧に条件を理解する力が求められます。
国語:作文と評論文の対策をしましょう。読んだ文章のキーワードになる言葉を短くまとめる練習をしたり、筆者の主張を要約したりする練習をすると効果的です。
理科・社会:複数の資料を総合的に活用する問題で、どの資料から何が分かるのか、情報を適切に分析する力を養っていきましょう。それをもとに、記述式の問題でしっかり得点できるように、正解できた問題も別の見方や考え方ができないか、検討してみることが大切です。
適性検査対策として、教科横断的な問題に取り組み、適性検査の形式に慣れることも必要です。
(5)小学6年生(9~11月)
冬が近づいてきたら、いよいよ過去問にも挑戦しましょう。過去問の解き方については、このあと詳しくお伝えします。
(6)小学6年生(12月~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、出題形式の似ている他校の過去問なども活用しながら、様々な問題に取り組んで仕上げをしていきましょう。間違った問題は復習もしてください。
②東京都立小石川中等教育学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的の1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。過去問で間違ったところは、その時点で復習が必要なポイントということです。残りの時間で復習し、もう一度解いてみることで、同じような問題に出会ったら確実に解けるようにしておくのです。
2つ目の目的は、時間の感覚を掴むためです。入試本番では、決められた時間で問題を解き終える必要があります。過去問に取り組む際には時間の感覚を身に着けるために、入試本番と同じスケジュールで解くことをおすすめします。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入試範囲の学習が一通り終わり、かつ間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある、6年生の秋ごろから取り組んでみることをお勧めします。過去問に挑戦して解けなかった問題は、直前期に向けてしっかり復習しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第一志望でしたら5年分程度、併願校として受験する場合でも、2・3年分は必ず解いてみましょう。小石川中等教育学校の独自作成問題である適性検査Ⅱの大問2や適性検査Ⅲは7年分程度遡って練習しましょう。
過去問は何度も繰り返し解く必要はなく、一周すれば十分です。もう既にできていることに時間を割くよりも、できないことを一つでも多くできるようにしたほうが、合格に近付けるからです。ですから、間違えた問題は時間をかけて復習し、解けるまで何度も挑戦しましょう。
③保護者様にできるサポートとは?
(1)自分の考えや経験を述べる練習をする
例年、適性検査Ⅰでは、自分の意見や経験を書く作文が出題されます。「今日はどんな一日だった?」「それについてどう思った?」など、家庭内の会話の中で、思考や経験の言語化を促しましょう。また、気持ちを言葉にすることがストレスの溜まりやすい受験生生活の中でよい感情の発散にもなります。
(2)興味や関心の幅を広げ、様々な経験をする
適性検査の問題には、観察や実験、身近な出来事を取りあげた問題がよく出題されます。理数教育に力を入れている小石川中等教育学校では、その傾向は顕著です。
植物や野菜を育てたり、一緒に料理をしたり、多くの経験をさせて引き出しを増やすことも、保護者様だからこそできるサポートの一つです。科学館や博物館を訪れたり百科事典などを読むのも効果的です。
(3)メンタルケア・体調管理のサポートをする
想像以上に精神的にも身体的にも負荷のかかる受検生生活。一方で、心身ともに大きく成長する大切な時期でもあります。
だからこそ、メンタル面のケアと体調管理は保護者様にもっとも力を入れていただきたいサポートです。受検本番はもちろん、日々安定した状態で生徒様が毎日を過ごせるように、食事や睡眠時間について親子で決まり事を作ったり、生徒様が安心して過ごせるような空間づくりをしましょう。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 東京都立小石川中等教育学校を受ける際の併願パターン
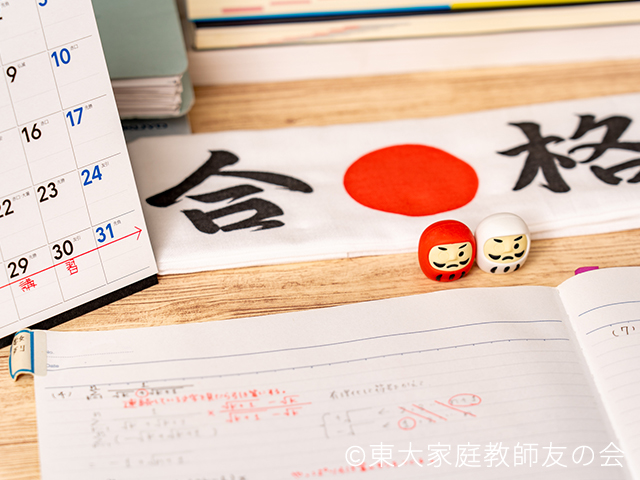
都立の中高一貫は、2月3日に一斉に一般入試を実施するため、都立中高一貫校同士の併願はできません。ですので、私立中学を併願先とすることになります。
一般的に都立中高一貫校を第一志望としている場合、適性検査型の入試をする私立学校を練習として受験するケースが多いものの、小石川中等教育学校の受検生の場合には、難関と言われる私立中学を受験している生徒様も多い点が大きな特徴です。
ここでは、難関私立校併願タイプと、適性検査型重視併願タイプの2パターンに分けて、ライターがこれまでに出会った生徒様の併願校を参考にオススメの併願パターンをご紹介します。
男女ともに、男子校・女子校を併願するかどうかで大きく傾向が異なるため、男子校には★を、女子校には☆を付しています。
共学校に強いこだわりがある場合は別ですが、男子校・女子校も選択の幅が広がるのでお勧めです。学校選びの際に参考にしていただけますと幸いです。
なお、この併願校情報は2024年度の入試をもとに作成していますので、2025年度の入試情報に関しては各校の募集要項を必ずご確認ください。
①難関私立校併願タイプ
小石川中等教育学校の受検生の中には、4科型入試の準備を続け、難関と呼ばれる私立中学を併願している生徒様も多いです。
「難関私立校に合格しても小石川は不合格だった」
「難関私立は不合格だったが小石川には合格できた」
という、どちらのパターンも多く見てきました。
報告書の持ち点や問題との相性によるものだと思いますが、どちらのパターンもありうるからこそ、併願校選びは慎重に行いたいですね。
※★=男子校、☆=女子校、・=共学
(1)1月
・栄東中学校
・市川中学校
・渋谷学園幕張中学校
★立教新座中学校
(2)2月1日
★武蔵中学校
★芝中学校
★本郷中学校
★海城中学校
★麻布中学校
☆女子院中学校
(3)2月2日
・渋谷学園渋谷中学校
☆吉祥女子中学校
(4)2月4日以降
・城北中学校
☆大妻中学校
②適性検査型重視併願タイプ
小石川中等教育学校の入試を想定して、練習として似た出題形式の学校を受験したい、という生徒様におすすめの併願先です。
※★=男子校、☆=女子校、・=共学
(1)1月
・栄東中学校
・市川中学校
・渋谷学園幕張中学校
(2)2月1日
・かえつ有明中学校(思考力特待)
・共立女子第二中学校(適性検査型)
☆玉川聖学院中等部(適性検査型入試)
・宝仙学園理数インター中学校(公立一貫型(適性検査))
・安田学園中学校(適性検査型)
(3)2月2日
☆小石川淑徳学園中学校(適性プレミアム入試)
・宝仙学園理数インター中学校(公立一貫型(適性検査))
・淑徳巣鴨中学高等学校(未来力入試)
・安田学園中学校(適性検査型)
(4)2月4日以降
・東京都市大学等々力中学校(アクティブラーニング型入試)
5. 東京都立小石川中等教育学校の受検対策をはじめよう!
都立小石川中等教育学校は、理数教育や国際教育に力を入れており、難関大学への現役での高い合格実績も誇る、都立中高一貫校の中でも特に人気のある学校です。
入試は、特別枠募集と一般枠募集があり、特別枠入試が2月1日、一般枠入試が2月3日に実施されます。一般入試は、報告書(200点満点)、適性検査Ⅰ~Ⅲの800点満点で合否が決定します。問題のうち、適性検査ⅠとⅡ(ただし、大問2は独自作成問題に差し替え)は都立中高一貫校の共同作成問題、適性検査Ⅲは理数系の独自作成問題です。
小石川中等教育学校の入試は、都立中高一貫校のなかでも難関とされており、適性検査で重視される「思考力・表現力・分析力」はもちろん、その土台となる4教科の学力が十分に身についていることが大切です。また、総合得点に占める報告書の割合が25%と高いため、学校の学習にもしっかりと取り組みましょう。
理数教育に力を入れている学校だからこそ、小学校段階で「算数・理科が好き」という気持ちを大切にしていくことが合格への何よりの秘訣です。
家庭教師が小石川中等教育学校合格をサポート!
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
小石川中等教育学校出身の家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会をもっと知る