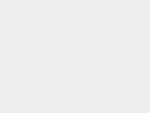1. 千代田区立九段中等教育学校の偏差値と基本情報

千代田区立九段中等教育学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①千代田区立九段中等教育学校の偏差値
千代田区立九段中等教育学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
|
2/3 |
男子 58 |
男子 67 |
②千代田区立九段中等教育学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
2006年 |
|
所在地 |
東京都千代田区九段北2丁目2‑1 |
|
アクセス |
都営三田線「九段下駅」徒歩約3分 |
| 校種 | 公立・共学(中高一貫) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・英語合宿、海外研修(オーストラリア2年・米国選抜研修)、ICT・DX活用の英語サロン設置 ・STEAM教育や起業家精神を養うカリキュラム、在外公館・企業との連携ディスカッションあり ・スーパーサイエンススクール指定。豊富な実験環境と探究授業が特徴 |
東京都で唯一の区立中高一貫校である九段中等教育学校。令和6年度には前身である第一東京市立中学校の開校から百周年を迎える伝統校でもあり、官公庁や大手企業などが多く集まる地域性を活かして様々な独自のカリキュラムを展開しています。ここでは、九段中等教育学校の特に注目したい3つの魅力をご紹介します。
①生きた英語を学ぶ「九段イングリッシュ」
未来に貢献できる国際的な人材の育成を目指し、少人数クラスでの授業や学校近隣の大使館訪問、3年生でのオーストラリア研修旅行などを通じ、4技能をバランスよく身に着けていきます。5年生のシンガポール海外研修は、学んだ英語を試す絶好の機会になっています。
②独自のキャリア教育プラン「九段自立プラン」
「九段自立プラン」は、主体的に学び行動できる力や将来の生き方を考える力を育成する、6年間を通じた独自のキャリア教育プランです。千代田区の恵まれた教育環境を活かし、本物に触れる体験を重視し、高校卒業後だけではなくその先の将来についても考えます。
③充実した学習環境
主に1年生から4年生までが学ぶ九段校舎と、5・6年生が学ぶ富士見校舎に分かれており、理科系科目の実験教室や蔵書約4万1千冊の図書室、平日夜8時まで利用できる自習室などがあり、集中して学習に取り組める環境が整っています。上級生になると学びの拠点が変わることで、中高一貫校に通う生徒に多い中だるみも予防できそうです。
2. 千代田区立九段中等教育学校の入試傾向

九段中等教育学校の入試は、例年2月3日に実施されます。ここでは、入試の概要や報告書の点数の換算方法、各試験の内容等についてお伝えするとともに、2024年度入試の適性検査で特徴的だった問題、合否を分けた問題などについて解説します。
①入試の特徴
入学者は、小学校4・5・6年生の各教科の学習の記録を点数化した報告書(200点満点)と試験日当日に実施される適性検査1(200点満点)、適性検査2(300点満点)、適性検査3(300点満点)の合計1000点満点で決まります。各適性検査の試験時間は45分間です。
九段中等教育学校の適性検査の問題は、全て独自作成問題で、例年、適性検査1は国語的な力を読解力や表現力を試す問題が出題されますが、適性検査2・3には明確な出題分野の区分がなく、算数・理科・社会の融合問題が出題されています。そのため、他の都立中高一貫校や私立中学校と比較して出題傾向が掴みにくい点が特徴だと言えます。初めて見るタイプの問題にも柔軟に対応できるような力を身に着けておく必要があります。
2024年度入試ではそれまでの男女別の定員が廃止され、千代田区民を対象にした区分Aは実質倍率2.0倍、千代田区以外の都民を対象にした区分Bは実質倍率4.9倍でした。
②報告書の換算方法
報告書は、小学校4・5・6年生の通知表の学習の記録を点数化したものです。
各評価の評定を、
|
評定3=40点 評定2=20点 評定1=1点 |
とし、各教科の合計点×200/1000(小数点以下は切り捨て)で計算します。
1000点満点のうちの200点、つまり五分の一は学校の成績で決まるわけですから、公立中高一貫校の受験を考えているのであれば、普段の学校生活もおろそかにはできませんね。
③適性検査1
適性検査1は、国語型の問題が中心で、最後に作文が出題されている点が大きな特徴です。詩が含まれる文章もよく出題されており、2024年度入試でも、詩の魅力について筆者が自らの考えを述べている文章が出題されました。
ここでは適性検査1の中心とも言える作文の問題について解説します。問題は、「自己と自己の重なりをつくるコミュニケーション方法」に対する自分の考えを、
|
<条件1> ①第一段落には「自己と自己の重なりをつくる」とはどのようなことかを、文章Ⅰの本文中の言葉を使って書く ②第二段落には、「自己と自己の重なりをつくるコミュニケーション方法」で会話した自分の経験を具体的に書く ③第三段落には、第二段落で書いた体験において、「自己と自己の重なりをつくる」上で大きな役割を果たしていたと考えられるしぐさや態度を書く |
|
<条件2> ①原稿用紙の正しい使い方で、書き出しは1マス空けて書き始めること ②言葉を正しく使い、百八十字以上二百字以内で書くこと ③記号も1字と数え、改行で空いたマスも字数に数えること |
の2つの条件に従って書くというものです。
ポイントは、第一段落で条件1の①「自己と自己の重なり」とは何かを明らかにして書けるかということと、第二・三段落で「共話」について十分に読み取れたことを示す自分の具体例が書けるかどうかの2点です。
まずは、「自己と自己の重なりをつくる」とは、「共話」によって相手と自分との心理的な距離を縮め、相手と自分を切り離す壁をなくすことであることを説明します。第三段落は単にしぐさや態度の具体例を挙げて終わるのではなく、自分が挙げた例が「自己と自己の重なりをつくる上で大きな役割を果たしたと思う」などと、三つの段落の内容を総括するような一文が書けるとよいでしょう。
作文の問題では毎年、自分の経験や考えを具体的に示すことが求められます。ですので、日頃から様々な事柄に対して、自分の考えを書く練習をすることが効果的です。条件2の②に「言葉を正しく使い」とあるように、適性検査1のみならず入試問題全体で、豊富な語彙力とそれを正しく運用していく能力が求められているように感じられます。作文に限らず記述問題に取り組む際には、書き言葉で書くことや、ら抜き言葉やさ入れ言葉などに気を付けるようにしましょう。
➃適性検査2
適性検査2は、様々な形式の資料の読み取り問題が多く、正確な資料の読み取りと情報処理能力が試されていると言えるでしょう。2024年度入試では、
|
大問1:立体図形 大問2:住んでいる町を調べる学習の方法 大問3:塩レモンの作り方と中和 |
に関する問題と、算数・社会・理科の分野に関する融合的な問題でした。
ここでは特徴的だった問題として大問2の問3を取り上げます。この問題は、3つの資料の中から必要な資料をすべて用いて、予想される「じゅうまえ市の未来」について書くというものです。
|
①最も大きな変化は「いつからいつ」「どのような人」に起こった変化か ②「何が原因」で大きく変化したのか ③じゅうまえ市が今後どのように変化していくか ④どの資料を根拠に説明しているか |
以上の4つを明らかにして書くことが条件とされている点が、この問題を解く鍵だと言えるでしょう。条件に沿って資料を読み取ることで確実に点数を取っていきたい問題です。
回答の流れとしては、①の最も大きな変化は、[資料10]より、1990年には53000人まで減った人口が2020年には96000人に増加したことです。その原因として(②)、[資料9]から鉄道が通ったことや[資料11]から市を活性化するプロジェクトに市の職員が参加するようになったことや、外国人や環境にもやさしい街づくりが行われていることがわかります。今後もそういったまちづくりが進められることで、人口が増えていくと予想される(④)ことを述べるのがよいでしょう。
この問題では、複数の資料を関連付けて考えられるかが試されており、適性検査の文系問題の典型的な形と言えます。こういった問題を解くためには、一つの問題について様々な角度から考えたり、ある事柄の変化に関して、根拠を複数の見方から説明できるように練習するとよいでしょう。
⑤適性検査3
2024年度は、
|
大問1:条件の整理と場合の数 大問2:地域の食文化 大問3:トマトの育て方と積算温度 |
と、適性検査2と同様に、算数・社会・理科の分野の融合的な問題が出題されました。
ここでは、大問1の問2を解説します。
この問題は、ある商品のバーコードの下に書かれた13けたのコードについて、けた番号3が□、けた番号2が△で表されています。二つの資料(バーコードの特徴とチェックデジットの計算方法)をもとに、□と△に入る数字の組み合わせを三つ答えます。
チェックデジットの計算問題は、適性検査でよく出題される形式ではありますが、この問題の場合、考えられる組み合わせのパターンは全部で10パターンあり、その中から任意の3つ答える、という点で戸惑いを感じた受験生は多かったのではないでしょうか。
与えられたバーコードの偶数桁のコードの和は24+△と表され、この3倍は72+3×△(…ⅰ)です。また、けた番号1以外の奇数のけたのコードの和は19+□(…ⅱ)であり、ⅰ+ⅱの和は91+□+△×3(…ⅲ)です。さらに、10からⅲの一の位を引いた数が9なので、(ⅲ)の一の位は1であることがわかります。以上より、□+△×3の計算結果の一の位は0になるので、求められる組み合わせは、(0,0)(1,3)(2,6)(3,9)(4,2)(5,5)(6,8)(7,1)(8,4)(9,7)で、この中から3つを挙げればよいです。
与えられた条件を丁寧に整理するだけではなく、記号を用いた計算が必要だったことに加え、導き出せた10パターンの中から任意の3つを答える、という点が少しクセのある問題だったと言えます。理数型の問題は、身近にあるものの規則性や実験・観察をもとにした問題が多いです。問題で出題されたもののなかで自分で試せるものは、実際にやってみるものよいかと思います。
⑥出題形式の似ている学校は?
出題形式の似ている学校としては、九段中等教育学校と同様に適性検査型の入試を実施されている「都立中高一貫校の問題」が参考になるでしょう。さらに資料の読み取り、記述式で答える問題が多いという特徴から、
|
・横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 ・埼玉県伊奈学園中学校 |
などが挙げられます。
そのほか、私立中学校でも公立中高一貫校志望の受験生をターゲットにした「思考力型」や「適性検査型」などと呼ばれる入試を実施している学校がありますので、そういった学校の入試問題を参考にしてみましょう。
3. 千代田区立九段中等教育学校の受験対策
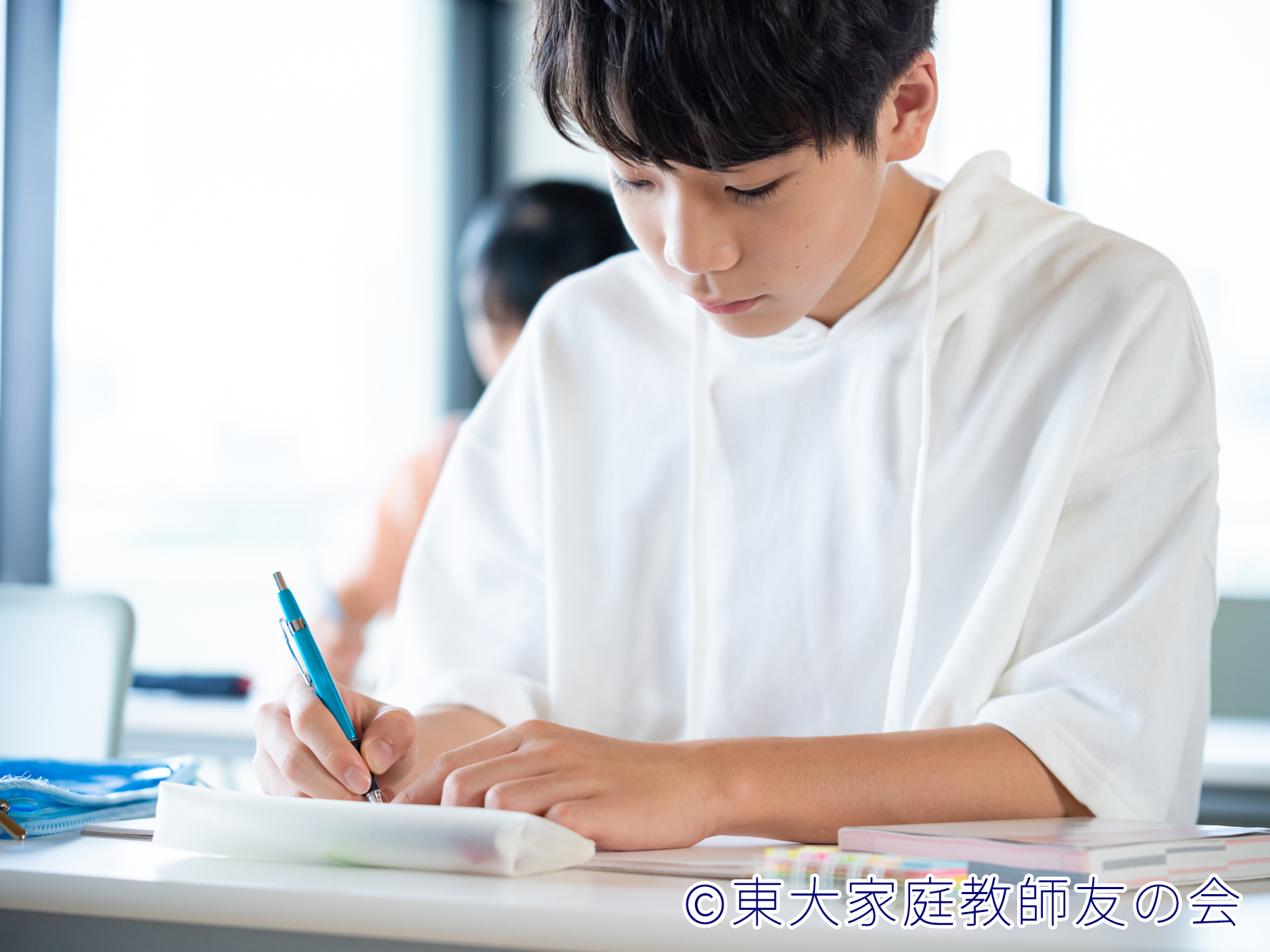
ここでは、九段中等教育学校を受験するにあたり、
「いつ、何をしたらいいの?」
「過去問の取り組み方は?」
「家庭でのサポートの方法は?」
といった、保護者様が気になる受験対策方法をお伝えします。
①【時期・教科別】受験対策
ここでは、「報告書」にも関わってくる小学校4年生から受験直前までの、時期別・教科別の受験対策方法をご紹介します。
(1)小学4年生
九段中等教育学校の場合、受験の際に提出する「報告書」の対象になるのは、4年生の成績からです。そのため、国語・算数・理科・社会に限らず、全ての科目において、学校の学習活動に十分に取り組み、評定をとっていくことを大切にしましょう。
この時期には、学習習慣を身に着けることが何より重要です。最低限、学校や塾の宿題などのやるべきことに取り組む時間を確保し、自分から学習に向かう「向学心」を育みましょう。
また、教養としての知識を身に付けたり、興味や関心を広げられるようにしましょう。
(2)小学5年生
5年生は、中学受験の土台固めの時期です。公立中高一貫校の適性検査で求められる思考力や表現力、分析力は、基礎基本の土台の上に育っていくものです。また、併願校も含め、実際に色々な学校に足を運んでみましょう。
算数:基礎計算の正確さとスピードを鍛えるとともに、論理的に考える力や条件を整理する問題の解き方などを身に着けましょう。
国語:語彙を増やすことに力を入れましょう。特に九段中等教育学校では、語彙力とその運用能力が求められています。正しい書き言葉や文法を意識して文章を書きましょう。
理科・社会:学校や塾で習ったことを丁寧に復習し、知識を問う問題に関しては確実に答えられるようにしましょう。また、身の回りの様々な出来事の規則性などに目を向けられるようになるとよいですね。
(3)小学6年生(4月~6月)
入試に向けての動きが本格化する6年生。受験校を具体的に絞っていくのもこの時期でしょう。
算数:文章題を中心に問題を正確に読み取り、どのような方法をとれば正解にたどり着けるのかを考える力を身に着けましょう。
国語:読解問題、特に九段中等教育学校で多く出題される、記述式の問題の練習をしましょう。特に、筆者の主張や表現の意味することがらを記述させるような問題は頻出ですので、確実に得点できるよう、答え合わせの際には、正解していたとしても必ず根拠を確認しましょう。
理科:実験や観察の結果を分析したり、考察したりする問題の対策を進めましょう。実験や観察に関する問題では、その結果の数値が何を表しているのか理解したり、データを分析する過程で、どのデータを組み合わせるのかを理解できるように意識するとよいです。
社会:時事的な問題に対応できるよう、新聞やニュース番組を見るように心がけましょう。また、それに対して自分がどう思うかを誰かと話したり、文章として書いてみることも作文や記述問題の力につながります。
適性検査対策として、教科横断的な問題に取り組み、適性検査の形式に慣れることも必要です。
(4)小学6年生(7月~8月)
「夏は受験の天王山」とも言われる季節。特に夏休み中は、体調管理と生活リズムを整えて過ごしたいですね。
算数:初見の問題への対応力を身に着けたい時期です。特に頻出の図形や条件の整理、場合の数などの問題では、別の解き方がないか考えてみたり複数の方法で解いてみることが力になります。
国語:作文の対策に力を入れましょう。評論文では、読んだ文章のキーワードになる言葉を短くまとめる練習をしたり、筆者の主張を要約したりする練習をすると効果的です。
理科・社会:複数の資料を総合的に活用する問題の対策をしましょう。どの資料から何が分かるのか、情報を適切に分析する力を養っていきましょう。それをもとに、記述式の問題でしっかり得点できるように、正解できた問題も別の見方や考え方ができないか、検討してみることが大切です。
(5)小学6年生(9月~11月)
冬が近づいてきたら、いよいよ過去問にも挑戦しましょう。過去問の解き方については、このあと詳しくお伝えします。
理科・数学タイプについては、九段中等教育学校で頻出のコンパスを使った作図の問題に力を入れて取り組み、より得点力を伸ばしていきましょう。
(6)小学6年生(12月~1月)
本番に向けてのラストスパートのこの時期は、出題形式の似ている他校の過去問なども活用しながら、様々な問題に取り組んで仕上げをしていきましょう。間違った問題は復習もしてください。
②九段中等教育学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的の1つ目は、入試問題の傾向を掴み、合格までの距離感を知るためです。過去問で間違ったところは、その時点で復習が必要なポイントということです。残りの時間で復習し、もう一度解いてみることで、同じような問題に出会ったら確実に解けるようにしておくのです。
2つ目の目的は、時間の感覚を掴むためです。入試本番では、決められた時間で問題を解き終える必要があります。過去問に取り組む際には時間の感覚を身に着けるために、入試本番と同じスケジュールで解くことをおすすめします。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入試範囲の学習が一通り終わり、かつ間違えた問題の復習に取り組む時間的・精神的な余裕のある、6年生の秋ごろから取り組んでみることをお勧めします。過去問に挑戦して解けなかった問題は、直前期に向けてしっかり復習しておきましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
九段中等教育学校が第一志望でしたら、5年分程度、併願校として受験する場合でも、2、3年分は解いてみましょう。
九段中等教育学校では、初めて見るようなタイプの問題に対応する柔軟性が必要なので、ある程度演習を積むことが大切です。特に、頻出のコンパスを使った作図の問題は、他校ではほとんど類題が見られないため、さらに遡って練習しましょう。
過去問は何度も繰り返し解く必要はなく、一周すれば十分です。もう既にできていることに時間を割くよりも、できないことを一つでも多くできるようにしたほうが、合格に近付けるからです。ですから、間違えた問題は時間をかけて復習し、解けるまで何度もチャレンジしましょう。
③保護者様にできるサポート
(1)自分の考えや経験を述べる練習をする
例年、適性検査1では、自分の意見や経験を書く作文が出題されます。「今日はどんな一日だった?」「それについてどう思った?」など、家庭内の会話の中で、思考や経験の言語化を促しましょう。また、気持ちを言葉にすることがストレスの溜まりやすい受験生生活の中でよい感情の発散にもはずです。
(2)興味や関心の幅を広げ、様々な経験をする
適性検査の問題には、観察や実験、身近な出来事を取りあげた問題がよく出題されます。植物や野菜を育てたり、一緒に料理をしたり、多くの経験をさせて引き出しを増やすことも、保護者様だからこそできるサポートの一つでしょう。科学館や博物館を訪れたり百科事典などを読むのも効果的です。
(3)メンタルケア・体調管理のサポートをする
普段の学校に受験勉強と、想像以上に精神的にも身体的にも負荷のかかる受験生生活。その一方で、心身ともに大きく成長する大切な時期でもあります。
だからこそ、メンタル面のケアと体調管理は保護者様にもっとも力を入れていただきたいサポートです。受験本番はもちろんですが、日々安定した状態で生徒様が毎日を過ごせるように、食事や睡眠時間について親子で決まり事を作ったり、生徒様が安心して過ごせるようにしてください。
4. 千代田区立九段中等教育学校を受ける際の併願パターン

なお、この併願校情報は2024年度の入試をもとに作成していますので、2025年度の入試情報に関しては各校の募集要項を必ずご確認ください。
①学力に余裕がある場合
(1)1月入試
|
・開智未来中学校 |
(2)2月1日
都内の私立中学の入試が本格的に始まる1日は、
|
・広尾学園小石川中学校 |
などとの併願がよく見られます。
・安田学園中学校
の適性検査型の入試も練習としておすすめです。
(3)2月2日
|
<男子校> <共学校> |
(4)2月4日以降
|
<男子校> ・立教池袋中学校 <女子校> ・品川女子中学校など |
②合格までもうひと踏ん張り必要な場合
(1)1月入試
|
・昭和秀英中学校 |
(2)2月1日
|
・東京成徳大学附属中学校 |
(3)2月2日
|
・宝仙学園中学校 |
の受験がよく見られます。
女子の生徒様であれば、大妻中野中学校との併願がよく見られましたが、大妻中野中学校は、2025年度入試では新思考力入試を廃止し、今後は4科入試の中で思考力を問う内容を出題することを発表していますので、併願の傾向にも変化が見られそうです。
(4)2月4日以降
|
・郁文館中学校 |
などが候補となるでしょう。
5. 千代田区立九段中等教育学校の受検対策をはじめよう!
千代田区立九段中等教育学校は、東京都で唯一の区立中高一貫校で、地域性を活かした様々な独自のカリキュラムを展開しています。
入学試験は例年2月3日に、全て独自作成問題で実施されます。小学校4・5・6年生の各教科の学習の記録を点数化した報告書(200点満点)、適性検査1(200点満点)、適性検査2(300点満点)、適性検査3(300点満点)の合計1000点満点で合格者を決定します。
試験時間は45分間です。1000分の200、つまり5分の1は普段の学校の学習への取り組みで決まりますので、受験を意識し始めたら、学校での学習も気が抜けません。国語算数理科社会以外の科目や宿題等にも真摯に向き合いましょう。
適性検査1は読解力重視の国語型で、作文が含まれます。適性検査2・3には明確な出題区別がなく、数学・社会・理科の教科横断的な問題が出題されます。そのため、他の適性検査・思考力型入試の学校と比較して出題傾向が掴みにくい点が特徴です。資料を多く読み取らせる分析力を問う問題や、記述で説明する、思考力や表現力をはかる問題が多く出題されるので、演習を積んでおきましょう。
受験に向けてご家庭で保護者様ができるサポートとしては、日常の出来事での経験や時事的な事柄への意見などを言語化する練習をすることや、様々な経験を通して、生徒様の興味関心を広げるような取り組みが挙げられます。何より、メンタルケアや精神面でのサポートが十分にできるよう、生徒様の様子を日頃から気にかけるようにしましょう。生徒様が保護者様に「しっかり見てくれている」と感じられるだけでも、精神的な安定に繋がってくるはずです。
素敵な春がやってくることをお祈りしています。
【参考文献】
・千代田区九段中等教育学校ホームページ
・声の教育社「千代田区立くだん2025年度用スーパー過去問」
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら