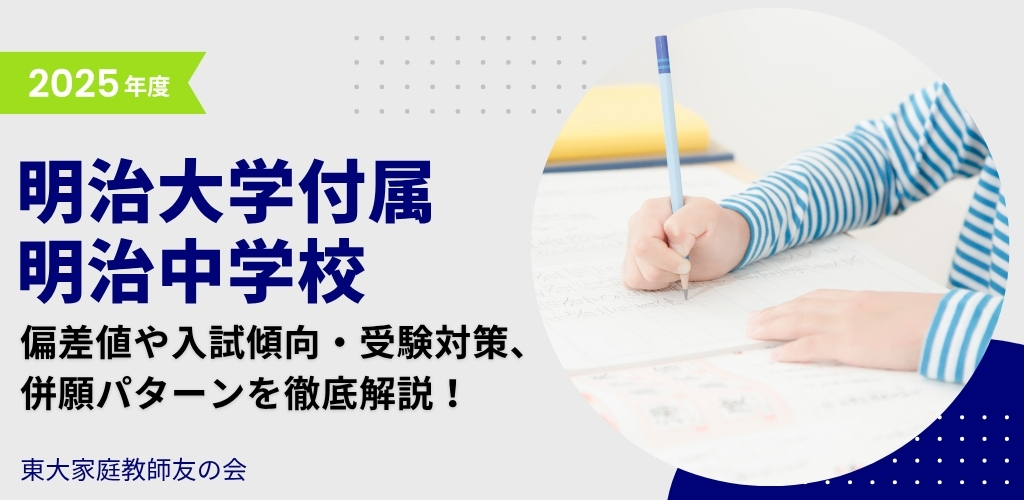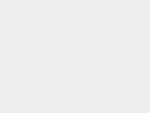1. 明治大学付属明治中学校の偏差値と基本情報

明治大学付属明治中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①明治大学付属明治中学校の偏差値
明治大学付属明治中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
SAPIX小学部 (合格率80%偏差値) |
|
2/2 |
男子 62 |
男子 71 |
男子 56 |
|
2/3 |
男子 62 |
男子 72 |
男子 56 |
明治大学付属明治中学校の偏差値は入試日程ごとに異なるため、受験する日程に応じた偏差値を確認して、志望校選びや学習計画に役立ててください。
②明治大学付属明治中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
1912年 |
|
所在地 |
東京都調布市富士見町4‑23‑25 |
|
アクセス |
京王線「調布駅」「飛田給駅」、JR南武線「矢野口駅」「三鷹駅」からスクールバス運行 |
| 校種 | 私立男女共学校(中高一貫) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・週6日制+7限目補講制度で学力基盤を強化 ・英語は少人数・習熟度別+外国人講師の会話授業 ・中3後半から高校学習内容に先取りし、英検・TOEIC・漢検等の資格取得を支援 ・中学では林間学校・移動教室・修学旅行、高校では体育祭・紫紺祭・野球応援など |
明治大学系列の付属校で共学校。明治大学への進学率は約9割で、国公立受験等条件によって、明治大学への推薦枠を持ったまま受験できます。
特徴的な点としては、大学との連携授業です。高校在学中に明治大学の教員からの授業を体験できたり、大学科目の先行履修が可能であったり、付属校ならではの優遇制度があります。
希望制にはなりますが、英語研修の機会が多いのも特徴です。海外での数週間~3か月に亘る研修が、大きな休み毎に設定されています。積極的に英語に触れていきたい生徒様には申し分のない環境と言えるでしょう。
2. 明治大学付属明治中学校の入試傾向

第一回・第二回入試は算数・国語・理科・社会の4科目の試験です。試験時間は、算数50分・国語50分・理科40分・社会40分、配点は各々100点・100点・75点・75点です。
入試問題は、算数でかなり差がつきやすい傾向にあります。算数を中心とした対策が大事でしょう。
算数は大問が多く、どの問題も概ね標準的ながらも、文章が長く、設定がやや複雑なものがあります。
本格的な問題ですので、日頃の勉強の成果が存分に試される問題となっています。
国語はそれ程差がつかないものの、記述問題の多さが特徴です。100字程度の要約問題が出題されるなど、本格的な記述問題です。日頃から読書をしつつ、文章を書く練習が必要となるでしょう。
①算数
例年、大問5題の出題で、大問1番が小問集合、大問2番以降が単元別の問題となっています。この傾向は回数によって変わりありません。解法記述欄があるため、式や考え方を採点者に伝わるように記述する必要があります。
単元別の大問では、速さ・数の問題・ニュートン算・割合・図形などがよく出題されています。どの大問も、標準的な問題ではありますが、やや応用的な論点も含まれているため、少し難しめの問題まで対応できるように過去問を使用して演習しましょう。以下、よく出る単元について補足して説明します。
速さは旅人算だけでなく、水量に関する問題や流水算・通過算といった特殊算も出題されています。図やダイヤグラムを書いて考えるようにしましょう。数の問題は規則性・つるかめ算・約数・倍数が頻出です。考えづらい問題は、具体的に書き出してみて、状況を理解していくことが大切です。
ニュートン算は、過去問と似たような問題が何度も何度も繰り返し出題されています。2024年度第一回でも、ニュートン算が出題されましたが、過去問と似た形式でした。過去問をしっかり解き直している生徒様とそうでない生徒様で差がついたと思われます。
割合は、食塩水や損益算、線分図を用いた問題が出題されます。標準的な問題が多いですから、過去問・問題集でよく演習しましょう。
図形は平面図形・立体図形どちらも出題されますが、平面図形の割合が高く、相似に関する問題が頻出です。立体図形が出題される場合、切断問題など応用的な問題もあり得ますので、難しい論点も対策しましょう。
②国語
例年、大問2.3題の出題で、大問1番が説明文、大問2番や3番で漢字・語彙に関する問題が出題されます。説明文の問題は大変長い文章が特徴的で、およそ10,000字の文章が出題されます。
長い文章を読み込むだけの読解力が必要ですから、普段から何十ページにも亘る本を読むようにして、対応できるようにしましょう。設問は語彙・接続詞・空欄補充などがあるものの、最も比重の大きい問題が記述問題です。
明治大学付属明治中学校では、記述問題が数多く出題され、字数も多いものでは100字、もしくは字数制限が無いものもあります。棒線部の近くだけではなく、本文全体を踏まえた上での記述問題も多く、とくに特徴的な問題は要旨に関する問題です。
2024年度第一回も、100字以内で要旨を答える記述問題があり、得点できる生徒様とそうでない生徒様で差がついた問題だったと思われます。本文全体を読解しつつ、論理的な文章が書けるように練習する必要があるでしょう。
③理科
例年、大問7題程度出題されており、物理・化学・生物・地学が満遍なく出題されています。またそれぞれの分野で、単元も満遍なく出題されており、幅広く対策する必要があります。この傾向は回数によりません。
物理・化学は計算問題中心の出題です。2024年度でも計算問題は多数出題されており、大問2番で溶解度、大問3番で気体の発生、大問6番でばねと浮力、大問7番で電熱線の問題が出題されました。これだけ多くの計算問題が出題されましたから、計算問題のできが合否を左右したと思われます。
計算問題以外でも、光・振り子などの現象理解の問題や、化学の知識問題も出題されています。計算問題だけでなく、全体的に学習するようにしましょう。
生物・地学は考察・実験問題で出題されることが多いですが、理解して解く問題と、知識問題のどちらもが出題されています。理解系の問題は、日頃から身近な現象理解を心掛け、知識問題は基本に忠実に学習してください。
④社会
例年、大問3〜4題の出題で、地理・歴史・公民が満遍なく出題されています。この傾向は回数により変化はありません。全体的に幅広く問われており、総合的な力が求められています。特徴的な問題としては、毎年最後の設問に出題される記述問題です。
前提となる文章や資料が提示され、生徒様の考えを問う問題が出題されています。2024年度第一回では、住民投票と日本国籍を持たない人に関する関係性についての記述問題でした。最近の時事についても理解していないと解けない問題で、差がついた問題だったと思われます。
時事問題の知識と共に論理的な文章が書けるように練習する必要があります。論理的な文章は国語の対策が活きてくるでしょう。
その他、単元別に見ますと、地理では地図帳を活用した学習が不可欠で、地形図や統計の問題が頻出です。また、色々なグラフ・表が提示され、時事問題と絡めた問題もよく出題されています。歴史は写真・絵・史料などの資料問題が多く、できごとの並べ替え問題も出題されます。
公民は満遍なく基本〜標準的な内容を網羅することが大切です。地理同様、時事問題と絡めた出題も多いです。時事問題は、日頃からニュース・新聞を見聞きして内容を把握すると共に、問題点などの把握が大事です。分からない内容を調べるようにしてください。
⑤問題の形式等が似ている学校は?
全体的な傾向としては、広尾学園小石川中学校に似ていると思われます。但し、理科については、あまり参考になりません。理科は、明治大学付属中野中学校が参考になるでしょう。
3. 明治大学付属明治中学校の受験対策

明治大学付属明治中学校の入試問題は全体的に標準的な問題ですが、やや難しい問題や、問題文が長い傾向があります。算数で最も差がつきますので、算数を中心とした対策が必要でしょう。
算数は、全般的に出題されますが、速さ・数の問題・ニュートン算・割合・図形が頻出単元です。これらの単元を中心に、少し難しめの問題まで対処できる様にしておくと良いでしょう。日頃の復習では解けるまで繰り返し解き、一度解けても時間を置いて再度解き直しをするようにしてください。
算数の次に差がつく国語では、記述問題を中心とした対策と文章の読解力が必要です。まずは要旨を掴む練習と毎日の読書から始めましょう。
理科と社会は知識の暗記は勿論ですが、理解をしながら学習を進めてください。
①時期別・教科別対策内容
(1)小学4年生
| 算数 |
算数は、塾のカリキュラムに沿って行いましょう。 明治大学付属明治中学校では、必ず計算問題が出題されます。 |
| 国語 |
国語も、カリキュラム・予習シリーズをもとに行いますが、文章が難しいと感じる場合は、少し簡単な文章から確実に読めるようにしてください。 また、日記を書くことも、文章を書くという意味で大切です。保護者様で添削して頂くと良いでしょう。 |
| 理科 |
理科は、生物・地学を中心とした暗記単元が始まりますから、今のうちにしっかりと暗記しましょう。 |
| 社会 |
社会は、地理分野が本格的に始まりますので、地図帳片手に場所を調べながら学習しましょう。 |
(2)小学5年生
| 算数 |
算数は、引き続き、カリキュラム通りに行って頂きたいですが、小学4年生の内容、及び小学五年生で習う内容も適宜復習するようにしてください。 |
| 国語 |
国語は、物語文・説明文共に、客観的に読む訓練です。 |
| 理科 |
理科は、物理・化学の計算問題が始まります。標準的な問題は解けるようにしましょう。 |
| 社会 |
社会は、歴史が始まります。全体的な流れを理解しながら、暗記をしてください。年号暗記も忘れずにしてください。 |
(3)小学6年生(4月〜6月)
| 算数 |
算数は、前学年までの復習をしっかりしながら、全体的なレベルを上げていく時期です。 |
| 国語 |
国語は、標準的な文章で、設問の解き方を確認してください。とにかく記述問題対策が大事です。本文全体を踏まえた上で適切な要約を書けることが必要でしょう。引き続き、文章の要約は継続して頂きたいですし、日記も書いて論理的な文章が書けるようにしましょう。 |
| 理科 |
理科は、引き続き、身の回りの事柄への理解を深めつつ、計算問題の力をつけましょう。 |
| 社会 |
社会は、公民が始まります。基本~標準的な事項は押さえましょう。時事問題対策として、ニュース・新聞は引き続きお願いします。 |
(4)小学6年生(7月〜8月)
| 算数 |
算数は、過去問を3〜5回分解きましょう。また、苦手単元があれば、夏休み中に克服しましょう。 |
| 国語 |
国語も、過去問を3回分は解いて、形式になれましょう。制限時間内に解き切れるか、文章を読むスピードはどうか、記述問題でポイントを外さずに論理的な文章が書けるか、そういった点を確認すると良いでしょう。語彙・漢字についてはこの夏休みで固めましょう。 |
| 理科 |
理科も、過去問を3〜5回分解きましょう。理解不足の所は、基本に戻って理解しましょう。 |
| 社会 |
社会も、過去問を3回分しましょう。過去問を通して弱点を見つけ、補強しましょう。 |
(5)小学6年生(9月~11月)
| 算数 |
算数は、過去問中心になりますが、とくに解き直しに力を入れてください。 |
| 国語 |
国語は、過去問を中心に進めますが、漢字・語彙の強化も忘れずに行なってください。 |
| 理科 |
理科も、やはり過去問を中心に学習します。 |
| 社会 |
社会も、過去問は解きますが、それと同時に、全般的な復習も忘れずにしてください。 |
(6)小学6年生(12月~1月)
| 算数 |
算数は、過去問の解き直し、速さ・数の問題・ニュートン算・割合・図形を含めた全般的な定着をさせましょう。 |
| 国語 |
国語は、時間配分・設問形式を忘れないために、1週間~2週間に1度は過去問に触れましょう。 |
| 理科 |
理科は、今まで習ってきた内容や、過去問の内容で、理解しきれていない所は無いか、確認してください。 |
| 社会 |
社会は、全般的な復習をしつつ、地図・地形図・統計・年号・資料を中心に確認してください。 |
②明治大学付属明治中学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方
算数・理科の計算問題は比較的似た問題が出題されますので、なるべくさかのぼって学習して、解き直しもしてください。国語・社会については、形式になれれば良いと思われますので、そこまで遡らなくても良いでしょう。
(2)いつから解き始めればよいか
算数と国語については、夏休み前から解き始めると良いでしょう。この2科目は差がつきやすい科目です。早めに解き始めた方が良いでしょう。
一方、理科と社会は夏休みに入ってから始めれば良いと考えます。あまり早く始めても、試験範囲の学習が終わっていない場合もありますので、焦らず夏休みに集中して学習しましょう。
(3)何年分を何周解けばよいか
| 算数 |
算数は、速さ・数の問題・ニュートン算・割合・図形といった、よく出る単元がありますし、素早く正確に解く練習も必要です。 |
| 国語 |
国語は、記述問題になれる必要がありますし、分量が多いですから、その対応も必要です。 |
| 理科 |
理科は、過去問を解くことで、理解しきれていない箇所を発見し、周辺事項を理解し直すようにしましょう。計算問題については、練習が必要です。 |
| 社会 |
社会は、出題形式になれる意味で、5~10回分行いましょう。 |
③保護者様にできるサポート内容
(1)成績が下降してきたら…
基本〜標準的な問題ができなくなっている可能性が高いです。塾などで難しい問題ばかりしていると、基本的な所がおろそかになり、土台が崩れ、成績が下降します。
ですので、保護者様には基本的な問題、たとえば小学4年生・5年生の単元に立ち戻って、再度復習をされることをおすすめします。
生徒様にも「少し前の単元に戻ってやってみようか。」とお声がけし、「ゆっくり基本からやり直してみよう。」と生徒様を責めずに、対応してください。また、試験の結果に一喜一憂せず、長い目で生徒様を見てあげてください。
(2)計算力対策
明治大学付属明治中学校は、計算力が鍵を握ります。計算問題は必ず出題されていますし、スピードも必要な試験です。毎日10問程度、四則演算の計算問題を解くと良いでしょう。
計算間違いが多い生徒様の場合、まずはゆっくりと正確に行う練習をしましょう。正確さが身についてから、スピードの順番でお願いします。
(3)理科の対策
明治大学付属明治中学校の理科は、これまで説明している通り、理解を問う問題が出題されています。保護者様としましては、身近な事柄について、生徒様と会話をして、一緒に調べて理解を促すようにしてください。
たとえば、
「洗濯物を干すと乾くのは何故だろうね?」
「シャボン玉の仕組みを一緒に考えてみようか」
「地震が起きる仕組みを一緒に調べてみようか」
「月の形が毎日少しずつ違ってくるのはどうしてなんだろう。」
など、日常当たり前のことをしっかりと調べることは、理科の対策にとても重要です。生徒様とご一緒に取り組んでみてください。
(4)時事問題対策
時事問題こそ、保護者様の出番です。今、ニュースや新聞で見聞きする内容は、保護者様にとっては常識的なことでも、生徒様には実感がわかない・わからないことも多いと思われます。
ニュースや新聞で出てきた内容を生徒様と会話するようにしてください。
たとえば、
「今円安が進んでいるってニュースで言っていたけど、どういうことかわかる?」
「男女の格差社会ってどういうことなんだろうね?」
と言った質問から、生徒様と一緒に会話をして、一緒に調べることは重要です。
取り組んで頂ければと思います。
(5)ケアレスミス対策
計算間違い・見間違い・勘違いなど全てケアレスミスと言われます。しかし、そのミスは放っておいて直るのでしょうか。また、優秀な生徒様は何故ケアレスミスが少ないのでしょうか。
まず、計算間違いからお話ししましょう。計算間違いをなくすためには、まず(2)でお話したように、ゆっくり、正確な計算から始めてください。そして、頭で計算(暗算)せずに、筆算をしっかりしましょう。また、計算の都度、確認をすると良いと思います。
次に、見間違い・勘違いについてです。文章の数字や人物には丸をつけるなど、目立つようにしましょう。また、何を答えるべきなのか、設問で聞かれていることにも印をつけます。答えを出したら、もう一度問題文を確認し、生徒様自身の解答も、もう一度確認です。
このように、徹底することで、今までのミスが格段に減ると思われます。保護者様も、生徒様の横でチェックして頂けると良いかと思います。
4. 明治大学付属明治中学校を受ける際の併願パターン

①1月
|
埼玉栄中学校・大宮開成中学校・西武学園文理中学校・栄東中学校 |
1月は練習として、埼玉栄中学校・大宮開成中学校・西武学園文理中学校・栄東中学校が挙げられます。
この中でしっかりと合格を手にすることで、精神的に落ち着けると思われます。栄東中学校がやや高めですので、無理はせず、受験しない選択肢はあると思います。
②2月1日
|
午前:広尾学園中学校(1次)・中央大学附属中学校(1次)・法政大学中学校(1次) 午後:東京農業大学第一高等学校中等部(2次)・青稜中学校(1次) |
午前は、広尾学園中学校(1次)で勝負する手がありますが、元々附属校をお考えであれば、中央大学附属中学校(1次)や法政大学中学校(1次)が良いと思われます。
午後は、東京農業大学第一高等学校中等部(2次)、もしくは抑え校として青稜中学校(1次)が良いでしょう。
③2月2日
|
午前:明治大学付属明治中学校(1次) 午後:東京農業大学第一高等学校中等部(3次)・青稜中学校(2次) |
午前は、明治大学付属明治中学校(1次)で決まりです。午後は、東京農業大学第一高等学校中等部(3次)・青稜中学校(2次)が候補に挙がって来るでしょう。
1日に午前・午後どちらも受験されると思いますから、2日は疲れも考慮して、午前・午後どちらかの受験が良いでしょう。状況に応じて、上記の3校の中からお考え頂ければと思います。
④2月3日
|
午前:明治大学付属明治中学校(2次) |
午前は、明治大学付属明治中学校(2次)で決まりです。午後は、広尾学園小石川中学校(3次)や法政大学中学校(2次)が候補に挙がります。
午前・午後どちらも受験されるかどうかは生徒様の状況に応じてご判断ください。
⑤2月4日
|
中央大学付属中学校(2次)・成蹊中学校(2次) |
4日は、中央大学付属中学校(2次)が良いでしょう。もしくは抑え校として、成蹊中学校(2次)もよろしいかと思います。
5.明治大学付属明治中学校の受験対策をはじめよう!
明治大学付属明治中学校の入試問題は、算数で最も差がつく傾向にあります。算数の問題は標準的な問題ではありますが、文章が長く、複雑な設定もあり、本格的な問題です。
単元としては、速さ・数の問題・ニュートン算・割合・図形が頻出ですから、これらの単元を中心に少し難しめの問題まで対策すると良いでしょう。国語は読書をして速読・精読のレベルを上げつつ、記述問題に対応できるように、要約練習を心掛けてください。
【参考文献】
・明治大学付属明治中学校
・明治大学付属明治中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・広尾学園小石川中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
・明治大学付属中野中学校2025年度版10年間過去問声の教育社
他の学校の入試傾向・受験対策
中学受験対策をご検討なら
東大家庭教師友の会をもっと知る
お問合せ・体験授業はこちら