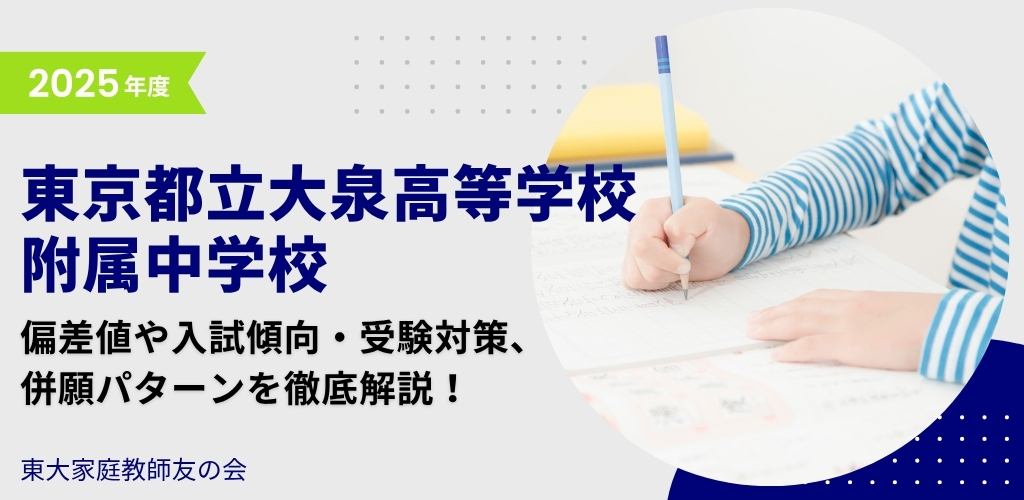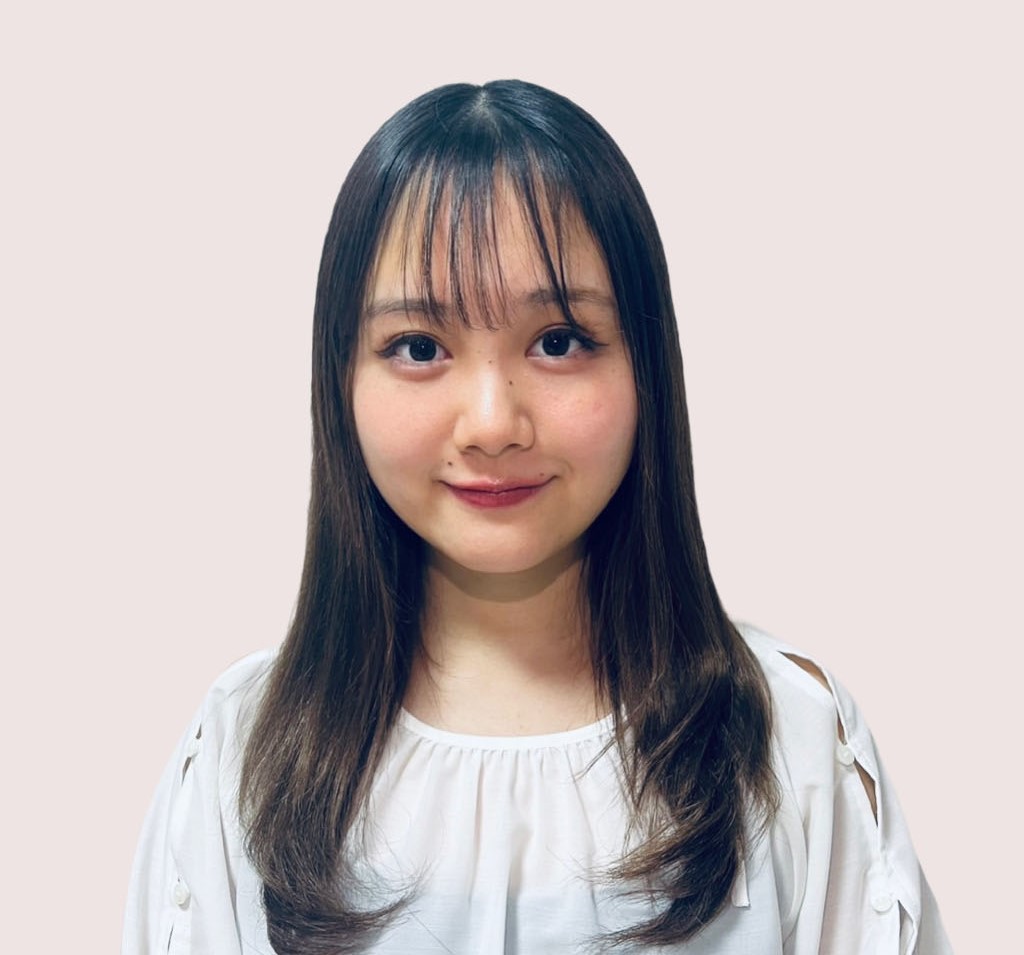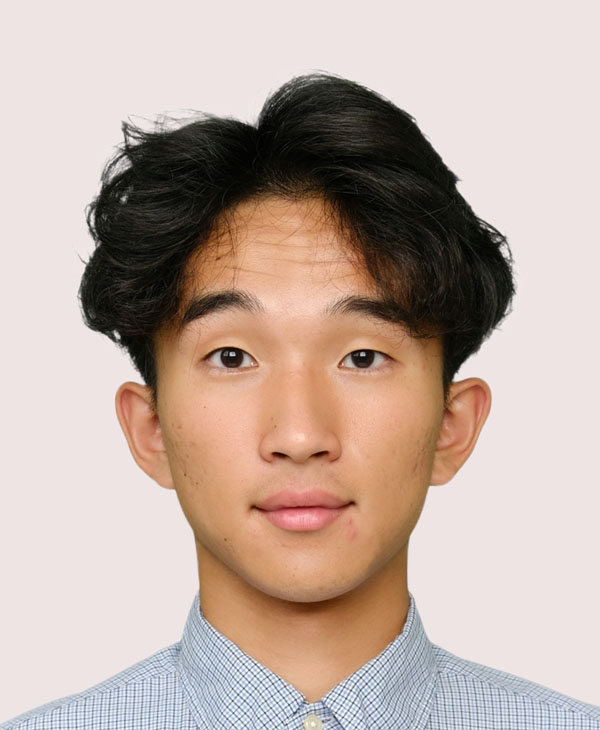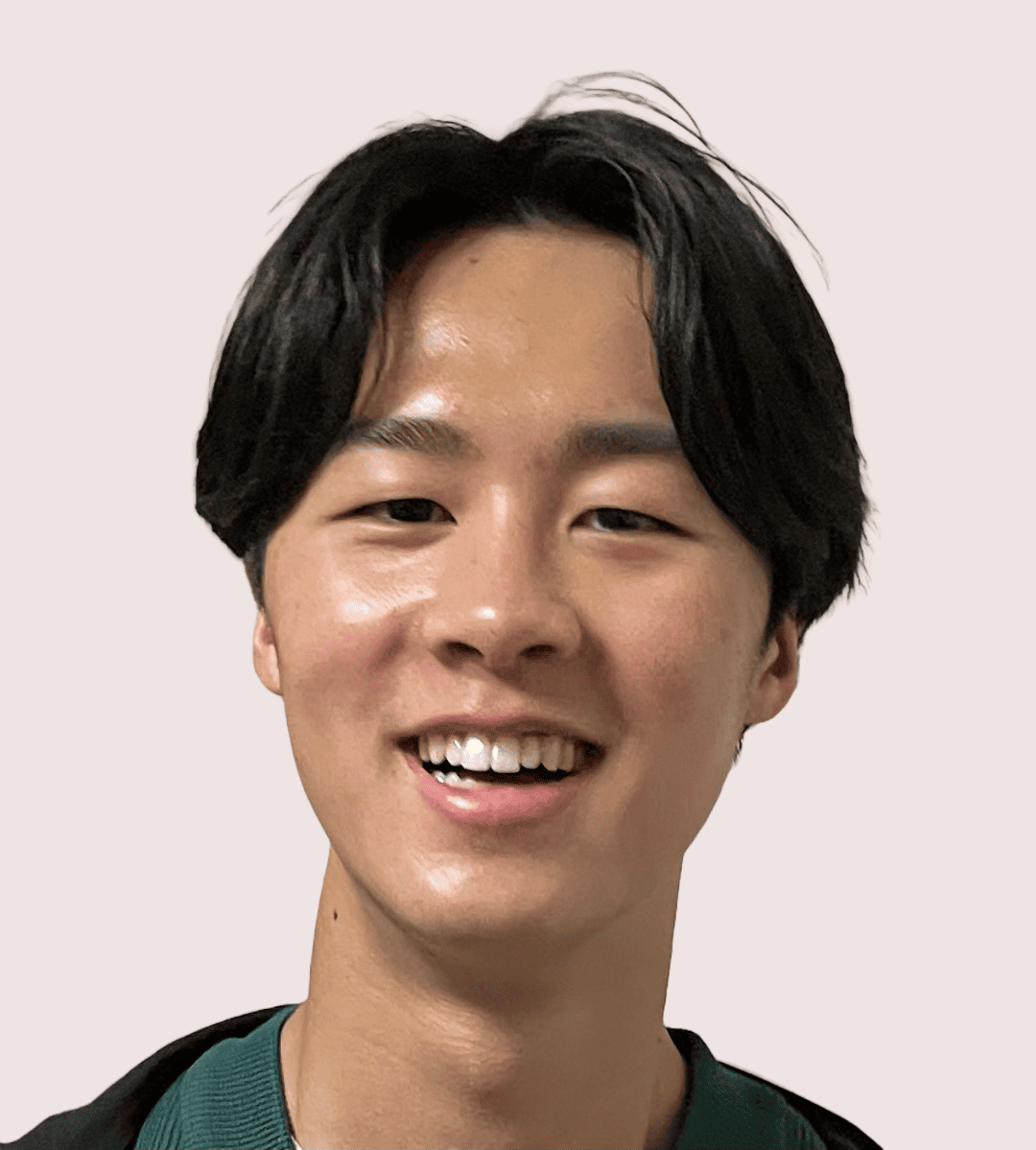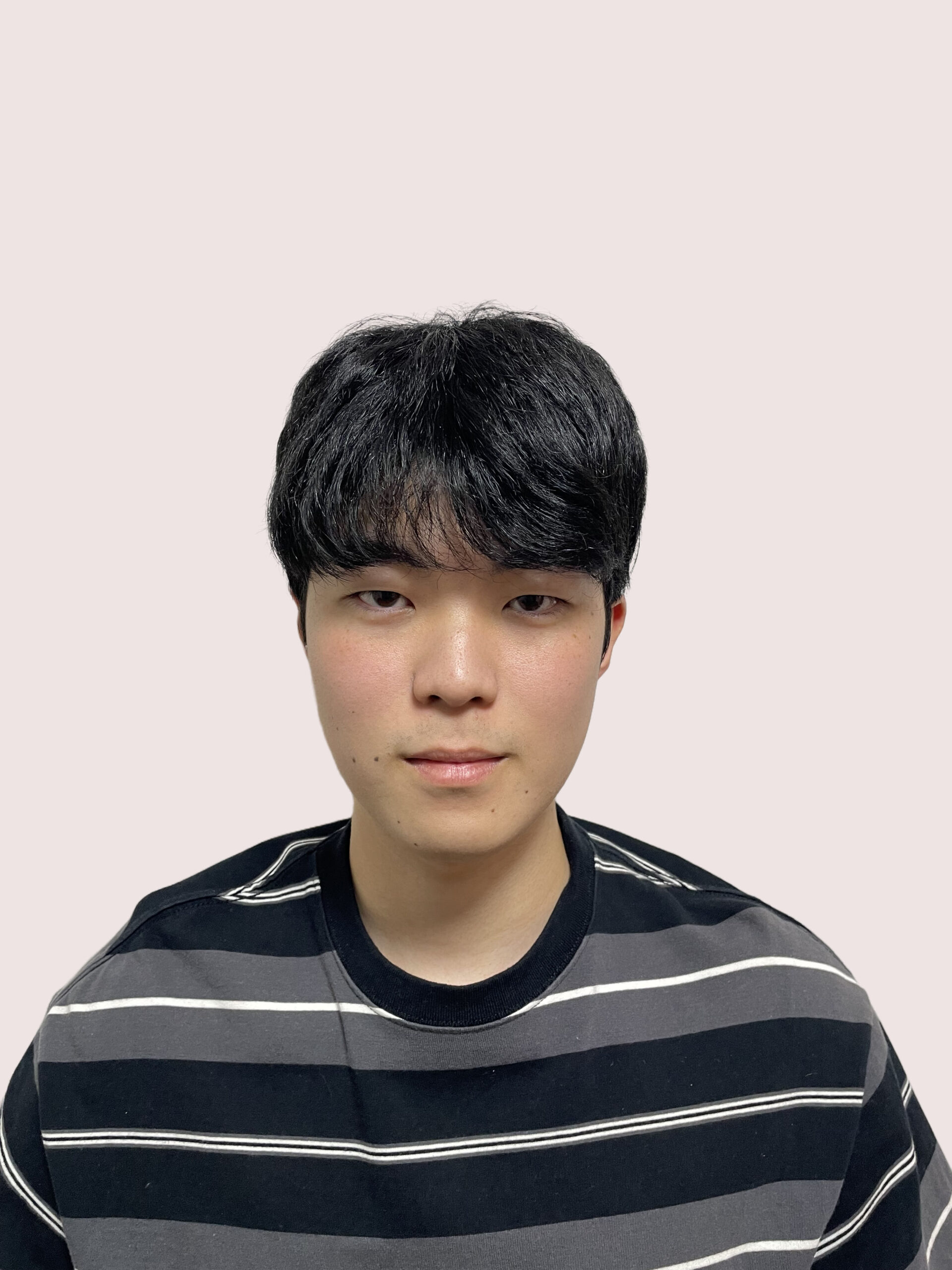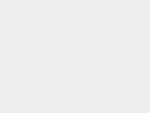![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 東京都立大泉高等学校附属中学校の偏差値と基本情報

東京都立大泉高等学校附属中学校の偏差値と基本情報について紹介します。
①東京都立大泉高等学校附属中学校の偏差値
東京都立大泉高等学校附属中学校の偏差値を、「四谷大塚ドットコム」「首都圏模試センター」「SAPIX」の最新データに基づいて、以下の表にまとめました。
| 入試日程 | 四谷大塚 (Aライン80偏差値) |
首都圏模試センター (合格率80%偏差値) |
|
2/3 |
男子 61 |
男子 67 |
②東京都立大泉高等学校附属中学校の基本情報
| 項目 | 内容 |
|
設立年 |
2009年 |
|
所在地 |
東京都練馬区東大泉5‑3‑1 |
|
アクセス |
西武池袋線「大泉学園駅」南口より徒歩約10分 |
| 校種 | 公立男女共学校(中高一貫) |
| コース | 普通科 |
| 特徴的な教育 | ・少人数授業(英・数)、JET/ALTによる実践英語、オンライン英会話 ・放課後TIRで教員・大学生による個別学習支援 ・長期休業中は100講座規模の補講・探究講座が開講 |
大泉高校・附属中学校は、東京23区内の都立高校の中でも有数の敷地面積を誇ります。正門から100メートル以上続く桜並木は、桜の時期には圧巻です。「教育課程の基準の特例」を活用し、独自の教育課程を編成している点も特徴です。
ここでは、大泉高校・附属中学校が特に力を入れている「探究教育」「独自の学習指導」「行事・部活動」の3つをご紹介します。
(1)「探究の大泉」でWellbeingを実現するための力を培う
「QC(Quest&Creativity):探究と創造」という活動では、答えのない社会で、自己と他者、社会全体の幸せを実現する力を養います。
中学1年生では「練馬地域探究」で探究の基礎・基本を学び、2,3年生では個人やグループでプロジェクトを立ち上げ、様々な社会課題について考えます。高校生では自らの興味関心に基づき、問いを立てて探究活動を行います。この探究活動が進路選択のきっかけとなる生徒も多いようです。
(2)自校完結型の学習指導
通塾しなくても希望進路を実現できるように工夫されており、中学校の全クラスで、英語と数学の授業は1クラスを2つに分け少人数で授業を行っています。また放課後には「ティーチャー・イン・レディネス(TIR)」で、教員や大学生のチューターが常時待機し、自学自習をサポートしています。
長期休業中にも様々な講座が用意されており、その数は年間を通して100近くにもなります。多くの生徒が、自分の進路希望や学力に合った講座を選択し受講しています。
(3)青春を謳歌できる行事・部活動
勉強だけではなく、行事や部活動にも全力投球できるのが大泉高校・附属中学校の生徒たち。
体育祭・文化祭・合唱コンクールの三大行事をはじめ多くの行事を通して、リーダーシップや協働して課題を解決する力を見に付けます。
一方部活動は、中高合わせて30もの部活動があり、多くの生徒が部活動と学習の両立を実現させています。広大な敷地と充実した施設を活用し、のびのびと活動する中で、生涯にわたる思い出と人間関係を作ります。
2. 東京都立大泉高等学校附属中学校の入試傾向

大泉高校附属中学校の入試は一般枠募集のみです。ここでは、気になる倍率などの入試概要や報告書の換算方法、2024年度入試の適性検査で特徴的だった問題や合否を分けた問題について解説します。
①入試の概要
2025年度入試の募集人数は160名です。2024年度入試の倍率は男子が3.53倍、女子が4.55倍と、例年女子のほうが倍率が高くなっています。
入学者は、小学校の成績である報告書の得点と(540点満点を300点に換算)、2月3日に行われる適性検査(Ⅰ・Ⅱは都立中高一貫校の共通作成問題を使用し、各45分100点満点を200点満点に換算、Ⅲは理数分野を中心とした独自作成問題で、100点満点を300点満点に換算)の総合得点(1000点満点)で決まります。
②報告書の換算方法
「報告書」は、5・6年生の「各教科の学習の記録」について、すべての教科の評定を
|
評定3…30点 |
として得点化し、その満点である540点を300点満点に換算します。
報告書は総合成績の30%を占め、都立中高一貫校の中でもその比率は高いと言えます。
③適性検査Ⅰ
共通作成問題が利用される適性検査Ⅰでは、文章の内容を的確に読み取ったり、自分の考えを論理的かつ的確に表現したりする力が試されます。
ここでは、適性検査Ⅰの得点の6割を占める〔問題3〕の作文についてお伝えします。2つの課題文の内容に触れながら、これから学校生活で仲間と過ごしていく上で言葉をどのように使っていきたいか、自分の考えを400字~440字で書きます。
まずは、課題文1と2のどちらの考え方を踏まえて書くのかを決める必要があります。課題文1は、短歌を繰り返し心の中でつぶやくことで自分の気持ちを保つことができるという内容で、文章2は人々の気持ちを想像して勉強していくうちに、すばらしい俳句が生まれるという内容でした。どちらを選んだかは得点に関係しないので、自分が意見や理由を書きやすかったり、具体的な内容と結びつけやすいほうの文章を選んで書きましょう。
段落の構成についての指定はありませんでしたが、文字数から考えても、
|
<段落1> |
という構成が最も書きやすいでしょう。問題に「これから学校生活で仲間と過ごしていく中で」とあるので、部活動や学校行事などの具体的な場面を想定して書けるかが重要です。
作文の問題では例年、テーマに関連して、自分の経験や考えを具体的に示すことが求められます。日頃から身近なできごとや話題について自分の考えを持ち、文章として書く練習をしましょう。良い作文を書くためには、豊富な語彙力と、それを正しく運用する力が必要です。使いこなせる言葉の量を増やせるように、日頃から活字に親しむ姿勢は大切にしましょう。
➃適性検査Ⅱ
適性検査Ⅱは、資料から情報を読み取り、課題に対して思考力や判断力、論理的に考察したり処理したりする力を試します。
大問1はマグネットシートを使って得点板の数字を作成することをテーマにした、条件を整理しながら解く問題でした。
大問2は公共交通機関の利用について、複数の資料から情報を読み取り、文章での説明を要する問題、大問3は摩擦について調べる実験から物体の性質を考える問題でした。
ここでは、最も配点が高く設定されている大問1についてお話します。
|
〔問題1〕 |
|
〔問題2〕
・マグネットをつける作業
の組み合わせて行います。 |
〔問題1〕〔問題2〕のどちらも、やみくもに手をつけるのではなく、どう作業を組み合わせるのがよいのか、ある程度の目星をつけてから解き進められるとよいでしょう。予測を立てるためには、条件を的確に読み取ることが重要です。
⑤適性検査Ⅲ
総合得点の30%を占める適性検査Ⅲは、理数分野から出題され、論理的思考力と空間把握能力が問われるような問題が頻出です。2024年度は、大問1が光電池をテーマにした理科の実験に関する問題、大問2はトイレットペーパーを題材に、その巻き数と体積について考える問題が出題されています。
ここでは、2024年度の「合否を分けた一問」と言えるであろう、大問1について解説をします。
|
〔問題1〕
近年、単位量あたりの数や量を求める問題は頻出です。過去問などでしっかり対策してきた受験生にとっては、迷いなく解けた問題と言えたでしょう。
1コマ進むごとにプロペラは8度回転することから、1秒間では8×960=7680度進むことになります。したがって、1秒間にプロペラが回転する回数は、7680÷360=21.3より、21回であることが分かります。 |
|
〔問題2〕
実験2と実験3の結果から、太陽光が全く当たらない「発電する板」が1枚でもあるとプロペラは回転しないこと、2つの接続点の間にある、全ての「発電する板」の面の半分に太陽光が当たっていれば、プロペラは回転することが分かります。
したがって、①④⑤に紙が置かれていても、それぞれの発電する板の半分には太陽光が当たっているので、プロペラは回転することが分かります。プロペラが回転する条件を丁寧に洗い出し、順序立てて説明できるかが求められる問題でした。 |
|
〔問題3〕
紙2枚の上に、重さ0.34gの円形の紙を載せたときに、上が浮かなくなる電流の大きさを求めます。
以上より□=5.03mAと求められ、小数第一位を四捨五入すると、5mAとなります。 |
比の関係を利用して解くことが分かれば、難なく解けた問題ではありますが、理科の要素に加えて数学的な思考力も求められる問題であり、まさに「適性検査」らしい問題と言えます。
この問題が、2024年度の適性検査において、合否を左右した一問だと言えるのではないでしょうか。
⑥解いておきたい!出題形式の似ている学校は?
適性検査・思考力型の入試問題を行っている学校が挙げられます。都立中高一貫校の中でも理数教育に力を入れている、武蔵高校附属中学校や小石川中等教育学校、富士高校附属中学校の独自作成問題は参考になるでしょう。
私立中学校では、城西大学附属城西中学校の適性検査型入試が、大泉高校附属中学校の問題を参考に作られているため、演習の際に必見です。
3. 東京都立大泉高等学校附属中学校の受験対策

ここでは、大泉高校附属中学校の合格に向けて、具体的な受験対策として、いつ・どのようなことに取り組めばよいのか、過去問はいつから解くのがよいのか、家庭で保護者様ができるサポートにはどのようなものがあるかなどをご紹介します。
①【時期・教科別】受験対策方法紹介!
(1)小学4年生
4年生では、まず学習習慣を定着させ、都立中高一貫校の入試に必要な思考力・分析力・表現力の土台として4教科の学習にしっかり取り組むことが大切です。
|
【算数】 【国語】 【理科・社会】 |
(2)小学5年生
都立中高一貫校の受験に必要な報告書の対象は5年生からです。特に大泉高校附属中学校は、総合得点に占める報告書の割合が30%と高く、すべての科目で学校での学習活動にも十分に取り組む必要があります。
|
【算数】 【国語】 【理科・社会】 |
(3)小学6年生(4月~6月)
いよいよ勝負の6年生。富士高校附属中学校の出題形式に焦点を当てて準備を始めましょう。
|
【算数】 【国語】 【理科】 【社会】 |
(4)小学6年生(7月~8月)
特に夏休み中は生活リズムを整え、目標を持って計画的に学習を進めましょう。
|
【算数】 【国語】 【理科・社会】 |
(5)小学6年生(9月~11月)
実はスランプに陥ってしまう生徒様も多い秋。モチベーションを保てるような工夫が必要ですが、いよいよ過去問に挑戦し始めるのに適した時期でもあります。過去問の活用方法については、このあと詳しくお伝えしていますので、そちらも合わせてお読みくださいね。
新しい知識のインプットよりも、演習のほうが多くなるこの時期、問題を解いた後は丸付けをするだけではなく、その問題の注目すべきポイントや別解にも目を通すなど、自分の答案と解答・解説を見比べてみましょう。自分の弱点を発見したり、新たな引き出しを手に入れたりすることができるかもしれません。気付いたことはどんどんメモをしながら学習を進めてください。
(6)小学6年生(12月~1月)
受験直前期には、過去問やこれまでに受けた模試の問題、併願校の過去問なども活用しながら、いままでやったことの抜け漏れがないかどうか確認しつつ、問題演習に取り組みましょう。
本番を意識して、本番と同じスケジュールで問題を解いてみるのがおすすめです。
②東京都立大泉高等学校附属中学校の過去問対策
(1)過去問の効果的な使い方は?
過去問を解く目的は2つあります。1つ目は、問題の出題形式を知り、傾向を掴むためです。もう1つは時間の感覚を掴むためです。適性検査は思考力・判断力・表現力・分析力が試されるだけではなく、時間との戦いでもあります。
限られた時間の中でどの問題を優先し、どの問題を後回しにするのかを判断する力はもちろん、試験時間の始めから終わりまで集中力を切らさないようにする訓練も必要です。実際に過去問を解く際には、試験時間を守るだけではなく、本番と同じスケジュールで解いてみることをお勧めします。
(2)過去問はいつから解き始めればいい?
入学検査範囲の学習が一通り終わり、間違えた問題の復習に取り組むための時間的・精神的な余裕のある6年生の秋(9月から11月)ごろから過去問に取り組むことをお勧めします。
それ以降の期間は、過去問を解いて間違えた問題にもう一回挑戦したり、他校の過去問から似たようなタイプの問題を解き、実践力を鍛えていきましょう。
(3)何年分を何周解けばいい?
第一志望でしたら5年分程度、併願校として受験する場合や併願校の過去問も、2・3年分は解いてみましょう。特に、大泉高校附属中学校の独自作成問題は、独自作成が始まって以降の問題をできるだけすべて解くことをお勧めします。
過去問は、一度できた問題を何度も繰り返し解く必要ありません。もうすでに解ける問題を何度も繰り返し解くよりも、今できていないものを1つでも多くできるようにすることのほうが、効率よく合格に近付けると考えるからです。できなかった問題の復習には徹底的に時間をかけ、何度でも挑戦しましょう。
③ご家庭で実践!保護者様にできるサポートとは?
(1)「なぜ?」をとことん大切にする
探究活動を大切にしている大泉高校・附属中学校。生徒様が持つ身近な物事に対する「なぜ?」という疑問をしっかり受け止め、真摯に向き合うようにしましょう。
保護者様も一緒に調べるなどして疑問を解決できたり、新たな発見ができると生徒様の自己肯定感を高めることにもつながりますし、入学後の学校での様々な探究活動や、課題に対して根気強く向き合う姿勢にもいい影響をもたらしてくれるはずです。
(2)学校の学習にも取りこぼしなく取り組ませる
大泉高校附属中学校への合格に向けては、報告書の内申点を高く保つことも大切です。適性検査の対策ももちろん大切ですが、学校の活動、特に国語算数理科社会以外の科目も、取りこぼしなくできているか、定期的に確認するようにしましょう。
介入のしすぎは生徒様にとってもよくありませんが、ほどよい距離感で生徒様を後押ししてあげられるとよいですね。
(3)生徒様ご本人の成長に着目して、前向きな声掛けをする
生徒様と向き合っていると、つい保護者様やご兄弟、他の生徒様と比較してしまいたくなってしまいますよね。ですが、生徒様一人ひとり、学習に集中できる環境や得意・不得意、やる気に火が着くタイミングは異なります。
他の人と比べたくなったり、口出ししたくなる気持ちを堪えて、生徒様ご本人の変化に目を向けるようにしましょう。そのことが多感な時期の生徒様の自尊心を守ることにもつながります。
模試の結果一つをとっても、保護者様の声掛け一つで生徒様の受け止め方も変わってきます。生徒様が少しでも前向きな気持ちで自分から学習に向き合えるような声掛けを心がけましょう。
受験期の親子関係は、その後も大きく影響する場合が多いです。中学受験が、親子の絆を強める一つのきっかけになるとよいですね。
とはいえ、受験期は不安や悩みが尽きない時期でもあります。
受験に詳しい家庭教師に頼ることで、保護者様の不安が軽減され、生徒様の学習もよりスムーズに進むはずです。
ご家庭だけで抱え込まず、必要に応じて家庭教師のサポートを検討してみましょう。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 東京都立大泉高等学校附属中学校を受ける際の併願パターン

ここでは、ライターが過去に出会った生徒様の併願校を参考に、大泉高校附属中学校を受験する生徒様におすすめの私立中学校をご紹介します。
大泉高校附属中学校を受験する生徒様は、1月入試は千葉県よりも埼玉県の学校への出願が目立ちます。最も多い併願校が西武学園文理中学校で、2科・4科型の入試はもちろん、適性検査型の入試も行っていることがその要因でしょう。
2月1日以降の入試では、宝仙学園中学校と併願する生徒様が多いことが特徴です。偏差値や探究的な学習、入試のタイプなど、多くの点で大泉高校附属中学校との親和性が高いことが理由として挙げられそうです。
併願プランを考える上では、大泉高校附属中学校に近い偏差値の学校を併願するパターンと、適性検査に近い形の出題形式の入試を行っている学校を併願するパターンの、大きく二つに分けられます。
①偏差値帯を重視した併願パターン
大泉高校附属中学校と、比較的偏差値帯の近い私立中学校を併願するパターンです。学習に対するサポートや、大学への進学実績などを重視した学校選びを行うご家庭におすすめの併願先です。
(1)1月入試
|
・立教新座中学校 |
(2)2月1日
|
・宝仙学園中学校 |
(3)2月2日
|
・明治大学附属中野中学校 |
(4)2月4日以降
|
・光塩中学校 |
②適性検査・思考力型入試を重視した併願パターン
適性検査型の入試を行っている中学校の中で、特に併願校としておすすめしたいのが城西大学附属城西中学校。適性検査Ⅰ・Ⅱは、都立中高一貫校の共通作成問題に、適性検査Ⅲは、大泉高校附属中学校の問題に準拠しているため、2月3日の本番に向けた最終確認や演習に適していると言えるでしょう。
(1)1月入試
|
・立教新座中学校 |
(2)2月1日
|
・宝仙学園中学校 |
(3)2月2日
|
・城西大学附属城西中学校 |
(4)2月4日以降
|
・跡見学園中学校 |
【参考文献】
・都立大泉高等学校・附属中学校学校ホームページ
・声の教育社「東京都立大泉高等学校附属中学校2025年度用スーパー過去問」
5.東京都立大泉高等学校附属中学校の受験対策をはじめよう!
東京都立大泉高等学校附属中学校の入試では、都立中共通問題である適性検査Ⅰ・Ⅱに加え、独自作成の適性検査Ⅲが課されます。理数分野の配点が高く、限られた時間の中で情報を分析・考察する力が求められるため、傾向をしっかり把握し、早めに対策を始めることが大切です。
「苦手な単元があって不安」「家庭だけでは対策が難しい」――そんなときは、家庭教師のサポートを活用してみるのもおすすめです。
ご相談からでもOK!お気軽にお問い合わせください。
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
家庭教師が大泉高校附属中学校合格へのサポートをいたします