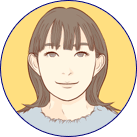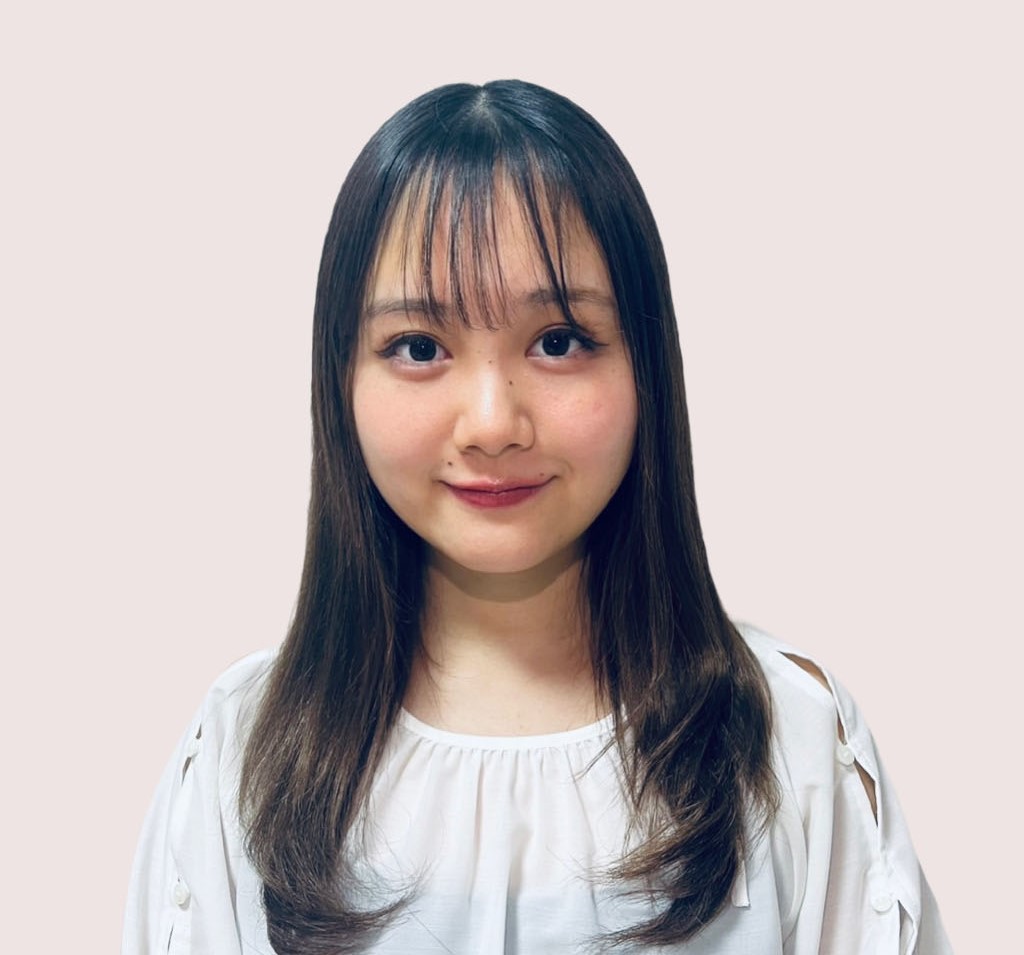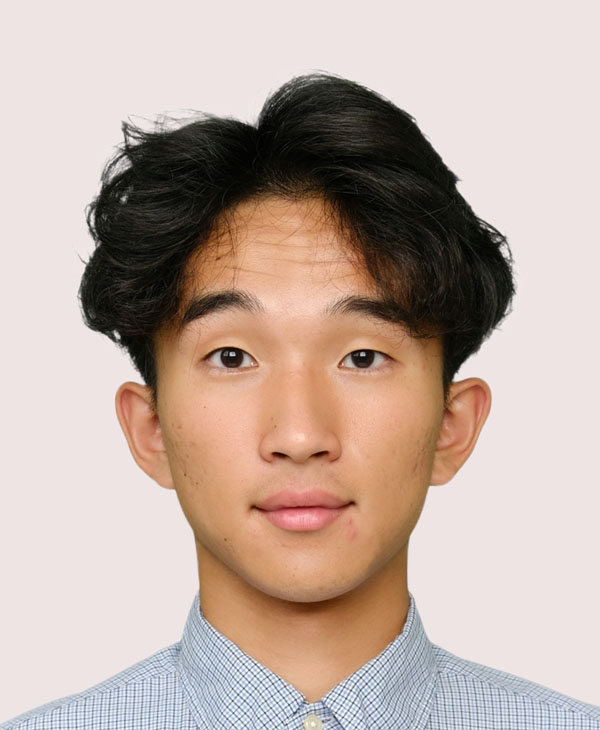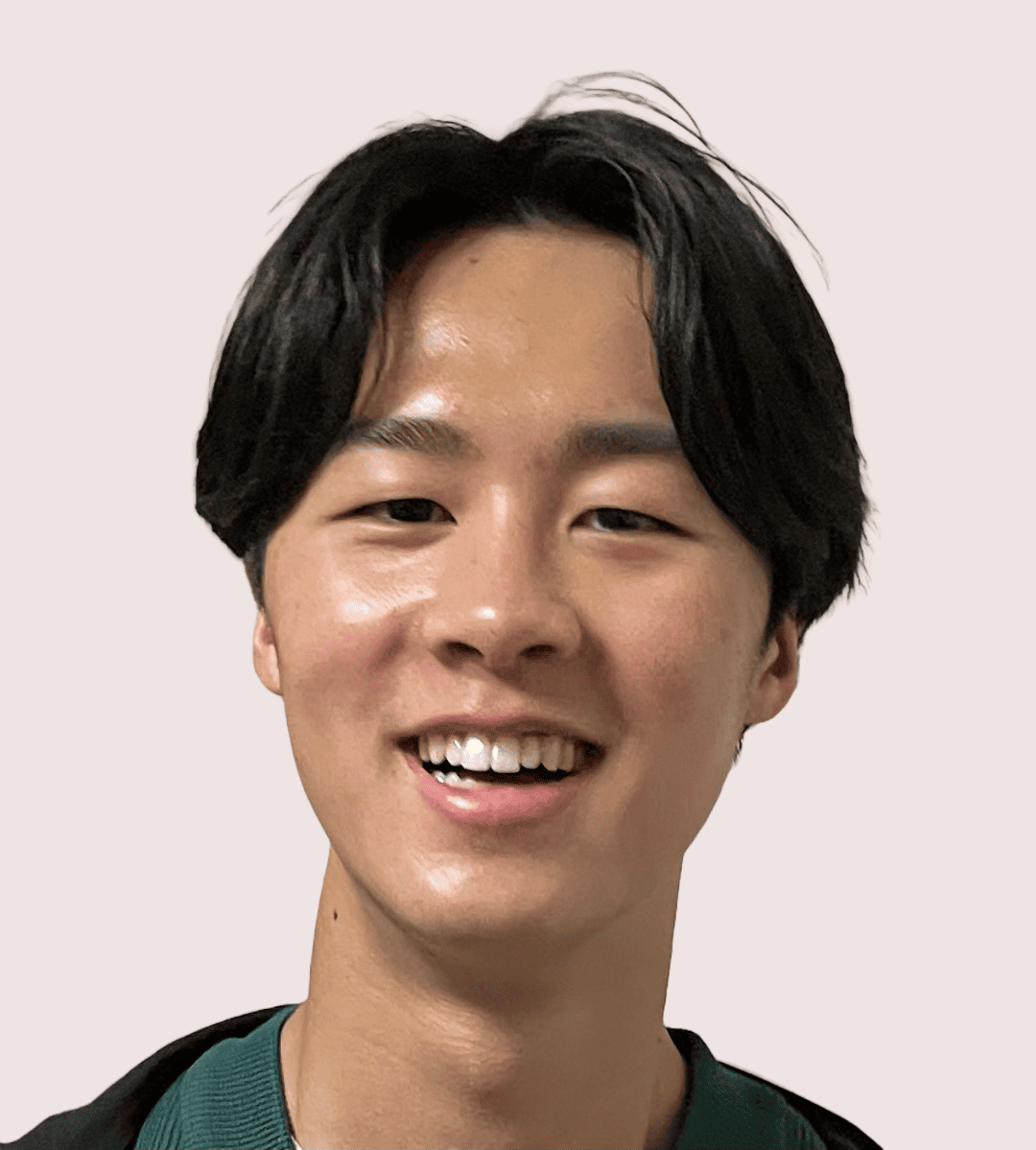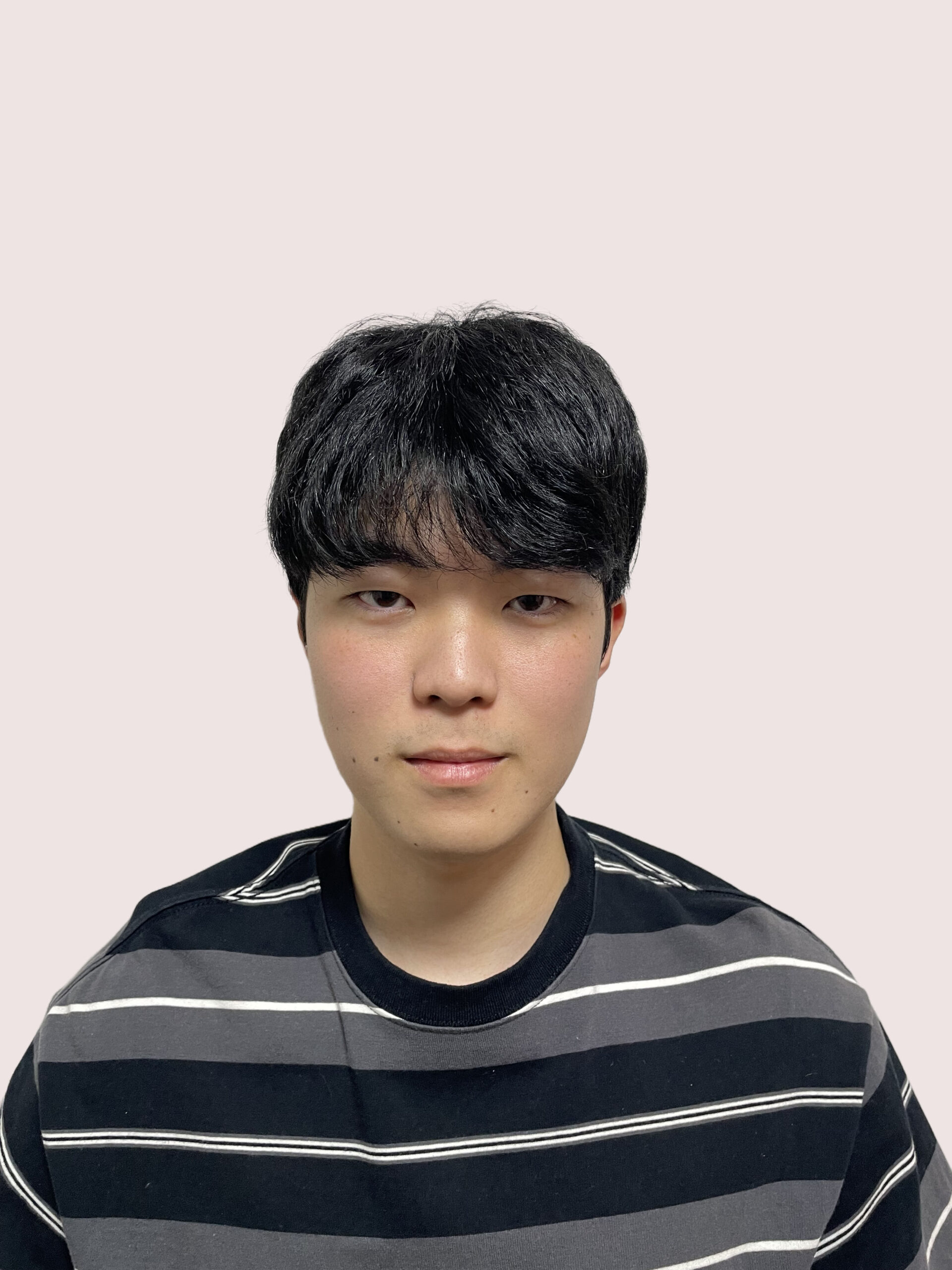![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 過去問を解く目的と活用法

中学受験において、過去問演習は単なる仕上げではなく、合格に向けた重要なステップです。
出題傾向や形式に慣れることで、本番で実力を発揮しやすくなります。
まずは、過去問を解く目的と効果的な活用法を4つのポイントで解説します。
①志望校の出題傾向を把握する
中学受験では、学校ごとに試験問題の内容が大きく異なります。
学校によって求める生徒像に差があるためです。
過去問を見て選択式の問題と記述式の問題どちらが多いのか、出題されやすいのはどの単元か、分析しておくと本番であわてずに解答できます。
傾向がわかれば、日々の学習の優先順位を見直すことができます。たとえば、塾の授業で志望校と似た形式の問題が出たときにより集中できますし、過去問でよく出るけれど苦手な単元があれば、早めに対策を始めるきっかけにもなります。
②過去問から入試傾向を分析する方法
過去問から入試傾向を分析する簡単な方法は、解答用紙の記入欄を確認することです。
分析のポイントは以下の通りです。
【解答形式のチェック】
記述問題がどれくらい出るか、一問一答が多いかを確認しましょう。形式の違いによって、復習内容が変わります。
【算数の答え方】
解答欄に単位の指定があるかどうかを確認しておくと、頻出の単元を把握できるでしょう。
【形式の変化】
毎年出題形式が変わっていないかどうかを見ることで 難易度の安定性を把握できます。安定していれば対策が立てやすくなります。
【配点の把握】
配点が低い問題で解答形式が変わった問題は、無理に正解を狙うよりも、配点の高い問題に時間をかけた方が得策なこともあります。
こうした情報を整理しておくことで、過去問を「ただの演習」ではなく「合格のための戦略材料」として活用できます。
③入試問題の難易度と相性を確認する
過去問を見て出題傾向をつかんだら、次は生徒様にとって入試問題がどのくらい難しいか確認しましょう。
志望校の偏差値と生徒様の偏差値が近くても、過去問と相性が良くない場合は早めに対策を練る必要があります。
過去問を解き始めた頃は点数を取れないかもしれませんが、過去問演習を繰り返すことで少しずつ改善できます。
もし、志望校や併願校で悩んでいたら、過去問との相性を判断材料に加えましょう。
生徒様の得意分野が出題される学校を受験した方がモチベーションを維持できますよ。
④時間配分を確認する
学校によって、科目ごとの試験問題の数や量に差があります。
大問にかかる時間が長い学校もあれば、1問ずつはすぐに解けるけれど問題数が多い学校もあります。
時間配分を間違えると得点が伸びないため、過去問演習でペースをつかんでおく必要があるのです。
2. 過去問演習のスケジュールの立て方

過去問演習は計画を立てて進めることで本番に向けて効率よく力を伸ばすことができます。
ここでは、取り組む時期・順番・年数・時間配分の考え方を詳しく解説します。
①過去問はいつから解き始めればよいか
中学受験の過去問は小学6年生の9月から解き始めると良いです。夏までに基礎を固めたうえで、秋以降に過去問を活用して実戦力を高めていきましょう。
詳細は以下ページをご覧ください。
▼過去問を解く時期の詳細については、以下ページをご覧ください
②過去問は何年分を何周するべきか
学校のレベル(偏差値)に応じて、解く年数と回数を調整しましょう。
・【第1志望校】5~10年分を1~2周
・【チャレンジ校】5年分をできれば2周
・【実力相応校】3〜5年分を1~2周
・【安全校】1~2年分を1周
・【腕試し校】1年分を1周
(1)第1志望校
第1志望校は出題傾向をしっかり把握し確実に解答できるよう、最低でも5年分は解きましょう。
小学6年生の9月より前に過去問に着手できる場合は、第1志望校を5年から10年に増やしても良いです。
(2)チャレンジ校
チャレンジ校の問題は難易度が高いため、1周目はなかなか点数が取れません。
必ず2周解いて出題傾向と時間配分を生徒様がつかめるようにしましょう。
2周目を全問解答する時間が足りなければ、1周目に間違えた問題だけでも良いので、もう一度問題を解くようにしてください。
(3)実力相応校
実力相応校は、3〜5年分を最低1周すれば傾向と対策を練れるでしょう。
今までの受験勉強の成果を発揮できればそこまで苦戦しないはずです。
(4)安全校・腕試し校
安全校、腕試し校は基本的な出題傾向を把握できれば良いので、1~2年分を解けば十分です。
ただし油断は禁物なので、解けなかった問題は忘れずに復習しましょう。
なお、科目により過去問をさかのぼる年数に差があっても構いません。
出題傾向が変化しにくい算数・国語は10年分を解いても良いですが、時事問題が古くなる理科・社会は5年分まで解けば十分です。
③解く年度の順番はどうするべきか
中学受験の過去問は新しい年度から解いていきます。
古い年度から解いてしまうと、最新年度の過去問を解けずに受験本番を迎えてしまうリスクがあるためです。
最近の出題傾向を早い段階でつかむことで、対策の方向性を見定めやすくなります。
繰り返し解く中で頻出単元も見えてくるので、苦手であれば重点的に復習し、得点源に変えていきましょう。
④解く学校の順番はどうするべきか
解くべき学校の順番は、以下の流れが効果的です。
1.第1志望校(5年分)
2.チャレンジ校(5年分)
3.実力相応校(3〜5年分)
4.安全校(1〜2年分)
5.腕試し校(1年分)
難易度の高い第1志望校やチャレンジ校から着手することで、幅広い学力を身に付けられます。
勉強不足の単元がみつかったら早めに対策ができます。
各学校を1年分ずつ解くと生徒様が混乱するため、第1志望校を3~5年分を解いてからチャレンジ校に進むのがおすすめです。
腕試し校の過去問を解いた後、時間に余裕があれば第1志望校の2周目に入るとより効果的です。
第1志望校の過去問と生徒様の相性が悪い場合は、志望校の見直しが必要です。
過去問が解けなくて不安な気持ちを抱えたまま演習を進めるのは生徒様にとっても負担が大きくなります。
何校か過去問を解いてみて手応えを感じた学校を第1志望校に変更しても良いでしょう。
志望校の中で出題傾向が似ている学校があれば、一緒に対策を練れるので効率良く点数アップを狙えますよ。
⑤1週間のうち、過去問演習にかける時間の目安は?
過去問演習にかける時間は、1週間だと1年度分が適切となります。
1科目の過去問を解く際の目安時間は、問題を解くのに60分、採点に30分、解き直しに60分となり、合計の所要時間は約2.5時間です。
過去問を1日1科目のペースで進めると、4科目で4日間かかります。
1週間でこなせるのは1~2年度分が限界となるのです。
小学6年生の9月から1月の腕試し校の受験本番まで18週間程度あります。
過去問演習を土日と平日どちらに行うのか親子で話し合っておきましょう。
3. 過去問演習を始める前に親が準備しておくべきこと5選

過去問演習をスムーズに進めるためには、事前準備がとても重要です。
環境を整え、必要なアイテムをそろえることで、集中力や学習効果が大きく変わります。
ここでは、演習前に保護者がやっておきたい準備を5つにまとめて解説します。
①過去問を購入し、問題と解答用紙を実寸大でコピーする
受験する可能性がある学校の過去問は全て購入しておきましょう。
学校説明会・入試説明会で過去問を配布・販売していることもあるので、情報をチェックしておくのがおすすめです。
過去問を購入したら、問題用紙と解答用紙を実寸大でコピーして、試験本番をイメージできるようにしてください。
解答用紙のサイズや記述欄の大きさに慣れておく必要があるためです。
②過去問は保護者様が管理し、答えの冊子は隠しておく
残念なことに、受験のプレッシャーで過去問の答えをカンニングしてしまう子どももいます。
過去問を購入したら、生徒様ではなく保護者様が管理しましょう。
答えのページは抜き取って問題の冊子と別々に保管し、生徒様が確認できない場所に隠しておくことをおすすめします。
保護者様がいない隙に過去問を先に解いてしまったり答えをカンニングしたりすると、実力以上の採点結果が出てしまいます。
採点結果が良すぎる場合は生徒様を疑うべきかもしれません。
③本番と近い状況で集中できる環境を整えておく
過去問は、できるだけ本番に近い環境で取り組むのが理想的です。
静かな空間、整った机、余計なものを置かないなど、集中しやすい環境を整えてあげましょう。
・テレビやスマホの音はOFF
・生徒様用の置き時計、保護者様用のタイマーを用意
・家族も協力して、演習中は静かに過ごす
など、「試験モード」に切り替えやすい状況づくりがポイントです。
④鉛筆・赤ペンなどの文房具、ごほうびアイテムも準備する
過去問演習及び丸付けで必要な文房具はあらかじめそろえておきましょう。
・鉛筆・消しゴム
・赤ペン
・ノート・ファイル類
また、演習後に生徒様のやる気を引き出すため、ごほうびアイテム(シールやスタンプ)を用意するのもおすすめです。「がんばったね!」と声をかけながらシールを貼るだけで、モチベーションがぐっと上がります。
⑤準備5:スケジュール帳に過去問以外の予定も全て記入する
過去問に取り組むスケジュールを親子で把握できるよう、カレンダーまたはスケジュール帳を用意してください。
・塾・模試の日程
・入試説明会や学校説明会
・小学校の行事
・家族の予定(旅行や通院など)
書き出してみると、思ったよりスケジュールが詰まっていることに気づけます。
その上で、「どこで過去問をやるか」親子で相談しながら無理のない計画を立てましょう。
とはいえ、仕事や家事、きょうだいの予定などで、なかなか過去問演習を見てあげられない…。そんなときは、中学受験に詳しい家庭教師のサポートを活用するのもおすすめです。限られた時間の中で効率よく対策を進めたいご家庭にもぴったりです。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 過去問を解く際に注意すること3点

過去問演習を効果的に進めるには、解く環境や順序に気をつけることが大切です。
ここでは、過去問を解くときに意識したい3つのポイントを解説します。
①本番に近い環境と時間配分で取り組む
受験本番の雰囲気に近付けるため、なるべく4科目連続で過去問を解きましょう。
科目の順番と開始時刻も本番と同様にします。
生徒様がどのくらい疲れるか自分で気付くことができます。
休憩時間の過ごし方も、予習復習をするのか、落ち着いて深呼吸してリラックスして待つのか、決めておけるといいですね。
制限時間内に解き終わらなかった箇所は、違う色のペンを使って最後まで解いてみましょう。
採点に含めるのは時間内に解いた問題だけですが、時間オーバーしてでも問題を解けたら自信につながります。
もし4科目連続で過去問を解く時間がなければ、平日に1科目ずつ解いても良いです。
ただし、第1志望校はなるべく4科目連続で解くことをおすすめします。
②難しい問題は後回しにしてOK
中学受験では、簡単な問題から順番に出題されるとは限りません。
大問2より大問3の方が簡単な問題なのに、大問2で時間がかかってしまい大問3以降の問題の点数が伸びない子どももいます。
難しい問題に出会ったら、一旦後回しにして次の問題に進むよう生徒様に教えてあげてください。
解けない問題を後回しにすることに罪悪感を感じる必要はありません。
遠回りしているように見えますが、解きやすい問題を見つけて解答用紙を埋めていくことで生徒様の自信につながり、合格への近道となるのです。
なお、国語の漢字問題は最初に解きましょう。
算数の計算問題も複雑でなければ最初に解くことをおすすめします。
③見直し用にマークを付けておく
すべて解き終わったら、必ず見直しをしましょう。
その際、自信の度合いによって印をつけておくと効率的です。
・自信がある問題:「〇」
・計算ミスが心配な問題:「△」
・解いたけど自信がない問題:「×」
・全然解けない問題:「?」
見直す際は「〇」「△」を優先的に確認しましょう。
5. 過去問を採点する際に気をつけるポイント3点
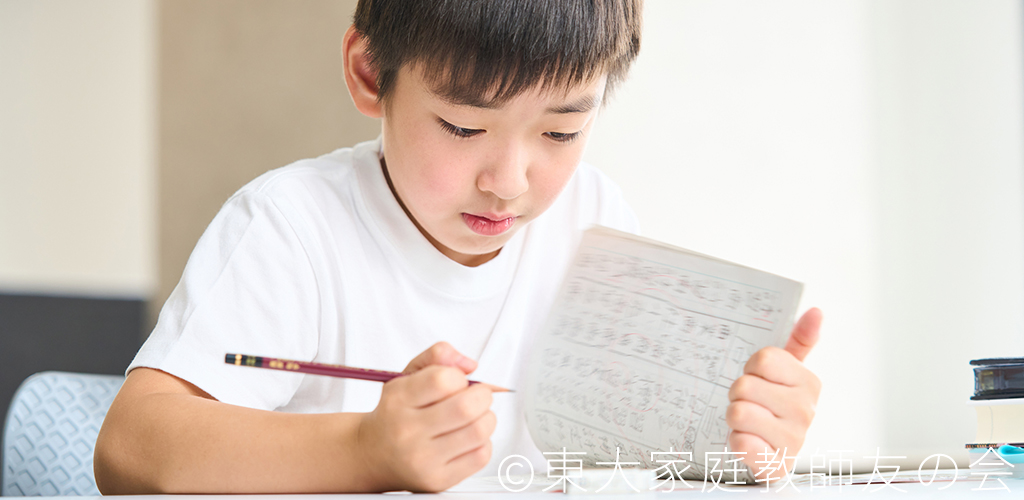
過去問の採点の際は、誰が丸付けを行うのか、ミスの種類をどうやって区別するのかがポイントとなります。
①採点は保護者様が行う
中学受験の過去問の採点は保護者様が行うことを推奨します。
生徒様が採点すると、部分点の判定を甘くしてしまう恐れがあるからです。
保護者様に採点されることで、生徒様が緊張感を持って過去問演習に取り組めるようになり、実力がつきやすくなります。
②科目ごとに見るべきポイントが異なる
教科ごとの採点のポイントは以下です。
・国語:漢字のとめ・はね・はらい
・算数:計算式の部分点、図形問題の理解度
・社会:都道府県などの漢字の正確さ
・理科:図や写真の理解度
保護者様が丸付けする際、記述問題の採点基準で悩むことが多いです。
言葉が一致していなくても内容が合っていれば丸になる可能性が高いので、解答・解説をよく読んで採点してみてください。
③採点結果からケアレスミスと理解不足を区別する
過去問を採点した後、間違えた問題を分析し、ケアレスミスか、そもそも理解できていなかったかをしっかり区別しましょう。
・ケアレスミス:計算ミス、解答欄のずれ、記述の書き漏れなど
・理解不足:問題の意味を取り違えている、知識が定着していない など
たとえば「ケアレスミスがなければ○点だったね」と伝えてあげると、生徒様のモチベーションアップにもつながります。
また、間違えた問題は日付を書き込みマークを付けます。
過去問の復習用ノートを用意し、間違えた問題を写しておきましょう。
6. 過去問の復習はどのように行えばよいか

過去問演習で最も大切なのは復習をしっかり行うことです。ここでは、効果的な復習の進め方を解説します。
①間違えた問題はその日のうちに確認する
過去問演習で間違えた問題は、その日のうちに必ず確認しましょう。
採点時に復習用ノートに写した問題を、生徒様が解き方を理解するまで時間をかけて模範解答を読みこみましょう。
出題の意図が理解できるようになると過去問が解きやすくなります。
また、過去問の解説には、出題されていないけど重要な豆知識が掲載されている場合もあります。
正解した問題の解説も読んでおくと良いでしょう。
②間違えた問題と似た問題を教科書から探して解く
知識不足が原因で過去問が解けなかった場合は、教科書や参考書の復習が必要です。
間違えた問題と似ている問題をいくつか探し、生徒様に解いてもらいましょう。
徐々に難易度を上げていき、理解度を高めていきます。
解けなかった問題が毎年出題される問題なら、優先的に解法を覚えましょう。
なお、小学6年生の9月以降に新しい問題集や参考書を買うことはおすすめしません。
生徒様が混乱するリスクがあります。
間違えた問題と似ている問題が見つからない場合は、塾の先生や家庭教師の先生に相談しましょう。
③満点ではなく合格者平均点を目標にする
中学受験の合格点は6~7割程度と言われています。
受験校により変動しますが、100点満点を狙う必要はありません。
合格者平均点や合格最低点は各学校のホームページや過去問の教材に掲載されています。
問題を復習する際は、正答率の高い問題を優先して解き直してください。
正答率が低い問題が解けなくてもあまり気にしなくて大丈夫です。
④解答用紙の記入欄をおさらいする
問題を正しく解けたのに解答欄を写し間違えて失点するパターンがあります。
例えば以下の4点です。
・数字を写し間違える
・問題番号と解答欄がずれる
・解答欄に単位を書き忘れる
・複数選択の問題なのに1つしか選ばない
非常にもったいないミスなので、過去問を解く際は解答用紙をコピーして本番同様に書き込む練習をしましょう。
⑤教科別の復習ポイント
(1)国語:記述に慣れる
国語の記述問題は配点が高いので、基本的なルールを守り点数を取れるようにしましょう。
理由を問われているときは、記述問題の文末は「から」や「ため」で終わる必要があります。
「〇文字以下で述べよ」と文字数が指定されている問題は、なるべく文字数上限ぎりぎりで解答欄を埋めてください。
国語の問題の文章を読むときのラインの引き方も重要です。
物語文であれば、登場人物の気持ちを表す言葉にラインを引きましょう。
説明文の場合は、問題提起、具体例、結論にラインを引くと読みやすくなります。
上手にラインを引くためには過去問演習を繰り返して読解問題に慣れていくことが大切です。
復習の時間を長めに確保し、生徒様が文章を理解できるまで保護者様がサポートしてあげましょう。
(2)算数:ケアレスミス対策・図形強化
算数は計算問題のミスと図形問題の解法でつまずく子どもが多いです。
計算問題を解くときは、途中の計算式を綺麗な字で書くようにしましょう。
素早く解くことも大切ですが、ケアレスミスを防ぐため注意深く計算式を記載した方が確実に点を取れます。
図形問題が苦手なら、作図の練習を繰り返しイメージ力を培いましょう。
制限時間内に解くには、解法に慣れ親しむのが一番の近道です。
また、立体図形の問題は、豆腐を包丁で切り、同じ図形を作り出す勉強法がおすすめです。
図形問題が頻出の学校なら、過去問や類題の復習に時間をかけましょう。
(3)社会:ニュースを見て思考力を養う
社会は過去問で頻出している単元を調べておきましょう。
知識の暗記が間に合わない可能性もあるので、よく出る問題を狙って復習すると効果的です。
また、基礎知識の暗記だけでは答えられない応用問題を出題する学校もあります。
ある地域の気候・地形・名産品を問われたり、生成AIやSDGsなど時事問題と関連した問題も出題されます。
社会の教科書を復習するだけでなく、ニュースなどで幅広く情報収集しておくことが大切です。
思考力を問われる記述問題は、問題文の中に答えのヒントが隠れています。
肯定的な意見と否定的な意見どちらを記述するべきか、問題文から読み取れるようになりましょう。
(4)理科:身の回りの現象に関心を持つ
理科は地学・生物・化学・物理と大きく4つのジャンルに分かれているため、出題傾向を分析しやすいです。
生徒様が苦手な単元が頻出ならしっかり復習して失点を防ぎましょう。
理科は暗記するだけではなく、身の回りの現象と結びつけて説明できるだけの知識力・応用力があると高得点を狙えます。
冬に室内を暖めると、窓が結露したり、部屋は暖まるのに足元は寒かったり、科学的に理由を説明できる現象が発生します。
受験までに身の回りのことに対する視野を広げて思考力を鍛えておけるといいですね。
7. 過去問演習にあたってよくある質問3選
過去問演習を行う際によくある質問を3点記載します。
①2周目以降も本番同様でやった方がいいのか
第1志望校は2周目も本番同様に全ての問題を解いた方が良いです。
第2志望校以下も時間があれば全ての問題を解くことをおすすめします。
時間がなければ間違えた問題だけ解き直すようにしましょう。
②過去問演習をスケジュール通りに進めるコツを知りたい
過去問演習をスケジュール通りに進めるためには体調管理が重要です。
受験本番に向けて、過去問演習・塾の宿題・小学校行事など多忙なスケジュールになりますが、今まで通りの生活リズムを維持できれば乗り越えられるでしょう。
早寝早起き、1日3食、適度な運動を意識して、生徒様の集中力とモチベーションが維持できる環境を整えてあげてください。
③過去問のコピーが大変なので、おすすめのコピー方法があれば知りたい
中学受験の過去問をコピーする方法は3つあります。
・方法1:コンビニのコピー機を使う
・方法2:自宅にコピー機を購入・レンタルする
・方法3:印刷業者に依頼する
方法1:コンビニのコピー機を使う
コンビニなどのコピー機を使う際は、早朝や深夜など空いている時間帯に使用しましょう。
過去問の4科目分の問題用紙・解答用紙を数年分コピーすると時間がかかるためです。
商業施設などでコピー機が2台並んでいるところを利用すれば、時間を気にせずコピーできます。
方法2:自宅にコピー機を購入・レンタルする
自宅にコピー機を導入する場合は、実寸大と同じA3サイズがコピーできる機種を選びましょう。
いつでも過去問を解けるようコピー機を購入するご家庭もあれば、家のスペースが狭く期間限定で活用するためレンタルするご家庭もあります。
方法3:印刷業者に依頼する
印刷屋がご自宅の近くにあるなら、過去問を持ち込んで1冊まるごとコピーを依頼できます。
印刷屋に過去問を郵送してコピーを依頼する場合は、返送まで日数がかかるので気を付けてください。
過去問のコピーはページ数が多く非常に大変なので、ご家庭に合った方法を選び、効率良く準備を進めてくださいね。
最後に|過去問のやり方を押さえて、自信を持って受験本番へ

中学受験の過去問演習には、スケジュールの立て方、準備、採点、復習までさまざまなポイントがあります。
一つひとつ丁寧に取り組むことで、着実に力がつき、本番に向けて自信を育てることができるでしょう。
とはいえ、すべてを家庭だけで進めるのは大変な場面もあります。
「復習のフォローが難しい」「思うようにスケジュールが進まない」など、不安があれば、家庭教師のサポートを検討してみてください。
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
家庭教師が過去問対策のサポートをいたします
あわせて読みたい|【東大卒元家庭教師監修】中学受験のいろはシリーズ
こちらもおすすめ|【東大卒元家庭教師が解説】書評シリーズ