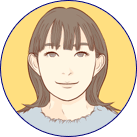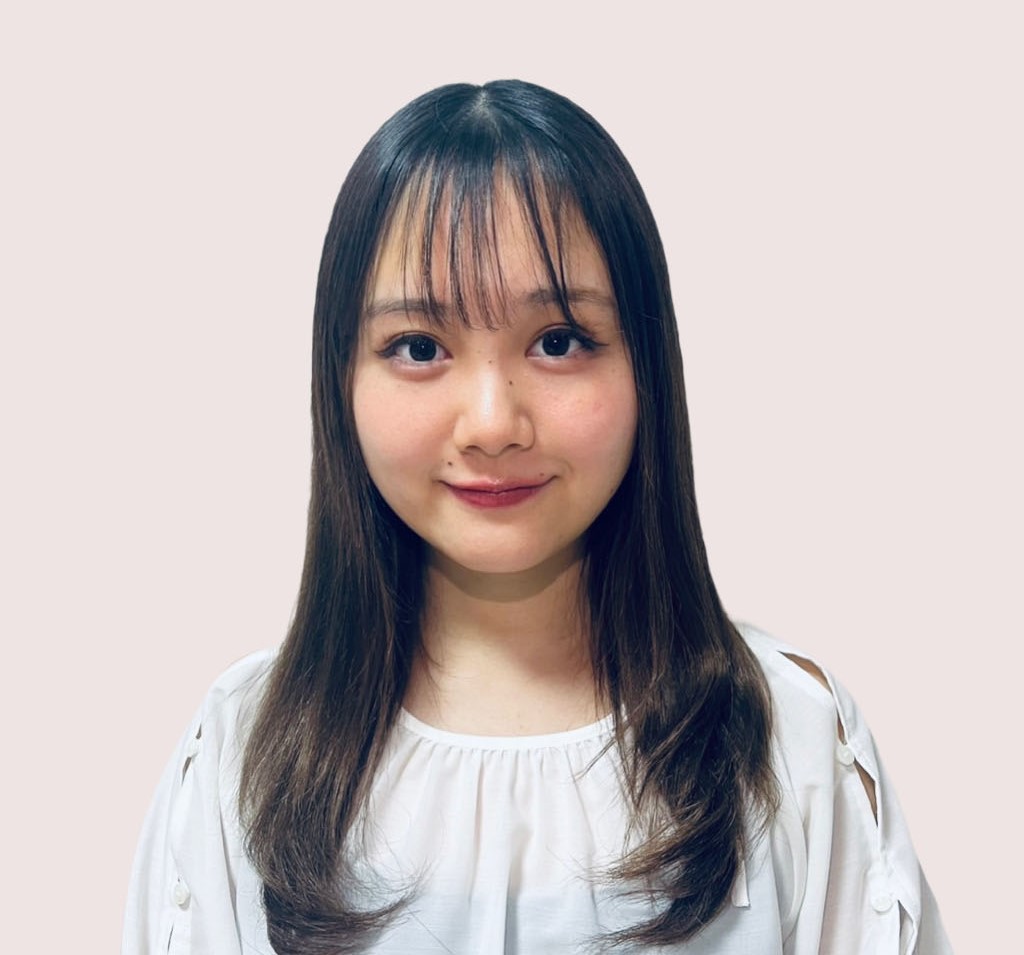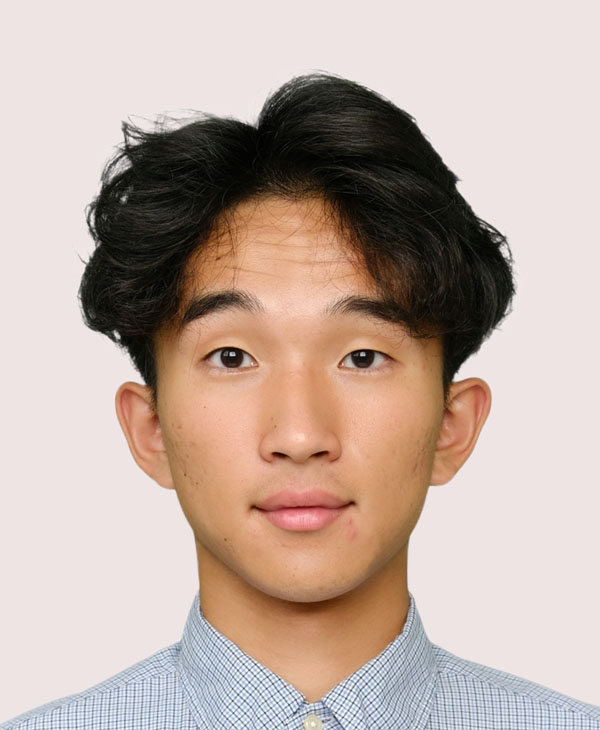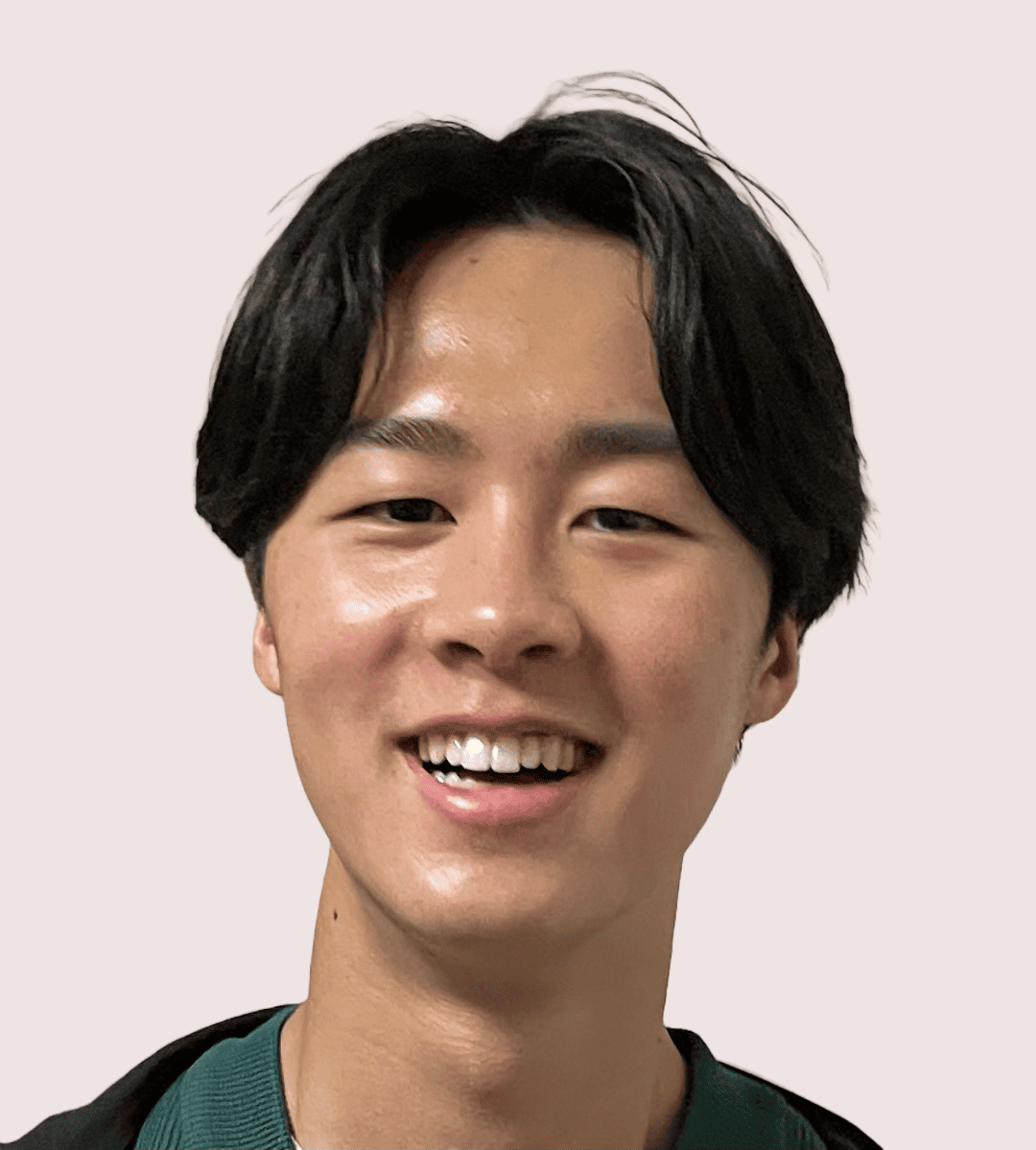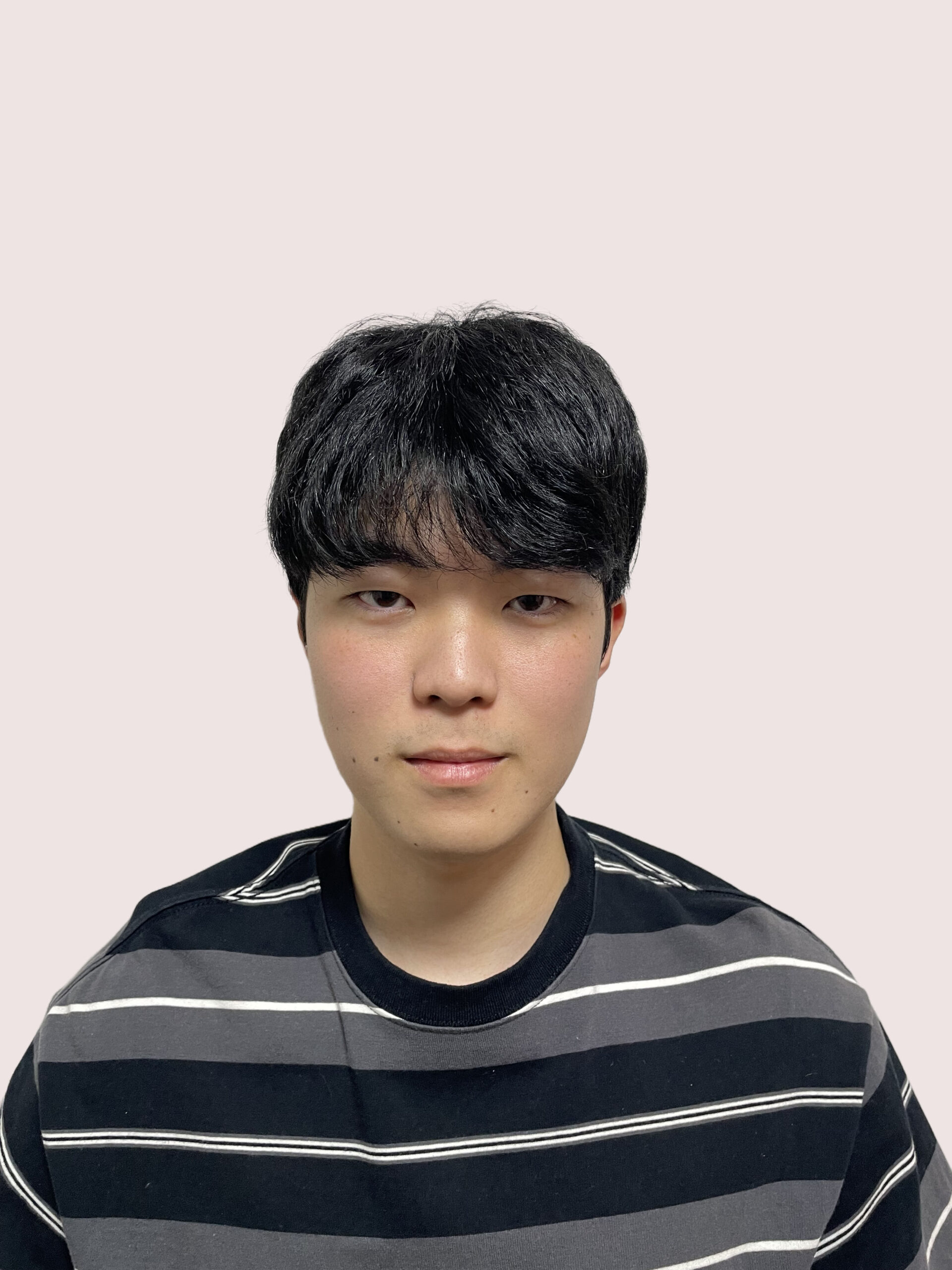![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 【中学受験】過去問は何点取れていればOK?時期ごとの目安

中学受験の過去問は、取り組む時期によって求められる点数が変わります。
最初から高得点を狙う必要はありません。大切なのは、「今の実力」を知り、「そこからどう伸ばすか」を考えることです。
まずは、過去問の目標点数を時期ごとに解説します。志望校合格に向けた学習計画を立てる参考にしてください。
① 初めて過去問を解いたときの正答率の目安
初めて過去問を解いたときの正答率は30〜50%程度が一般的です。
安全校だと50%を超えることもありますが、チャレンジ校だと20%程度またはそれ以下となります。
中学受験の過去問はレベルが高いため、最初から高い点数をとるのは困難です。点数が低くてもこの時点で志望校を変える必要はありません。
ただし、初めて過去問を解いたときの正答率が20%以下、または合格ラインの半分以下の点数だった場合は危機感を持ちましょう。
科目によって得点の傾向も異なります。
・【国語・社会】:知識があれば点を取りやすい
・【算数・理科】:初見では解き方がわかりにくく、得点が低くなりやすい
また、学校独自の出題傾向がある場合も初回の正答率は低くなるでしょう。
初めて過去問を解いたときの正答率が低くても落胆する必要はありません。過去問での結果を分析し、学習計画を立てることが大切です。
基礎固めできていない単元が見つかったら復習し、解き方がわかっているのに点数に結びつかない場合は過去問演習を繰り返せば良いのです。
中学受験は100点満点を狙う必要はありません。
学校のレベルにもよりますが合格ラインの目安は60点前後です。
過去問対策は、合格ラインから何点離れているかで生徒様の実力を確認していきましょう。
②9月・10月の目安|合格ラインの50~70%
過去問は9月から解き始めるよう推奨されています。
この時期は、合格ラインの50~70%を目指しましょう。チャレンジ校であれば、40~60%程度でも大丈夫です。
生徒様の実力が合格ラインに届かないことを自覚するのもこの時期です。
9月・10月に良い点数が取れなくても落ち込む必要はありません。
生徒様の現状が把握できれば良いので、改善の余地は十分にあります。
特に9月の段階では点数よりも、どこでつまずいているのかを明確にすることに意味があります。
③11月の目安|合格ラインの70~80%
11月に入ると、過去問の得点も徐々に上がってきます。
この時期は、合格ラインの70~80%を目指すのが理想です。
チャレンジ校を目指す場合は、80%以上の得点率を維持することが望ましいです。
実力相応校であれば、60~70%程度の得点でもまだ間に合います。
受験本番までまだ時間があるので、11月以降に得点が伸びる可能性は十分あります。
得意科目と不得意科目で点数に差が出る頃なので、過去問の結果を自己分析や対策に役立てましょう。
④12月の目安|合格ラインの80~90%
12月は、合格に向けた仕上げの時期。
この段階では、合格ラインの80~90%を取れるようにしておきたいところです。
チャレンジ校を目指す場合は90%以上、実力相応校であれば70~80%程度の得点でも良いでしょう。
12月に生徒様の正答率が伸び悩んでいたら、過去問でミスした問題を解けないまま放置しているのかもしれません。
「解答を見て理解したつもり」でも、実際には解けないケースがよくあります。
12月からは合格ライン到達に向けて、よりポイントを絞って勉強を進めていかなければなりません。
過去問の出題傾向が把握できたら類題を探して解き、同じミスを繰り返さないようにしましょう。
過去問同様の問題が出題されたり、他の受験校で類題が出たりするかもしれませんよ。
⑤1月の目安|合格ラインの90~100%
1月は本番目前。合格ラインの90~100%に到達していることが理想です。
受験本番で良い点数をとるために、苦手な問題を1問ずつ減らしていきましょう。
過去問で合格ラインに到達していても、気が緩んでしまうと受験直前に失速します。
受験本番で緊張してしまい、普段の実力を発揮できないこともあります。
本番の不安な気持ちに打ち勝つために、1問でも多く解けるよう苦手な問題を克服しておきましょう。
2. 過去問で点数がとれなかった際の対応方法
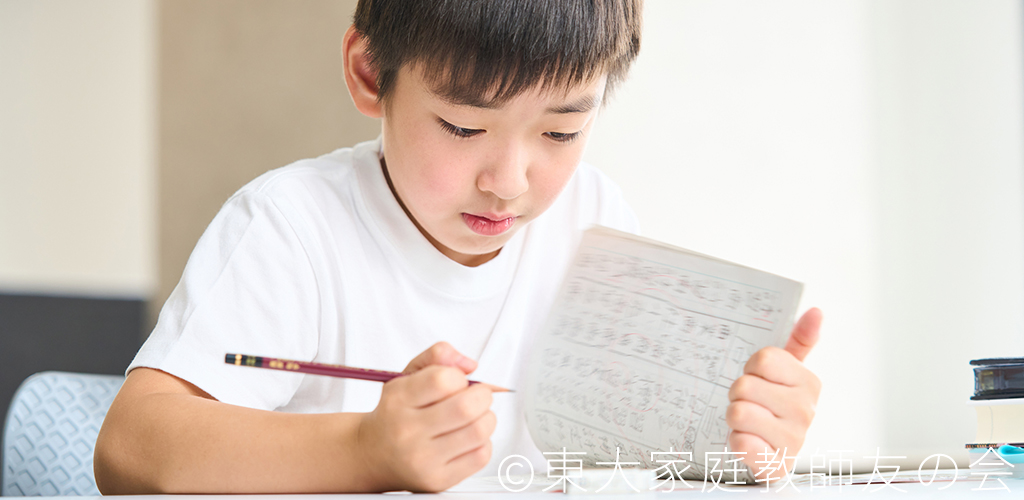
中学受験の過去問で思うように点数がとれなかった時は、「受験生の平均点を上回ったかどうか」や「制限時間内に解けたかどうか」で対策が異なります。状況ごとの対応を見ていきましょう。
①受験者平均点を下回った場合
過去問の点数が受験者平均点を下回っている場合は、基礎知識の復習が必要です。以下を丁寧に行いましょう。
・間違えた問題の原因分析: 計算ミス・知識不足・時間不足などを特定
・出題単元の把握: 特に点数が低かった科目・単元は重点復習
・基礎固め: 一問一答式の問題集で基礎から徹底復習
この段階では、焦って過去問を繰り返すよりも、土台を固めることが最優先です。
②受験者平均点は超えているが合格点に届かない場合
過去問の点数が受験者平均点以上とれているものの合格ラインに届かない場合は、応用問題に挑戦し実力の底上げを図る必要があります。
学校独自の難易度が高い問題が出題される場合もあるので、過去問を繰り返し解き、志望校の応用問題の解き方のコツを掴みましょう。
もし弱点となる単元が残っていたら、生徒様が克服するための時間を設けると良いですね。
受験直前期のみ家庭教師を依頼する生徒様もいらっしゃいますよ。
また、記述問題では部分点がもらえる場合があります。最後まで解けなくても途中まで解答用紙に記入すれば1点もらえるかもしれません。
答えを間違えてもいいから解答用紙をなるべく埋めてくるように、生徒様にアドバイスできると良いですね。
生徒様は過去問で平均点以上とれていてすでに実力が備わっているので、さらなる高みを目指して努力できるよう保護者様がサポートしてあげましょう。
③時間が足りなかっただけで、時間をかければそれなりに解ける場合
制限時間内に解けなかった場合は、以下の2つのパターンがあります。
(1)解くスピードが遅い
生徒様の解答スピードが遅い場合は、どこでつまずいているか確認が必要です。
社会であれば知識を思い出すまで時間がかかっているため、練習すれば改善します。
すぐに思い出せないならその問題を後回しにして先に進むテクニックを生徒様に覚えてもらいましょう。
算数だと記述問題など思考力が問われる問題でつまずくパターンが多いです。
図や書き方を効率化できるよう、過去問を解きながら慣れていきましょう。
過去問を繰り返し解き時間配分を意識できるようになると、最後まで解き終わってから見直す時間も確保できるかもしれません。
過去問対策で自信をつけてメンタル面を強化し、本番に向けてコンディションを整えられると良いですね。
(2)問題数が多く、捨てる問題を選ぶ必要がある
問題数が多く捨てる問題を選ぶ必要がある場合は生徒様の決断力が問われます。
一般的には、解き方が全く思いつかない問題や生徒様の不得意分野の問題をあきらめることが多いです。
一度捨てると決めた問題でも、他の問題を解き終わって時間が余ったら、途中まででも良いので解き進めましょう。
部分点がもらえるかもしれませんよ。
過去問対策はひとりで進めると、苦手な単元があったり、解き方がわからない問題が残ってしまい、不安を感じることも多いです。
そんな時は、家庭教師のサポートを活用するのがおすすめです。
家庭教師なら、生徒様の苦手分野を的確に把握し、効率よく克服できる学習計画を一緒に立てることができます。
過去問が解けなくて悩んでいる方は、ぜひ検討してみてくださいね。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
3. 過去問の効果的な復習方法と科目別の対策ポイント

過去問の復習方法で重要なポイントは、間違えた問題をすぐに確認することと、解けなかった単元の教科書を復習することです。
また、科目によって過去問の復習方法も異なります。
全ての単元をまんべんなく復習する方法では受験本番に間に合わないため、科目ごとに効率良く復習する方法を知る必要があります。
ここでは、過去問の復習の基本ステップと、教科別のポイントをご紹介します。
①復習の基本ステップ
1.間違えた問題をすぐに見直す
時間が経つと考えた過程を忘れてしまうため、なるべく当日中に振り返りましょう。
2.間違いの原因を分類する
「知識が抜けていた」「設問の読み間違い」「ケアレスミス」など、原因ごとに対策を整理するのが重要です。
3.弱点となった単元をテキストで復習する
問題だけでなく、その単元自体の理解が浅ければ、参考書やテキストに戻って再確認しましょう。
4.もう一度解き直す(+類題にも挑戦)
同じ問題を解き直すことで「本当に理解できたか」を確認。類似問題も解けば、知識が定着しやすくなります。
②教科別の復習ポイント
(1)国語の復習ポイント
記述問題は配点が高く、合否を左右する重要なポイントです。
「〜から」「〜ため」など、文末表現を意識しながら解答する練習をしましょう。
文字数制限がある問題は、なるべく上限ぎりぎりまで書くのが基本です。
また、読解では「どこに線を引くか」が理解の鍵になります。
・【物語文】:登場人物の気持ちを表す語句
・【説明文】:問題提起・具体例・結論
にラインを引くように意識すると、読みやすくなります。
(2)算数の復習ポイント
算数は「計算ミスが多い」「図形問題が苦手」という生徒様が多い教科です。
まずは途中式を丁寧に書き、ミスを防ぐことが大切です。
図形問題に強くなるには、作図の練習や、立体の切断イメージを鍛えるのが効果的です。
たとえば豆腐やスポンジを切って断面を観察するなど、実体験を通じた理解も力になります。
(3)社会の復習ポイント
社会は暗記だけでなく、背景知識や思考力も問われます。
まずは過去問で頻出の単元を洗い出し、重点的に復習しましょう。
最近はSDGsや時事問題、図や資料を読み取る問題も増えています。
ニュースや新聞などに日頃から触れ、「なぜそうなるのか?」を考える習慣が大切です。
記述問題では、問題文の中からヒントを読み取り、根拠のある答えを書く力も養いましょう。
(4)理科の復習ポイント
理科は物理・化学・生物・地学と分野が広く、それぞれに出題傾向があります。
まずは苦手な単元を特定し、繰り返し復習することが重要です。
また、理科は暗記だけでなく、「身の回りの現象と結びつけて理解する」ことが高得点につながります。
たとえば冬に窓が結露する理由や、部屋の上と下で温度差が生まれる理由など、日常生活の中の疑問を科学的に説明できる力を養いましょう。
4. 受験直前でも過去問で点数がとれないとき、志望校は変えるべき?判断の目安とは

受験直前期になっても過去問の点数が思うように伸びないと、不安になりますよね。
この時期の志望校変更は慎重に判断する必要がありますが、現在の得点状況や志望校のレベルによっては、見直しを検討したほうが良いケースもあります。
以下では、「チャレンジ校」「実力相応校」「安全校」のケース別に対応を解説します。
①チャレンジ校の場合
志望校がチャレンジ校で、過去問を何度解いても合格ラインに届かない場合、短期間で合格ラインまで成績を上げるのは難しいです。
仮に合格できたとしても、その学校の授業についていけず、入学後に苦労するリスクもあります。
このような場合は、志望校のレベルを少し下げることを前向きに検討してもよいでしょう。
どうしてもチャレンジ校を受験したい場合は、併願校に安全校を増やす、午後受験を追加するなど、他の学校に合格できるよう工夫しましょう。また、今までの勉強のペースでは合格は難しいため、勉強時間を増やしたり、一層集中して勉強したりするなど危機感を持って勉強に取り組むことをおすすめします。
②実力相応校の場合
志望校が実力相応校の場合、過去問を解いて出題傾向を把握すればまだまだ成績アップが狙えます。
最後の詰め込みで合格に届くかもしれないので、志望校は変更しなくても良いでしょう。
ただし、単元ごとの抜けやミスの傾向は早めに洗い出し、効率よく復習を進めましょう。
③安全校の場合
志望校が安全校なのに点数が取れない場合、基礎固めが不十分です。
志望校は変えなくて良いですが過去問対策よりも教科書の復習を優先しましょう。
基礎を押さえるだけでも、得点が安定し始めるケースは多くあります。焦らず、「なぜ点が取れないのか」を冷静に分析することが大切です。
5. 過去問で点数がとれなかったときの保護者様の声かけ・対応ポイント

過去問で点数がとれなかったとき、保護者様がどのような声をかけるかで、生徒様の気持ちは大きく変わります。
まずは点数のことを指摘する前に、努力したことや最後までやりきったことを認めてあげることが大切です。
「難しかったね」「頑張ったね」と過去問を最後まで解き終わったことをほめてあげましょう。
次に、「生徒様が過去問の難易度をどのように捉えたか」を聞いてみます。
難しいと感じていて点数も低かったのなら、生徒様が焦らないよう「他の子も最初はあまり点数がとれないよ」とフォローしてあげましょう。
易しい問題だと思っていたのに点数が取れていないのなら原因を探る必要があります。
ケアレスミスで失点したのか、緊張や焦りで上手く解けなかったのか、何かしら理由があるはずです。
過去問演習で対策を練れば試験本番までに上手に解けるようになるでしょう。
過去問の採点が終わったら、なるべくすぐに親子で一緒に見直しを行いましょう。
「なぜ間違えたのか?」「次に同じような問題が出たら解けそうか?」といった視点で確認します。
必要に応じて間違えた問題の単元の復習も行いましょう。
過去問演習はなかなか高い点数をとれなくて生徒様にとっても辛いと思いますが、「新しいことを学ぶと楽しいよね」と声をかけて、中学受験を終えた後に明るい未来が待っていることを伝えてあげてくださいね。
生徒様が「できなかった自分」を責めることなく、「次はできるようにしよう」と思えるようなサポートを心がけていきましょう。
最後に|過去問が解けないときは、家庭教師のサポートも検討しよう

中学受験の過去問は難しく、最初はなかなか思うように点数が取れないものです。
しかし、間違えた問題を一つひとつ見直し、解き方を理解していくことで、着実に点数は伸びていきます。
受験本番までの時間を有効に使い、1問でも多く解けるようにしていきたいですね。
もし「このままで間に合うのか不安」「自宅学習だけでは難しいかも」と感じたら、家庭教師に頼ってみるのも一つの方法です。
生徒様の学習状況や性格に合わせた丁寧な指導で、ラストスパートをしっかりサポートします。
中学受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
家庭教師が過去問対策のサポートをいたします
あわせて読みたい|【東大卒元家庭教師監修】中学受験のいろはシリーズ
こちらもおすすめ|【東大卒元家庭教師が解説】書評シリーズ