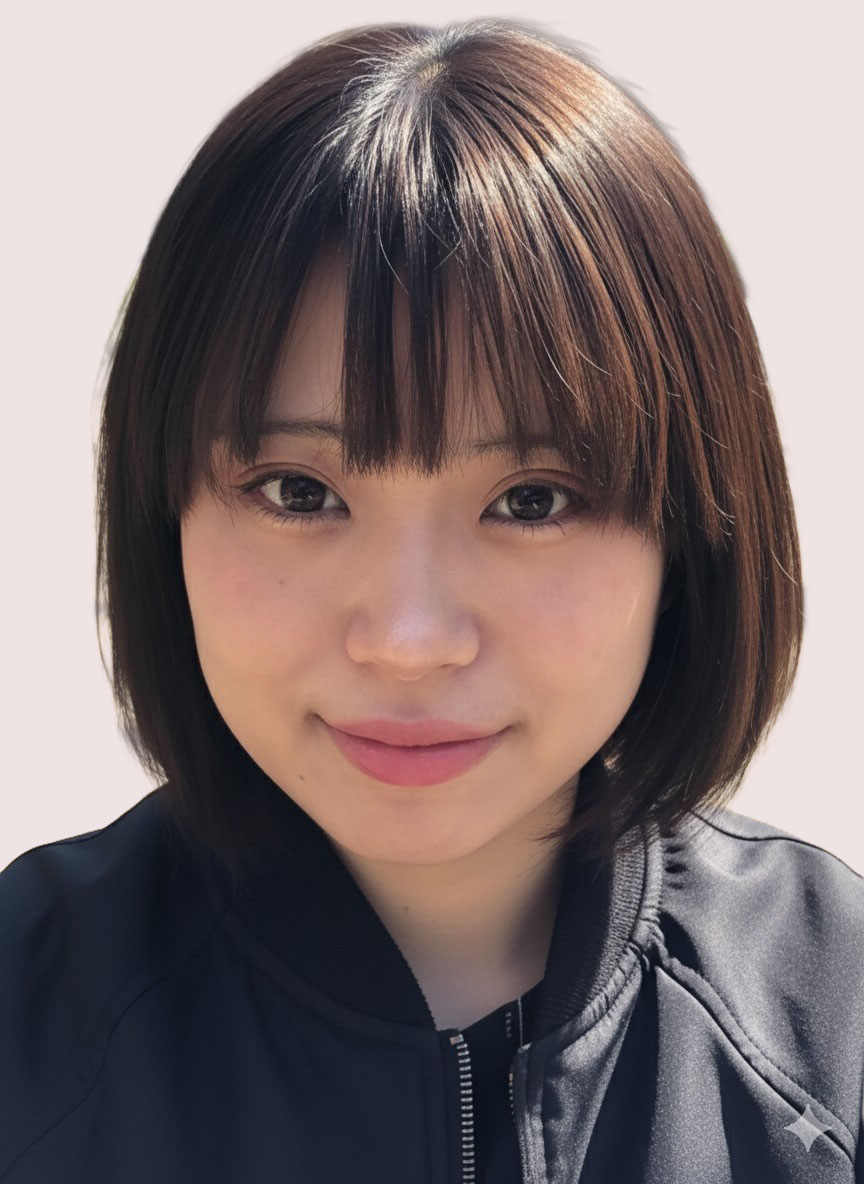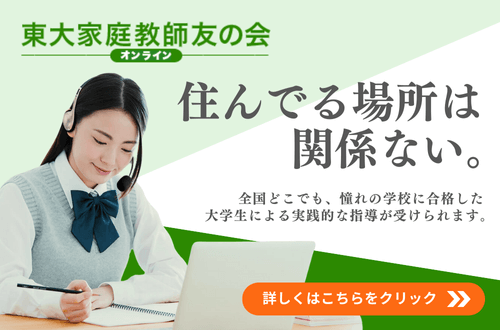1. 大学受験の小論文対策でよくある悩みとは?
小論文は、他の教科と異なり「正解が一つではない」という特徴があります。
そのため、多くの受験生が悩みを抱えています。特に初めて本格的に対策する方にとっては、出題形式や評価基準の曖昧さが大きな壁となることもあります。
ここでは、小論文対策においてよくある代表的な悩みを紹介します。
①書き方が分からない
小論文は「自分の意見を論理的に展開する力」が求められるため、自由作文のように書いてしまうと評価されません。
導入→主張→根拠→結論
上記の構成を理解していないと、読みにくく一貫性のない文章になりがちです。
②自分で添削できない
小論文の添削では、誤字脱字よりも「論理の飛躍」や「説得力の不足」といった構造的な課題が重視されます。
こうした点は、書き手本人では気づきづらいため、客観的なフィードバックが不可欠です。
「なぜその結論になるのか」「根拠は十分か」といった専門的な観点からの指導があるかどうかで、文章力の伸び方に大きな差が出ます。
③志望校の出題傾向や形式が分からない
大学によって小論文の出題テーマ・文字数・評価基準は大きく異なります。こうした傾向を把握せずに対策を始めると、努力が空回りしてしまう可能性があります。
2. 入試形態別|大学受験における小論文対策のポイントと対策法
入試形態によって小論文に求められる力は大きく異なります。自己PRが中心の形式もあれば、課題文の論評が求められるものもあり、共通の型では対応しきれません。
ここでは、一般入試・総合型選抜(旧AO)・学校推薦型選抜における小論文の特徴と対策方法を紹介します。
【一般入試】論理構成と表現力が鍵
一般入試の小論文では、課題文に対する自分の意見を、明確かつ論理的に述べる必要があります。
内容が正しいだけでなく、主張→根拠→具体例→まとめといった構成が整っているかが重視されます。例えば「格差社会」についての課題に対して、自身の意見とともに、統計や社会現象を根拠として使えるかどうかが鍵になります。
【総合型選抜(旧AO)】自己理解と独自性が鍵
総合型選抜では、自己理解・価値観・将来像など「自分自身をどう言語化できるか」が問われます。
小論文のテーマも「自分にとっての学びとは?」など、抽象的なものが多く、自分の経験と絡めて論じる力が求められます。高校時代の活動を通じて得た気づきや課題意識を深掘りし、他者と違う視点で展開できるかが評価ポイントです。
【学校推薦型選抜】志望理由との一貫性が鍵
推薦入試では、学部の理念や求める人物像に沿った文章が書けているかが重視されます。例えば教育学部であれば「子どもとの関わり方」や「授業づくりへの考え方」など、将来の教育現場を意識した実践的な視点を文章に盛り込めているかが評価のポイントになります。
単なる理想論ではなく、実際にどのように教育に関わっていきたいのか、自分なりの行動イメージを具体的に語れると評価が高くなります。
大学の募集要項や過去の出題例を参考に、「その学部にふさわしい」文章を意識する必要があります。
3. なぜ小論文対策は「個別指導」が効果的なのか?
①課題が人によって異なる
小論文には明確な「模範解答」がなく、テーマに対する切り口や意見の展開方法は人によって大きく異なります。例えば「SDGsについてどう思うか」というテーマでも、環境面から論じる人もいれば、教育・ジェンダー・経済格差といった観点から書く人もいます。
また、入試形態によっても求められる力が異なりますし、語彙の使い方や論理の組み立て方にも個性が出るため、一人ひとりの弱点もバラバラです。
そうした個々の課題に対して的確にフィードバックできるのが、個別指導の大きな強みです。
②添削とフィードバックで弱点が明確に
小論文対策において最も伸びる瞬間は「自分の文章のどこが問題なのか」に気づけたときです。例えば、構成が弱い・根拠が曖昧・主張と結論がズレているといった課題は、自分一人ではなかなか見つけにくいものです。
教師による添削では、そうした論理のずれを明確に指摘し、具体的な修正アドバイスを受けられます。定期的なフィードバックを繰り返すことで、自分のクセや弱点を理解し、合格レベルの答案に近づけることができます。
4. 小論文対策は塾と家庭教師、どちらが合う?
対策の手段としてよく検討されるのが「塾」か「家庭教師」かという選択です。どちらにも利点があるため、自分の学習スタイルや目的に合わせた選択が必要です。
ここでは、それぞれの特徴と向いているタイプを整理します。
| 塾 |
塾では複数の講師による体系的なカリキュラムが整っているため、全体像をつかみながら段階的に実力を伸ばすことが可能です。 |
| 家庭教師 |
家庭教師は、指導内容もスケジュールも完全にカスタマイズ可能で、受験生一人ひとりのレベルや志望校に応じて柔軟に対応できるのが特徴です。 |
5. 小論文の家庭教師なら東大家庭教師友の会へ
東大家庭教師友の会では、難関大の小論文試験を突破してきた教師が、一人ひとりの課題に合わせて指導を行います。
「家庭教師とうまくやれるだろうか」「家庭教師との相性を重視したい」と考えていらっしゃる方もご安心ください。 生徒様の「こんな家庭教師がいい!」というご要望を聞き、生徒様にぴったりの家庭教師を見つけます。
①難関大合格者による添削
実際に東大・慶應・早稲田などで小論文入試を突破してきた教師が、経験に基づいた実践的なアドバイスを提供します。
模範解答ではなく「なぜこの表現が良くないのか」「どこを変えると説得力が上がるか」を指摘しながら、受験生をサポートします。
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
②志望校別・目的別の学習プラン
「今の実力でこの大学は受かる?」「推薦と一般、どちらを優先すべき?」といったご相談から、受験日までの学習プランを一緒に作成します。対策に使う題材や資料も、生徒様に合わせて選定します。
生徒様専用の授業計画書を作成してから
指導を開始します
生徒様一人一人、置かれているご状況や抱えているお悩みは異なります。
当会では、生徒様専用の授業計画を作成し、生徒様のペースに合わせて授業を進めていくため、生徒様が抱えているお悩み・つまずき等を丁寧に解消することができます。
-
- 1.ヒアリング
教師が生徒様の目標、成績、お悩み、得意分野、苦手分野等をヒアリング - 2.授業計画作成
当会と教師で授業計画のすり合わせ - 3.三者面談
教師、保護者様、生徒様の三者面談を実施。授業計画のご説明を実施。
- 1.ヒアリング
③オンライン指導や短期集中指導にも対応
対面での受講が難しい方や限られた期間で成果を出したい方のニーズにお応えできるよう、オンライン指導・短期指導にも完全対応しています。
6. まとめ
小論文対策には、「何をどう書けばよいか分からない」という不安や、「自分の文章を誰かに見てほしい」というニーズがつきものです。
大学や入試形態によって求められる内容も異なるため、画一的な対策では限界があるのが現実です。
本記事で紹介したように、構成の型を理解し、志望校に合わせた指導を受けることで、小論文の得点力は着実に伸ばせます。
個別の添削や学習プランの作成を希望される方は、ぜひ一度、東大家庭教師友の会へお問い合わせください。
▼東大家庭教師友の会では、大学受験へ向けた指導が可能です。ぜひ併せてご覧ください。
東大家庭教師友の会の料金
当会では、「入会金」「指導料」「交通費」「学習サポート費」以外のご料金は、一切ご請求しておりません。指導キャンセル料や教師交代費、解約金等は一切発生いたしませんので、ご安心ください。
ご入会時
体験授業料0円
ご入会金 22,000
体験授業は1ご家庭様につき1人のみ無料でご受講いただけます。2人以上受ける場合、1人につき2,420円(税込)の体験授業料が発生します。
月々のお支払い
交通費は教師が所持する定期区間を除きます。
口座振替でお支払いの場合、手数料385円(税込)が発生します。

東大家庭教師友の会「7つの0円」
大学受験・高校生向けのコース料金
入会までの流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
東大家庭教師友の会オンライン
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る