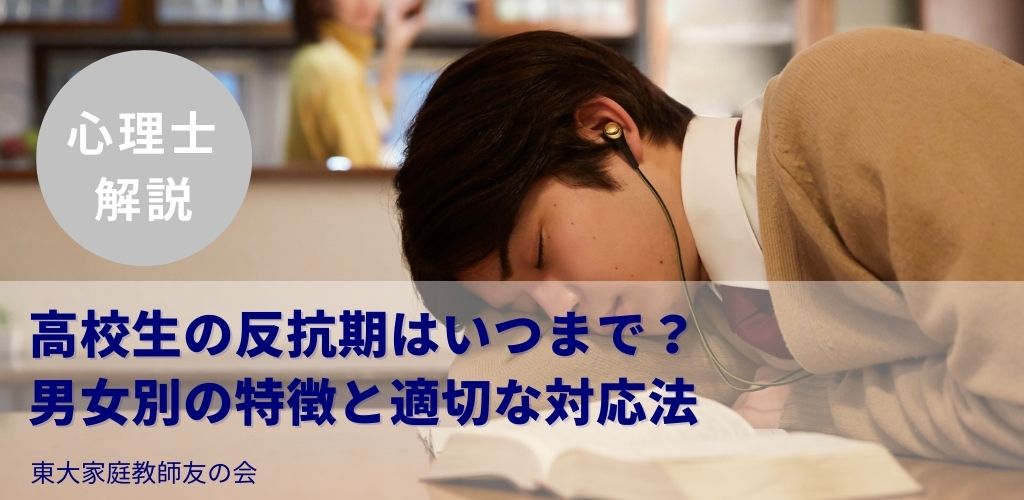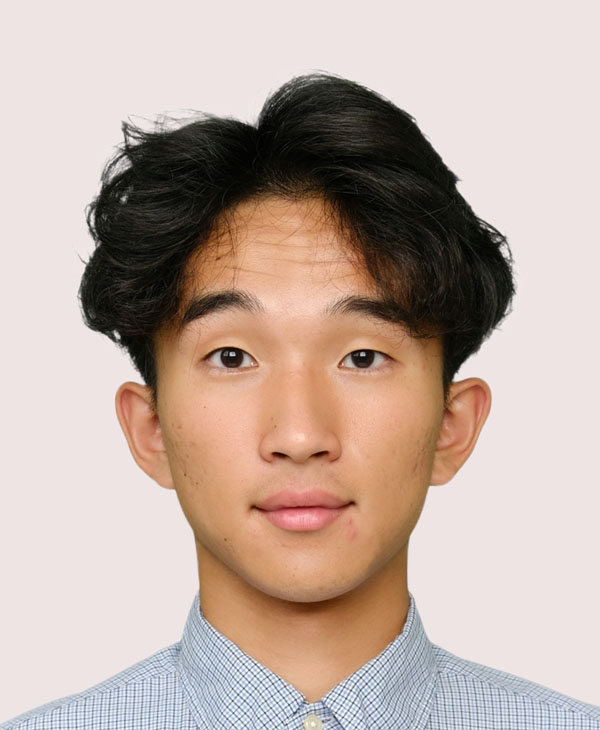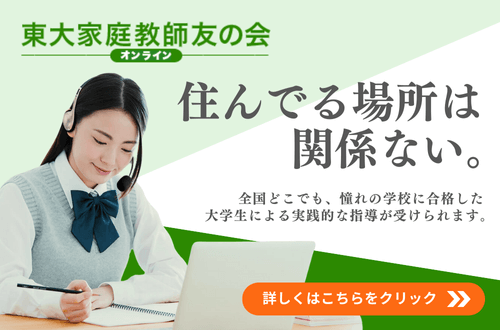![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業実施中!
1. 【男女別】高校生の反抗期の特徴
高校生は中学生よりも大人として見られ、社会からはそれ相応の振る舞いが求められます。しかし心理的にはまだ未成熟で、子ども特有の万能感(「自分たちは何でもできる」という思い込み)が強い子もたくさんいます。そのため、中学生の頃よりも
|
・大人の言うことを無視する ・高圧的な態度をとる |
といった行動が目立つことがあります。保護者様からすると「手に負えない・・・」と感じられるかもしれませんが、これは自立へ向かう過程でよく見られる姿です。
①男女共通の特徴
(1)思考力と行動力が増す
高校生になると、中学生の頃よりも考える力がぐんと伸びます。子どものためを思って話していても、言い負かされたりうやむやにされてしまうことも珍しくありません。
また、行動範囲が一気に広がることで、友達との付き合いや外の世界に夢中になり、口論や家出、トラブルに巻き込まれるリスクも出てきます。
(2)欲求と現実のギャップでストレスがたまる
音楽、アニメ、ライブなど、成長するにつれて好きなものや興味のあるものがはっきりとし、子どもの世界が広がっていきます。その世界をもっと知りたい、自分もやってみたいという思いが強くなる一方で、時間・お金・親の許可などの制約に直面し、欲求が満たされないことがあります。
このように欲求が何らかによって阻止され、満足されない状態にあることを心理学では「フラストレーション」と呼びます。フラストレーションが溜まると、攻撃的な態度や反抗につながることがあります。
(3)親とのコミュニケーションを拒む
親の意見よりも自分の判断を優先したい気持ちが強くなります。そのため、親との会話を避けたり、挨拶をしなくなることもあります。これは親への反発心だけでなく、自分の世界を守りたいという成長の表れでもあります。
保護者様は、無理にコミュニケーションをとろうとせず、子どもが話したいときに受け止められる環境を整えることが大切です。
②高校生男子の特徴
(1)態度で反発を示すことが多い
高校生男子は体格や筋力が成長するため、母親だけでは制止できない行動をとることもあります。
言葉よりも態度や行動で自己主張する傾向があり、物にあたったり、部屋や家具を壊すなど、ストレスのはけ口として暴力的な行動に出る場合もあります。ときには自室に閉じこもって家族との関わりを避けることもあり、家庭内の雰囲気がピリピリしやすいのが特徴です。
(2)外の活動を優先し、家庭内ルールを軽視しやすい
部活動や友人との遊び、アルバイトにのめり込むなど、家庭より外の活動を重視する傾向が強まります。
門限を破ったり勉強を投げ出したりと、家庭内でのルールを軽視する行動が見られることもあります。保護者様にとっては心配ですが、子どもにとっては自立や交友関係の広がりの一環であることも理解しておく必要があります。
③高校生女子の特徴
(1)言葉で反抗することが多い
男子のように暴力や物にあたる行動は少ないものの、言葉で強く反発する傾向があります。皮肉や嫌味を言ったり、親の言葉を聞き流したりと、会話の中で反抗が表れやすいのが特徴です。
(2)感情の揺れが激しい
思春期の女子はホルモンバランスの変化により、気持ちの浮き沈みが大きくなります。ちょっとしたことでイライラしたかと思えば急に涙を流すなど、気持ちが不安定になりやすい時期です。
保護者様にとっては戸惑う場面も多いですが、まずは気持ちを受け止め、安心できる雰囲気を保つことが大切です。
(3)他人の目や友人関係に敏感になる
高校生女子は「周囲からどう見られているか」や「友人との関係」に影響を受けやすい傾向があります。友達から仲間外れにされることを恐れたり、SNSでのやり取りに一喜一憂したりする姿も珍しくありません。親よりも友達や先輩との関係を優先することが増え、家庭での関わりが二の次になることもあります。
これは仲間意識が高まり、自分の社会的な立ち位置を気にするようになる「自然な成長の一部」です。保護者様は無理に介入しようとせず、子どもが相談してきたときに安心して話せるよう、耳を傾ける姿勢を大切にしましょう。
2. 高校生で反抗期は遅い?いつまで続く?
「中学生の頃は落ち着いていたのに、高校生になってから急に反抗的になった」――。
そのような変化に戸惑う保護者様は少なくありません。高校生で見られる「遅い反抗期」には、性格や家庭環境、友人関係など、さまざまな要因が影響しています。
ここでは、反抗期が遅れて表れる理由と、終わりの目安について解説します。
①反抗期が遅い原因と背景
・親からかまってもらえなかった
中学生のころに保護者様の関心が兄弟姉妹に向かっていたり、忙しさから話を聞いてもらえなかったりすると、子どもは自分の気持ちを抑えて過ごすことがあります。満たされなかった「甘えたい」「認めてほしい」という思いが積み重なり、高校進学という環境の変化をきっかけに、反抗として表れることもあります。
・抑えていた気持ちが爆発する
高校生になると行動範囲が広がり、自分の意思を強く持つようになります。
「この部活を続けたいのに親がやめろと言う」「友達と出かけたいのに制限される」など、親の期待と本人の希望がぶつかる場面も増えてきます。これまで我慢してきた思いが積み重なり、高校生になって初めて爆発することもあります。
②高校生の反抗期はいつまで?終わりのサイン
多くの場合、反抗期は高校卒業のころには落ち着いていきます。
愛媛大学の研究(注1)によると、反抗心が弱まっていく背景には次の2つの要因があります。
|
(1)心理的な成長 価値観が育ち、感情のコントロールがしやすくなることで精神的に安定し、反抗心は自然に低下していきます。
(2)感謝の心の芽生え 一人暮らしや進学を通して、親からの金銭的・精神的支えの大きさに気づくようになります。その結果、感謝や申し訳なさの気持ちが芽生え、反抗心は和らいでいきます。 |
高校生の反抗期は「満たされなかった思い」や「自立への強い欲求」といった背景を経て表れますが、成長とともに自己理解が深まり、親への感謝を実感できるようになる過程で自然と終息に向かいます。
反抗期の終わりは、子どもが社会に出る準備を整えていくなかで訪れる「成長のサイン」とも言えるでしょう。
3. 【男女別】手に負えない!高校生の反抗期への接し方
高校生の反抗期に「手に負えない…」と感じ、どう接したらよいか悩む保護者様も少なくありません。
ついきつく注意してしまい、その後「言いすぎたかもしれない」と自己嫌悪になることもあるでしょう。
ここでは、男女別に反抗期の高校生への適切な関わり方をご紹介します。接し方のポイントを押さえることで、親子関係がこじれるのを防ぎ、落ち着いて向き合うことができるようになります。
① 男女共通の接し方
(1)注意より「対話」を大切にする
高校生は大人への移行期にあり、子ども扱いをされることを嫌います。そのため「一方的に注意する」のではなく、「理由を伝えながら対話する」姿勢が重要です。
たとえば帰宅時間については、
|
×:「もっと早く帰ってきなさい」 ○:「晩ごはんの準備もあるから、○○時には連絡を入れてくれると助かるんだけど、どうかな?」 |
理由を示しつつ、最終的な選択を子どもに委ねることで受け入れやすくなります。
また、「最近帰ってくるのが遅くて心配だよ」と保護者様の気持ちを素直に伝えるのも効果的です。
即効性は薄いですが、大切なのは「対話」です。長期的に信頼関係を築く姿勢を意識しましょう。
(2)価値観の違いを話し合う
親が考えていることと子どもが考えていることがズレていることはよくあります。
たとえば「部屋は常にきれいにするべき」と親が思っていても、子どもは「多少散らかっていても構わない」と感じているかもしれません。こうした価値観の違いを一方的に押し付けるのは逆効果です。
|
・親は「なぜ部屋をきれいにしてほしいのか」を伝える ・子どもは「なぜ片付けないのか」を説明する |
といったやり取りを通して折り合いをつけることが大切です。
保護者様が柔軟に歩み寄る姿勢を示すことで、子どもも「自分の意見をちゃんと聞いてくれる」と感じ、次第に対話がスムーズになります。
(3)意見がぶつかるときは一旦距離をおく
どうしても意見がぶつかるときは、無理にその場で解決しようとせず、いったん時間をおきましょう。ポイントは次の2つです。
|
・先ほどまでの険悪な雰囲気を引きずらない ・無理に解決に持ち込まない |
時間をおくことで、子どもが自然と行動を変える場合もあります。話を再開するのは、子どもの方から切り出してきたときで十分です。
②高校生男子への接し方
(1)行動を制限するより安全を優先する
外出や遊びを厳しく制限すると、かえって反発が強くなることがあります。「どうして自分だけ…」と不満が募り、家庭内での衝突につながりかねません。
大切なのは、一方的な制限ではなく「最低限のルールを一緒に決めること」です。たとえば、
|
・「出かけるときは必ず連絡する」 ・「帰宅時間は守る」 |
こうしたルールづくりは、子どもの自主性を尊重しつつ安心できる環境を整え、家庭内の衝突を防ぐことにつながります。
(2)任される経験で責任感を育む
体力や行動力が増す高校生男子には、エネルギーを発散できる場が必要です。
部活動やアルバイトなど「任されたことをやり遂げる経験」を積むことで、自分の行動に責任を持つ意識が芽生えます。
「やらされている」のではなく「任されている」と感じられることが大切で、この実感が自己肯定感の向上にもつながり、家庭内の対立も和らぎやすくなります。
③高校生女子への接し方
(1)感情を否定せずに受け止める
高校生女子は感情の起伏が大きく、人間関係のストレスも抱えやすい時期です。そこで「泣かないで」「怒らないで」と感情を抑え込むのではなく、まずは「そう感じているんだね」と受け止めることが大切です。
気持ちを受容されたと実感すると、落ち着いたあとで冷静に話し合えるようになり、親の言葉にも耳を傾けやすくなります。
(2)自己表現の場を尊重する
女子は友人関係や他人の目を強く意識するため、趣味や友人との関わり、SNSなどが「自分らしさを表現できる大切な場」となります。
|
・家庭でのちょっとした会話に耳を傾ける ・「そんなことより勉強でしょ」と否定せず、楽しむ時間を認める |
こうした対応が、「親に受け止めてもらえている」という安心感につながり、家庭内の衝突を和らげていきます。
▼女子特有の反抗期に関する記事はこちら
「【心理士解説】女子の反抗期の特徴と年代別の接し方、やってはいけないNG対応
ここまでの内容を整理すると、高校生の反抗期における男女別の特徴と接し方は次の通りです。
男女共通
・特徴:自立心が強まり、親と衝突しやすい
・接し方の基本:一方的に注意せず、対話を重視する
・効果的な関わり:衝突したら一旦距離をおき、落ち着いてから話す
男子
・特徴:行動範囲が広がり、エネルギーが有り余る
・接し方の基本:厳しく制限せず、安全を優先する
・効果的な関わり:部活やアルバイトなど任される経験を通して責任感を育む
女子
・特徴:感情の起伏が大きく、人間関係に敏感
・接し方の基本:感情を否定せず、まず受け止める
・効果的な関わり:趣味や家庭での小さな会話など、自己表現の場を尊重する
男女で表れ方に違いはありますが、根底にあるのは「自立への欲求」です。
保護者様は安心感を示しながら、子どもが自分で考え行動できる環境を整えてあげましょう。
4. やってはいけない!反抗期の高校生へのNG対応
反抗期の高校生は、親のちょっとした言葉や態度で心を開いたり、逆に閉ざしてしまったりします。
「子どものためを思って言ったのに、余計に反発された」「距離をとられてしまった」と悩む保護者様も多いのではないでしょうか。
ここでは、ついやってしまいがちなNG対応を3つ取り上げます。気づかないうちに繰り返していないか、一緒に確認してみましょう。
① 怒鳴る・強制する
子どもが言うことを聞かないと、つい声を荒げたり「言うことを聞きなさい!」と強制してしまうことがあります。その場では従うように見えても、心の中では「自分の気持ちは理解してもらえない」と感じ、親への信頼は薄れてしまいます。
大切なのは、子どもの考えや気持ちを受け止めたうえで、ルールを一緒に話し合うことです。
たとえば、家庭での勉強時間や部屋の片付けなど、日常生活のルールを押し付けるのではなく、理由を説明して納得できる形で合意することで、子どもも素直に従いやすくなります。
②他の子どもと比べる
「お兄ちゃんはできたのに」「○○ちゃんを見習いなさい」といった比較は、子どもの自尊心を大きく傷つけます。
比較された子どもは「自分はダメなんだ」と感じ、やる気を失ったり、親に本音を隠すようになることもあります。
子どもはそれぞれ成長のペースや得意・不得意が違います。たとえば、勉強は苦手でもスポーツが得意な子もいます。比べるのではなく、「昨日よりできたね」「あなたらしいね」と本人の努力や成長に目を向けて言葉をかけてあげましょう。
③プライバシーを無視する
日記やスマホを勝手に見ることは、信頼関係を壊す大きな要因です。
高校生は自分の世界を大切にし、他人に踏み込まれたくない気持ちが強い時期です。プライバシーを尊重されないと「信用されていない」と感じ、家庭が安心できる場所ではなくなってしまいます。
もちろん安全のために見守りは必要ですが、疑うのではなく「心配だから」と素直に気持ちを伝え、必要なときは本人の同意を得ながら関わることが大切です。
5. 反抗期の高校生が勉強しないときの上手な促し方
大学受験を控える高校生。親としては「悔いのない受験にしてほしい」と願うものです。
しかし現実には思うように勉強せずアニメやゲーム、スマホに時間を費やしてしまう子どもに頭を抱える保護者様も少なくありません。
ここでは、反抗期の高校生に無理なく勉強を促す方法を3つご紹介します。
① 勉強の先にある将来を具体的に伝える
高校生にとって「大学受験の先にどんな未来があるのか」をイメージするのは難しいものです。
「将来のため」と言われてもピンとこず、目の前のゲームやYouTubeの方が楽しく感じるのは自然なことです。
親ができるのは、勉強の先にある楽しみや成長のイメージを具体的に伝えることです。
|
・大学生活の自由で楽しい一面 ・興味のある分野を学び、将来につながる可能性が広がること ・一人暮らしやアルバイトなど、自立の一歩を踏み出せること |
こうした話をしてあげると、「受験勉強=将来の楽しみや成長のために必要なこと」と前向きに捉えやすくなります。
また、勉強のモチベーションには大きく2種類あるとされています。
|
(1)内発的動機づけ 「将来の夢につながる」「知識を得るのが楽しい」といった、自分の内側から湧き出る意欲
(2)外発的動機づけ 「成績が上がったらご褒美」「親に怒られるからやる」といった、外部からの働きかけによる意欲 |
短期的にはご褒美や叱責で勉強させることも可能ですが、長続きはしません。(心理学ではアンダーマイニング効果と呼ばれます)
反抗期の高校生には、「自分で勉強しようと思える理由=内発的動機づけ」を育てることが最も効果的です。
②自分のペースで勉強できる環境を整える
「集中できる環境」は子どもによって異なります。
静かな部屋が好きな子もいれば、少し音がある方が落ち着く子もいます。大切なのは、親が一方的に押し付けるのではなく、子どもの意見を聞きながら一緒に環境を作ることです。
たとえば、
|
・家では気が散りやすいなら図書館や自習室を活用する ・勉強道具を整理して取りやすくする ・移動時間を減らしたいなら家庭教師を活用する |
といった工夫で「自分に合った学習環境」を整えると、勉強の習慣化がしやすくなります。
さらに、勉強の開始時間や科目の順番はできるだけ本人に任せると「やらされている」という感覚を減らせます。
親は進み具合を細かくチェックせず、見守る立場に徹することがポイントです。
③第三者のサポートで「親以外に相談できる関係」を作る
反抗期の高校生にとって、親からの「勉強しなさい」は反発の原因になりやすいです。
そこで効果的なのが、家庭教師や塾講師といった第三者の存在です。
親には言えない不安や悩みも、信頼できる第三者になら話せることがあります。特に家庭教師はマンツーマンで関わるため、勉強面だけでなく進路や将来の相談相手にもなりやすいのが特徴です。
「親以外に相談できる関係」を持つことで、子どもは安心感を得られ、勉強にも前向きに取り組みやすくなります。
東大家庭教師友の会では、年齢の近い大学生の家庭教師が、勉強だけでなく学校生活や悩みごとにも寄り添います。
ご相談からでも大丈夫です。まずはお気軽にお問い合せください。
![]() 反抗期高校生サポート
反抗期高校生サポート
無料体験授業実施中!
6.高校生の反抗期に寄り添いサポートしよう
高校生の反抗期は中学生の頃とは違い、親子関係や学習面にも影響が出やすい時期です。関係性を悪化させないためには、
|
・子どもとのコミュニケーションを大切にする ・お互いの思いを話し合う ・必要に応じて距離をとる |
といった工夫をしながら、親子で乗り越えていくことが大切です。
時間が経てば反抗心は自然に落ち着き、以前のような親子関係に戻っていきます。親が焦ったり感情的になったりすると、その不安やイライラが子どもに伝わってしまうため、どっしり構えてサポートすることを意識しましょう。
【脚注】
注1)江上園子,田中優子(2013).第二反抗期に対する認識と自我同一性との関連
【参考文献】
今福理博,斉藤汐奈(2020).思春期における第二反抗期経験と対人依存及び家族関係との関連の検討
臼井利明(1997).青年心理学の観点からかみた「第二反抗期」
大学受験の指導ができる家庭教師のご紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
オンラインでの指導も可能です
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る
反抗期の高校生の勉強フォローなら東大家庭教師友の会
あわせてチェック|反抗期の関連記事