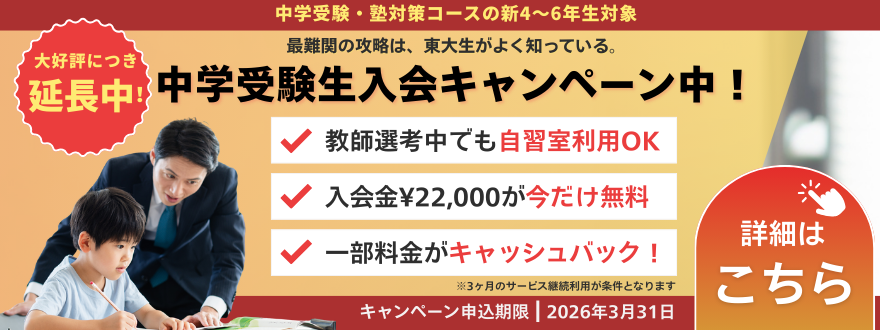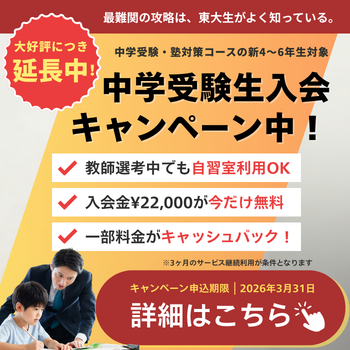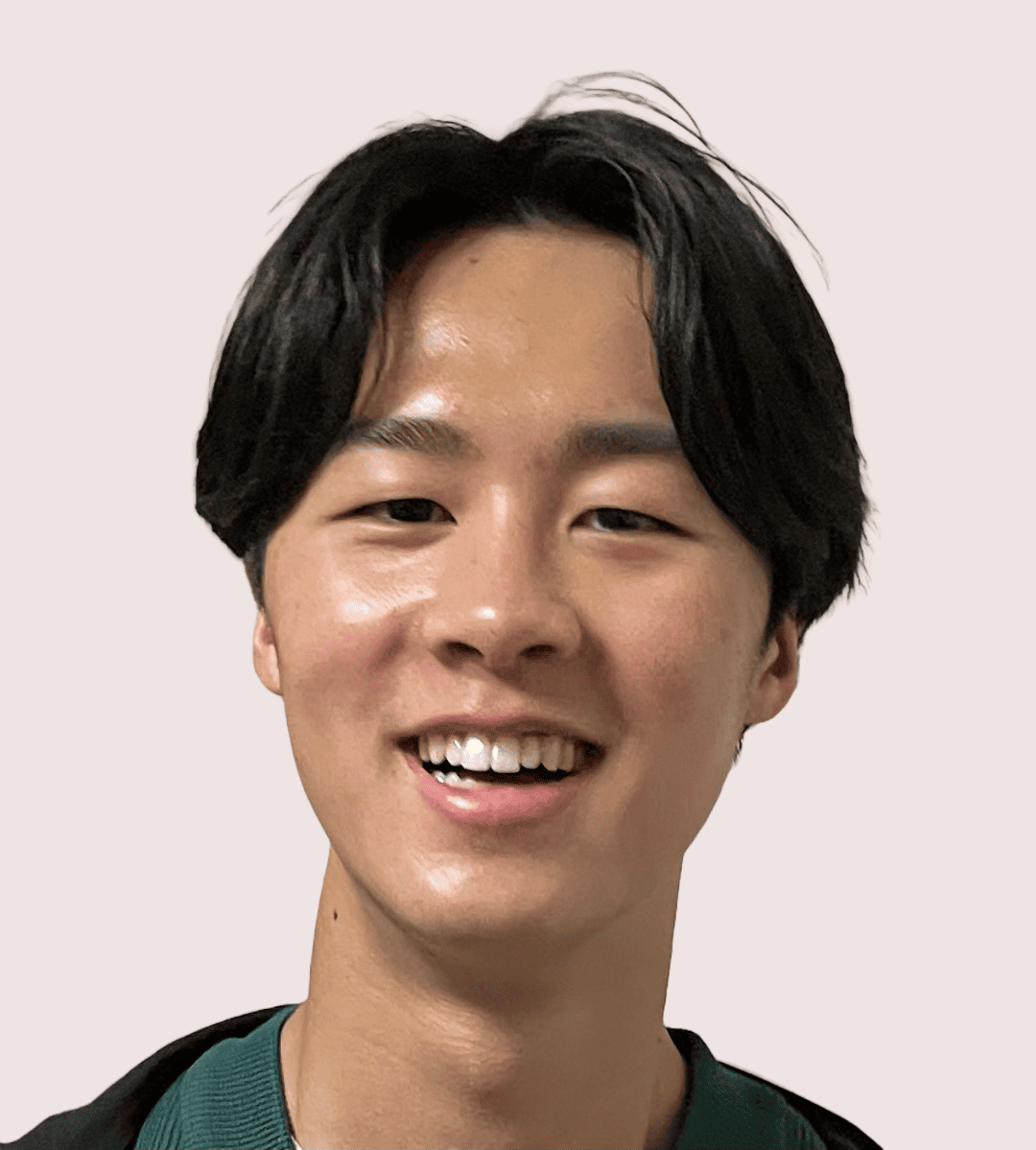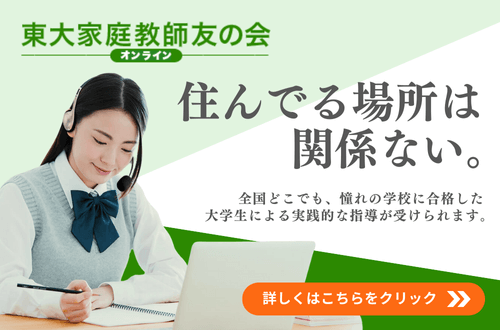![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1.馬渕教室についていけない原因とは?多くのご家庭が抱える「3つの壁」

①難しくて終わらない宿題の量
馬渕教室は中学受験を見据えてカリキュラムを設計しており、小学校で学ぶ内容に加えて中学受験の対策に特化した内容も数多く学びます。
このためどうしても宿題の量は多く、そして内容も難しくなります。
毎日の授業の予習・復習のみならず、定期的なテスト対策、長期休暇中の課題など、膨大な量の宿題をこなす必要があります。
時間管理能力や自己管理能力がまだ十分に身についていない小学生にとっては、この量の宿題をこなすことは容易ではありません。
少しでも宿題を溜めるようになるとそこから一気に溜まる量が増える悪循環に陥る可能性があります。
この状態になってしまいますと、復習の効率が悪くなるため成績が下がっていきます。
②ハイスピードな授業進度とクラス落ちへの恐怖
馬渕教室は小学校で学習する内容を短期間で終え、応用問題や発展的な内容に多くの時間を割いて授業をします。
そのため、基礎が十分に定着していない生徒様は、途中でつまずいてしまう可能性が高くなります。
また、授業内容の理解は出来ている場合でも、クラス落ちへの恐怖はいつでもつきまといます。
特に上位のクラスほど、周囲のライバルは手ごわく、少しでも穴があるとそこからクラス落ちになってしまう可能性があります。
③頑張っているのに成績が上がらない焦り
馬渕教室についていけないと感じる生徒様の中には宿題をしっかりこなし、授業の予習復習もしっかりこなしているはずなのになかなか成績が上がらないと焦っている方もいると思われます。
そういった生徒様の場合、いわゆる「我流」に陥っている可能性があります。
自分に合ってなおかつ効果のあるやり方を見つけられなければ、たとえ机に向かって勉強していてもうまくいかないことがあるのです。
もし、これらの壁をご家庭だけで乗り越えるのが難しいと感じる場合は、馬渕教室のカリキュラムを熟知したプロの力を借りるのも一つの手です。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
2.【学年別】馬渕教室が「きつい」と感じてしまう理由
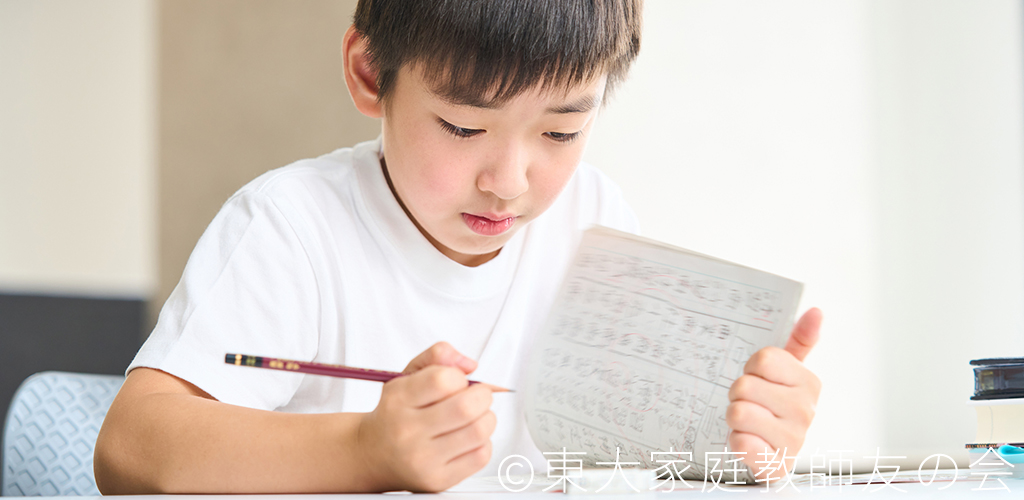
①小学4年生|学習習慣と抽象概念の壁
小学4年生の場合、中学受験の勉強を始めたばかりで、まだ学習習慣が身についていない生徒様が多くいます。
そのため、授業のペースについていけなかったり、宿題をきちんとこなせなかったりすることがあります。
また、抽象的な概念の理解が難しく、算数の図形問題や理科の実験などでつまずくケースも見られます。
②小学5年生|難易度急上昇とプレッシャー
小学5年生になると、学習内容がさらに高度になり、難易度も上がります。
算数では、割合や速さといった抽象的な概念が登場し、理科では、物理や化学の分野も扱われるようになります。
これらの内容を理解するには、高度な思考力や応用力が必要となるため、基礎がしっかりしていない生徒様はついていくのが難しくなります。
また、この時期から受験に対する意識が高まり始め、精神的なプレッシャーを感じる生徒様も増えてきます。
③小学6年生|過去問演習での点数の伸び悩み
小学6年生は、受験本番に向けて、過去問演習や志望校別の対策など、より実践的な学習に取り組む時期です。
これまでの学習内容を総復習し、応用力を高める必要があります。
しかし、それまでの学習内容が十分に定着していない生徒様は、過去問を解いてもなかなか点数が伸びず、自信を失ってしまうことがあります。
また、受験が近づくにつれて、精神的な負担も大きくなり、集中力を維持できなくなる生徒様もいます。
3.馬渕教室の授業についていくには?成績を上げる学習のコツ

馬渕教室のハイレベルな授業についていくためには、生徒様自身がどのように学習に取り組むべきなのでしょうか。
学年を問わず共通する学習法と、学年別の学習法について解説します。
①全学年共通:宿題の優先順位付け(取捨選択)と復習サイクル
保護者がまず行うべきは、子どもの学習状況を把握することです。
授業の理解度、宿題の取り組み方、テスト結果などを観察し、つまずいているポイントを見つけましょう。多くの場合は宿題が終わらずに苦労されていると思われます。
馬渕教室の宿題には難しいものも含まれており、愚直にその全てをやろうとすると睡眠時間を削ることになってしまいます。
小学生の睡眠時間が貴重であることは言わずもがなですので、宿題に優先順位をつけることを検討しましょう。
具体的には、「基本問題はちゃんと解く、難問は思い切って捨てる」方針をとるとよいです。
基本問題がしっかり解けると応用問題が解けるようになるので、やがて入試本番の難問レベルでも解けるようになるでしょう。
②【学年別】今日からできる対策のコツ
(1)小学4年生|基礎学力と習慣化
小学4年生の場合は、まず学習習慣を身につけることを目標にしましょう。
毎日決まった時間に机に向かい、宿題や復習を行う習慣をつけることが大切です。
また、基礎的な内容を確実に理解することも重要です。漢字や計算などの基礎学力をしっかりと身につけることで、その後の学習がスムーズに進むようになります。
(2)小学5年生|応用力強化と苦手克服
小学5年生の場合は、応用力を高めることを意識した学習に取り組みましょう。
基礎的な内容を理解した上で、さまざまなパターンの問題を解くことで、応用力を高めることができます。
また、苦手な分野を克服することも重要です。苦手な分野を放置すると、さらに理解が難しくなり、悪循環に陥ってしまいます。
苦手な分野は、基礎から丁寧に学習し、一つずつ克服していくようにしましょう。
(3)小学6年生|実践演習と解き直し分析
小学6年生の場合は、実践的な学習に力を入れましょう。
過去問演習や志望校別の対策など、受験本番を意識した学習に取り組むことが重要です。
過去問演習では、時間配分や解く順番なども意識しながら、本番さながらの緊張感を持って取り組むようにしましょう。
また、間違えた問題は、必ず解き直し、なぜ間違えたのかを分析することで、弱点を克服することができます。
優先順位付けやスケジュールの管理は、親子関係だからこそ喧嘩になってしまうこともあります。
第三者が間に入ることで、スムーズに学習習慣が定着するケースは少なくありません。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4.ご家庭でのサポートと「塾フォロー」という選択肢

保護者様がご家庭で行うべきサポートは多岐に渡ります。
ここでは、家庭でのサポート方法と、それでも解決しない場合の『家庭教師(塾フォロー)』という選択肢について解説します。
①保護者様ができる具体的な声かけと環境づくり
まずは、学習状況を観察し、つまずきを把握しましょう。
「わからない所はない?」と優しく声をかけ、否定せずに共感することが大切です。
宿題は「早くしなさい」と急かすのではなく、「どれからやる?」と計画を立てさせ、主体性を促します。
解けない問題は答えを教えず、ヒントを出して一緒に考えましょう。テスト結果が悪くても頭ごなしに叱らず、努力の過程を褒めてから改善策を話し合います。
また、静かな学習環境や生活リズムの整備も不可欠です。
親も一緒に学ぶ姿勢を見せ、「頑張ったね」と具体的に認めることで、生徒様の自信とやる気を引き出しましょう。
②馬渕教室の対策に「家庭教師」が有効な理由
上記の内容を保護者様が全て実践して精力的にサポートしたとしても、上手くいかない場合もあると思われます。
両親ともに忙しい共働き家庭であればなおさらそうですし、そもそも高学年では扱う内容もハードです。
そこで塾のフォローを第三者にしてもらうという選択肢が有用になってきます。特におすすめなのが家庭教師です。
家庭教師は生徒様のスケジュール管理に強いという特徴があります。家庭に入って授業をするので、生徒様のモチベーションの維持・管理に特に効果的です。
また、具体的な学習プランの設定にも役立ちます。
とくに宿題の取捨選択や今実践しているものより効果の上がる学習法について、懇切丁寧に解説してくれる家庭教師は必ずや生徒様が馬渕教室についていくための助けとなるでしょう。
東大家庭教師友の会には、実際に馬渕教室に通い、難関中学を突破した教師が多数在籍しています。後輩である生徒様のつまずきポイントを正確に理解し、最適な指導を行います。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
5.馬渕教室からの転塾はあり?失敗しないための検討ポイント

馬渕教室に通っているものの、どうしてもついていけない、あるいは、生徒様の学習スタイルに合わないと感じる場合、転塾を検討することも一つの選択肢です。
しかし、転塾は生徒様の学習環境を大きく変えることになるため、慎重に検討する必要があります。
①転塾を考える前に確認すべきこと
まず、なぜ転塾を検討するのか、その理由を明確にしましょう。
授業についていけないのか、宿題が多すぎるのか、クラスの雰囲気が合わないのか、など、具体的な理由を洗い出すことが大切です。
理由を明確にすることで、転塾先を選ぶ際の判断基準が明確になります。
次に、生徒様の意見をしっかりと聞き、転塾についてどう思っているのかを確認しましょう。
生徒様が転塾に前向きなのか、それとも今の塾に留まりたいと思っているのか、生徒様の気持ちを尊重することが大切です。
生徒様が納得しないまま転塾してしまうと、転塾先でもうまくいかない可能性が高くなります。
そして、転塾先の候補をいくつか選び、それぞれの塾の情報を収集しましょう。
授業内容やカリキュラム、クラスの雰囲気、講師の質、費用などを比較検討し、生徒様に合った塾を選ぶことが重要です。
体験授業や説明会に参加し、実際に塾の雰囲気を肌で感じることも大切です。
また、転塾する時期も重要なポイントです。
一般的には、学年の切り替わりや長期休暇のタイミングで転塾するケースが多いですが、生徒様の学習状況や志望校の受験スケジュールなどを考慮し、最適な時期を選ぶ必要があります。
②失敗しない転塾先の選び方・チェックリスト
転塾先を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしましょう。
| 授業内容・カリキュラム | 生徒様の学力や学習スタイルに合った授業内容・カリキュラムであるかを確認しましょう。難易度が高すぎる、あるいは低すぎる塾では、生徒様の学習意欲を低下させてしまう可能性があります。 |
| クラスの雰囲気 | 少人数制なのか、大人数制なのか、競争意識が強いのか、協調性を重視するのか、など、クラスの雰囲気が生徒様に合っているかを確認しましょう。 |
| 講師の質 | 講師の経験や実績、指導力、生徒への接し方などを確認しましょう。体験授業や説明会で、実際に講師と話してみるのも良いでしょう。 |
| 費用 | 入塾金や授業料、教材費など、費用が家計に負担にならないかを確認しましょう。 |
| 通塾の利便性 | 自宅や学校からの距離、交通手段などを考慮し、通塾しやすい場所にあるかを確認しましょう。 |
| サポート体制 | 個別面談や進路相談など、保護者へのサポート体制が充実しているかを確認しましょう。 |
転塾は、生徒様の学習環境を大きく変える重要な決断です。焦らずに、じっくりと検討し、生徒様にとって最善の選択をするようにしましょう。
もし、転塾について迷うことがあれば、塾の先生や学校の先生、または専門家などに相談することも検討しましょう。
まとめ|馬渕教室についていけない悩みを解消し、中学受験を成功させるために
馬渕教室は、ハイレベルな授業と多くの宿題で知られる難関中学受験塾です。
ついていくためには、生徒様自身の努力はもちろんのこと、保護者様のサポートも不可欠です。
そして、保護者様のサポートで足りないところも出てくるため、場合によっては家庭教師の利用や転塾の検討も必要になることは示した通りです。
東大家庭教師友の会には馬渕教室出身で、現在京大や阪大などの難関大学に在籍する家庭教師が多数揃っています。
彼らは馬渕教室のカリキュラムを知り尽くしており、馬渕教室についていくための方法を熟知しています。まずはお気軽にご相談ください!
▼当会では、馬渕教室生の指導も承っています。
中学受験指導ができる家庭教師をご紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
小学生の生徒様の声
中学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会【関西】の特徴
当会には、京大生約2,200名、阪大生約1,800名、神戸大生約2,200名が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
オンラインでの受講も可能です
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る
ご利用の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
中学受験に強い家庭教師をお探しなら
あわせてチェック|馬渕教室の関連記事