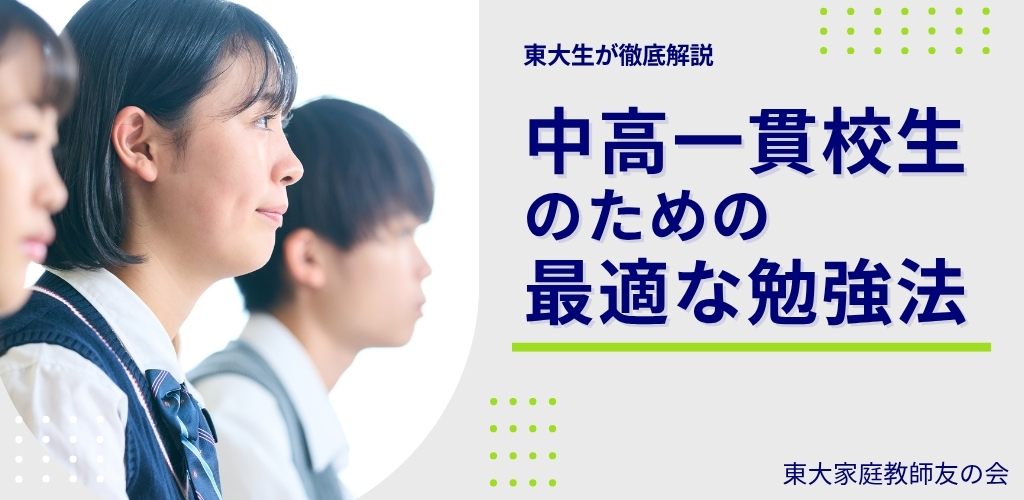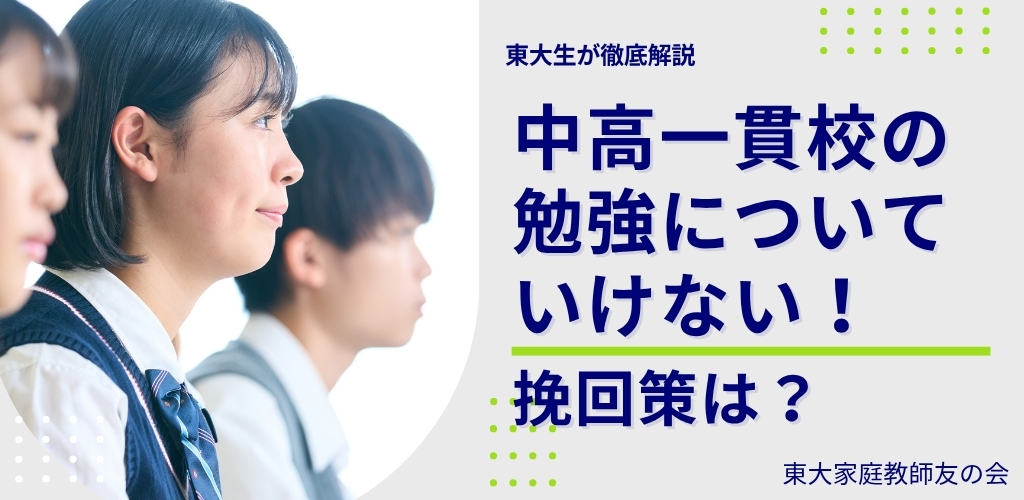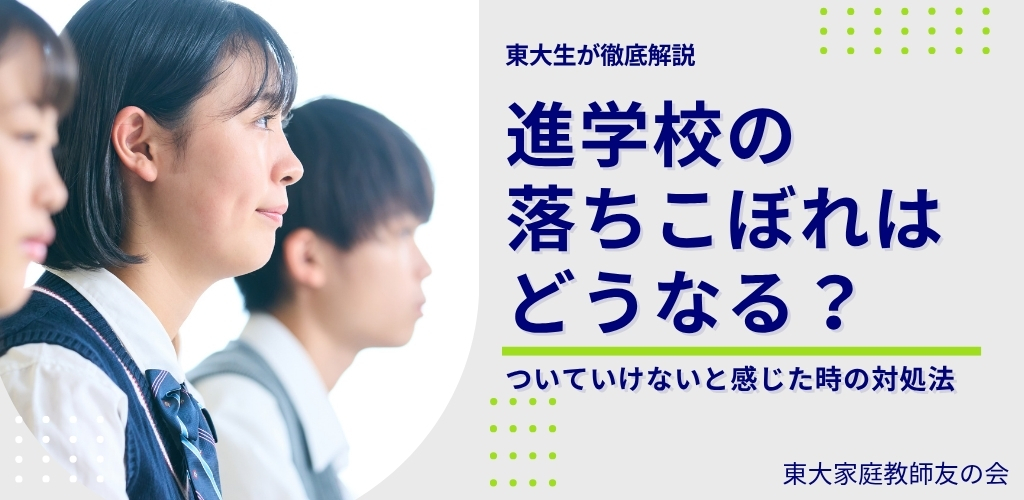1. 中高一貫校生のよくある悩み

中高一貫校に通う生徒様は、6年間という長いスパンで学習に取り組める反面、ペース配分やモチベーションの維持に悩むケースも少なくありません。特に、学校ごとの独自カリキュラムに戸惑いを感じたり、周囲との学力差に焦りを感じたりすることもあるでしょう。
そうした中高一貫校ならではよくある悩みをご紹介します
①授業スピードが速くてついていけない
「授業の進みが早すぎて、ちょっとでも分からないと置いていかれる感じがする…」
「みんな理解しているのに、自分だけついていけてない気がして焦る…」
②勉強のやる気が続かない・モチベーションが保てない
「やらなきゃって思うけど、なんだか気持ちが続かない…」
「目標がハッキリしないから、なんとなくダラダラしてしまう…」
③定期テストが難しくて点が取れない
「ちゃんと勉強しているつもりなのに、全然点が取れない…」
「テストのレベルが高すぎて、やる気がなくなる…」
このように、中高一貫校では授業のスピードや難易度の高さ、長期間の学習へのモチベーション維持など、特有の悩みを抱える生徒様が少なくありません。
次の章では、中高一貫校出身で東京大学に在籍している私だからこそ伝えられる「中高一貫校生に効果的な勉強法」をわかりやすくご紹介します。
2. 中高一貫校生に効果的な勉強法

中高一貫校の悩みを解決するためには、勉強方法に工夫が必要です。
ここでは、中高一貫校での勉強の基本となるポイントを、3つご紹介します。
①宿題と復習に優先的に取り組む
1つめのポイントは、「宿題と復習に優先的に取り組む」ことです。
まず、最も優先すべきは、宿題や小テストの勉強です。
中高一貫校では、学校ごとに独自のカリキュラムで授業が進んでいくことが多いです。そして宿題や小テストは、そのカリキュラムをこなすために必要な実力がつくように出されています。
予習が重要な授業であれば予習が重点的に宿題として出されますし、復習が重要な授業であれば、復習を中心とした宿題になります。
まずは宿題にしっかり取り組みましょう。
その上で余力があれば、復習をしておくと良いでしょう。授業のノートを見返すだけでも、内容が記憶に定着しやすくなります。
②「受け身」ではなく「自分から」の学習
2つめのポイントは、「わからないところは、積極的に先生に聞く」ことです。
中高一貫校では、高校受験がない分、授業の進度が早く、内容も高度になる傾向があります。そのため、ただ先生の話を聞くだけの「受け身」の学習では通用しにくく、「自分から学ぶ姿勢」が重要です。少しでも疑問が浮かんだら、すぐに先生に聞いてみましょう。
③宿題はなるべく学校で完結
3つめのポイントは、「できるだけ『学校で宿題を終わらせる』という気持ちを持つ」ことです。
校風によってある程度違いはありますが、中高一貫校は、比較的学習しやすい環境であることが多いです。休み時間や放課後のスキマ時間を活用し、できそうな宿題は終わらせておくと良いでしょう。
また、「学校で宿題を終わらせる」という気持ちを持つことで、授業中の集中力もアップします。
効率よく勉強することができれば、自由時間を部活や趣味に存分に使うことができ、生活にメリハリもつきます。
3. 学年別のおすすめ勉強法

次に、中1から高3までの学年ごとに意識すべき勉強のポイントをまとめました。
「今の自分に必要なこと」だけを押さえておけば、ムリなく効率よく学力アップが狙えます。
中学1年生:まずは勉強習慣の定着
中学1年生は、小学校からの大きな環境の変化に戸惑いやすい時期です。
この時期に「学校生活が楽しい」と感じられるかどうかが、その後の学習意欲にも大きく影響します。
そのため、中学1年生のうちは「無理をせず、まずは勉強習慣をつけること」が最も大切です。以下の3つのポイントを意識すると良いでしょう。
(1)無理をしない
中高一貫校では中学から大学受験を見据えたカリキュラムが組まれていますが、まずは心身の健康が第一です。
無理をすると学校が楽しくなくなってしまい、勉強へのモチベーションも下がってしまいます。疲れたときはしっかり休むことも大切です。
(2)宿題と小テストの勉強にしっかり取り組む
この頃から宿題と小テストをおろそかにしないことで、基礎的な勉強のルーティーンを構築することができます。
特に中学1年生の夏前までは授業の進度がそこまで速くないため、丁寧に取り組めば良い成績を取ることができ、好循環を作れます。
(3)苦手教科はすぐに先生に相談する
もしこの時点で苦手な教科があった場合は、すぐに先生に相談するなどの対応をとると良いでしょう。特に英語や数学といった教科においては、中学1年生で学ぶ内容が、その後の大学受験までの基礎になります。今の時点できちんと理解を積み上げることが大切です。
中学2年生:苦手の芽を早期に摘む
中学2年生は、中学1年生と比べてかなり学校に慣れてくる時期です。その分、中だるみが出てきたり、勉強についていきにくくなったり、人間関係のトラブルが出てきたりと、悩むことも増えてきます。
そこで、勉強法としては、以下を意識してみましょう。
(1)自分なりの目標を立てる
定期テストや英検など、自分なりの目標を立て、そこに向かって頑張るのがおすすめです。
「少し背伸びすれば届きそうな目標」を立てることを意識すると良いでしょう。
(2)苦手教科ときちんと向き合う
中学2年生は、苦手教科がはっきりしてくる時期でもあります。もし苦手だと感じる教科があれば、時間をとって1年生から遡っておくと良いです。動画授業や学習アプリ、塾・家庭教師なども活用すると良いでしょう。
(3)得意教科は先取りしてみる
苦手教科よりは優先度は下がりますが、得意教科は少し先取りしてみるのも手です。学校の授業をより深く理解できるようになり、自信につながります。
中学3年生:中高一貫校ならではの受験準備
中高一貫校と言えど、中学3年生は中学の最高学年であり、部活や委員会、生徒会などの課外活動が忙しくなることが予想されます。
一方で、授業は進度の早さから高校生の範囲に入っていることも多く、気を抜くと授業についていくのが難しくなるでしょう。
そのため、うまく両立していくことを意識した勉強が大切になります。
(1)メリハリをつける
中学3年生は、「授業中や勉強中は集中し、それ以外の時間は思う存分楽しむ」という感覚を養っていく良い機会です。
集中できるルーティーンや環境を探してみましょう。
(2)スキマ時間を活用する
忙しい中で学習の時間をとるには、工夫が必要です。そこで、スキマ時間を活用することを意識してみましょう。
休み時間にささっと小テストの勉強をしておく、放課後に宿題を終わらせてから帰るなど、ちょっとした工夫を積み重ねることが大切です。
(3)「高校内容の基礎」に今から取り組む
中学3年生の内に高校内容の基礎を完成することができれば大学受験で非常に有利です。
英語では、英文法の基礎をしっかりと身につけ、語彙力を高めるために英単語や英熟語を増やしていくことを目指しましょう。
また、数学では「数学I」および「数学A」の前半部分の内容を理解し、問題演習を通じて定着を図ることを目標としましょう。
高校1年生:受験を見据えた勉強の習慣化
高校1年生は、受験を見据えた各教科の勉強が本格化してくる時期です。時間割も変化し、理科・社会などのウェイトが大きくなってきます。
少しずつ勉強に力を注ぐ割合を増やしていくと良いでしょう。
(1)英語・数学は、宿題以外にも成績UPのための勉強をする
特に国公立大学の受験を検討している場合、英語と数学は文理を問わず重要です。
中学までは宿題をベースとした学習がメインでしたが、高校1年生からは本格的に授業以外でも勉強をしておくと良いでしょう。
(2)理科・社会・古典・英単語はこまめな復習で知識を定着させる
理科・社会・古典が本格化するのは高校2年生以降ですが、今のうちから知識を定着させておくことで、高校2年生以降がぐんと楽になります。
英単語もまとめて、スキマ時間にこまめに復習しましょう。
(3)現代文は要約の練習が効果的
現代文は重要な教科ですが、他の教科と比べて時間が割きづらい教科でもあります。
そこでおすすめなのが要約です。授業で出題された文章はもちろんのこと、その日見た番組の内容などでも構いません。誰かに話すつもりで内容を手短にまとめる練習をすると、要点をつかむ訓練になります。
また、進路は少しずつ考え始めると良いでしょう。学校のシステムにもよりますが、少なくとも文理は高校2年生では決める必要があります。
高校2年生:文理に合わせて集中特化
高校2年生では、文理も分かれ、いよいよ受験勉強が始まります。
中高一貫校では先取り学習もあるため、高校2年生時点で高校3年生までの学習内容が終了することも少なくありません。
志望校対策以外の勉強は、高校2年生で終わらせるつもりで臨むと良いでしょう。
(1)文系:英国(数)は高校2年生で仕上げるつもりで学ぶ
中高一貫校であっても進度が遅い可能性があるのが、社会です。
一方、英語・国語・数学では、他に比べて1年分のアドバンテージがあることが多いです。
そのため、文系の場合は、高校2年生で英国(数)を仕上げる心づもりで勉強すると良いでしょう。
(2)理系:数学と理科に集中する
理系にとっては、高校2年生が最も厳しい年と言っても過言ではありません。
場合によっては数IIIと理科の両方に取り組む必要があり、学習量も難易度も格段に増えます。
ここで数IIIと理科の苦手をなくすことができれば、非常に有利になります。
(3)メリハリをつけて勉強する
学校によっては、高校2年生で部活は引退と決まっていることがあります。そのため、高校2年生は部活に熱を入れたくなる年でもあります。
両立のために、これまで以上にメリハリのついた生活を意識しましょう。
高校3年生:志望校に合わせた逆算学習
高校3年生は、受験勉強の仕上げの年です。人によって時間割が変化したり、受験方法によっては総合型選抜などの対策が必要であったりと、個人での勉強が増えていきます。
そのため、以下のような点に気をつけて勉強をすると良いでしょう。
(1)自分の現在の実力と勉強の目的を把握する
一人ひとりに必要な勉強が異なるため、自分のことを自分でしっかりと把握している必要があります。
先生にも適宜相談しながら取り組みましょう。
(2)似た進路の友人と情報を共有する
可能であれば、自分と似た進路の友人と情報を共有しながら受験勉強を進めると良いでしょう。やる気アップにもつながります。
その他、志望校や使用する教科に合わせて、工夫しながら学習を進めると良いでしょう。
まとめ
この記事では、中高一貫校での効果的な勉強法をご紹介しました。
学年ごとのポイントを押さえながら、自分に合った勉強法を見つけていくことが大切です。
1人では効率の良い勉強法が分からないという場合には、中高一貫校に理解のある家庭教師を活用し、学力アップを目指すことも検討してみてください。
▼当会では、中高一貫校生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
あわせてチェック|中高一貫校の勉強法を解説
東大家庭教師友の会をもっと知る