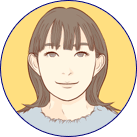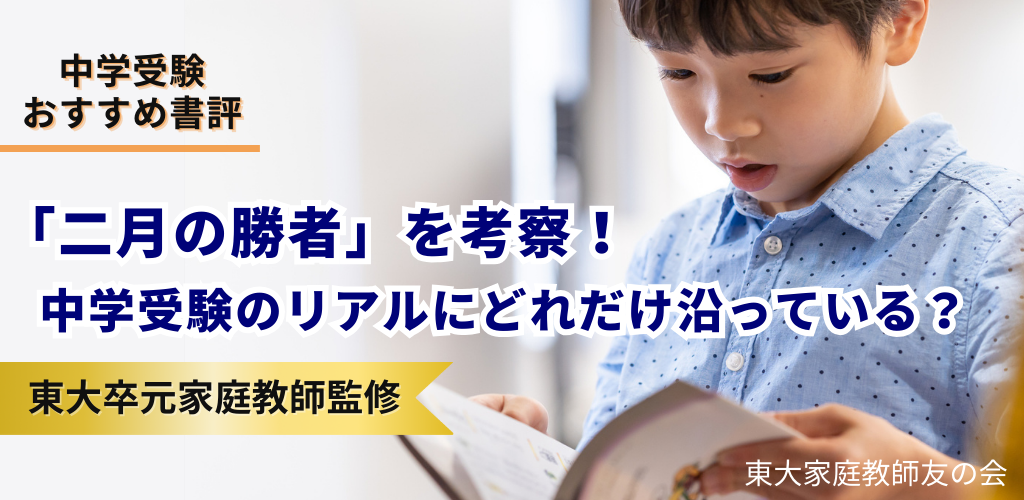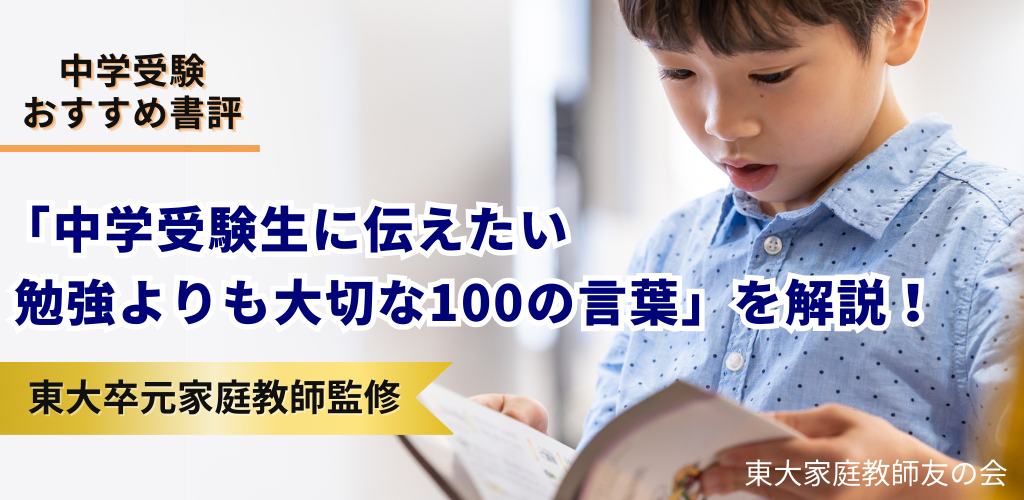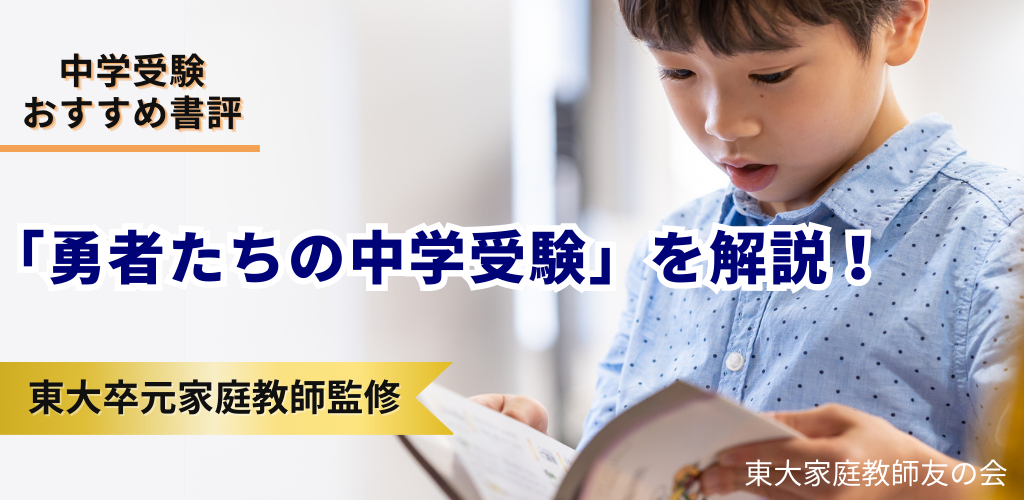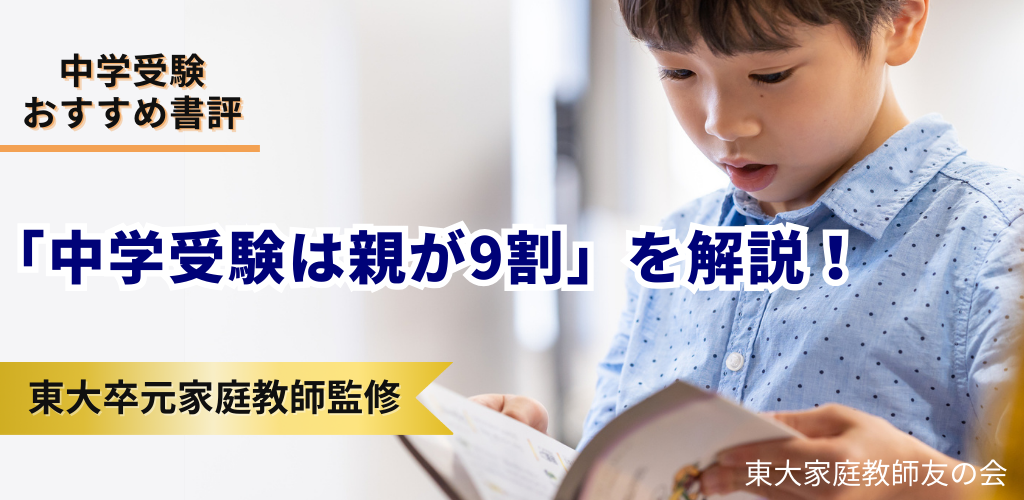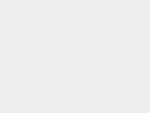![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
1. 【中学受験】併願校は何校受ける?「七五三」の法則とおすすめの内訳

中学受験の併願校は、5校から8校程度を出願するのが一つの目安です。
中学受験では「七五三(しちごさん)」という言葉が、縁起担ぎや目安として使われることがあります。これは「7校出願、5校受験、3校合格」できると理想的、という意味合いです。
併願校を検討する際は、偏差値や難易度に応じて、一般的に以下の4つのカテゴリーに分けて考えます。
・チャレンジ校:現在の学力よりも偏差値がかなり高い、挑戦となる学校
・実力相応校:模試の合格可能性が50%〜80%程度の、学力に見合った学校
・安全校:模試で合格可能性が80%以上ある、合格をしっかり確保するための学校
・腕試し校:本番の雰囲気に慣れるため、または早めに合格を得て精神的な余裕を持つために受験する学校
これらをバランス良く組み合わせることが重要です。
おすすめの内訳は以下です。
・第1志望校:1校
・チャレンジ校:1校
・実力相応校:1〜2校
・安全校:1〜2校
・腕試し校:1〜2校
第1志望校がチャレンジ校の場合、不合格が続くリスクを避けるため、実力相応校と安全校を厚め(多め)に設定するのが一般的です。
第1志望校が実力相応校の場合は、実力相応校をしっかり確保しつつ、チャレンジ校を2校に増やすなど、挑戦の機会を増やす組み方も可能です。
2. 【中学受験】併願校選び「2つの戦略」

併願校を選ぶ際は、合格を確実にするための戦略的な「型」を知っておくことが重要です。ここでは、特に意識すべき2つの戦略をご紹介します。
①第1志望~第3志望までの学校に合格する
併願校選びで最も優先すべきは、第1志望校から第3志望校(納得校)のいずれかには合格できるプランを組むことです。
中学受験で第1志望校に合格できるのは、一般的に「受験者の3人に1人」と言われる厳しい世界です。もし不合格が続くと、生徒様は自信を失い、その後の試験にも悪影響が出かねません。
「第2・第3志望校」の準備では、以下の2つの視点で学校を選びます。
「第2・第3志望校」の準備
・第1志望校が不合格でも「ここなら通いたい」と思える学校を第2・第3志望校に設定する
・第2・第3志望校は実際に入学した場合の満足度を親子でよく話し合っておく
「合格体験」のための安全校
・現在の偏差値より10~15程度低い「安全校」も受験する
・早い段階で「合格した」という経験を積む
生徒様の可能性を信じるあまりチャレンジ校ばかりを受験させるのではなく、「進学しても良いと思える学校」と「確実に合格を得る学校」をバランス良く組み合わせることが大切です。
②合格率を上げる「複数回受験」を活用する
2つ目の戦略は、「複数回受験の優遇制度」が設定されている学校を積極的に活用することです。学校側が「第一志望として強く希望してくれる受験生」を評価するため、同じ学校を複数回受験することで、合格の可能性が上がる制度(優遇制度)を設けている学校が多いためです。
優遇制度の内容は学校によって様々ですが、主に以下のようなケースがあります。
加点方式:2回目以降の試験の合計点に、ボーナス点(例:10点加点など)が加算
高得点採用方式:1回目と2回目で受験した教科のうち、点数が高い方の結果を合否判定に採用
繰り上げ合格の優遇:合格ボーダーライン上に複数の生徒が並んだ場合、複数回受験している生徒様が優先的に繰り上げ合格
学校が設けているルールを戦略的に利用して、生徒様の実力に加えて「制度」の面からも合格を掴み取るチャンスを広げましょう。
3. 【中学受験】併願パターンの組み方|1月午後入試で合格シミュレーション

首都圏での中学受験では、併願パターンを工夫することで、精神的な余裕を持って本番に臨めます。
①1月中に「腕試し校(千葉・埼玉)」を受験する
中学受験は一般的に2月1日が本番スタートですが、その前の1月中に受験可能な千葉県・埼玉県の学校に挑戦する戦略です。例としては、埼玉県の栄東中学校が例年1月10日頃、千葉県の渋谷教育学園幕張中学校が例年1月20日頃に行われています。
期待できる効果
◎2月1日の本命校受験前に合格を一つでも得ておくと、リラックスして本番に臨める
◎入学の意思がなくても、試験会場の独特な雰囲気や緊張感に慣れる
◎体力に不安がある場合、受験日程を分けることで負担を軽減できる
注意点
・受験日が早まるため、計画の見直しが必須
・「基本問題の復習」と「過去問演習」のどちらを優先するか判断
・試験当日にベストコンディションで臨めるように体調管理
②2月1日・2日に「午後入試(東京・神奈川)」を活用する
約20年前に導入された「午後入試」により、2月1日や2日に、午前と午後の2校を受験することが可能になりました。
期待できる効果
◎1日で2校受験できるため、早期に合格を勝ち取るチャンスが単純に増える
◎その日の夜にWEBで合否が判明することが多く、翌日以降の受験スケジュールをすぐに調整できる
◎2教科または1教科入試が多く、試験時間が短い傾向がある
注意点
・1日に2校受験するため、体力&気力が大きく消耗
・合格者数は午前入試より少ない傾向がある
・午前入試の会場から午後入試の会場までの移動手段の確認
・昼食をどこで、どのように取るか事前に決めておく
③2月2日までに「合格」を掴む併願パターンを考える
1月の腕試し校も含め、2月2日までに最低1校の合格を確保するパターンを考えます。2月3日以降は倍率が高くなるため、生徒様のモチベーション維持も難しくなります。
期待できる効果
◎2月1日の合否がその日の夜にWEBで判明するため、翌日以降の併願スケジュールをすぐに修正できる
◎2月1日に合格できれば、自信を持って2月2日にステップアップし、レベルの高い学校に挑戦できる
◎チャレンジ校から安全校まで幅広く用意しておくと、どんな結果でも慌てずに試験に挑める
注意点
・もし2月1日が不合格なら、2月2日は受験校のレベルを下げて「確実な合格」を掴みにいける
・臨機応変に動けるよう、2月2日以降は願書を2校以上出しておく
・模試の結果が不安なら、2月1日はあえてハードルの低い学校から始め、初日の緊張の中で合格を掴む経験を優先する
・併願スケジュールで困ったら塾や家庭教師の先生に相談し、客観的なプランを組んでもらう
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4. 【中学受験】併願校はいつ頃決定? 検討開始から最終決定までのスケジュール

併願校をいつまでに決めるべきか、目安となるスケジュールを「検討開始」と「最終決定」の2つの時期に分けて解説します。
(1)併願校の「検討開始」時期(小5~小6夏)
第一志望校が決まってから、本格的に併願校の検討を始めましょう。
検討開始時期の目安
①小5の春頃~:第一志望校の検討を開始。この時期に、併願校の「候補」を10校ほどリストアップ
②小6の1学期頃:第一志望校を決定。第一志望校に選ばなかった候補を中心に、本格的な併願校の検討を開始
③小6の夏休み頃:この時期までに併願校の「仮決定」ができると理想
夏休みまでに仮決定するメリット
・過去問対策に集中できる
・成績変動に対応できる
・学校説明会や文化祭に参加して最終確認できる
(2)併願校の最終決定時期
最終決定時期の目安
①小6の11月まで:第一志望校の最終決定
②小6の12月まで:模試の結果や本人の意向を踏まえ、併願校をすべて最終決定
5. 【中学受験】併願校の「話し合い方」と「すり合わせ」3つのコツ
併願校は複数校選ぶため、生徒様との話し合いがスムーズに進まないこともあるでしょう。生徒様の意向を引き出しつつ、併願校のバランスを調整するための「話し合い」と「すり合わせ」の3つのコツを解説します。
①いつから話し合いを始めるべきか
併願校についての話し合いは、第一志望校の検討を始めるのと同じ、小学5年生の春ごろからスタートするのが理想です。
早めに話し合いを始めることには、大きなメリットがあります。まず、第二、第三志望校の候補が絞れていれば、小学5年生の夏から秋にかけて、効率的に学校見学を進められます。さらに、早い段階で過去問を下調べできるため、志望校と併願校の傾向に合わせた学習計画を立て、試験対策にじっくりと時間を費やせます。
逆に、小学6年生になると受験勉強も本格化し、併願校について親子でゆっくり話し合う時間的な余裕がなくなりがちです。小学5年生のうちに、生活リズムを整えながら、進路について親子で気軽に意見交換できる時間を作るよう心がけましょう。
②生徒様の意向をどう引き出すか
併願校選びは、生徒様の「学校選びの基準」を明確にすることから始まります。これは、志望校について親子で話し合うプロセスの中で、自然と見えてくるはずです。
基準が見えてきたら、保護者様は各学校の長所・短所を客観的に伝え、生徒様に併願校を検討してもらいましょう。その際、一方的に情報を与えるだけでなく、「その学校に何を期待しているか」「何に不安を感じているか」を丁寧にヒアリングすることが重要です。
生徒様ご自身の目標や価値観、あるいは将来の夢なども聞き出しながら、それらを踏まえて併願校を決めていくのが理想です。また、学校選びは流動的であることを理解しておきましょう。実際に学校見学に行くと、生徒様の印象が一気に変わり、それまで併願校だった学校が第一志望校に繰り上がることもあります。まれに、入試1ヶ月前に志望校が変わるケースもあるほどです。
どのような経緯をたどったとしても、最終的には生徒様の意向を尊重し、「ご自身で志望校と併願校を決める」というプロセスを大切にしてください。
③生徒様の意向と親の意向をどうすり合わせるか
併願校のすり合わせは、生徒様の動機づけと、保護者様による「合格を確実にする」ための現実的な調整が重要です。生徒様は第一志望校合格を信じ、併願校(特に安全校)の受験を嫌がることがあります。しかし、希望通りチャレンジ校ばかりではリスクが高すぎます。
まず、併願校を前向きに検討してもらう工夫をしましょう。「第一志望校と似ている点」や「具体的な長所」を伝え、「この学校で頑張りたい」という気持ちを引き出してください。
受けたい学校が、難しいところばかりになっているなら、「最低でも1校は合格する」必要性を早めに伝え、希望通りにいかない可能性も話し合います。
もし意向が合わなければ、「なぜ中学受験をするのか」という原点に立ち返り、家庭の方針を再確認してください。「親が選ぶ1校」「生徒様が選ぶ1校」といったお互いの意見を組み合わせるのも、良い方法です。生徒様のお気持ちを第一に尊重しながらも、保護者様は冷静に『合格の可能性』を分析し、ご家庭として納得できる着地点を探ることが大切です。
6. 【中学受験】併願校選び「親のNG行動」失敗談3選

併願校選びでよくある失敗例を3点紹介します。もし当てはまっていたら、保護者様のサポートで早めに軌道修正しましょう。
①併願校がチャレンジ校ばかりになる
問題点
①すべて不合格になるという最大のリスクを抱えることになる
②「落ちるかもしれない」というプレッシャーが常にかかり、生徒様は過度なストレスを感じる
③学習面でも、難関校対策に偏るあまり、基礎学力の定着がおろそかになる恐れがある
対策
・「チャレンジ校は1校だけにする」など、なるべく早めに話し合い、併願校のバランスを見直しましょう
・入学後に周囲との学力差を感じて学校生活に適応できない可能性もあるので、生徒様の精神力や適応力も考慮して判断しましょう
②併願校が安全校ばかりになる
問題点
①「合格はできる」という安心感はあるが、生徒様が本来持っている力を伸ばすチャンスを逃してしまう可能性がある
②試験問題が簡単すぎると、学習意欲の維持が難しくなることもある
対策
・安全校だけでなく、実力相応の適切なレベルの学校(適正校)にも挑戦するよう促す
・生徒様がご自身の力を過小評価しないよう、「将来の目標を高く設定する」などの声がけをして自己評価が下がるのを防ぐ
③塾の先生に薦められるまま併願パターンを採用してしまう
問題点
①塾の先生の提案(合格実績などに基づく)を、ご家庭の方針や生徒様の校風との相性を確認しないまま採用するのは危険である
②学校見学をしないまま入学すると、生徒様が「イメージと違った」とギャップを感じ、学校生活になじめないリスクがある
対策
・受験勉強でどれほど忙しくても、親子で1度は学校見学をする
・見学してイメージと違えば、他の併願校を探しても全く問題ないので見直しをしましょう
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
7. 【中学受験】併願校選びに関するよくある質問

併願校選びに関してよく寄せられる3つの質問と、タイプの異なる学校を併願する際の注意点について解説します。
①生徒様から併願校の意思が出ない場合どうするべきか
生徒様が受験勉強に追われ、併願校について考える余裕がないケースです。以下のサポートをしてあげましょう。
【保護者様のサポート案】
①保護者様が代わりに情報収集し、各学校の特徴をまとめた比較リスト(チャートや表)を作成する。リストには、「入試情報」「通学時間」「共学/別学」「設備」など、生徒様が興味を持ちそうなポイントを簡潔にまとめる。
②受験勉強の休憩中など、生徒様がリラックスしているタイミングでリストを見せ、意思を引き出す。その際に「ここに載っているのは全部素晴らしい学校で、どの学校に行っても楽しい中学生活が送れるよ」と肯定的な声がけをする。
②共学と男子校・女子校は併願できるか
併願は可能です。ただし、入試問題の出題傾向が異なるため対策が必要です。
志願者の層や学校の方針が違うため、入試問題には特色が出ます。一般的に、男子校は理系科目(算数・理科)、女子校は文系科目(国語・社会)の難易度が高い傾向があり、共学校はバランス良く出題する傾向がありました。
そのため、併願する場合は、必ずそれぞれの過去問を解き、出題傾向を把握しておくことが重要です。ただし、近年は変化も見られます。例えば、算数が難化している女子校も増えています。これは、学校側が求める生徒像の変化に伴い、従来の暗記力よりも「思考力」を問う問題が増加傾向にあるためです。
過去問と全く同じ問題が出るとは限りませんから、日々のニュースを見て親子で内容について話し合うなど、世の中のできごとに興味を持ち、思考力を鍛えておくと良いでしょう。
③私立中学校と公立中高一貫校は併願できるか
併願は可能です。しかし、試験内容が大きく異なるため、両立するには入念な準備が必要です。
私立中学校と公立中高一貫校では、試験内容が大きく異なります。多くの私立中学校が4教科(国・算・理・社)の学力入試を実施するのに対し、公立中高一貫校は4教科入試ではなく、「適性検査」および「作文」を実施するのが一般的です。
「適性検査」は、資料の読み取りや記述式の問題が多く、高い読解力・表現力が問われます。また、公立中高一貫校は私立中学に比べて学費が安いため人気が集中し、倍率が非常に高くなるのが特徴です。そのため、合格を目指すのであれば、この適性検査に特化した専門の対策をしっかり練る必要があります。
8. 【2026年2月受験の注意点】サンデーショックに注意
2026年2月入試は、2月1日が日曜日になっている、いわゆる「サンデーショック」の年です。
青山学院中等部や立教池袋中学校、フェリス女学院中学校など、例年2月1日に第1回入試を行いますが、2026年はこれを2月2日(月)に移動します。
この変更により、併願パターンや倍率が、例年の動向とは異なる可能性があるので、注意が必要です。
例えば、男子の場合、例年なら併願できない2月1日校(例:開成、麻布、早稲田など)と、青山学院中等部や立教池袋との併願受験が可能になります。女子の場合も、2月1日校(例:桜蔭、雙葉など)を受験した後、2月2日に青山学院中等部やフェリス女学院を受験するという、新たな併願パターンができます。
塾や家庭教師の先生と、出願先をよく話し合って決めましょう。
▼「サンデーショック」とは?
2月1日が日曜日の場合、一部のミッションスクール(キリスト教系の学校)は、入試日を2月2日にずらすことがあります。日曜礼拝などと入試が重なることを避けるためです。例年とは異なる併願が可能になるため、過去のサンデーショックでも、出願動向への影響が見られました。
9. 【中学受験】最適な「併願パターン」で納得のいく春を!

これまで、中学受験の併願校選びにおける「校数」「戦略」「スケジューリング」「時期」「話し合い方」「NG行動」「よくある質問」について解説しました。
まとめると以下のようになります。
・中学受験の併願校選びは、小5の春から親子で対話と情報収集を始め、家庭の方針を固めることが土台となる。
・「1月校」「午後入試」「複数回受験」などの戦略を活用し、チャレンジ校から安全校までバランス良く組み、2月2日までの合格を目指す
・小6の12月までに、生徒様の意思と合格の現実性をすり合わせ、親子で納得できる最適な併願パターンを最終決定する
志望校と併願校のパターンがスムーズに決まれば、生徒様も保護者様も安心して最後の追い込みである「受験勉強」に専念できます。
この記事で解説したポイントを参考に、ぜひ生徒様にとって魅力的で、かつご家庭の方針にも合った最適な併願パターンを完成させ、親子で納得のいく春を掴み取ってください。
▼当会では、中学受験生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
あわせて読みたい|【東大卒元家庭教師監修】中学受験のいろはシリーズ
こちらもおすすめ|【東大卒元家庭教師が解説】書評シリーズ
小学生の生徒様の声
中学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会の特徴
当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
【学校別】中学受験の入試傾向・受験対策
東大家庭教師友の会をもっと知る
中学受験に強い家庭教師をお探しなら