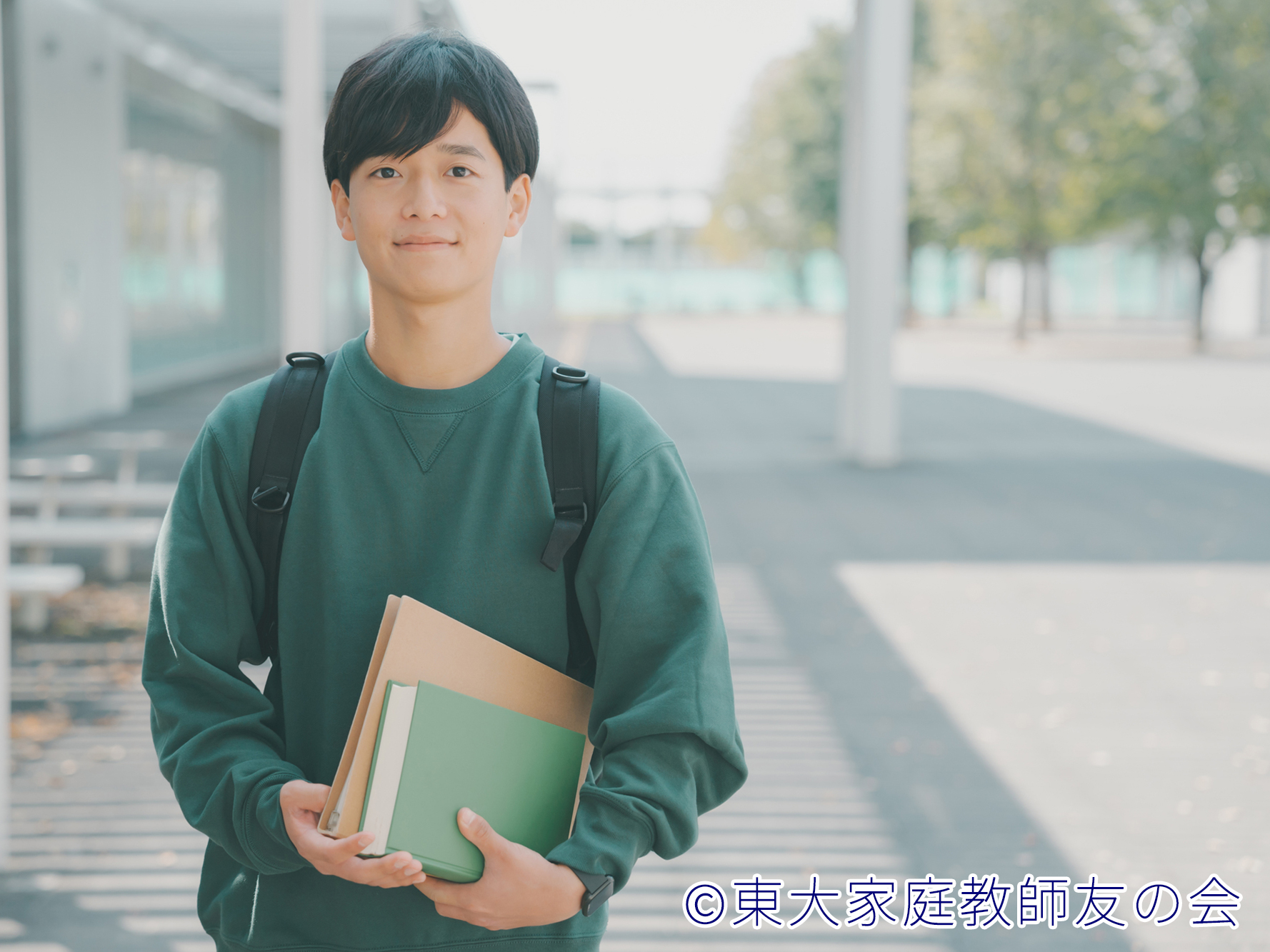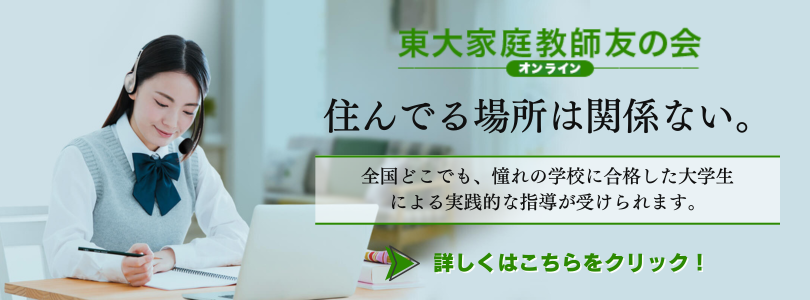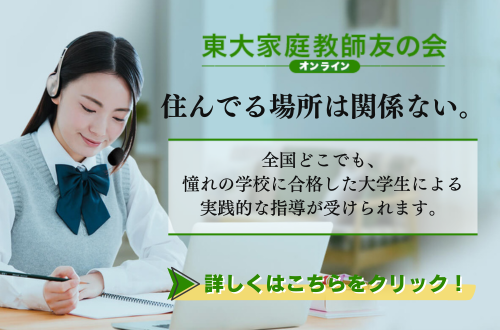![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
京都大学入試の仕組み&京大入試のギモンを解決!
京大の全入試形式はこちら!
京都大学には一般入試と特色入試、外国学校出身者向け入試と留学生向け入試の大きく分けて4種類の入試があります。ここではこのうち「一般入試」と「特色入試」について解説します。
まずは一般入試についてです。京都大学の一般入試は基本的に他大の前期試験と同じ試験日程で実施されます。一応法学部のみ特色入試、という形で後期試験がありますがそれは後程説明します。京大の前期試験の特徴はどの学部でも最低三教科、二日以上の試験であることで、特に医学部は国語数学英語理科に加えて面接で計三日間の試験を行います。これは体力的にかなり厳しい試験です。各学部・学科の試験科目や配点は後述します。
次に特色入試は大きく分けて二種類あります。全ての学部のいわゆる「推薦入試」と法学部のいわゆる「後期日程」です。まず「推薦入試」の部分についてですがここは一言で言えば怪物しか受からないような入試です。最もそれがよく現れているのが日本唯一の数学専門の研究所・京都大学数理解析研究所への「才能の登竜門」となる京大理学部の数学入試です。検索すれば出てきますがそこで出題される問題はどれも凡人の頭脳では一生追いつけないような難問ばかりで、他の学部も同様に難しいです。よくこの入試は「超天才しか受からない」などのように言われますが、実際には違います。周囲の脳裏に一生焼き付くほどの才能を持ち、その上で死ぬ気で努力しないと受からないのです。
もう一つの特色入試が法学部の「後期試験」です。こちらは日本語と英語の文章を読んで問いに答えるというシンプルな小論文です。しかし、募集定員はわずかに20人である上、受験生のほとんどは東大か京大の前期試験を受けた人であり、受験生のレベルも覚悟も段違いです。この国においてこれほど受けにくい入試は共通テストの得点率ボーダーが驚異の「99%」である国際教養大学のC日程ぐらいしか他には考えられないでしょう。
以上のことから、京都大学の入試はどれをとっても非常に厳しい戦いになります。なので、その中では比較的「マシ」な試験といえる前期日程で挑むとよいでしょう。
入試の仕組み・入試予告情報
●共通テスト利用科目
大学入試センター試験の教科・科目と同様になります。文系は5教科8科目/6教科8科目、理系は5教科 7科目となり、一般的な国公立大学同様です。
●外国語「英語」の利用方法
大学入学共通テストの英語に関して、京都大学は「リーディング」を150点満点、「リスニング」を50点満点に換算して利用します。2020年まで実施されていたセンター試験よりもリスニングの比重が少し大きくなっています。
※追試の有無など、新型コロナウイルスの影響等による変更が行われることも考えられるため、大学からの情報に注意してください。
入試期日については、常に大学からの最新情報をご確認ください。
各学部各教科配点(2024年度)
※記載の配点は全て第2段階選抜の配点です。
※共通テストで配点が「-」となっている箇所は、第1段階選抜のみに使用されます。
※令和5年度一般選抜入学者選抜要項を参考に作成しています。(2023.8.22時点)
|
総合人間学部(文系)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から2科目選択(各25点)、理科は発展2科目でもよい。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
|
|
| 国語 | – |
150
|
||
| 数学 | – | |||
| 理科 | 100 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 外国語 | – | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
650
|
||
| 地歴 | 100 | |||
| 数学 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
総合人間学部(理系)
(
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
|
|
| 国語 | – |
100
|
||
| 数学 | – | |||
| 理科 | – | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 外国語 | – | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
700
|
||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 150 | |||
|
文学部
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から2科目選択(各25点)、理科は発展2科目でもよい。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
500
|
||
| 地歴 | 100 | |||
| 数学 | 100 | |||
| 外国語 | 150 | |||
|
教育学部(文系)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から2科目選択(各25点)、理科は発展2科目でもよい。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 200 |
650
|
||
| 地歴 | 100 | |||
| 数学 | 150 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
教育学部(理系)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
650
|
||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 100 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
法学部(前期日程)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から2科目選択(各30点)、理科は発展2科目でもよい。地公の選択は世界史Bか日本史Bのどちらか一方を必ず含めること。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
|
|
| の国語 | 60 | 270 | ||
| 数学 | 60 | |||
| 理科 | 30 | |||
| 外国語 | 60 | |||
| 地歴/公民 | 60 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
650
|
||
| 地歴 | 100 | |||
| 数学 | 150 | |||
| 外国語 | 150 | |||
|
法学部(後期日程/特色)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から2科目選択(各30点)、理科は発展2科目でもよい。地公の選択は世界史Bか日本史Bのどちらか一方を必ず含めること。
二次試験は学科試験を課さない。日本語と英語の文章を題材に、読解力、論理的思考力、表現力などについて評価する。
|
|
| の国語 | 60 | 270 | ||
| 数学 | 60 | |||
| 理科 | 30 | |||
| 外国語 | 60 | |||
| 地歴/公民 | 60 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 小論文 | 100 | 100 | ||
|
経済学部(文系)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から2科目選択(各25点)、理科は発展2科目でもよい。
二次試験の外国語は英語のみ。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
550
|
||
| 地歴 | 100 | |||
| 数学 | 150 | |||
| 外国語 | 150 | |||
|
経済学部(理系)
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は英語のみ。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 |
650
|
||
| 数学 | 300 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
理学部
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は英語のみ。
|
|
| 国語 | 50 | 225 | ||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 25 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 | 975 | ||
| 数学 | 300 | |||
| 理科 | 300 | |||
| 外国語 | 225 | |||
|
医学部医学科
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
面接の結果によっては学科試験の成績の如何にかかわらず不合格となることがある。調査書は面接の参考資料にする。また、面接の参考資料として受験者全員に対し志望理由等を記載した書類の提出を求める。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 | 1000 | ||
| 数学 | 250 | |||
| 理科 | 300 | |||
| 外国語 | 300 | |||
| 面接 | 非公表 | |||
|
医学部人間健康科学科
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。 二次試験の外国語は英語のみ。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 150 | 750 | ||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
薬学部
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は英語のみ。
募集は薬科学科・薬学科を合わせた学部単位で行っている。
|
|
| 国語 | 50 |
250
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 50 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 100 | 700 | ||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
工学部
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は英語のみ。
出願時に第2希望学科まで選択できる。
|
|
| 国語 | 50 |
200
|
||
| 数学 | – | |||
| 理科 | – | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 100 | 800 | ||
| 数学 | 250 | |||
| 理科 | 250 | |||
| 外国語 | 200 | |||
|
農学部
|
共通テスト | 備考 | ||
| 科目 | 配点 | 満点 |
共通テストは地歴/公民から1科目選択。
二次試験の外国語は独・仏・中選択可。
出願時、第1~第6希望学科を全て選択できる。
|
|
| 国語 | 100 |
350
|
||
| 数学 | 50 | |||
| 理科 | 50 | |||
| 外国語 | 50 | |||
| 地歴/公民 | 100 | |||
| 二次試験 | ||||
| 科目 | 配点 | 満点 | ||
| 国語 | 100 | 700 | ||
| 数学 | 200 | |||
| 理科 | 200 | |||
| 外国語 | 200 | |||
京大入試のギモン
Q1.共通テストの点数の割合がかなり低いのですが、共通テストの対策はやらなくても大丈夫なんですか?
―結論から言うとダメです。大学入試では合格ラインの付近はたった1点、それどころか0.1点未満の差が合否を分ける混戦状態であり、多くの受験者がこの近辺でひしめき合います。それに、二次試験の問題の難易度は基本的に共通テストより高いです。ではここまでのことを踏まえて以下の質問に答えてください。あなたは今から共通テストか二次試験のどちらかを「1点」だけ上げれば合格できるとします。さて、どちらを上げに行きますか?もちろん、共通テストの方を上げますよね。
つまり、共通テストは二次試験に比べて1点を取る難易度が低いのです(圧縮を考慮しても、です)。もちろん二次試験の得点率が著しく低い場合はそちらを優先しなければなりませんが、二次試験の割合が共通テストより高いことだけを理由に共通テストの対策を怠ってはならない、ということは理解して頂けたかと思います。
また、共通テストに関するもうひとつのギモンとして、傾斜配点が「-」となっているところ(工学部の数学など)はどういう扱いになっていますか?というものがよくありますが、ここは「センター試験で受験する必要はあるが、合否の判断には使わない」ということになっています。つまりここは何点であっても調整後の得点は0点です。しかし、他大学の入試との兼ね合いもあります。配点が「-」であってもその科目で手を抜くべきではないでしょう。
Q2.例えば英検一級を持っていることで、入試で有利になることはありますか?
―現状、京都大学の一般入試では英検やTOFEL、IELTSなどで好成績を収めることで英語の試験が免除されたり、加点されるということはありません。ですが、英検などの資格は取るだけ損、ということはありません。それらの資格が取れる、高得点を出せることは何よりもあなたの実力の証明になります。
英検に話を絞れば、共通テストは英検2級~準1級レベル、二次試験は準1級~1級レベルの実力が必要とされています。京都大学を受験する上でのひとつのマイルストーンとして、これらの級を取ってみる、というのも立派な作戦の一つです。友の会では英検対策のできる家庭教師も派遣していますので(詳しくはコチラ)、是非参考にしてみてくださいね。
※一部の学部では英検やTOFELなどのスコアが特色入試の出願に必要になっています。詳細は大学発表の情報を参照してください。
Q3.所謂内申点のような制度はありますか?
―ありません。京都大学では一応高校発行の調査書の提出を求めています(高認の場合他のもので代用)が、それはあくまで受験生が卒業見込み、または卒業済みであることを確認するためのものに過ぎません。一部の学部の特色入試では評定平均4.0または4.3が1つの出願要件になりますが、少なくとも一般入試には必要ありません。
ここ数年の大学入試の一連の改革で、文部科学省は調査書の重視を1つの柱に掲げました。しかし、京都大学などの難関国立大学はことごとくこの方針に反対しています。こうした大学はそう簡単には国からの圧力に屈しないので、これからも京都大学などは調査書を高校卒業見込みまたは卒業済みかどうかを調べるためだけの運用にとどめるでしょう。
ただしひとつだけ、もしかしたら調査書記載の高校の成績が関係するのではないかと言われているケースがあります。それは「合格最低点で同点になった受験者が複数人いて、なおかつ全員合格にすると定員を大幅に超過する場合」です。といっても、得点の算出は小数点刻みであり、国公立大学は入学辞退者が出ることなどを見越して予告した定員より少し多めの人数を合格にするので、このようなケースはレア中のレアと言ってもいいでしょう。
2024年京都大
入試傾向と対策ポイント
英語の傾向・対策
【傾向】「高度な和訳・英訳スキルが求められる」
長年、京大英語の出題は[Ⅰ]と[Ⅱ]は難しい英語の長文を読んで下線部のある箇所を和訳する、[Ⅲ]はこなれた日本語の文章が2つ与えられるのでそれを全て英訳する、という形式が定着していました。近年その傾向は変化していますが、京都大学が受験生に求めている英語力は昔の時代から変わっていません。
京都大学が求める英語力は与えられた文章をどんなに難しくても噛み砕き、自分の言葉で表現する力です。この国語の基本ともいえる力を、英語と日本語の相互変換の能力とセットで試しているに過ぎないのです。
問題に対して時間はそこまで不足するわけでもないので、一度立ち止まって出題者の意図を汲み、そうして得た答えを齟齬なく採点者に伝えることを意識しましょう。
【対策】「単語・文法を叩き込み、とにかく演習」
まずは英文和訳についてです。京都大学は論文の一節などをほとんどそのまま出題します。つまり、実際に学問の世界で使われる難解な英語表現や構文もそのまま読まされるのです。このような出題に相対するためには、単語と文法の幅広い知識を持ち、その上でそれらを正確に運用する能力を身につける必要があります。一見簡単な単語であっても文脈によって意味が変わることもしばしばであり、品詞の違い、多義語、似た単語の区別といったことを正確に把握できていない人は話についていけずに迷子になるでしょう。
また、下線部を訳す問題で下線部だけを読むのもNGです。解答のヒントはしばしばその前後の文脈にあるからです。そして、解答が出来上がったら必ず自分の書いた日本語を一読してください。ここで、自分でその日本語の意味が分からなかったら、その解答は不正解です。「この解答を読む人がいる」ことを常に意識してください。
和文英訳も同じです。単語と文法の正確な知識を得ることが第一です。しかし、英訳に使うべき表現は簡単なものに絞らなければなりません。英訳問題の採点は減点式であり、背伸びして難しい表現を使っていると、どこかで間違いを指摘され、それが続いてゼロ点または一桁点に……という悲劇に見舞われることになります。
よって表現はそれこそ中学レベルの簡単なものに、ということなのですが、そこにも難題があります。それはそもそも与えられた日本語の表現が難しいことです。ではどうするか?結局、与えられた日本語を頭の中で簡単な日本語に変えてから、その内容を逐一英訳していく、ということになります。
こうした問題の対策には過去問演習が有効です。そして、実際の演習で大切なことは過去問などを解き終えるたびになるべく添削をもらうことです。英訳問題なら必須ですし、和訳問題であっても、京大のような長い和訳を書かせる大学の問題であれば添削をもらった方が安心です。その度に自分の解答の不足が見えます。
知らない単語は暗記する、有用な英訳の型を身につけるなど、英語の学習はこうした地道な作業の繰り返しです。なかなか面倒に聞こえますが、この程度のことはやらないとライバルに勝つことはできないのです。
国語の傾向・対策
【傾向】「精巧で丁寧な読みが必要」
文系・理系で問題が異なりますが京大の国語は第一問・第二問は現代文、第三問は古文という形式が定着しています。漢文はどういうわけか半世紀にわたり出題されていません(但し出題範囲には入っています!)。解答は基本的に全て記述式で、たまに第一問で漢字の知識を問う年がある程度です。しかし文章はかなり短く、一見して時間的にはやや余裕があるように見えます。
しかし、京大国語には「そもそも問うていることが高度過ぎる」という問題があります。書かれていることを単に抜き出して表現・文末等を変える程度にして書いているようでは足りません。文章全体の流れを汲み、問題文を睨みながら一語一句の裏にある筆者の意図として出題者が想定することを正確に掴み、それを齟齬なく不足なく限られた解答スペースにまとめる、ということをしないといけないのです。
また、京大国語は日本語の表現自体が大切にされている試験でもあります。それが証拠に京大は筆者の日本語表現の巧さを存分に味わえるような比較的やわらかめな文章を好き好んで出題しています。そのような文章を出すぐらいですから、当然、京大は受験生の側にもそれに相対できる高度な表現力を求めているのです。
【対策】「難しいからこそ基本に立ち返る」
上に見たように京大の国語は大学の入学試験として明らかに最高レベルの高度な要求を課しています。そのような難題に立ち向かうにはどうするのか、それは国語の基本である「文法」というところに立ち返る必要があるのです。
現代文は難しすぎるので先に古文から。古文に関しては重要な単語と文法の意味を確実に把握することに尽きます。それが出来ればある程度文章の全体像は見えます。そしてその上で文脈を見ながら解答を作ることになります。
現代文もやることは同じです。抑えるべきポイントは「しかし」や「それでも」といった接続詞です。こうした部分に注目すると文章全体の論理展開が見えやすくなり、解答作成の足掛かりが掴めるようになります。
その先はただひたすら「慣れ」でしょう。本を普段から読む子が国語は有利、ということはよく知られていますがまさしくその通りで、彼らは普段から無意識のうちに読解の鍛錬を積んでいます。その習慣が無い人も今からでも遅くはないので本を読むべきではありますし、そして「点を取る」ということに着目するなら演習の回数をこなす、ということに帰着します。結局、普段から日本語を面倒くさがることなく運用しているかどうかで差がつくのです。
また、理系であっても国語を対策するべきである理由はもう1つあります。それはこの教科の試験が最初にあることです。配点は低くともここを得意とすることで本番の調子に弾みをつけることができ、メンタル的にはとてもいい地固めになります。その後に控える高配点教科を好調な状態で受けられることからも、国語を対策することには大きな意義があるのです。
数学の傾向・対策
【傾向】「自分で一から解答を作らせる」
京大の数学は難しい、手が付かない……これは今まで一度でもその問題に当たったことがある人は余程の数学強者でない限りは実感したことかと思います。京大は毎年理系は6題、文系は5題出題するのですが、果たして京大数学の何が難しいのかというと「それらしい誘導がほとんどない」ところです。
京大数学は昔から一切ブレないコンセプトとして、受験生に対して「全て自分の頭で考える」ことを課しています。そのために誘導に乗らせるようなことをせず、それどころか別解をいくつも作れるような問題を出して受験生が個性豊かな解法を提示することを待っているのです(別解が実に26通りもあるような問題が出題された年があるぐらいです)。
そしてそのような厳しい出題に対しなんとか答えを出しても、解答課程にミスがあるとすぐに大幅減点を喰らいます。それもそのはず、採点者は全員魔境・京都大学理学研究科所属の数学者です。恐ろしく数学の出来る人たちが相手なので誤魔化しは全く通用しません。
また、近年は計算ミスもバッサリ減点されています。2007年から登場した大問を問一と問二に分ける形式の問題はオール・オア・ナッシングで採点されており、さらにそうでない計算問題も最終結果が間違っているとほとんど部分点を貰えないレベルまで減点されているような印象を受けます。
そしてもう一つ忘れてはいけないことがあります。それは「本番は極限状態でこれらの難題に当たらねばならない」ということです。普段の演習で出来ていたとしても、油断は全く出来ないのです。
【対策】「本番は数学を頼らない!」
取り敢えずは教科書に書いてある定理・公式を全て自分で証明・導出できるようにしましょう。中間値の定理(数Ⅲ)以外はほぼ全て証明可能なはずです。それが出来たらいよいよ問題演習です。特に夏は数学の勉強のしどきで、この時期にひたすら過去問と、他大学で出題されたいわゆる「良問」を解いていきます。
実は出題パターンは限られていて、それを知ってしまえばあとはそこから解法を捻りだすだけのシステマティックな作業になることがだんだん分かってくるはずです。逆にそうならない場合は演習不足、ということです。ひたすら地道にやりましょう。
それが出来たら後は他教科を伸ばしましょう。秋以降も当然数学は真面目にやるべきですが、上に書いたように入試本番は極限状態の中で問題を解くことになるので、そこでは計算ミスなど普段は絶対やらないようなミスが次々に起こるのです。そのようなことを織り込んで合格するためには英語、理科、社会といった当日のコンディションで点数がブレにくい教科で確実に得点することが重要になります。数学はそれこそ誰でも解けるような簡単な問題を確実に解くようにすれば良く、難問は「解ければ万々歳」なのです。
そして、簡単な問題を確実に取るために必要なスキルは「問題の難易を見極めること」なのですが、これも普段の問題演習の量が関係します。ちゃんと問題演習を積み重ねた人は、たとえ数学が大の苦手であってもその勘は冴え渡っていますし、中途半端に得意な人ほどそれが出来ないから「危ない」のです。己の才能を過信せず、愚直にやっていくことが京大合格への近道です。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
日本史の傾向・対策
【傾向】「満遍なく、しかし量の多い出題」
京大の日本史は第一問から第三問まで語句の穴埋めと一問一答、第四問が200字論述×2となる形式が定着しています。また、問題に登場する資料はどれもマイナーで、受験生にとってはほぼ初見の資料が多く、そうした資料への対応力が求められます。
出題される年代やジャンルには論述含めて偏りがなく、当たり前ですがヤマを張ることは現実的ではありません。その一方、求められる知識はそのほとんどが教科書レベルで落ち着いています。しかし問題なのはその量の多さです。難易度がそこまで高くない一方で出題される量は多く、特に知識問題を速く、正確に処理できない限り、ライバルに水をあけられてしまいます。
【対策】「とにかく穴を作らない!」
上で見たように京大の日本史は「広く浅く」の出題となっており、こうした出題に対応するためにはとにかく「穴を作らない」ことが肝心です。マニアックな知識を身につけることに固執しないで、基本的な知識を大切にする姿勢で勉強しましょう。
普段から学習する際に念頭に置くべきこととして、やはり「時代背景を正確に抑える」ことがあります。時代背景は言ってしまえば歴史と言う大きな物語の中での世界設定です。当時の権力者は何を考えてこのような政策をしたのか?当時の流行はどこから生まれたのか?こうした疑問を常に持ち、立ち止まり、持ち合わせの知識か、教科書にある知識で対処していく習慣をつけている人は日本史でも世界史でも強いです。
上記のようなことが出来ると、第四問の論述において書くべきことも見えやすくなります。論述対策は一通りの知識を身につけてから日本史の総まとめ的にやっていきましょう。一度書いたら先生に見てもらい、添削をもらうようにしてください。
世界史の傾向・対策
【傾向】「難易度は標準、でも量が多い!」
京大の世界史は第一問と第三問でそれぞれ300字ずつの論述問題、第二問と第四問が短答式+小論述の問題となる形式が定着しています。かつては教科書の範囲を飛び越えた出題がなされたこともありましたが、現在ではその閾を越えない出題が心掛けられています。
出題として、第一問と第二問がアジア、第三問と第四問が欧米・アフリカとなっていることが多いです。大抵はアジア史とヨーロッパ史で終わりなのですが最近はアメリカ史の出題も多く、またたまにアフリカ史も出題されます。分野としては政治史が中心ですが文化史の知識なしには取れない小問も混ざっています。
以上のような出題傾向がみられますが、求められる知識はそのほとんどが教科書レベルで落ち着いています。しかし問題なのはその量の多さです。難易度がそこまで高くない一方で出題される量は多く、特に知識問題を速く、正確に処理できない限り、ライバルに水をあけられてしまいます。
【対策】「時の流れも地図も大事に」
上で見たように京大の世界史は「広く浅く」の出題となっており、こうした出題に対応するためにはとにかく「穴を作らない」ことが肝心です。マニアックな知識を身につけることに固執しないで、基本的な知識を大切にする姿勢で勉強しましょう。
普段から学習する際に念頭に置くべきこととして、まずは「時代背景を正確に抑える」べきです。時代背景は言ってしまえば歴史と言う大きな物語の中での世界設定です。当時の権力者は何を考えてこのような政策をしたのか?当時の流行はどこから生まれたのか?こうした疑問を常に持ち、立ち止まり、持ち合わせの知識か、教科書にある知識で対処していく習慣をつけている人は世界史でも日本史でも強いです。
また、特に世界史で重要なこととして「地図を見る」ということがあります。民族大移動、戦争、文化の伝播……実際に地図を見て、目で追っていかないと分からないことがこと世界史には多いです。そしてそこに「時の流れ」という要素がつくことで世界史が扱うことは立体的なものになります。これを大きな「歴史の流れ」と見て、頭にある知識を使って捉え、その流れに乗ることが出来るか?これを京大は見ようとしているのです。
上記のようなことが出来ると、第一問・第三問の論述も怖くありません。論述対策は一通りの知識を身につけてから世界史の総まとめ的にやっていきましょう。一度書いたら先生に見てもらい、添削をもらうようにしてください。
地理の傾向・対策
【傾向】「様々な資料への簡潔な説明を求める」
京大の地理は全体として資料が多く、その上で40字程度の短い記述問題が大量に出される傾向にあります。さらにその一方で出題範囲はほぼ偏りがなく、その分バリエーション豊かな知識を必要とします。その上で高度な論述力を求めるところに京大地理の難しさがあります。
ものを説明する際に「なるべく手短にお願いします」と言われたら大抵の場合は説明に困ると思います。自分が十分知ってると思っていることであっても、いざ短くまとめろと言われたら大体の人は項垂れますし、字数や時間を気にせず自分が知っていることをそのまま伝える方が楽に決まっています。そこから不要だと考えられる部分を切り捨てる際に何を捨てるか、この選択が一番難しいのです。京大地理の論述の難しさはまさしくそこにあるといえます。
【対策】「やれることは全部やる!」
京大が求めるオールラウンドな知識とその応用力、統計や地形図に対する深い読解力・分析力、ポイントを鋭く突いた記述を短時間で作成する能力は一朝一夕に身につくものではありません。千里の道も一歩から、というわけで普段からの学習が重要です。そして、地理においてやれる範囲のことは「全て」やるべきです。
まずは教科書の内容を理解するときに地図帳を積極的に使いましょう。気候変動や産業の発展の仕組み、人口・宗教の分布の理由、これらをちゃんと説明できるように、そして出来たらその説明をどんどん短く、簡潔にしていきましょう。余計なものを切り捨てる練習が必要です。
ただし知識は豊富に持っておいた方がよいです。実際に説明をする過程で具体的な地名や産品を言う必要はあまりないのですが、その説明をしやすくするためのイメージを確保する、裏付け的に持っておくといった感じで、あるに越したことはないのです。
それと読図・統計分析に関して。これらは「検索能力」が全てです。必要な情報を素早く探し出すには普段から訓練することが肝心ですし、何より検索にも知識が必要です。知識はモノ捜しの手がかりです、上でも書いた「知識を身につけること」の重要性はこの点にもあります。
理科(2科目受ける場合の注意点)
【傾向】「3時間もあるのに時間が足りない!?」
2科目受験の場合京大の理科はエクストリームスポーツの一種だと考えた方がよいです。3時間通しで水も飲めないなかで問題を解かされ、そしてそれだけ時間があるのにあまりに量が多すぎて時間内には到底終わらない、この「しんどさ」は一度経験しないと分からないかもしれません。
その上京大の理科の難易度は「揃いません」。科目、年、大問によってバラバラです。このため順番通りに解こうとするとほとんど得点の見込みもないような難しい問題に時間を使い過ぎて簡単な問題を解く時間がなくなり不合格、ということが起きます。
このため、京大の理科は特に「時間配分」に気を付けて勝負しなければなりません。このため、実際の問題を使用して3時間通しでの演習をすることをお勧めします。「簡単な問題を拾う」ということを意識して一度でもやれば違います。本番でどのようにすれば自分の得点を最大化できるのかが理解できるはずですし、とにかく長いようであっという間に過ぎ去ってしまう180分の有効な使い方をその場で決められるようにしなければなりません。もう少し細かい対策は各科目の個別の対策ページに記します。
物理の傾向・対策
【傾向】「長い!重たい!難しい!」
京大の物理は理科全体でも特に「長い!重たい!難しい!」の三重苦です。「解答はじめ」の合図とともに問題用紙を開くと、図とともにやたらと長いリード文が出てきます。それもそのはず、京大の出題はそのほとんどが「全く初見の設定の中で受験生に知恵を絞らせる」セットです。そのために説明も非常に長く、もたもたしていると到底間に合いません。
問題の序盤はまだ教科書レベルの簡単なものであることが多いです。しかし、そこを越えると一気に問いかけが高度になり、「丁寧に文章を読んでいないと」迷子になってしまいます。そうなってしまうともう時間切れまっしぐらです。
そしてこのような出題が3つも続きます。これが「重たい」のです。物理ともう1教科に90分ずつ時間を割くとすれば1問あたり30分で手際よく終わらせなければなりませんが、その問題は大抵大学入試の常識に収まりきらない難易度でかかってきます。難しいのに時間がない、これが京大物理の最大のポイントです。
そして危険なポイントはこれだけではありません。京大物理は基本的に共通テストの数学で見たような穴埋め形式になります。勘がいい人はここで察することが出来るかと思われますが、「一度ミスを犯してしまうとその先もドミノ倒しのように間違えてしまいます」。これが京大物理の真の恐ろしさです。
【対策】「取れるところを確実に」
以上に見たように京大の物理は非常に恐ろしい試験です。とても定期テストのようにはいきません。そこで、京大物理に関しては「満点を取る」という意識は初めから捨てて、「とにかく点を取る」という方針で闘うのみになります。そのやり方を以下に書きます。まずはしっかり全範囲を学習して過去問演習を積んで、その上でこの解説を読んでください。
まずは出された問題3つの出題ジャンルをざっと確認しましょう。京大は原子も含めて偏りのない出題をするので穴がないようにする必要がありますが、それでも分野の得意苦手はいつまでもついて回ります。それも含めて、「取れそうな問題から」解き始めるようにしましょう。これは年や大問によって難易度にとんでもないバラツキがあるためです。順番に解くとマズいことになるかもしれません。
そして問題を解くときは誰でも解くような簡単なものを確実に正解する、という意識を持ちましょう。最初の「イ」「ロ」だけでなく、途中にも良く見るとそこだけ独立していたり、あるいは単なる知識で解けたりする設問があるのです。こういう所は受かる人は全員取ります。確実にモノにしましょう。
そして、問題を解く際に絶対に心がけるべきことがあります。それは「リード文をちゃんと読む」ということです。一見、「なんだこれ」と思うような設定の問題が、リード文を注意深く読むことでわけが分かって、そのまま最後まで解き進められた、ということが京大では多いです。こういう「実は簡単」な問題を取るためにリード文をちゃんと読む必要があります。
長々と書きましたが京大の物理の基本は「難問は捨てる、解けるところを確実に、そしてリード文をちゃんと読む」です。90分しか割けない以上、こうした点に気を配る必要があるのです。
化学の傾向・対策
【傾向】「未知の設定から難問が繰り出される」
京大の化学も分量が非常に多く、時間内に処理しきれない場合がほとんどです。そして出てくる図とリード文は全て受験生が知らないようなことばかり書かれています。これを持ち合わせの知識でいかに対処するか、出題者はここを見たがっています。
問題は[Ⅰ][Ⅱ]で理論または無機化学、[Ⅲ][Ⅳ]で高分子化合物を含む有機化学を出題する構成となっています。そしてそのどれもが難問揃いではあるのですが、後半の有機化学は比較的取り易いことが多いです。というのも、有機化学の出題パターンはかなり限られており、問題演習を十分に積んでいれば完答できるケースがほとんどです。大半の現役生がここには本番直前まで手をつけられず、中高一貫生・浪人生の稼ぎどころになっています。
一方、理論化学は厄介な出題が多いです。実験をもとに考えさせる出題が基本ですが、この実験の意図が不明確であると言われる年すらあるほどです。相当奇妙な問題が出ると思った方がいいですし、場合によってはここを「捨てる」しかなくなってしまいます。
【対策】「有機を完答し難問を捨てる勇気を」
京大化学には以上に見たような特徴があります。傾向を読んだ時点で分かるかと思いますが、とりあえず本番で先に倒してしまうべきなのは有機です。もちろん全ての分野を満遍なく学習していないと水底に沈められるのは明白ですが、やはり京大は「理論より有機の方が比較的楽」です。
楽な理由は上に書いた通り、出題パターンが限られるためです。もちろんこのマンネリ化を克服するための努力を出題側もしてはいますが、それでも限界があります。ここを狙わない手はありません。有機化学の花形ともいえる構造決定は慣れてしまえばただのパズルゲームです。まずは覚えるべきことを覚え、演習の数をこなしましょう。問題を解いているうちに覚えることもあります。
それができたら理論と無機です。無機化学はあまり出題されませんがいつ出てもおかしくないので出て困らない程度にはしましょう。知識は共通テストレベルで問題ありません。
理論化学は年によって難易のバラツキが本当に激しいので「理論で完答する!」は「宝くじで1等を出す!」と大差ありません。危険な賭けです。やはりここは「誰でも解けるところで確実に正答する」ことに尽きます。難しくて手がつかない問題はきれいさっぱり捨てたほうが良いでしょう。
生物の傾向・対策
【傾向】「『生物』を超えた『生物学』を出題」
京大の生物は「厳選されたリード文とデータをじっくり時間をかけて考察し、字数制限のない解答欄に自分の言葉を論理が通るように書く」ことを非常に大切にしています。必要な知識は教科書レベルに留まり、過度にマニアックな問題は排除されています。その分、「考察させる」というところに重点を置くため、生半可な学力では当然返り討ちに遭います。
この点は論述に最もよく現れます。90分の試験にもかかわらずトータル1500字に迫る小論文並みの論述量を課す年度もあったほどですから、まず時間は足りません。そしてその上、これだけの字数を書いたところで採点は非常に厳しく、論理的に甘さのある答案はバッサリ減点されます。このため、京大の生物は日本一難しいと言われることもしばしばです。
さらに京大の生物では生物入試にもかかわらず高校数学をフル活用しないと解けない計算問題がよく出題されています。それもそのはず、京大が入試でやりたいのは「生物」の垣根を超えた「生物学」です。生物学を研究する研究室自体が様々な学部に存在する以上、生物単独の学力だけで太刀打ちすることを京大が許すはずがないのです。
【対策】「『生物』だけをやらない!」
こうした特徴を持つ京大の生物に向き合うためにはまず「生物」という教科にこだわる姿勢を改めなければなりません。そもそも受験はトータルバランスで他教科とのバランスを大切にしなければいけないのですから、他の教科と一緒に上げなければならないのは明白です。
だからこそ、普段の勉強でするべきこととして「このことは別の教科でもいえそうだ」といったことを積極的に発見することがあります。この積み重ねが「教科」の垣根を越える幅広の教養を生み、最終的にはあなたの味方になります。そしてこの教養を得た人だけが、京大生物の長い長い論述問題を攻略できるのです。
実際に問題を解く際は知識問題を確実に正答する、ということをまず念頭に置きましょう。ここは基本的に教科書レベルのことしか聞かないのでここで落とすと後に響きます。論述で巻き返すのはほぼ不可能であるためです。なにせあの長大な量に緻密な論理性を求めるのですから、いくら細心の注意を払ったところですぐさま高校生の国語力の限界に差し掛かります。そのためか京大の生物で8割を取れるような人はまずいない、と言われています。
それともう一つ大事なことがあります。それは「早めに過去問に手をつける」ということです。京大の生物はその他大学とは異なる出題からオーソドックスな問題集ではほとんど相手にされず、十分な過去問演習を積まないで、つまり「京大生物を知らずに」挑んだ受験生が門前払いを喰らってしまうことが往々にしてあります。早めに京大生物という「生物学を志す者のための前哨戦」を肌感覚で知っておくに越したことはないのです。
地学の傾向・対策
【傾向】「地学以外の教科の素養も必要」
京大の地学は全体的にバランスの良い出題をしますが、基本は考察です。他の理科の分野にも言えることとして「知識は教科書レベルで、そこから深く考察をさせる」ということを大切にしています。とはいえそこは京都大学、単純な教科としての地学では終わりません。物理・化学の考え方を応用しないと解けないような問題がしばしば出題されるのが特徴です。
【対策】「『地学』自体に真摯に向き合うこと」
京大の地学は非常に高度です。しかし、地学そのものに普段から本やテレビで慣れ親しみ、日ごろから問題演習を積み重ねていれば決して突破不可能な相手ではありません。
というのも、地学は他に比べて奇抜な出題をしづらいのです。他分野と組んだ奇抜でトリッキーな出題をしまくる化学や生物に比べ、非常に大人しいという印象を受けます。このため、十分な問題演習・過去問演習をすることで本番の対応は十分行えるようになります。そして、この地盤を作り上げるためには、日ごろから進んで地学分野に興味を持って様々な知に触れること、これが重要となるのです。
京都大学に合格するには?
入試までの過ごし方
さて、実際に京都大学に合格しようと思ったら何をしなければならないのでしょう?次は京大入試までの過ごし方や学習のやり方について解説していこうと思います。
入試に向けた勉強はなるべく早くから始めるのが吉です。まれに直前期に始めてそのまま受かってしまうような人はいますが、それはほんの一部のレアケース。早め早めの対策をしないと、大半の人は入試を突破できません。特に京都大学のような難しい大学はなおさら、です。
具体的な時期として、教科書の内容は高2のうちに終わらせるのが理想です。といっても、大半の学校は高3の秋ごろまでは教科書の内容の授業が続きます(特に理科と地歴公民)。そのような場合、既に習った範囲のみ入試対策に回す、というやり方でもいいのですが正直京大レベルならその時期の内容は先取りして授業よりも早いペースで終わらせてしまった方がいいと思います。その方が全体的に自分がどの分野が得意でどの分野が苦手かが早いうちに分かり、実際の入試での作戦が立てやすくなるのです。
勉強時間は今やっている部活との相談です。直前期には1日10時間ほどを受験勉強に費やしてそれでも足りるかどうか、という状況になりますがそれまではどうかというと、これはあなたがやってる部活や習い事などの種類で2つのパターンに分岐します。
まず、運動部などで一日何時間も部活動などに時間を費やしている人。引退が凡そ高3の夏ですから、部活を引退したらすぐに最低1日8時間程度の勉強時間を確保するようにしてください。予習復習をしっかりやっており、普段から好成績を確保出来ていてもそうでなくてもここの切り替えはしっかりするべきだと思います。といっても、部活動にきっちり打ち込めている人であればそのあたりは心配しなくてもいいでしょう。引退しても未練が消えずにその後もズルズルと部活に顔を出す、という状況が一番マズいです。学習状況に遅れがある方はまずはそこを取り戻すところから始めましょう。
次に、あまり部活をやっていない人や帰宅部の人です。こちらの方々は高2の冬ごろに1日3~5時間程度から始めて、月ごとに徐々に勉強時間を伸ばす、というやり方でどんどん時間を確保していく必要があります。というのも、あまり部活をやらない人はいざ入試直前となっても上手い具合にスイッチを入れられない傾向にあります。というより、スイッチの入れどきが存在しないのかもしれません。どちらなのかは定かではありませんがともかく、そういった人は最初は負担軽めの状態から始めて徐々に体を慣らしていく、という方針でいくべきです。その場合は高2の冬など、かなり早くから対策を始める必要があります。
そして最後に体調管理はきっちりしましょう。試験本番に体調を崩すと100%の実力を発揮できなくなります。睡眠時間をきっちり確保する、バランスの取れた食事をきちんと摂る、試験前日に詰め込み過ぎない、などなどこのあたりのことは自分の過去の経験も踏まえて実行してください。また、京大入試はとても体力を使う試験です。特に運動部に入らなかった人は勉強の合間などに体力づくりの運動を行うことも考えましょう。
▼部活と勉強の両立でお悩みの方はこちらもチェック!
どんな勉強をすればいい?
京都大学では非常に難易度の高い問題が出題されます。付け焼き刃での対策ではどうにもならない場面ばかりなので、まずは早め早めに学校で勉強する内容を終わらせて、共通テストの対策から入っていく必要があります。
難関国立大学の対策においてはよく「二次試験対策中心、共通テストは直前期だけやっておけばいい」と言われます。それは一理あるのですが、まずは共通テストに必要となる知識を抑え、そのレベルの問題が解けるようになっておく必要があります。それをしないことには二次試験の難しい問題には手がつきません。このあたりの順序を間違えないようにしましょう。
基本事項を覚え、標準的な難易度の問題が解けるようになってきたらいよいよ、京大の過去問や難しめの模擬試験、他の難関大学の問題を利用した二次試験対策に入ります。ここで使える教材は色々ありますが、最も参考になるのは間違いなく過去問です。ここで基本的な事柄を応用する力、そして難問に食らいつけるだけの粘り強さを身につける必要があります。
ですが、このあたりまでくると単に難易度が高いというだけにはとどまらない問題が発生してきます。問われることが高度になれば、採点の基準もまたわかりづらいものになっていきます。一人で勉強していて、自分がその答案で一体何割取れているのかわからないような状況では不安になるでしょうし、何より他に答案を見てくれる人がいないせいで自分の出来を過信してしまい、本番で返り討ちに遭うことが一番恐ろしいことです。
それに、そもそもまわりより早い段階から一人で勉強を進めること自体に難がある場合も出てくるでしょう。そういう場合は予備校に行ったり、家庭教師を雇ったり……といった作戦をとることが出来ます。特に、そこで実際に京都大学の入試を経験した人、成功した人と出会えて、その人と一緒に戦えるならばそれが理想的です。
東大家庭教師友の会では実際に京都大学の入試を経験し、見事合格を勝ち取った現役京大生の先生をご紹介することが出来ます。もちろん当会所属の教師を雇うだけで安心する、という訳にはいきませんが、是非京都大学に合格したいという方を友の会は全力でサポートいたします。
大学受験対策をご検討の方へ
京都大学在籍の家庭教師のご紹介
当会には京大生約2,200名が在籍しています。
大学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会【関西】の特徴
当会には、京大生約2,200名、阪大生約1,800名、神戸大生約900名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
オンラインでの指導も可能です
東大家庭教師友の会オンラインHPを見る