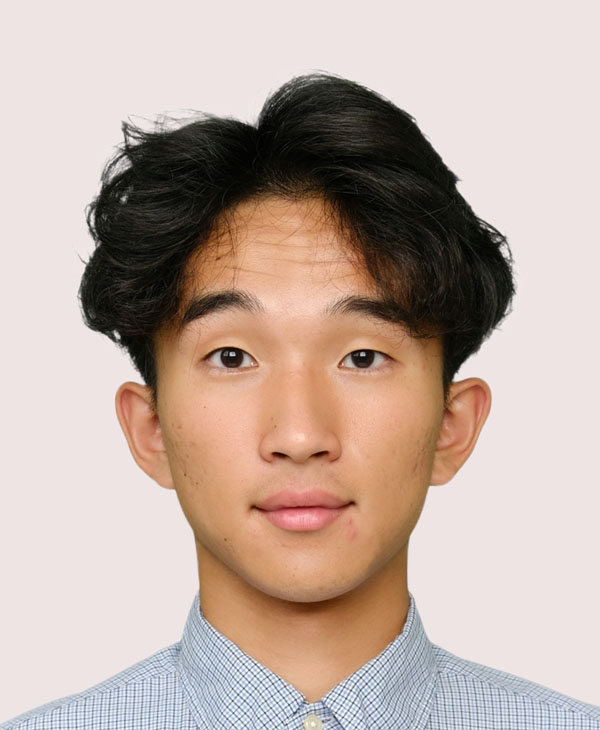![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業実施中!
1.都立高校入試の「共通問題」とは?
東京都立高校の一般入試(学力検査)では、基本的にすべての受験生が同じ問題を解きます。この東京都教育委員会が作成する統一の試験問題を「共通問題」と呼びます。
都立高校には、共通問題のみを使う「共通問題校」と、一部の教科を独自に作成する「自校作成校」があります。まずはこの2つの違いを理解しておきましょう。
①「共通問題校」の定義
都立高校のうち、国語・数学・英語・社会・理科の5教科すべてで、東京都教育委員会が作成した共通問題を使用して学力検査を行う高校を「共通問題校」と呼びます。
進学指導重点校など一部を除き、ほとんどの都立高校が共通問題校に該当します。
②「自校作成校」との違い
進学指導重点校など一部の高校では、国語・数学・英語の3教科(または英語のみ)を独自に作成した「自校作成問題」を使用して入試を行います。理科と社会については、これらの高校も共通問題を使用します。
▼「自校作成校」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
③「共通問題」を使用しない高校一覧
多くの都立高校は共通問題を使用していますが、一部の高校では入試方式が異なります。下表で全体の概要を確認しましょう。
| 区分 | 校数 | 入試方式 |
| 共通問題校 | 都立高校の大多数 | 5教科すべて共通問題を使用 |
| 自校作成校 | 11校 | 国語・数学・英語を独自作成(国際高校は英語のみ) |
| チャレンジスクール | 7校 | 作文・面接で選抜 |
| エンカレッジスクール | 6校 | 作文・実技・面接などで選抜 |
自校作成校(11校)
国語・数学・英語の学力検査を独自の問題で実施する高校です(国際高校は英語のみ自校作成)。 共通問題よりも難易度が高く、思考力・記述力・応用力が重視されます。
チャレンジスクール(7校)
小・中学校で不登校経験があったり、長期欠席等を理由に全日制の高校を中退した生徒が、自分のペースで学び直すことを目的とした高校です。 調査書・学力検査はなく、作文と面接で選抜が行われます。
エンカレッジスクール(6校)
中学校までの学習内容を基礎から学び直し、社会で生きる力を身につけることを目的とした高校です。学力検査はなく、調査書・面接・作文・実技などで選抜が行われます。
2.【2026年度入試向け】都立高校 共通問題の出題範囲
都立高校の共通問題は、原則として中学校3年間で学習する全ての範囲から出題されます。マークシート方式と記述式が組み合わされており、知識だけでなく「考える力」も試されます。
ここでは、教科ごとの出題範囲と重要テーマをまとめました。苦手分野の洗い出しや、これからの学習計画づくりの参考にしてください。
①国語の出題範囲
【漢字・知識】 読み書き、部首、熟語の構成
【文学的文章】 小説、物語文の読解
【説明的文章】 論説文、説明文の読解
【古典】 古文の読解
【作文】 200字程度の意見文
②数学の出題範囲
【計算・小問集合】 四則計算、方程式、平方根、確率
【関数】 一次関数、二次関数
【図形】 平面図形、空間図形(角度、面積、体積、証明)
③英語の出題範囲
【リスニング】 対話文や案内の聞き取り
【文法・語彙】 単語、熟語、文法知識
【対話文・長文読解】 メール、物語、説明文などの読解
【英作文】 質問に対する意見文
④理科の出題範囲
【物理】 運動とエネルギー、電流と磁界、科学技術
【化学】 化学変化とイオン、酸・アルカリ
【生物】生命の連続性(遺伝)、細胞、生態系
【地学】 地球と宇宙、気象、地層と岩石
⑤社会の出題範囲
【地理】 日本・世界の地理、地形図・統計資料の読み取り
【歴史】 古代から近現代までの日本の歴史(年表・史料の読解)
【公民】 現代社会、政治、経済、国際社会
3.都立高校 共通問題 過去問の入手法と効果的な解き方
都立高校入試対策で最も効果的なのが過去問演習です。実際の試験形式に慣れ、時間配分の感覚を身につけることで、本番での得点力を大きく伸ばすことができます。
①過去問はどこで手に入る?
過去問は主に次の2つの方法で入手できます。
(1)東京都教育委員会の公式サイト
過去の試験問題と正答表が無料で公開されています。まずは公式サイトで問題の形式を確認してみましょう。
【公式サイトURL】:https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/admission/high_school/ability_test/
(2)市販の過去問題集
書店では、より多くの年度を収録した過去問題集が販売されています。詳しい解説やリスニングCD付きのものもあり、本格的な演習に最適です。最低でも5年分以上収録されているものを選ぶと安心です。
②過去問はいつから?何年分解くべき?
過去問は、やみくもに解くだけでは効果が半減してしまいます。適切な時期に、目的意識を持って取り組むことが大切です。
いつから始める?
何年分を解くべき?
最低でも過去3年分は解きましょう。余裕があれば5〜7年分に挑戦すると、より多くの出題パターンに触れることができます。
効果的な解き方「3つの鉄則」
1.本番と同じ時間で解く
必ず時間を計り、本番と同じ50分の制限時間で解きましょう。時間内に全問を解き終えるペース配分を身体で覚えることが重要です。
2.解きっぱなしにしない
丸付けをした後が最も大切です。なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを分析しましょう。解説をじっくり読み込み、分からなかった問題は必ず解き直してください。自力で理解が難しい場合は、塾や家庭教師に質問して確認するのも効果的です。
3.最低3回は繰り返す
同じ問題を最低3回は繰り返し解きましょう。1回目で見つかった弱点を、2回目、3回目で克服できているかを確認します。最終的にすべての問題を自力で満点で解ける状態を目指しましょう。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
4.【5教科別】都立高校 共通問題の入試傾向と具体的な対策
東京都教育委員会が公開する「都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表等」をもとに、国語・数学・英語・理科・社会の5教科の出題傾向と効果的な勉強法を解説します。 自分の得意・不得意に合わせて、効率的な対策を立てましょう。
①国語の入試傾向と対策
(1)出題分野と配点
国語は大問5問構成です。令和7年度(2025年度)入試でも構成や配点に大きな変更はなく、漢字だけで20点を占めるのが大きな特徴です。
| 大問 | 出題分野 | 配点 |
| 大問1 | 漢字の読み | 10点(5問) |
| 大問2 | 漢字の書き | 10点(5問) |
| 大問3 | 文学的文章の読解 | 25点(5問) |
| 大問4 | 説明的文章の読解+作文(200字) | 30点(4問+作文) |
| 大問5 | 古典を扱った対話文・解説文(200字) | 25点(5問) |
(2)各分野の入試傾向
◎大問1・2:漢字
【例年の傾向】
漢字の読み書き問題が各2点で出題されます。高校入試としては難易度は高くなく、特に大問2の書き取り問題は、小学校6年間で習ったものから出題されることがほとんどです。音読みと訓読みは、ほぼ半分ずつの割合で出題されています。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
読み・書きともに5問ずつ出題され、中学校の教科書レベルの標準的な問題が中心でした。取りこぼしなく確実に得点することが大切です。
◎大問3:文学的文章
【例年の傾向】
登場人物の心情を読み取る選択式問題が中心です。主人公は、受験生とほぼ同年代であることが多く、難易度は標準的です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
にしがきようこ『アオナギの巣立つ森では』からの出題でした。小学生の主人公の視点で物語が進み、登場人物の心情も比較的読み取りやすく、標準的な難易度でした。
◎大問4:説明的文章
【例年の傾向】
選択問題4問と200字作文が出題されます。題材は人類学・歴史・美術など幅広く、本文の主張に沿って自分の考えを論理的にまとめる力が求められます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
中田星矢『文化のバトンを受け継ぐコミュニケーション』からの出題でした。本文のテーマである「社会的学習」を踏まえ、自分の体験を交えて意見をまとめる力が必要でした。
◎大問5:古典
【例年の傾向】
いくつかの文章を組み合わせて出題されますが、古文や漢文を直接読む問題は少なく、全体として難易度は高くありません。文法問題(歴史的仮名遣い・助詞・係り受け)が頻出です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
和歌に関する対談文と、『六百番歌合』の解説文による複合形式で出題されました。設問はすべて選択式です。「ない」の意味と用法を問う文法問題も出題され、助動詞「ない」と形容詞「ない」を区別する力が求められました。
(3)効果的な対策・勉強法
◎大問1・2:漢字
漢字は最も確実に得点できる分野です。中学校で習う漢字を総復習し、読み書きを正確に仕上げましょう。書き取りでは、止め・はね・はらいに注意して丁寧に書くことが重要です。
◎大問3・4:読解・作文
読解問題では、本文中に必ず答えの根拠があります。選択肢を選ぶときは、「本文のこの部分にこう書いてあるから、この選択肢が正しい」と根拠をもとに説明できる状態を目指しましょう。
語彙力や表現力を高めるには、中高生向けの新書を月1冊程度読むのも効果的です。
作文では、180字以上を確実に書けるよう練習を重ねましょう。構成は次のパターンを意識すると安定します。
|
・本文の主張を簡潔に要約 ・それに対する自分の意見を具体的な体験を交えて述べる |
この「本文要約+自分の意見」の型を身につけておくと、どんなテーマにも柔軟に対応できます。
◎大問5:古典
「誰が・何に対して・どう考えているか」を整理しながら読むことが大切です。助詞の意味や用法、言葉の係り受けなどの文法問題は頻出なので、類題演習で反復練習を行いましょう。
◎時間配分の目安
国語は試験時間50分との戦いです。以下の時間配分を目安に、過去問演習でペースをつかみましょう。
|
●大問1・2 (漢字): 計4分以内 ●大問3・5 (小説文・古典): 各12〜15分 ●大問4 (説明文+作文): 残り約20分 |
時間のかかる作文は最後に回し、解きやすい問題から確実に得点していくのがおすすめです。
②数学の入試傾向と対策
(1)出題分野と配点
数学は 大問5問構成です。令和7年度(2025年度)入試でも、大きな構成変更はありませんでした。特に大問1(小問集合)が 46点 と高配点である点が特徴です。
| 大問 | 出題分野 | 配点 |
| 大問1 | 小問集合(計算、方程式、確率など) | 46点(9問) |
| 大問2 | 文章問題 | 12点(2問) |
| 大問3 | 関数 | 15点(3問) |
| 大問4 | 平面図形 | 17点(3問) |
| 大問5 | 空間図形 | 10点(2問) |
(2)各分野の入試傾向
◎大問1:小問集合
【例年の傾向】
計算力や基礎知識を幅広く確認する問題が出題されます。
問1〜問6では、正負の数・文字式・平方根・方程式などの基本的な計算問題が中心です。
問7では、確率・資料の活用・関数などの応用的な小問が出題されることが多く、2024年度には初めて「箱ひげ図」が登場しました。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
正負の数・文字式・平方根・方程式・確率・作図など、9問が出題されました。標準的な計算力と基礎知識が問われるため、ここで満点を狙うことが合格への第一歩です。
◎大問2:文章問題
【例年の傾向】
「先生が示した問題をもとに生徒が問題を作る」という設定の文章題形式が定番です。問2は証明問題が多く出題されます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
文章題をもとに連立方程式を立てる問題が出題されました。例年通り「先生が示した問題をもとに生徒が問題を作る」形式で、文章から条件を正確に読み取る力が問われました。条件を文字式で整理すれば解きやすく、難易度自体は高くありませんでした。
◎大問3:関数
【例年の傾向】
一次関数と二次関数に関する問題が出題されます。放物線の変域や2点を通る直線を求める問題は頻出です。関数と図形の融合問題も多く、関数分野全体の理解が問われます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
一次関数のグラフと図形を組み合わせた問題が出題されました。座標計算や面積の求め方など、関数の基本を確実に理解していることが求められました。
◎大問4:平面図形
【例年の傾向】
合同・相似・円周角などの性質を利用する問題が中心です。やや複雑な条件が設定されることもあり、与えられた情報を整理して筋道立てて解く力が求められます。証明問題が毎年出題されるため、書き方の型を練習しておきましょう。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
円周角の定理や三角形の合同・相似を利用した証明問題が出題されました。図形の性質を正確に理解し、論理的に記述する力が問われました。
◎大問5:空間図形
【例年の傾向】
平面図形や三平方の定理と組み合わせた問題が定番で、辺の長さや体積を求める問題が頻出です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
立体の体積・表面積を求める問題が出題されました。平面図形や三平方の定理を活用し、複数の知識を組み合わせて考える総合力が問われました。
(3)効果的な対策・勉強法
◎計算力を徹底的に鍛える
大問1は確実に得点できる分野です。毎日コツコツと計算練習を続け、速く・正確に解く力を養いましょう。
正負の数、文字式、平方根、方程式など、幅広い分野の計算に慣れておくことが重要です。「途中計算の工夫」や「符号ミスをなくす」ことを意識し、15分以内で全問解き切ることを目標に練習しましょう。
◎過去問で出題パターンを身体に覚え込ませる
都立数学の共通問題では、出題単元や問題形式がある程度決まっています。
一次関数・証明・空間図形など、過去問を繰り返し解くことで「このタイプならこう解く」という解法パターンを身につけましょう。数字や設定を変えて再登場することが多いため、パターンの定着が得点力に直結します。
◎「なぜそうなるのか」を説明できるようにする
応用問題や証明問題では、答えを導くだけでなく「なぜその式や考え方になるのか」を説明できることが大切です。「なぜその公式を使うのか」「なぜ相似が成り立つのか」を自分の言葉で整理する練習をしておくと、記述問題でも強くなります。
◎時間配分を意識して解く
数学の試験時間は50分です。難問に時間を使いすぎると、解けるはずの問題を落としてしまうことがあります。以下を目安に時間配分を意識しましょう。
|
●大問1:15分以内 ●大問2〜5:残り35分 |
「時間がかかりそう」と感じた問題は一度後回しにし、解ける問題から確実に得点する戦略が重要です。
③英語の入試傾向と対策
(1)出題分野と配点
英語は、大問4問構成。令和7年度(2025年度)入試でも、リスニングと読解問題が中心の構成に変更はありませんでした。
| 大問 | 出題分野 | 配点 |
| 大問1 | リスニング | 20点(5問) |
| 大問2 | 図表の読み取り(英作文あり) | 24点(4問+英作文) |
| 大問3 | 長文読解(対話文形式) | 28点(7問) |
| 大問4 | 長文読解(対話文) | 28点(7問) |
(2)各分野の入試傾向
◎大問1:リスニング
【例年の傾向】
A(対話文)とB(スピーチ)の2部構成です。Aは対話文を聞いて内容に合う選択肢を選ぶ問題、Bはスピーチを聞いて英語で答える記述問題が出題されます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
問題Aでは対話文と質問を聞いて内容に合う選択肢を選ぶ問題が3問、問題Bでは商業施設の館内放送を題材にした選択問題と記述問題が1問ずつ出題されました。
◎大問2:図表の読み取り・英作文
【例年の傾向】
パンフレットや地図などの資料をもとに、会話文やメール文の内容を読み取る問題です。「3文で書く」という条件つきの英作文(12点相当)が出題されるのが特徴です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
日本の高校生と留学生の会話を題材に、空欄を補う選択問題、Eメールの内容に一致する選択肢を選ぶ問題、Eメールの内容を完成させる英作文が出題されました。英作文は例年通り「3文で書く」指定があり、文の構成力と語彙の正確さが求められました。
◎大問3:対話文の読解
【例年の傾向】
やや長めの会話文を読み取り、登場人物の意見や関係性を理解する力が問われます。語彙レベルは英検3級程度で、傍線部前後を読めば答えにたどり着ける問題が中心です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
3人の中学生と留学生の対話文が出題されました。指示語や代名詞の内容を問う選択問題が多く、本文の下線部前後を丁寧に読むことで答えの根拠を見つけやすい構成でした。
◎大問4:物語文の読解
【例年の傾向】
登場人物の心情や行動理由を読み取る問題が中心です。傍線部の示す内容を答える問題、ストーリーに沿って選択肢を並び替える問題、本文の内容を問う問題が出題されます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
地域のボランティア活動を題材にしたスピーチ形式の物語文が出題されました。本文内容の理解を問う問題のほか、指示語の内容を答える問題や、物語の時系列に沿って英文を並べ替える問題が出題されました。
(3)効果的な対策・勉強法
◎毎日5分でもOK!単語学習を習慣にする
語彙力は一朝一夕には身につきません。英検3級レベルの単語帳を1冊決め、毎日少しずつでも良いので繰り返し学習しましょう。「通学中の電車で10個覚える」など、生活の一部に組み込むのが継続のコツです。
◎リスニングは「耳を慣らす」ことが最重要
リスニング問題の音声は英検3級より若干速めです。過去問の音声を1.25倍速で聞く、洋楽・海外ニュース・映画を英語音声で視聴するなどして、スピードと発音に慣れましょう。
「内容を完璧に理解する」よりも、「聞き取れる音を増やす」ことを意識してトレーニングするのが効果的です。
◎長文読解は「先に設問を読む」
試験時間50分では、全文を最初にじっくり読むのは非効率です。本文を読む前に設問をざっと確認し、「何を問われているか」「本文のどこを探せばよいか」を意識して読み始めましょう。本文中の根拠を探しながら読む練習を重ねることで、スピードと正確さを両立できます。
◎英作文は「簡単な文」で正確に書く
高得点を狙うには、難しい単語や複雑な構文にこだわらず、自分が確実に正しく書ける簡単な文法・単語で表現することが大切です。
例えば、「I think that ~ because …」「It is important for me to …」のような基本表現をいくつかストックし、3文で書く練習を重ねましょう。3文の中で主張・理由・まとめが揃っているかを確認すると、内容も明確になり、減点を防ぐことができます。
④理科の入試傾向と対策
(1)出題分野と配点
理科は大問6問構成。令和7年度(2025年度)入試でも、各分野から幅広く出題される構成に変更はありませんでした。
| 大問 | 出題分野 | 配点 |
| 大問1 | 小問集合(物理・化学・生物・地学) | 24点(6問) |
| 大問2 | 小問集合(物理・化学・生物・地学) | 16点(4問) |
| 大問3 | 地学 | 16点(4問) |
| 大問4 | 生物 | 12点(3問) |
| 大問5 | 化学 | 16点(4問) |
| 大問6 | 物理 | 16点(4問) |
(2)各分野の入試傾向
◎大問1・2:小問集合
【例年の傾向】
4分野(物理・化学・生物・地学)の基礎知識を幅広く問う問題が出題されます。特に大問2は「レポートを読んで答える形式」で、レポート内の文章や図を丁寧に読み取る力が求められます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
例年通り、4分野の基礎知識をまんべんなく問う構成でした。
大問2は毎年恒例の「レポートを読んで答える形式」で、4問中2問が完答形式(すべて正解して初めて得点になる設問)でした。情報量が多く、文や図表から内容を正確に読み取る力が求められました。
◎大問3:地学
【例年の傾向】
天気と天体の問題が毎年出題され、岩石、地震、地質の問題も頻出です。グラフや模式図、観察記録をもとに推論する問題が多く、知識とデータの関連付けが求められます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
地質と岩石をテーマにした問題が出題され、観察結果の表や模式図をもとに知識とデータを組み合わせて考える問題でした。
◎大問4:生物
【例年の傾向】
人体や植物に関する問題が頻出です。遺伝や生殖の問題は以前はよく出題されていましたが、最近は出題頻度が低めで、今後の出題に注意が必要です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
タマネギの根の細胞分裂を題材に出題されました。顕微鏡観察の結果をもとに、各分裂期の特徴を比較する設問や、図の情報を読み取る問題が中心で、資料と知識を照らし合わせて正確に読み取る力が求められました。
◎大問5:化学
【例年の傾向】
化学変化・イオン・物質の特徴を問う問題が毎年出題され、計算問題も頻出です。実験結果の把握だけでなく、目的や手順などの理解も必要です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
化学変化に関する問題が出題され、反応前後の質量変化や生成気体の種類を考える問題など、知識と計算を組み合わせて考える力が求められました。
◎大問6:物理
【例年の傾向】
電流と磁界、運動、光などが頻出です。特に電流と磁界の関係は毎年登場する定番分野です。グラフや文章・図・計算を組み合わせた総合問題も多く、法則性を見つける思考力が求められます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
電流と磁界をテーマにした問題が出題され、電磁誘導の法則やコイルの向きと電流の関係を、実験結果や図をもとに論理的に考える力が求められました。2021年度の出題と共通点があり、過去問題を理解しておくことが有効です。
(3)効果的な対策・勉強法
共通問題の理科は、単語や公式の暗記だけでは対応できない問題が多いのが特徴です。
図や表の読み取り、実験や観察の考察、計算を伴う問題など、思考力や読解力が必要な問題が得点差を生むポイントとなります。
問題文の前置きが長く情報が多い問題は、重要な箇所に線を引くなどして整理しながら読む練習をしておきましょう。
|
【重点的におさえておきたい内容】 ●主な実験器具・指示薬の使い方 ●化学反応式・電離式の書き方 ●グラフや表の読み取り方 |
天体分野は3年生の後半に学習するため演習時間が限られます。短期間でも集中して演習を行い、自信を持って解けるようにしておきましょう。
⑤社会の入試傾向と対策
(1)出題分野と配点
社会は、大問6問の構成で100点満点です。日本地理、世界地理、歴史、公民の出題割合はほぼ均等ですが、日本地理と世界地理をまとめて「地理」と考えると、出題割合はおおむね2:1:1です。
| 大問 | 出題分野 | 配点 |
| 大問1 | 小問集合 | 15点(3問) |
| 大問2 | 世界地理 | 15点(3問) |
| 大問3 | 日本地理 | 15点(3問) |
| 大問4 | 歴史 | 20点(4問) |
| 大問5 | 公民 | 20点(4問) |
| 大問6 | 総合 | 15点(3問) |
(2)各分野の入試傾向
◎大問1:小問集合
【例年の傾向】
地理・歴史・公民の基礎知識を問う定番問題です。地形図の読み取り、用語選択、歴史年表や制度用語から出題されます。等高線や縮尺、方位の問題も毎年登場し、基本的な図の読み取り力が求められます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
例年通り、地形図の読み取りや歴史・公民の基本用語を選択する問題でした。
「方位マーク」を読み取る設問や、逗子駅と海岸の位置関係をもとに地点を特定させる問題など、図と文章を組み合わせた判断力が問われました。
◎大問2:世界地理
【例年の傾向】
気候・輸出・産業・地形・宗教などの知識を、資料や地図と関連づけて問う出題が定番です。雨温図や統計資料の読み取り、国の特色を示す文章から国を特定する問題も頻出です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
条件を満たす都市や国を選ぶ問題、雨温図・統計資料の読み取り問題が出題されました。文章中のキーワード(気候・主要産業など)を手がかりに、地図上で国を特定する形式でした。
◎大問3:日本地理
【例年の傾向】
都道府県名の特定、統計資料やグラフの読み取り、地域の産業や気候の特色を問う問題が多く、記述も含まれます。「資料をもとに理由を述べよ」といった形式が定番です。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
都道府県名の特定問題に加え、資料・統計から答える記述問題が出題されました。記述では、設問条件を正確に読み取り、簡潔にまとめる力が必要でした。
◎大問4:歴史
【例年の傾向】
出来事を年代順に並べ替える問題、年表の穴埋め、資料の読み取り問題が定番です。江戸時代の改革を行った人物や政策は繰り返し出題される頻出テーマです。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
人物や出来事の並び替え問題、年表の穴埋めなど例年通りの形式でした。前近代・近現代の文化・制度を資料と絡めて問う設問もあり、歴史知識だけでなく資料解読力も求められました。
◎大問5:公民
【例年の傾向】
人権・憲法・制度・経済などの基本知識を問う問題が中心です。思考力・判断力・表現力を問う記述問題も出題されます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
基本的人権や条件に合う法律を選択する問題、文章やグラフを活用した記述問題が出題されました。
◎大問6:総合
【例年の傾向】
地理・歴史・公民の知識を統合して問う融合問題です。文章・グラフ・地図を組み合わせ、複数の観点から答えを導く設問が出題されます。
【令和7年度(2025年度)の傾向】
国の特定、グラフと文章の読み取りが出題されました。グラフの内容を正確に読み取り、文章中の記述と照らし合わせて根拠をもって選択肢を判断する力が求められました。
(3)効果的な対策・勉強法
共通問題の社会では、単なる暗記力よりも「語句の意味や背景を理解しているか」が重視される傾向にあります。 知識を丸暗記するのではなく、「なぜそうなるのか」「どのような関係があるのか」を意識して学ぶことが得点アップの鍵です。
◎地理分野
各国・都道府県の特徴だけでなく、地域全体の気候・産業・歴史的背景を関連付けて理解することが大切です。地図帳や資料集を活用し、興味を持って学ぶことで記憶にも残りやすくなります。
◎歴史分野
世界の出来事と日本の出来事の関連を意識しましょう。時代ごとのつながりを整理し、「世界史の動きの中で日本がどう変化したか」を理解することが大切です。ニュースや時事問題にも関心を持ち、最新の社会情勢を自分の言葉で説明できるようにしておくと安心です。
◎公民分野
基本的人権や制度の知識を確実に押さえ、文章やグラフを読み解く力を身につけておくことが重要です。
5.家庭でできる「都立共通問題校」受験サポート
ここでは、都立共通問題校の受験に向けて、ご家庭でできるサポートや声かけのポイントを紹介します。
日々の悩みや不安を受け止める
受験期のお子様は、「思うように成績が伸びない」「本当に合格できるのだろうか」といった不安や焦りを抱えています。一番大切なのは、その気持ちを否定せずに受け止めてあげることです。
「もっと頑張りなさい」と励ますよりも、「そうか、不安なんだね」と共感の言葉をかけてあげましょう。話を聞いてもらえるだけで、お子様の心は軽くなります。
模試の結果が思わしくないときも、感情的に叱るのは避けましょう。結果を責めるよりも、「次のテストでどこを伸ばせるか見つかったね」と前向きな視点を示してあげることで、お子様のモチベーション維持につながります。
お子様が落ち着いていられる環境を整える
ご家庭がお子様にとって、心身ともに休まる「安全基地」であることが理想です。
生活リズムを整えるサポート
朝食や夕食の時間を一定に保つ、就寝時間を決めるなど、規則正しい生活リズムを維持できるようサポートしてあげましょう。質の良い睡眠と栄養バランスの取れた食事は、記憶力や集中力を保つうえで欠かせません。
勉強に集中できる環境をつくる
勉強中はテレビの音量を下げる、兄弟姉妹に静かにするよう伝えるなど、ご家庭全体で協力できると理想的です。
また、スマートフォンやゲーム機を一時的に預かるなど、集中を妨げる要因を減らすルールを一緒に決めておくのもおすすめです。
ご家庭のサポートは、お子様にとって大きな支えになります。焦らず、どっしりと構えてお子様を見守ってあげてください。
都立共通問題校受験に向けて、対策をはじめよう
今回は、都立高校「共通問題校」の受験を考えているお子様をお持ちのご家庭に向けて、共通問題校攻略のポイントをご紹介しました。
共通問題の出題範囲は、中学校で学ぶすべての内容に及びます。つまり、学校で配布されている教科書の内容をしっかり理解しておくことが基本です。各教科の入試問題の形式や、よく出題される単元を分析することで、効率的に学習の計画を立てることができます。本記事の内容を、ぜひ学習計画作りの参考にしてください。
「受験勉強の進め方に不安がある」「効率よく対策したい」といった場合は、家庭教師による個別サポートもおすすめです。
まずはご相談からでも大丈夫です。志望校合格に向けた第一歩として、気軽にお問い合わせください。
【参考】
東京都教育委員会「都立高等学校入学者選抜 学力検査問題及び正答表等」
共通問題校対策・高校受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
高校受験の合格体験記
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
都立高校 共通問題対策なら東大家庭教師友の会
あわせてチェック|高校受験対策を解説!