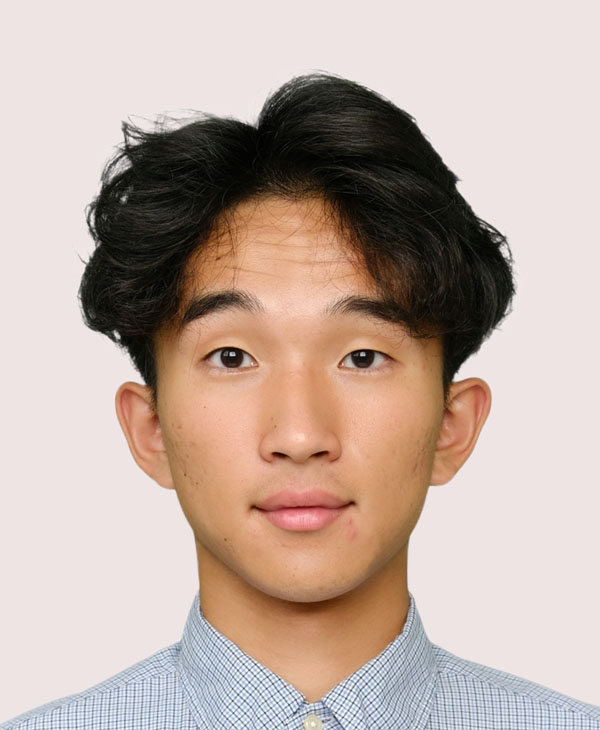![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業実施中!
1.【2026年度入試向け】都立自校作成校 難易度ランキング一覧
まずは、自校作成校(独自問題)の対象となる11校と、その偏差値・倍率の目安を一覧で確認してみましょう。志望校選びや学習計画を立てる際の参考にしてください。
| 学校名 | 偏差値 | 倍率 | 区分 | 独自作成科目 |
| 日比谷高校 | 73 | 1.57倍 | 進学指導重点校 | 国語・数学・英語 |
| 国立高校 | 73 | 1.42倍 | ||
| 西高校 | 72 | 1.31倍 | ||
| 戸山高校 | 71 | 1.74倍 | ||
| 立川高校 | 71 | 1.40倍 | ||
| 青山高校 | 70 | 1.72倍 | ||
| 八王子東高校 | 70 | 1.41倍 | ||
| 新宿高校 | 68 | 1.72倍 | 進学重視型単位制高校 | |
| 国分寺高校 | 68 | 1.54倍 | ||
| 墨田川高校 | 60 | 1.05倍 | ||
| 国際高校 | 68 | 1.50倍 | 国際学科 | 英語 |
※偏差値:「みんなの高校情報」より2025年4月入学者向け模試の結果を基にした数値です。教育内容等の優劣を示すものではありません。偏差値は模試の受験者層によって変動するため、あくまで目安としてご活用ください。
※倍率:東京都教育委員会「令和7年度東京都立高等学校入学者選抜受検状況」より引用。
進学指導重点校(7校)
都立高校の中でも、特に難関大学への進学指導に力を入れることを目的に指定されたトップ校です。伝統校が多く、学習面だけでなく学校行事にも力を入れているのが特徴です。
進学重視型単位制高校(3校)
進学指導重点校に次ぐ進学実績を持つ学校群です。大学進学を重視する点は重点校と同じですが、生徒が自分の興味や進路に合わせて自由に授業を選択できる「単位制」が特徴です。
国際高校(1校)
英語の授業時間が多く、帰国子女や在京外国人の生徒も多く在籍しています。英語のみ自校作成問題(独自問題)が出題されます。
このように、自校作成校は都内でもトップクラスの難関校がそろっています。
では、これらの学校が独自に実施する「自校作成問題」と、一般的な都立高校入試で使われる「共通問題」にはどのような違いがあるのでしょうか。次章で詳しく解説します。
2.都立高校入試の自校作成校とは?共通問題との3つの違い
自校作成校とは、都立高校の中でもトップクラスの進学校が、入試問題の一部を独自に作成する学校のことです。
●国語・数学・英語(リスニングを除く)の3教科を自校で作成する学校
日比谷・国立・西・戸山・立川・青山・八王子東・新宿・国分寺・墨田川
●英語のみ自校で作成する学校
国際
これらの学校が実施する「自校作成問題」と、他の都立高校で使われる「共通問題」にはどのような違いがあるのでしょうか。
違い①:求める人材像
まず根本的な違いは、「どのような生徒に入学してほしいか」という学校側の人材像です。
●共通問題
中学校の学習内容が、基礎から標準レベルまでしっかり定着しているかを確認するのが主な目的です。
●自校作成問題
難関大学進学やその先を見据えた教育を行うため、単なる知識だけでなく「自ら考える力」や「表現する力」を持った生徒を求めています。
言い換えれば、自校作成問題は学校からの「高度な授業に対応できる力を持っていますか?」というメッセージでもあるのです。
違い②:問題の傾向(知識を問うか vs 思考力を問うか)
求める人材像が違うため、問題の傾向も異なります。
共通問題はマークシート形式が中心ですが、自校作成問題では記述式の比重が高く、思考力や表現力を問う問題が多く出題されるのが特徴です。
●共通問題
教科書知識や基本的な解法を覚えていれば、比較的ストレートに解答できる問題が中心です。
●自校作成問題
知識があるのは大前提。その上で、複数の知識を組み合わせたり、複雑な条件を整理したりしないと解けない、初見の問題が多く出題されます。
例えるなら、共通問題が「交通ルールを知っているか試す筆記試験」だとすれば、自校作成問題は「実際の路上で、予期せぬ事態に対応しながら運転できるか試す路上試験」のようなものです。
違い③:合否をわける力(速さ・正確さ vs 応用力・記述力)
出題傾向が違うため、合格に必要な力も変わってきます。
●共通問題
幅広い知識を、時間内に正確に処理する「正確さ」と「スピード」が重視されます。
●自校作成問題
複雑な問題文を読み解く「読解力」、答えまでの道筋を論理的に組み立てる「思考力」、それを自分の言葉で表現する「記述力」が求められます。
もちろん自校作成校でも正確さやスピードは必要ですが、それ以上にじっくり考え抜く思考力や応用力といったワンランク上の力が合否の決め手となります。
3.【教科別】都立自校作成校の出題傾向と対策ポイント
この章では、国語・数学・英語それぞれの出題傾向と、合格点を確保するための対策ポイントを詳しく解説します。効率的な学習の参考としてご活用ください。
①国語の出題傾向と対策
●問題の特徴
共通問題に比べて課題文の分量が多く、文章の難易度も高い傾向があります。 語彙も教科書レベルを超えた言葉が多く登場し、読み慣れていないと内容を理解するのに時間がかかります。
近年は大学入試改革の影響を受け、図や表から情報を読み取る問題や、2つの課題文を比較して考察させる問題など、複数の情報を組み合わせて読み解くような問題が出題されています。
記述式だけでなく「最も適切な選択肢を記号で選ぶ」タイプの問題も多く、選択肢自体に情報量が多いのが特徴です。文章を正確に読み取る力と、細部まで丁寧に確認する姿勢が求められます。
●合格点をとるための対策
まず長めで難度の高い文章に日常的に触れることが大切です。 新書や評論文などを活用し、教科書レベル以上の文章に読み慣れておきましょう。
漢字は漢検2級程度を目安に学習しておくと、文章理解や知識問題の両方に効果的です。
また、図表を含む問題や一つの大問で複数の課題文を扱う問題にも取り組み、最新の出題傾向に慣れておくと安心です。
●類題として挑戦しておきたい他の難関校の過去問
選択式の問題に慣れるためには、東京学芸大学附属高校の過去問に挑戦するとよいでしょう。
記述力を伸ばすには、慶應女子高校や開成高校の過去問が有効です。
また、選択問題と記述問題の両方が出題される桐光学園高校の過去問もおすすめです。
②数学の出題傾向と対策
●問題の特徴
数学は共通問題に比べて出題数が少なめです。
その代わり、答えを導くまでに複数のステップを踏む必要があり、解答に時間がかかる傾向があります。
ただし、出題分野自体は大きく変わることがほとんどないため、各校の傾向を把握しやすい点は安心材料です。
近年は、作図や証明、途中の計算過程の記述を求める問題が増えており、単に答えを出すだけでなく、解答の過程を論理的に整理する力が求められます。
●合格点をとるための対策
まずは過去問を分析して頻出分野を把握することが大切です。
記述式問題や作図・証明問題が多いため、解答の過程を整理して書く力(記述力)が重視されます。家庭教師や塾での添削指導を受けると、効率よく力を伸ばせます。
よく出題される分野の様々なタイプの問題に取り組み、問題を見た段階で答えまでの道筋がイメージできるようにすると、試験本番でも安心です。
●類題として挑戦しておきたい他の難関校の過去問
自校作成校の数学は、手間はかかるものの、奇問・変則問題は少ない傾向があります。そのため、オーソドックスな難関私立校の入試問題を幅広く演習することが有効です。特に、慶應義塾、早稲田実業、早稲田高等学院、淑徳、栄東などの問題に触れておくと、自校作成校の問題を解くうえでよい練習になるでしょう。
逆に、私立難関校で稀に出題される「ひらめきが必要な問題」は、自校作成校では出題される可能性が低いため、優先度は下げて構いません。
③英語の出題傾向と対策
●問題の特徴
長文読解では、自然科学系の題材が出題されやすい傾向があります。
共通問題では、本文中に答えの根拠がほぼ明確に示されていることが多いのに対し、自校作成校では、根拠の表現が変えられていたり、傍線部から離れた箇所に書かれていたりする場合があり、一筋縄では回答できない問題が出題されます。
●合格点をとるための対策
特に重点的に対策したいのは、長文読解と英作文です。
長文読解の総語数は、共通問題が約2000語程度なのに対し、自校作成校では2300~3000語とやや長めです。読むスピードも大切ですが、最も重要なのは、求められている情報を正確に読み取る力です。
文章中で「見たことはあるはずなのに意味が分からない単語」は、その都度確実に理解していくことが必要です。
英作文では、単語のスペルミスや文法ミスが命取りになります。日頃から自分の使いこなせる文法・単語で正確に文章を作る練習をしましょう。数学の記述問題と同様に、家庭教師や塾の先生に添削してもらうのもおすすめです。
●類題として挑戦しておきたい他の難関校の過去問
早稲田・慶應系列校の長文問題が自校作成校の問題に類似しており参考になります。特に慶應女子高校は科学分野の長文が出題されるため、進学指導重点校を志望する受験生にとって有効な練習となります。
④「都立国際高校」を受験する場合の独自対策
都立国際高校の入試では、英語の難易度が他の自校作成校より高いため、十分な対策が必要です。
都立国際高校には、国際バカロレアコースと国際学科の2コースがありますが、ここでは国際学科の一般入試について解説します。
●出題内容:長文読解・英文法・英作文
●英作文:80~100語程度の文章作成
●長文読解・文法問題:英検2級程度の英語力があると安心
海外経験があるなど英語が得意なお子様も、出題形式に慣れ、正確な文法で回答できるよう事前に練習しておくことをおすすめします。
4.自校作成校の受験勉強はいつから始めるべき?開始時期の目安
「自校作成校の対策は、いつから始めれば間に合うの?」これは、多くの受験生や保護者の方が抱える悩みのひとつです。
結論から言うと、スタート時期の目安は以下の通りです。
結論:理想は中2の冬から、遅くとも中3の春までにはスタートを
自校作成校の入試では、中学3年間で習うすべての範囲から、思考力を問う応用問題が出題されます。そのため、中学3年生になってから慌てて準備を始めると、基礎固めと応用演習の両立が難しくなります。
中学2年生の冬は、部活動も本格化する前で比較的学習時間を確保しやすい時期です。この段階で中学1・2年生の学習内容、特に苦手分野を完璧に復習しておけば、中学3年生になったときにスムーズに応用問題の演習へ移行できます。
もし部活動などで忙しく、開始が遅れたとしても、中学3年生の春休みまでには受験勉強を本格化させましょう。
中学3年生になると、学校の授業内容も難しくなり、定期テストや学校行事にも追われるため、基礎からじっくり復習する時間はほとんど取れなくなります。
「もう中3の夏になってしまった…」という場合でも、諦める必要はありません。大切なのは、残された時間を最大限効率的に使うことです。まずは現状を正確に把握し、志望校の過去問を参考に、どの単元を優先すべきかを決めて集中的に勉強しましょう。
効果的に対策を進めたい方へ
自校作成校は学校ごとに出題傾向や難易度が異なるため、一人ひとりに合わせた個別の学習が欠かせません。
「どう進めてよいか分からない」「記述の添削をしてほしい」「家庭だけでは不安」という場合は、家庭教師による個別サポートもご検討ください。
高校受験に詳しい教師がお子様の状況に応じた最適な対策プランをご提案します。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
5.家庭でできる「自校作成校」受験のサポート方法
自校作成校という高い目標に挑むお子様にとって、ご家庭のサポートは大きな力になります。「過干渉にならずに、どうやって応援すればいいの?」と悩まれる保護者様も少なくありません。
ここでは、ご家庭ですぐに実践できる具体的なサポート方法を2つご紹介します。
①学習計画を「見える化」して共通問題とのバランスをとる
自校作成校を目指すと、どうしても独自問題(国・数・英)に重点を置きがちです。 しかし、どの自校作成校もハイレベルな受験生が集まるため、理科・社会で確実に点数を取ることが合否に大きく影響します。
そこで効果的なのが、学習計画を「見える化」することです。
例えば、カレンダーや学習アプリを使って「今日は英語長文」「今週は理科の一問一答」といった取り組み内容を記録しておくと、学習の偏りを防ぎやすくなります。
自校作成校を目指すお子様は、すでに一定の学習習慣が身についていることが多いでしょう。
そのため保護者様が「勉強しなさい」と指示するのではなく、テスト結果や学習計画を一緒に確認しながら、声かけをするのが効果的です。
例えば、「理科や社会の進み具合はどう?」と尋ねることで、お子様自身が各教科のバランスを意識しながら学習を進めやすくなります。
②親子の対話で記述力の土台となる思考力を育む
ご家庭での食卓やリビングでの何気ない会話は、思考力を鍛える絶好のトレーニングの場になります。
自校作成校の入試では、時事ニュースや社会問題など、大人でも考えさせられるテーマが長文の題材として出題されることがあります。そうした問題に初めて直面したとき、少しでも聞き覚えのあるテーマであることが、お子様の心理的なハードルを大きく下げてくれます。
普段の会話の中で、「最近の○○のニュース、どう思う?」と、ぜひお子様の意見を聞いてみてください。大切なのは、正解を求めるのではなく、お子様が自分の考えを持ち、言葉にすることです。
こうした対話を重ねることで、記述問題に対応できる思考の幅が広がるだけでなく、高校進学後も自分の考えを持って物事に向き合える力が自然と身につきます。
6.自校作成校受験に向けて、対策をはじめよう
自校作成校の問題は、各高校の求める生徒像に基づいて作られているため、学校ごとに特徴や傾向に違いがあります。
ただし共通しているのは、共通問題では測りきれない思考力や表現力を問う問題が多く、正確さやスピードも同時に求められるという点です。
こうした力を身につけるには、できるだけ早い段階から計画的に対策を始めることが大切です。 まずは志望校の過去問に親子で目を通し、出題の特徴をつかむところから始めてみましょう。
「何から取り組めばよいか分からない」「家庭だけでの対応に不安がある」という場合は、家庭教師によるサポートの活用もおすすめです。お子様の目標や学力に合わせて、最適な学習プランをご提案いたします。
まずはご相談だけでも大丈夫です。お気軽にお問い合せください。
自校作成校対策・高校受験の指導が可能な家庭教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
高校受験の合格体験記
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
家庭教師が自校作成校合格へのサポートをいたします
あわせてチェック|高校受験対策を解説!