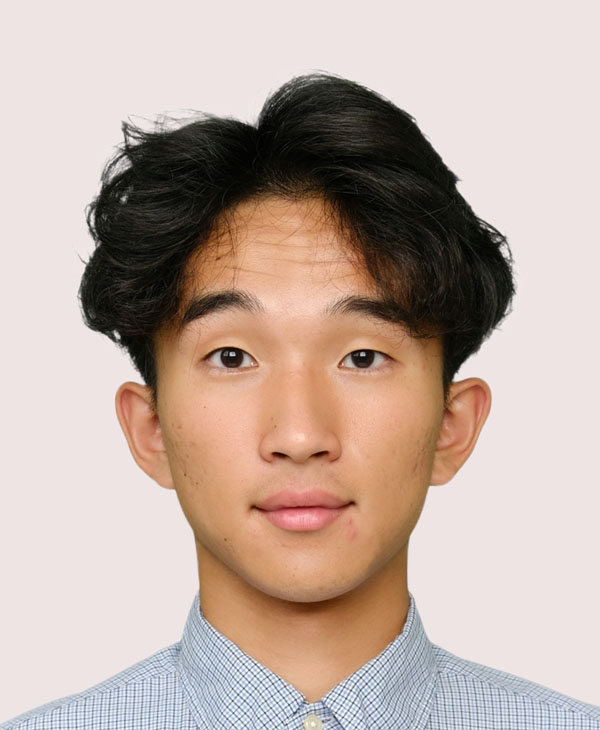![]() 家庭教師に相談する
家庭教師に相談する
無料体験授業実施中!
1.中学の定期テストで450点を取るのはどれくらい難しい?高得点のポイント
定期テストで450点を取るというのは、5教科合計で平均90点以上を取ることを意味します。1教科でも大きく失点するとすぐに目標から遠ざかってしまう、非常に高いレベルです。
① 5教科すべてで平均90点以上が必要
「得意な科目で苦手な科目をカバーする」という考え方では、450点に到達するのは困難です。例えば1科目で80点を取ってしまった場合、他の4科目で95点以上を取らなければ、目標には届きません。苦手科目を放置せず、全体を底上げする意識が不可欠です。
② 丸暗記では通用しない、本質的な学力が求められる
教科書やワークの内容をただ暗記するだけでは、安定して90点以上を取ることは難しいです。定期テストには、必ず応用問題や思考力を試す問題が含まれています。これらの問題に対応するためには、「なぜそうなるのか」という本質的な理解を深め、応用力を鍛えることが高得点へのカギとなります。
③ 高校受験で難関校を狙えるレベル
定期テストで450点を安定して取れる力がつくと、高校受験でも難関校を十分に狙える学力に到達しています。
通知表の評定も高くなり、内申点が有利に働きます。「自分の勉強法は正しい」という確信が持てるため、大きな自信と次へのモチベーションにつながるでしょう。
このように450点は決して簡単ではありませんが、到達できれば学力・自信・進路すべてに良い影響をもたらします。
次章では、なぜ点数が伸び悩むのか、その原因を見ていきましょう。
2.中学生の定期テストで点数が伸び悩む4つの原因

さらなる得点アップを目指すためには、まず今の勉強法を見直し、点数が伸び悩む原因を明らかにすることが欠かせません。
ここでは、多くの中学生がつまずきやすい4つの原因を解説します。
①テスト本番を意識できず、勉強効率が悪い
「すべての勉強内容をノートにまとめる」「同じ問題集を何周もする」──このような勉強に時間をかけすぎていませんか?
限られたテスト対策期間で成果を出すには、試験本番から逆算し、優先順位をつけて勉強することが大切です。闇雲に時間をかけるだけでは、本当に必要な対策がおろそかになってしまいます。
②問題を解くスピードが遅く、時間が足りない
問題の解き方はわかっているのに、最後の問題までたどり着けない…これは意外と多い失点パターンです。
90点以上を狙うなら、制限時間内に全ての問題を解き切れるスピードを意識する必要があります。普段の演習から時間を計るなど、本番を想定した練習をしましょう。
③ケアレスミスが多い
解き方を理解していても、計算ミスや解答の写し間違い、条件の読み落としなどで数点を落としてしまうケースは少なくありません。
安定して高得点を取るには、ケアレスミスを防ぐための対策が必要です。例えば、計算過程を丁寧に書く、解答を書き写す前に指差し確認をする、問題文の条件に印をつけ読み落としを防ぐ、といった習慣をつけましょう。
④応用力・思考力が不足している
定期テストでは、教科書やワークの類題だけでなく、初めて見るような応用問題が必ず出題されます。基本的な問題が解けるだけでは、90点以上の高得点には届きません。
高得点を狙うためには、日頃から「なぜそうなるのか?」という疑問を大切にしましょう。原理や法則を深く理解しようと努めることが、単なる暗記ではない本物の思考力を養い、応用問題も解ける力につながります。
3. 定期テストで高得点(450点以上)を取るための勉強計画

450点を安定して取るためには、ただ「長時間勉強する」だけでは足りません。いつ・どの教科に・どれくらい時間を使うのかを明確にし、効率よく学習を進めることが必要です。
ここでは、勉強時間の目安やスケジュールの立て方、時期別の具体的な対策方法を紹介します。
①勉強時間・スケジュールの目安
高得点(450点以上)を目指す場合、目標となる勉強時間は以下の通りです。
・普段(平日):1~3時間程度
・普段(休日):3~5時間程度
・テスト2週間前〜直前(平日):4〜5時間程度
・テスト2週間前〜直前(休日):6~8時間程度
ここで大切なのは「ただ時間を増やす」のではなく、教科ごとの優先順位をつけること です。苦手科目に重点を置きつつ、得意科目は短時間で高得点をキープできるよう効率よく回すのがポイントです。
また、勉強のスケジュールは「やる気に左右されない仕組み」にするのがおすすめです。例えば、「月曜・水曜は英語、火曜・木曜は数学を重点的に」といった固定ルールや、「寝る前の30分は必ず暗記科目(英単語や理社の用語)に充てる」といった習慣を決めておけば、迷わず勉強に取り組めます。
②時期別の定期テスト対策方法
テスト勉強は「直前に詰め込む」だけでは効果が出ません。
「普段からの積み重ね → テスト2週間前 → 数日前・直前」の流れを意識することで、安定して450点を狙える計画が立てられます。
(1)普段からできること
大前提として、全科目で満点を目指す意識を持ちましょう。
そのためには、次の習慣を日常的に続けることが大切です。
・授業の予習・復習を欠かさず、その日の疑問はその日のうちに解決する
・問題集を少しずつ進めて演習量を確保する
・英単語・漢字・理社の用語など、基礎知識を毎日コツコツ覚える
こうした積み重ねがあれば、テスト直前期に「応用問題対策」に時間を割くことができます。
(2)テスト2週間前
ここからが本格的なテスト勉強のスタートです。
1.目標を設定する
「次の定期テストで450点以上を取る」「学年10位以内に入る」など、数値で明確にすることがポイントです。
2.やるべき勉強を洗い出す
テスト範囲を確認し、自分の得意・不得意を整理して「どこに時間をかけるか」を決めましょう。
3.計画を立てる
テスト当日から逆算し、1日ごとの勉強内容を手帳やアプリに落とし込みます。
注意したいのは、「時間のかかるわりに成果が出にくい勉強」を避けることです。
例えば、用語を何十回も書く、まとめノートをゼロから作る、といった作業は効率が悪く、点数につながりにくいです。
インプットは効率的に済ませ、アウトプット(演習・解答練習)を重視しましょう。
(3)テスト数日前・直前
この時期は仕上げに徹します。やるべきことは次の3つです。
・間違えた問題の徹底復習
・学校の教材や問題集を使った模擬テスト形式の演習
・テスト範囲の総復習(インプットの最終確認)
点数アップには体調管理も重要です。睡眠時間を削って勉強するのではなく、しっかり休養を取り、当日にベストな状態で臨みましょう。
③モチベーションを維持するコツ
高得点を取るためには、勉強のモチベーションを保つことが不可欠です。
進捗を報告したり、わからないところを相談したり、時には競争できるようなハイレベルな勉強仲間やライバルを見つけることも効果的です。さらに、勉強管理アプリの利用もおすすめです。アプリでは、目標設定や勉強時間の可視化・分析ができるほか、同じレベルのライバルの勉強記録を見ることも可能です。
小さな目標を毎日達成したり、ライバルや尊敬できる人の存在を意識したりすることで、自然にモチベーションが維持できます。
また、人間は勉強に取り掛かると作業興奮でドーパミンが分泌され、やる気が湧いてきます。10分でもよいので、まず勉強を始めることが大切です。
4. 【科目別】定期テストで450点以上を取るための勉強法

ここでは、科目ごとに高得点を取るための具体的な勉強法を紹介します。テスト結果から現状を分析し、自分の弱点を補強していきましょう。
①【5教科共通】の高得点勉強法
(1)解法や暗記事項を体系的に理解する
問題を解くためのパターンや覚えるべき事項を、グループ化・パターン化してノートに整理しましょう。図やイラスト、箇条書きを活用することで、後で見返したときに解法を素早く引き出せるようになり、解答スピードが上がります。
(2)本質的な理解を心がける
公式や定理をただ丸暗記するのではなく、「なぜそうなるのか」という原理を理解することが大切です。そうすることで、応用問題や初めて見る問題にも対応できる力が身につきます。
(3)本番を意識して対策する
普段の勉強からテスト本番を意識することで、得点力が上がります。時間配分や解く順番、「捨て問」の見極めを意識しながら問題演習に取り組みましょう。
また、過去問を解き直して出題傾向を把握したり、間違えた問題を分析して重点的に復習したりすることで、効率的に対策を進めることができます。
②【英語】で90点以上を取る勉強法
英語は単語、文法、リスニング、長文読解といった総合力が問われる科目です。日頃から問題集を通して、基礎的な練習を積み重ねましょう。
長文読解では、単語や文法だけでなく、設問が何を求めているかを意識することが重要です。パラグラフごとに文構造を把握し、通読と精読を使い分けて時間配分に気をつけましょう。
テスト2週間前からは、授業で扱った文章を読み込み、読解ポイントや単語を暗記レベルまで仕上げておくのが効果的です。
③【数学】で90点以上を取る勉強法
数学の得点力を上げるには、基本問題と応用問題を効率よく使い分けることが大切です。基本問題は解法がすぐに浮かぶものは飛ばし、応用問題や練習問題に時間を割き、対応力を養いましょう。
(1)応用問題・初見問題の対策方法
応用問題や初見問題を解く時のポイントは以下の通りです。
1.問題文を「見える化」する
図やグラフをかいて状況を整理し、文章を正確に式に変換しましょう。
2.手持ちの「武器」を試す
問題文を読んでどのパターンの問題に似ているかを思い出し、自分が知っている解法が使えないか試行錯誤してみましょう。
3.具体的な数字で実験する
簡単な数字で試してみて、規則性を見つけるのも有効な手段です。特に数の規則や場合分けの問題で役立ちます。
(2)テスト本番でのコツ
テストが始まったら、まず全体の問題に目を通して、解く順番と時間配分を考えましょう。得点できる問題から丁寧に解き、残りの時間を応用問題に回します。そして、最後の5分は必ず見直しに使い、計算ミスがないか確認することが重要です。
④【国語】で90点以上を取る勉強法
国語は90点以上を取ることが難しい科目です。だからこそ、漢字、文法、既習の文章など、暗記で確実に得点できる分野で満点を目指しましょう。
漢字・文法
漢字:できるようになるまで繰り返し問題を解きましょう。
文法:基本的なルールに加え、特に間違えやすい例外的用法も確実に押さえることが高得点につながります。
授業で扱った文章
事前に読解ポイントや文章の流れ、筆者の主張をしっかりつかんでおきましょう。そうすることで、テスト本番で設問を見たときに、問題文の該当箇所を素早く見つけ出せるようになります。
初見の文章
初見の長文は、段落ごとに要点を整理しながら読み進めましょう。指示語や言い換え表現に注意を払い、文章の構造(順接、対比、因果関係など)を正確に把握することが解答のカギです。長文読解は慣れが必要なので、普段から週に一度は問題を解く習慣をつけましょう。
⑤【理科】で90点以上を取る勉強法
理科で高得点を取るには、単なる暗記ではなく、「なぜそうなるのか」という原理や法則の深い理解が不可欠です。原理や法則を自分の言葉で説明できるレベルまで理解することで、記述問題にも自信を持って対応できます。教科書の図やグラフを読み取り、視覚的に理解することも、知識の定着に非常に効果的です。
生物・物理・地学
学んだ内容を日常生活に関連付けて考えると覚えやすくなります。
初見の実験・考察問題
図や表をかいて、実験の目的や手順を読み解く練習を重ねましょう。
計算問題
数学の知識が必要になることもあるため、単位変換や文字式の復習も忘れずに行いましょう。
⑥【社会】で90点以上を取る勉強法
社会は、ただ暗記するのではなく、背景や流れを把握することが重要です。
イラストや図を用いながら、自分だけのオリジナルノートを作成し、出来事の流れやパターンを整理しましょう。
整理した知識をもとに、「もし記述問題で出題されたらどう答えるか」を想定することで、記述問題への対応力がつきます。
地理では統計や地図、歴史では資料を読み取る練習も行い、応用力を養うことが大切です。
5. 定期テスト対策で保護者様ができる3つのサポート

中学生のお子様が定期テストで成果を出すためには、保護者の方の適切なサポートが不可欠です。ここでは、お子様のやる気を引き出し、学習をサポートするための3つのポイントを解説します。
①自主性を育むコミュニケーション
(1)対話で信頼関係を築く
「定期テストで〇〇点以下なら、部活を禁止」「スマホを取り上げる」 といった罰やご褒美で勉強を強制するのは逆効果です。まずは、親子で円滑なコミュニケーションを築きましょう。
テスト結果だけでなく、「毎日机に向かっていてすごいね」「難しい問題に挑戦しているね」のように、小さな努力やその過程を褒めることが大切です。信頼関係が築ければ、お子様は安心して勉強の悩みや状況を話してくれるようになります。
また、テストが返ってきたら、「どうすればもっと良くなるかな?」と一緒に改善点を話し合うことが大切です。
「なんでこんな問題もできないの?」ではなく、「ここはもう少しで完璧だね!どうすれば解けるか一緒に考えてみようか」のように、前向きな言葉でサポートしましょう。
(2)お子様の学習ペースに寄り添う
学校や塾の進度は、すべてのお子様に完璧に合っているわけではありません。お子様が「今のやり方でいいのかな?」と疑問を抱くこともあるでしょう。
定期テストの計画を立てる際や結果が返ってきた時に、お子様の学習ペースや方法が合っているか確認し、必要に応じてアドバイスをしてあげてください。授業内容が簡単すぎると感じる場合は、応用問題や予習に挑戦してみるよう促すのも良い方法です。
(3)知的好奇心を刺激する
450点を目指すには、「やらされている勉強」ではなく、自ら進んで楽しく学ぶことが不可欠です。
お子様の知的好奇心を高めるために、様々な体験をさせてあげましょう。例えば、科学館や博物館に足を運び、教科書の内容を実物で見てみることで、学びへの感動が深まります。また、家に本を置くことや、留学生と話す機会を作るなど、学びが「楽しい」と感じられるきっかけを意識的に提供してあげてください。
②スマホやゲームとの賢いつきあい方
お子様のスマホやゲームの利用について、不安を感じている保護者の方は多いでしょう。ただ利用時間を制限するだけでは、かえって反発を招き、自己管理能力が育ちません。
親の役割は、お子様が自己管理できるようにサポートすることです。スマホやゲームを無意味に制限するのではなく、正しい使い方を一緒に考えることが大切です。
例えば、YouTubeの学習系動画で苦手な単元を復習したり、勉強管理アプリで学習時間を記録したりすることは、学習効率を高める非常に効果的な活用法です。デジタルツールを勉強の味方にする方法を一緒に探しましょう。
③集中できる学習環境の整備
(1)規則正しい生活習慣をサポートする
夜遅くまでの勉強は、翌日の授業の集中力を低下させ、かえって効率を悪くします。
お子様が規則正しい生活を送れるように、朝食、夕食、入浴、就寝、起床の時間を一定に保つようサポートしましょう。体調を万全に整えることが、テスト当日のパフォーマンスを上げる上で不可欠です。
(2)快適な勉強空間を整える
お子様が自分の部屋だけでなく、リビングや和室などでも気分転換しながら勉強できるよう、静かで居心地の良い空間を整えてあげましょう。勉強する際は、テレビやゲームの音を小さくしたり、スマホなど集中力を削ぐものを近くに置かないようにしましょう。
(3)必要に応じてサポートする
お子様からの勉強の質問に答えたり、一緒に参考書や問題集を選んだりすることも、大切なサポートです。
しかし、「応用問題の解説が難しくなってきた」「計画通りに進まず、どうサポートしていいかわからない」など、お子様の学習レベルが上がり、保護者の方での対応が難しいと感じた場合は、塾や家庭教師のサポートを検討することも一つの選択肢です。
![]() 家庭教師がサポート
家庭教師がサポート
無料体験授業実施中!
計画的な学習で定期テスト450点超えを実現しよう
定期テストで450点以上を取るには、「やらされる」勉強ではなく、自ら進んで楽しく学ぶ姿勢が何よりも大切です。
「勉強はつまらないもので、定期テスト期間は誘惑を絶って勉強漬けになるべきだ」とと思われがちですが、高校生や大学生、社会人になっても勉強は続くので、勉強が楽しくなるように工夫することがずっと大切です。
私の好きな言葉に、「これを知る者はこれを好む者に如かず。これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」という孔子の言葉があります。
知っているだけでは足りず、それを好きになること、そして楽しむことが最も深い学びにつながるという意味です。
中学校で身につけた学びの習慣は、お子様の未来を確実に豊かにします。勉強、部活、学校行事、そのすべてを楽しんで、充実した中学生活を送られることを願っています。
もし、学習計画でつまずいたり、もっと効率よく成果を出したいと感じたときは、信頼できる家庭教師のサポートも検討してみてください。お子様に合った学び方を見つけることで、きっと勉強がもっと前向きなものになるはずです。
▼当会では、定期テスト対策はもちろん、中学生の受験・中高一貫校生への指導が可能です。ぜひ併せてご覧ください。
定期テスト対策・中学生の指導ができる家庭教師のご紹介
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
中学生の生徒様の声
東大家庭教師友の会の4つの特徴
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
定期テスト対策なら東大家庭教師友の会
あわせて読みたい|中学生の勉強法の関連記事