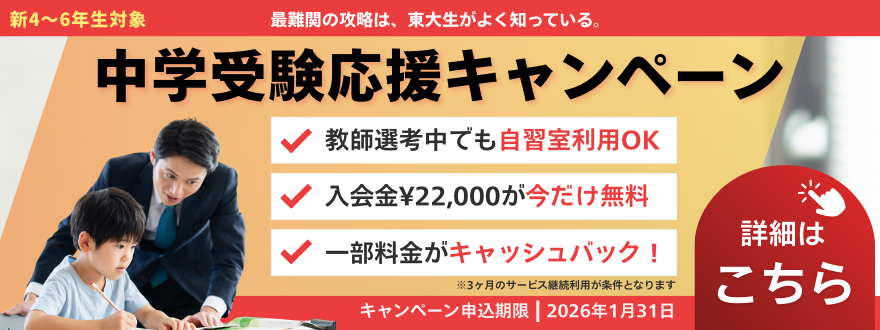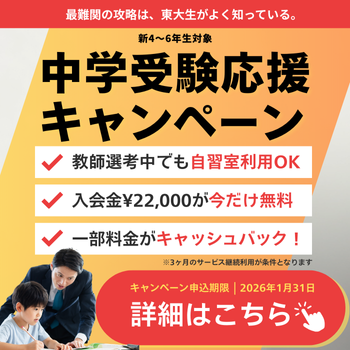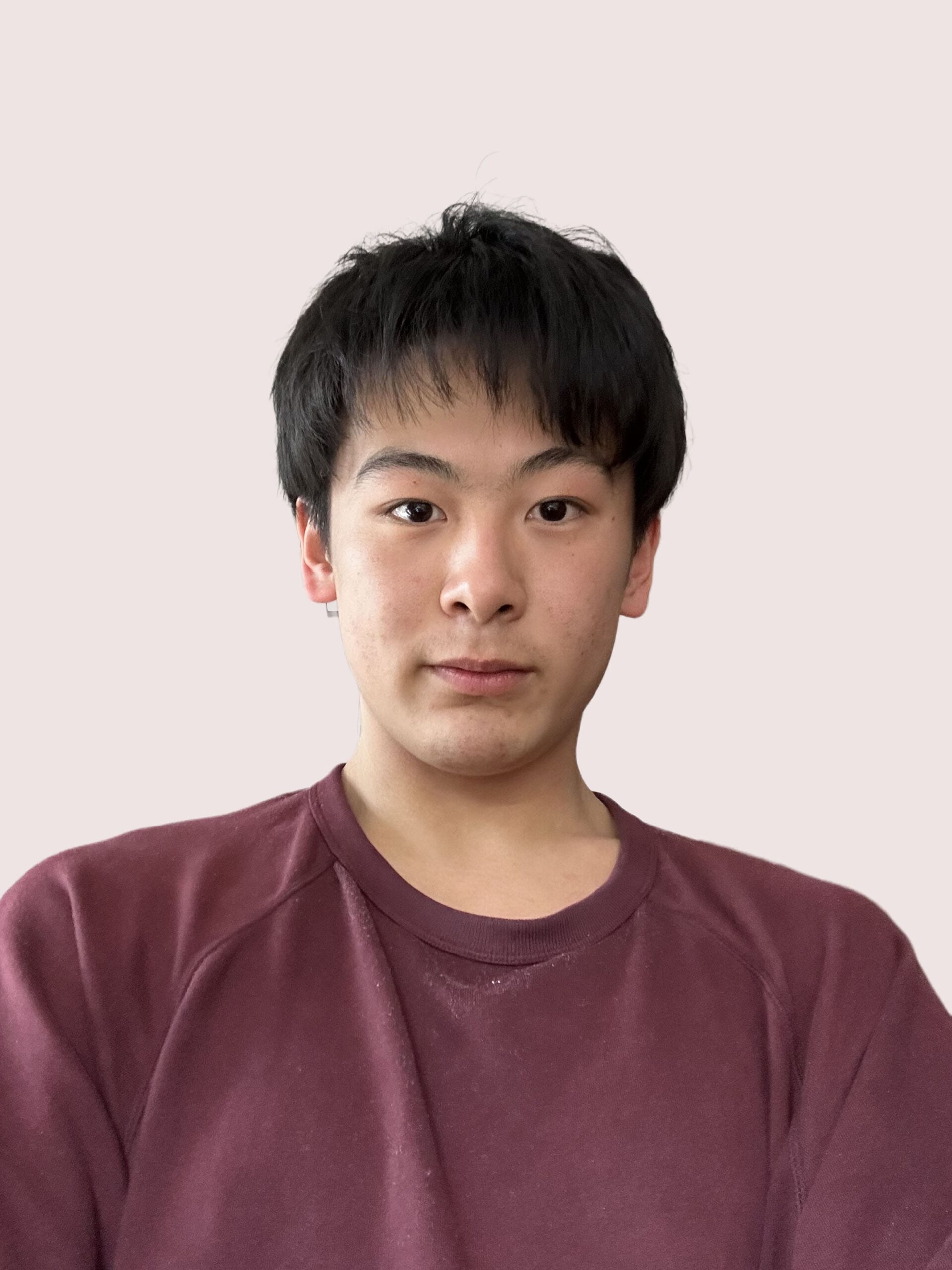1. 日能研の学習力育成テストとは?日程と仕組み

日能研の学習力育成テストは、授業内容の理解度を測るための復習テストです。日能研に通室する生徒様が対象で、4年生前期から始まります。
テストの点数は、クラス分けの基準の1つとなっています。範囲や傾向はあらかじめ決められているので、きちんと対策すれば、高得点を取ることは十分可能です。
| 4・5年生 |
6年生 |
|
|
試験回数 |
2週に1回 |
前期:原則週1回(公開模試の開催週は除く)。 後期:2週に1回 |
|
開催曜日 |
土曜日 |
日曜日 |
|
受験科目 |
4科目(国語、算数、社会、理科)、または2科目(国語、算数) |
4科目(国語、算数、社会、理科)、または2科目(国語、算数) |
|
配点 |
・国語、算数(150点満点) |
・国語、算数(150点満点) |
|
時間 |
・国語、算数(4年生:40分・5年生:50分) |
・国語、算数(50分) |
2. 日能研育成テストの出題範囲・難易度・平均点の目安
①出題範囲(4年・5年・6年)
| 国語・算数 | 理科・社会 | |
| 4年生 | カリキュラム2回分 | カリキュラム1回分 |
| 5年生 | カリキュラム2回分 | カリキュラム2回分 |
| 6年生前期 | カリキュラム1回分 ※ | カリキュラム1回分 ※ |
| 6年生後期 | カリキュラム2回分 | カリキュラム2回分 |
※公開模試を挟むときは2回分
②出題傾向と難易度・配点
授業で習った内容の確認が大半を占めます。ただし、共通問題の後半には、授業で扱わなかった問題も出題されることがあります。
また、応用問題には、授業で習わない入試問題に類似した実力問題、記述式問題も出されます。同様の復習テストは他の大手塾でも実施されますが、日能研の学習力育成テストの難易度は比較的易しめです。
|
(1)国語・算数 共通問題(100点)と、基礎問題(50点)または応用問題(50点)の計150点 標準クラスは、「共通問題」と「基礎問題」を受験。 上位クラスは「共通問題」と「応用問題」を受験。
(2)社会・理科 共通問題(70点)と、応用問題(30点)の計100点 全学年、クラスにかかわらず同じ問題を受験。
|
国語・算数は、以下の点数を目標の目安とすると良いでしょう。
【共通問題+基礎問題を受験する場合】
共通問題100点と基礎問題50点の、150点満点中100点が第一目標です。
【共通問題+応用問題を受験する場合】
共通問題100点と基礎問題50点の、150点満点中100~120点が目標点数となります。
3. 日能研育成テストによるクラス昇降(クラス分け)基準

生徒様の努力や頑張りが反映されるのは、やはりクラスの上がり下がりです。特に保護者様は、志望校合格に近づくためクラスアップを願ってやまないのが、正直なところでしょう。
では、その基準はどういったものなのでしょうか?
①クラス替えの頻度と評価基準
| 頻度 | ・4年生、5年生:約2カ月に1度 ・6年生:ほぼ毎月 |
|
基準 |
・「学習力育成テスト」の共通問題の順位 ・「学習力育成テスト」の基礎問題、応用問題の点数 |
②テストごとの席順変動システム
日能研では、学習力育成テストや全国公開模試など、毎回のテスト後、成績順に教室での席順が変わります。最前列の真ん中がクラス1位の席で、その両隣が2位、3位。またその隣が4位、5位という仕組みで、以後、順々に列が後ろになっていきます。
「テストごとに席順が変わるのはリアル過ぎる」と話される保護者様もいらっしゃいますが、あまり深刻に考え過ぎず、前向きに取り組んでください。
4. 日能研育成テストで点数が上がらない3つの原因
毎週のように行われる日能研の育成テスト。「今回こそは」と親子で意気込んでも、結果を見てがっかり…という経験はございませんか?
|
「授業も宿題も真面目に取り組んでいるのに、なぜか点数に結びつかない…」 「テスト直後は『できた!』と言っていたのに、答案を見るとケアレスミスだらけ…」
|
点数が取れない原因は、生徒様の努力不足や能力だけの問題ではありません。学習力育成テストの点数が伸び悩む生徒様には、いくつか共通した「つまずきの原因」があります。
原因1:授業の「わかったつもり」と演習不足
生徒様は授業を聞いて、「わかったつもり」になっていませんか?授業やテキストの内容が分かることと、その知識をテストで正しく使えるかは別の話です。
-
「わかったつもり」になっている生徒様は、授業を聞く・テキストを読むことに満足してしまい、実際に手を動かして問題を解く量が、不足している場合が多いです。
-
また、宿題や問題集を解いた後、丸付けをして終わりになっていませんか?なぜ間違えたのか、どうすれば次は正解できるのか、という振り返りのプロセスが抜けている場合は、要注意です。
原因2:計算・漢字など基礎問題での失点
-
思ったより点数が取れていない場合は、計算ミスや漢字ミスを起こしている可能性が高いです。素早く正確に計算する、漢字を丁寧に書く、というのは日ごろからの習慣付けが重要です。
-
テスト本番で計算・漢字ミスをする生徒様は、この日々の継続ができていない可能性が高いです。
-
また、問題には正確に答えられていますか?「先頭の5字を抜き出しましょう」など、さまざまな問い方があるので、問題にきちんと答えるということを、毎日の学習でも意識しましょう。
原因3:テスト後の解き直しが「作業」になっている
学習力育成テストの後の復習・解き直しは、ただ答えを写すだけの「作業」になっていませんか?
間違えた問題の解説を読み、赤ペンで答えをノートに写すだけでは、生徒様の頭には何も残りません。
-
テストの点数やクラスの昇降だけを見て、一喜一憂せず、テスト結果は次の行動に繋げる出発点と捉え、テストの復習・解き直しに取り組みましょう。
ここまで、点数が伸びない原因を解説しましたが、「親が教えると喧嘩になる」「宿題を回すだけで手一杯」というご家庭も多いのではないでしょうか? 育成テスト対策は、日能研のカリキュラムを熟知した第三者に任せるのも一つの近道です。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
5. 【学年別】日能研育成テストの対策・勉強法(4年・5年・6年)
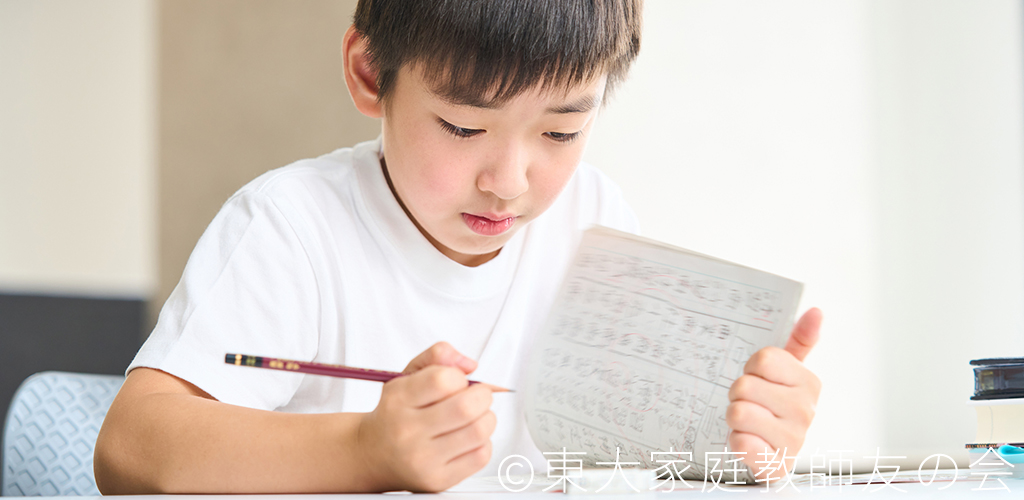
① 基本の学習サイクル(全学年共通)
塾には、その塾にあった学習のシステムやサイクルがあるものです。
日能研の理想的なサイクルは、以下の通りです。
|
授業を受け、間違えた問題を解き直す。
|
⬇︎
|
宿題『栄冠への道』を解き、間違えた問題を解き直す。
|
⬇︎
|
学習力育成テストを受け、テストの復習を行う。
|
日能研では予習ではなく、解き直しに重きを置くほうが賢明です。解き直しの際には、「解き方を丸暗記しない」ことに気をつけましょう。
学習力育成テストは復習テストですから、解き方を暗記すれば、ある程度の点数を取ることはできます。ですが、それでは本番の入試には通用しません。
学習は、解き方・考え方を理解することが大切になります。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
② 【4年生】基礎定着と学習習慣の確立
| 国語 |
内容を「正しく理解する」練習をする 授業で扱った文章と、宿題に出た『栄冠への道』の文章を音読し、内容を誰かに語ってみましょう。 |
|
算数 |
計算力を身につける 計算問題は『計算と漢字』教材を用いて、時間を測りながら、毎日取り組みましょう。10問を7分〜10分間が目安です。1回で正解することを目標にしましょう。 授業と宿題で、間違った問題の解き方を見直して、テストに臨むことが大切です。 |
| 理科・社会 |
興味付けを最優先に あまり点数や結果にこだわらなくてよろしいかと思います。授業の内容をしっかり理解できているかを『栄冠への道』で確かめましょう。 |
③ 【5年生】算数の難化対策と理社の暗記
| 国語 |
得点力を身につけるための習慣 漢字の読み書きは『計算と漢字』を用いて、「トメ、ハネ、ハライ」に注意しながら完璧にします 。書き損じが多いときは、前学年の教材に戻ってやり直しましょう。 「正しいものを1つ選びましょう」「先頭の5字を抜き出しましょう」など、問い方にも慣れていきましょう。テキストの本文や問題文に、線を引くようにすると良いです。聞かれたことに正確に答える習慣を身につけましょう。 |
|
算数 |
基礎問題を落とさないようにする 分数、小数の四則混合計算の単元で、確実に高得点を取ってジャンプアップしていきましょう。 5年生は、中学受験の単元の基礎部分をすべて学習します。授業と宿題で、間違った問題の解き方を見直して、テストに臨むことが大切です。 また問われていることに、正しく答える練習をしましょう。普段から、問題文にチェックをいれる癖をつけるといいでしょう。 |
| 理科・社会 |
基本事項の暗記に取り組む 授業が週1回となり、テスト範囲が2回分に広がります。基本姿勢は4年生と変わりませんが、理科の生物や地学、社会の地理や歴史などの暗記分野は、しっかりと見直したうえでテストに臨みましょう。 |
④ 【6年生】入試演習と過去問への接続
| 国語 |
内容を正しく読み取り、自分の言葉で表現する 授業で扱った文章や、宿題の『栄冠への道』の文章を要約し、誰かに語ってみましょう。自分の言葉で、正しく記述できるようになることが大切です。 またテスト対策のために、黙読で取り組むようにしましょう。他の読書も並行して行い、語彙力を増やしましょう。 |
|
算数 |
効率を考えて、復習する 5年生のときの単元の正答率を参考に、自分の得意不得意を理解したうえで、授業に臨みましょう。 授業と宿題で間違った問題の解き方を見直して、テストに臨むことが大切です。ただし、特訓授業や過去問演習もありますから、効率の良さが大切になります。 テストの軸足は徐々に、学習力育成テストから全国公開模試へ移していきましょう。 |
| 理科・社会 |
理解を深めて定着させる 『栄冠への道』で考え方を整理し、『メモリーチック』で知識を定着させ、テストに臨むリズムを身に付けます。目標とする得点率は75%です。 |
6. 日能研育成テスト結果が悪かった時の復習法と家庭サポート

①「正答率」を活用したクラス別復習法
テスト後の復習には、正答率表を利用することをおすすめします。これは復習する問題を絞る、という方法になります。
具体的にどのように絞るのかは、現在の所属クラスに応じて、正答率表を基に決めればいいでしょう。
| 上位クラス | 正答率20%以上で間違っている問題 |
|
中位クラス |
正答率40%以上で間違っている問題 |
| 下位クラス | 正答率60%以上で間違っている問題 |
4・5年生のあいだは復習する教科を国語、算数の2科目にして、見直す問題数を絞るのも効果的な方法です。
算数、国語を優先すべき理由
・入試の主要教科である国語、算数を優先する
・まずは「学習サイクル」の確立が先決であり、テスト後の復習を習慣づける
これにより、勉強を嫌いにならない程度に量を抑えておくこともできます。
②「計算と漢字」をルーティン化する
学習力育成テストだけではなく、本番の入試でも、大半の中学校では計算問題や漢字の書き取りが出題されます。そこでおすすめなのは、毎朝30分間いっしょに『計算と漢字』という日能研の教材に取り組む、というものです。
特に、以下2点を抑えると良いでしょう。
|
①決まった時間に取り組むこと
|
③苦手単元を『本科テキスト』で可視化する
4教科の間違った問題の正答率を、『本科テキスト』の類題に書き込んでおくことをおすすめします。その理由は、生徒様はもちろん、保護者様も一目で得意不得意、これから力を入れるべき単元が分かるからです。
日能研では、学年が上がるごとに同じ単元を難度を少しずつ上げながら、繰り返し学習するため、次回同じ単元を学習する際に、その正答率を参考にすることができます。
これは本科教室の復習をする春、夏、冬の期間講習でもいえることで、生徒様の苦手を知ってから、授業を受けるとスムーズな習得につながります。
生徒様は「苦手だなあ」と嫌な気持ちになるのではなく、「また一から頑張ろう!」という気持ちで臨むことが大切です。先ほどの、正答率表も参考に、復習すべき単元を決めましょう。
▼日能研についていけない際の対策の詳細は、以下ページも併せてご覧ください。
④保護者様ができる家庭内サポートと外部連携
学習サイクルを身に付けるのは、小学生の生徒様だけでは難しい場合が多いです。そのため、成績アップには保護者様の手助けが大事になります。
生徒様へのサポートは、主に以下の通りです。
|
・授業の間違い直しの箇所の選定
|
小学生ですから、細かく丁寧にサポートすれば効果はあがります。ですが、これらすべてをご家庭様だけで解決するのは大変な場面もあり、また親子だからこその反抗もありえます。
「親が勉強を見るのには限界がある…」 「6年生に向けて、今のうちに苦手を潰しておきたい」
そうお考えの場合は、日能研の指導経験が豊富な「東大家庭教師友の会」にご相談ください。
難関中学出身の教師が、生徒様の状況に合わせて日能研のテキスト(本科教室・栄冠への道)を使ったフォローを行い、育成テストの点数アップとクラス昇格をサポートします。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
まとめ|日能研育成テストは対策次第でクラスアップ可能
日能研の学習力育成テストは、日々の授業の定着度を測る重要なテストです。 4年生・5年生のうちに正しい「解き直し」のサイクルを身につけることが、6年生での志望校合格に直結します。
|
4年生:学習サイクルの定着と国語の読み込み |
成績に一喜一憂せず、今回の結果を次の学習計画に活かしていきましょう。もしご家庭でのサポートに限界を感じたら、プロの力を借りることも検討してみてください。
▼当会では、日能研生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
中学受験塾対策ができる家庭教師をご紹介
SAPIX・日能研・早稲田アカデミー・四谷大塚などの通塾経験や、通塾生の指導経験がある教師が在籍しています。
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
小学生の生徒様の声
中学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会の特徴
当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
ご利用の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
中学受験に強い家庭教師をお探しなら
あわせてチェック|日能研の関連記事
東大家庭教師友の会をもっと知る