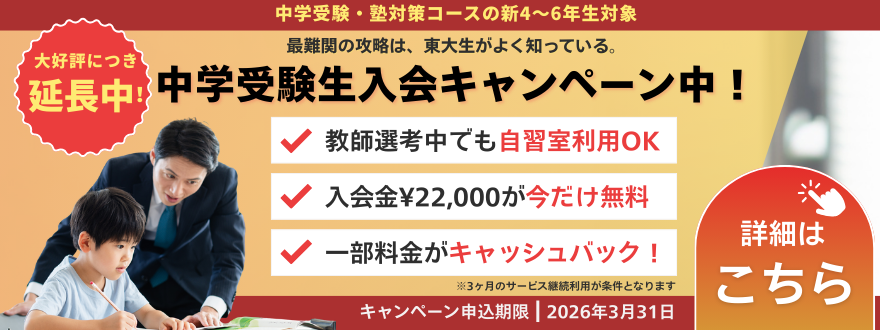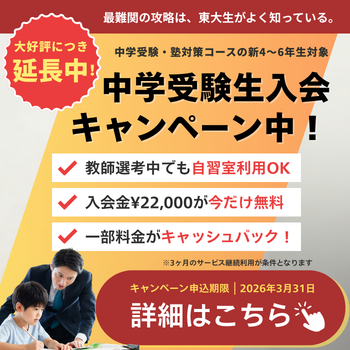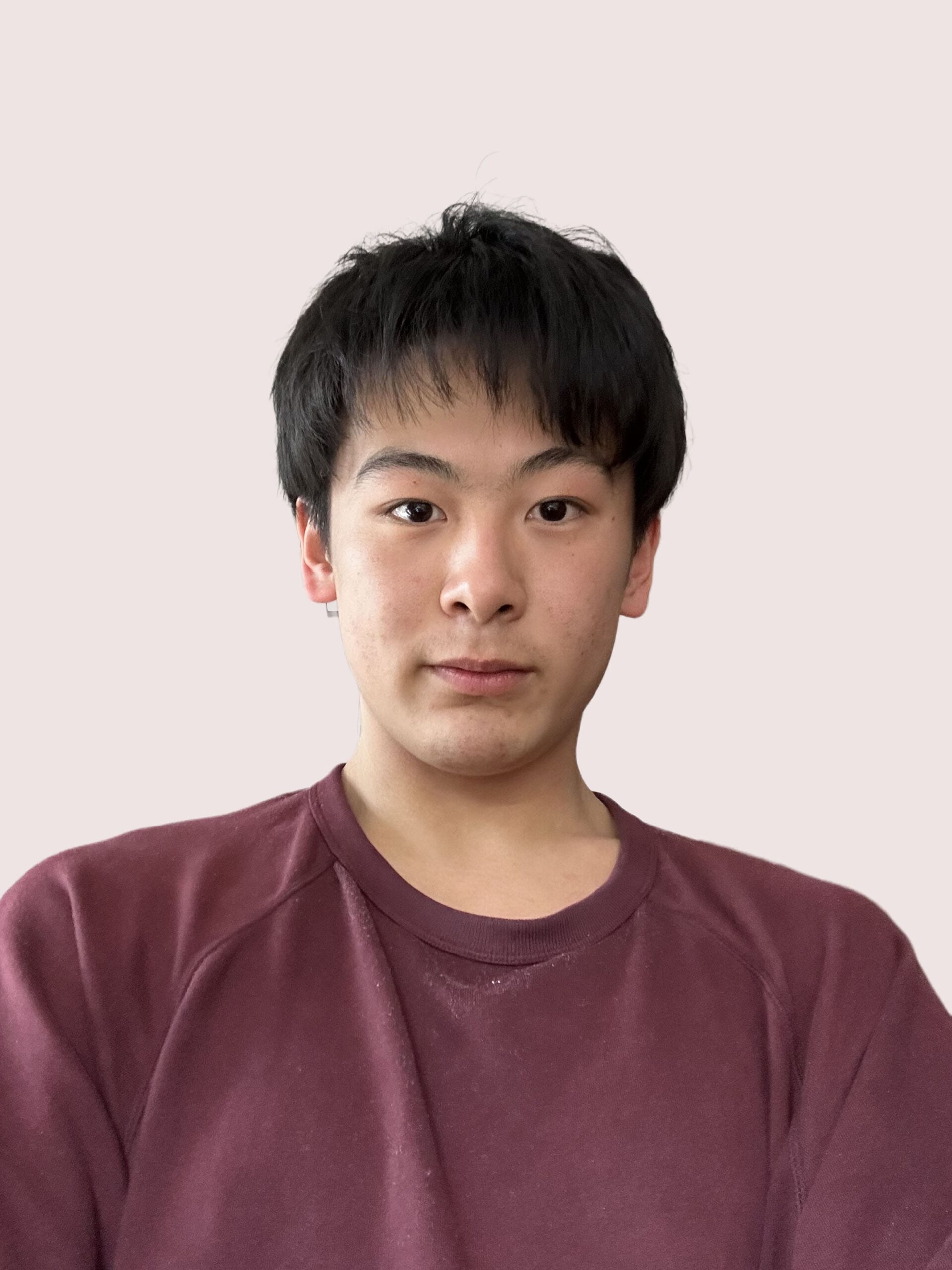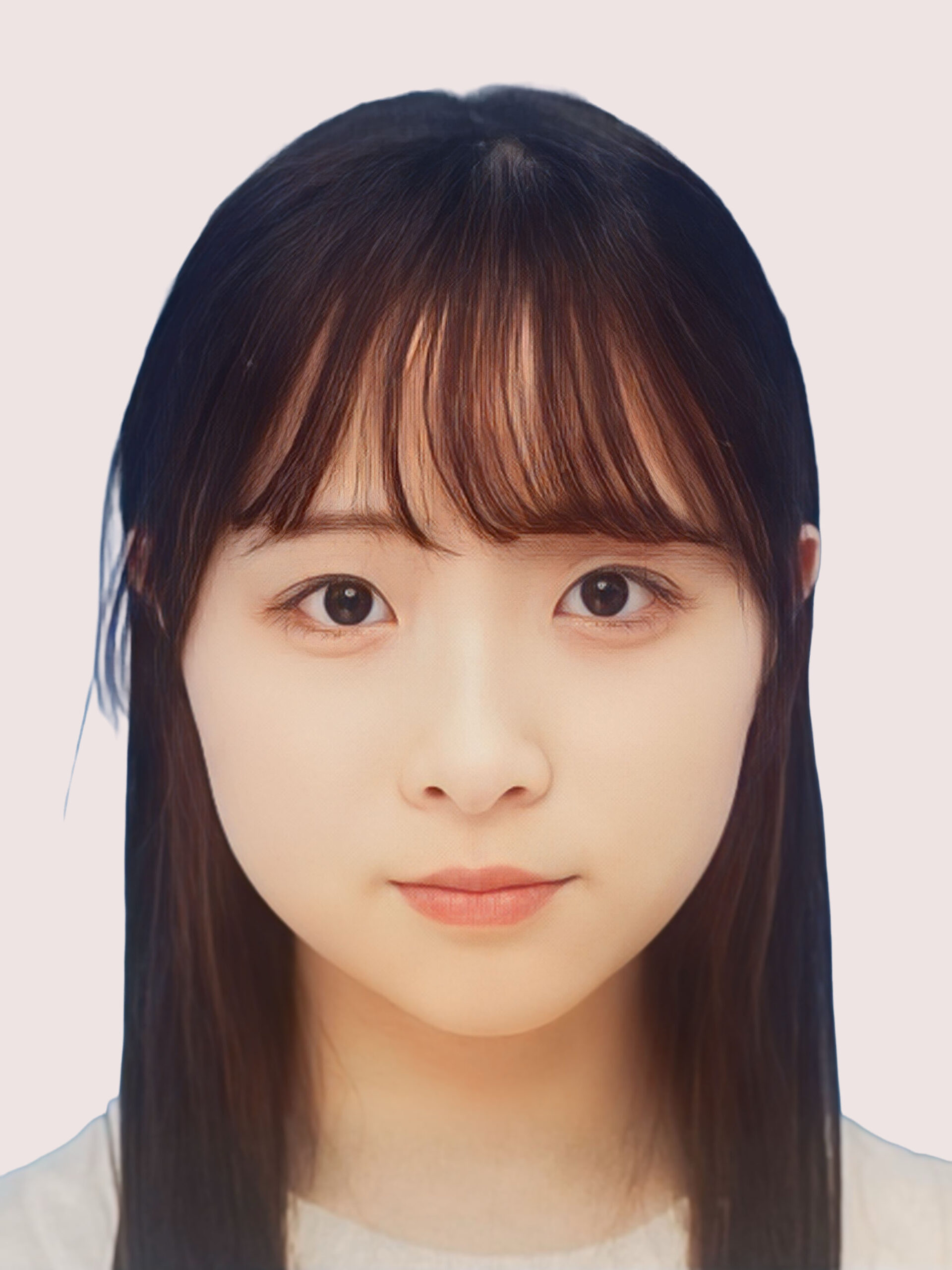1. なぜ「日能研についていけない」のか?東大家庭教師友の会が分析
「うちの子、日能研の授業についていけてないかも…」 そう感じるのは、実は生徒様の能力だけの問題ではありません。
日能研独自の「学習システム」や「環境」が、生徒様に合っていない可能性があります。
なぜつまずいてしまうのか、その原因を具体的に見ていきましょう。
原因①:繰り返しの学習で、わからないまま進んでしまっている
日能研の最大の特徴は「スパイラル方式」というカリキュラムです。
これは、一つの単元を一度で終わらせず、学年が上がるごとに難易度を上げながら、何度も繰り返し学習する仕組みです。
一見、しっかり定着しそうなシステムですが、ここには大きな落とし穴があります。
■「またやるから大丈夫」という油断
-
苦手な単元があっても、「どうせまた後で出てくるし」と後回しにしてしまい、弱点をそのまま放置しがちです。
■再登場時には、ハードルが高くなっている
次に同じ単元が出てくるときは、基礎ができている前提で「応用・発展」レベルから始まります。基礎が抜けたままでは、授業の内容が全く理解できません。
■雪だるま式にわからなくなる
「なんとなく」で済ませてきたツケが、高学年になって一気に回ってきます。気づいた時には復習すべき範囲が広すぎて、手遅れになるケースが少なくありません。
原因②:席順・クラスアップのプレッシャーで「勉強嫌い」に
日能研といえば「成績順の座席」が有名です。テストの結果によって、定期的に座席やクラスが変わります。
負けず嫌いな子にはゲーム感覚で楽しめますが、マイペースな生徒様や、繊細な生徒様には、強烈なプレッシャーになってしまいます。
▼プレッシャーが引き起こす悪影響
■自己肯定感の低下
-
「席が下がって恥ずかしい」「友達に馬鹿にされるかも」という恐怖心が先に立ち、塾に行くこと自体が苦痛になります。
■本末転倒な学習姿勢
「内容を理解すること」よりも「一つでも前の席に行くこと」が目的になってしまい、答えの丸暗記など、間違った勉強法に走るリスクがあります。
■「どうせ無理」というあきらめ
頑張っても上のクラスに行けない経験が続くと、「自分は何をやっても無駄だ」と感じてしまい、鉛筆を持つことさえ嫌になってしまいます。
原因③:宿題の量が多すぎて重要な問題に集中できていない
日能研のテキスト『栄冠への道』などは、とても中身が充実しています。しかし、「すべてをこなすのは困難」な量でもあります。
特に、真面目な子や「テキストは全部やるもの」と考えている保護者様の場合、次のような失敗パターンになりがちです。
▼「宿題全部やる」が招く失敗パターン
■「作業」になってしまう
-
膨大な量を終わらせることが目的になり、ただ答えを埋めるだけの「作業」になってしまいます。これでは頭に残りません。
■大事な問題に時間を使えない
本来やるべき「基礎の反復」よりも、今の実力では解けない「難問」に時間を使いすぎ、結局何も身につかないまま時間だけが過ぎていきます。
■睡眠不足で集中できない
宿題を終わらせるために睡眠時間を削り、翌日の学校や塾の授業で集中できなくなる……これでは逆効果です。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
2. 日能研についていけない状態からの脱出!【学年別】挽回ロードマップ
学年によって、学習の壁や優先すべき対策は全く異なります。
ここでは、日能研のカリキュラム特性を踏まえた学年別の「挽回ロードマップ」をご紹介します。
①4年生:まずは「計算と漢字」と「ノートの取り方」
4年生は、受験学習の基礎体力と「塾に通うリズム」を作る時期です。成績そのものよりも、学習習慣の定着を最優先しましょう。
(1)計算と漢字の徹底
日能研のテキスト『計算と漢字』は、すべての学習の土台です。
■朝学習の習慣化
-
登校前の10〜15分を固定し、毎日必ず取り組みましょう。
■カリキュラムの日程を守る
テキストに指定された日付通りに進めることで、ペース配分を体感させます。
■丁寧さを重視
答えが合っているかだけでなく、「トメ・ハネ・ハライ」や「途中式」が雑になっていないか、保護者様がチェックしてあげてください。
(2)ノートの取り方を覚える
日能研は「考えのプロセス」を大切にするため、ノート記述を重視します。ただの板書写しにならないよう、家庭での振り返りが重要です。
■余白を持たせる
-
ぎちぎちに書かず、後で教師のコメントや自分の気づきを書き込める余白を作らせてください。
■復習時の活用
「授業で教師は何と言っていた?」とノートを見ながら問いかけ、授業内容を思い出せるノートになっているか確認しましょう。
②5年生:全てを解こうとせず「解くべき問題」だけに集中する
5年生は学習内容が高度化し、歴史や比(算数)などの重要単元が登場します。
宿題(家庭学習)の量が急増するため、ここでパンクしてしまう生徒様が最も多いです。
(1)取捨選択がカギ
真面目な生徒様ほど、宿題を「全部やらなきゃ」と追い詰められがちです。今の実力に見合わない難問は、勇気を持って捨てましょう。
- テキストや『栄冠への道』の問題番号を見て、優先順位をつけてあげてください。「今回は基本問題だけでOK」と割り切ることで、消化不良を防げます。
■育成テスト対策
テストでの正答率が低い応用問題に時間を割くより、正答率50%以上の問題を確実に取る練習の方が、クラスアップにつながります。
▼日能研のクラスアップ(クラス分け対策)について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください
(2)「栄冠への道」の活用
家庭学習用テキスト『栄冠への道』の使い方を見直します。
- 基礎的な「学び直し1」と、標準的な「学び直し3」を完璧にすることを最優先してください。応用的な「学び直し2」は、余裕がなければパスしても構いません。
■解説の精読
解くだけでなく、解説(考え方の指針)をしっかり読む習慣をつけましょう。
③6年生:過去問対策に追われて通常授業がおろそかになっていないか確認する
6年生の後半(特に9月以降)は、過去問演習や『日特(日能研入試問題研究講座)』が始まり、スケジュールが限界まで埋まります。
(1)スケジュールの見直し
「過去問」「日特」「通常授業(本科)の復習」「模試(公開模試)の直し」……全てを完璧にこなすのは不可能です。
- 第1志望校の頻出単元を最優先し、それ以外の単元の復習は後回しにするなど、戦略的な間引きが必要です。
■睡眠時間の確保
睡眠を削ると、授業の集中力が下がり逆効果です。最低限の睡眠時間を決めて、そこから逆算して勉強量を調整してください。
(2)弱点補強に特化する
過去問を解きっぱなしにするのが一番のムダです。
- 過去問で間違えた単元は、必ず『本科テキスト』に戻って基礎概念を確認してください。
■「銀本」等の活用
類似問題を解く必要がある場合は、日能研の入試問題集(銀本)などから、似た傾向の問題をピンポイントで選んで解くのが効率的です。
▼日能研の選抜クラス(TMクラスなど)を目指す方は、以下の記事もご覧ください
3. 日能研についていけない時の対処法|転塾か?家庭教師との併用か?
現状を打破するための選択肢として、大きく分けて「他塾への転塾」と「家庭教師の併用」の2つが考えられます。
それぞれのメリット・デメリットを整理し、生徒様にとって最善の道を探りましょう。
選択肢①「転塾」のメリット・デメリット
今の環境を変えることで、生徒様のやる気を引き出す方法です。
【メリット】
- 新しい環境や先生に出会うことで、「もう一度頑張ろう」という前向きな気持ちが生まれることがあります。
■生徒様の性格や学力に合った塾を選び直せる
「競争が激しい塾」から「面倒見の良いアットホームな塾」へ移るなど、生徒様の性格によりフィットした指導方針の塾へ軌道修正できます。
【デメリット】
- 日能研は独特な「スパイラル方式(同じ単元を何度も繰り返して深める)」を採用しているため、他塾とは進度や学習順序が大きく異なります。転塾した時点で「まだ習っていない単元」が多数見つかり、その穴埋めに追われて余計に勉強が遅れてしまう危険性があります。
■環境変化による精神的ストレス
新しい教師の指導法や、新しい友達の輪に馴染むまでには時間がかかります。受験までの貴重な時間を「慣れること」に費やしてしまうリスクがあります。
選択肢②「家庭教師の併用」のメリット・デメリット
日能研に通い続けながら、プロのサポートをプラスする方法です。
【メリット】
- 使い慣れたテキスト(本科教室や栄冠への道)をそのまま使い、日能研のカリキュラムに沿って学習を続けられます。転塾のような「未習単元の穴埋め」をする必要がありません。
■「わからない」をその場で解決できるピンポイント指導
集団授業では質問しづらい苦手な単元も、家庭教師ならマンツーマンで理解できるまで解説してもらえます。テスト直し(解き直し)の精度も格段に上がります。 - ■学習スケジュールの最適化
日能研は宿題の量が多い傾向にあります。プロの家庭教師が「今、生徒様が絶対にやるべき問題」と「今はやらなくていい問題」を選別(取捨選択)してくれるため、効率よく勉強が回るようになります。保護者様が管理する負担も軽減されます。
【デメリット】
- 日能研の月謝に加え、家庭教師の指導料が必要になるため、経済的な負担は大きくなります。
■生徒様の自由時間が減る
通塾以外の空いている時間に家庭教師の授業を入れることになるため、生徒様がリラックスできる時間が削られる可能性があります。オーバーワークにならないよう、時間のバランス調整が必要です。
4. 日能研についていけない悩みは「家庭教師の併用」で解決できる3つの理由
「日能研のカリキュラムは気に入っているけれど、成績が伸びない」 そうお考えの保護者様には、今の環境を変える「転塾」よりも、現在の学習環境を活かした「家庭教師の併用」がおすすめです。
集団塾である日能研と、個別指導である家庭教師を組み合わせることが、なぜ成績向上に効果的なのか、その理由をご紹介します。
理由①:日能研のカリキュラムやテスト傾向を熟知している
家庭教師であれば、日能研で使用しているテキストやカリキュラムに合わせて指導を行うことが可能です。
新たな教材を増やすのではなく、今手元にある教材を最大限に活用することで、効率的に学習を進めることができます。
- 家庭教師は、授業用テキスト「本科教室」と復習用テキスト「栄冠への道」の役割を理解し、「本科教室のどこを復習すれば、栄冠への道の問題が解けるようになるか」を的確に指示・指導できます。
■テストのやり直し(解き直し)が徹底できる
日能研で頻繁に行われる「学習力育成テスト」や「全国公開模試」の結果をもとに、家庭教師が弱点を分析します。出題傾向に合わせた対策や、間違えた問題の「解き直し」を一緒に行うことで、着実に実力を定着させます。
「日能研の進め方」を尊重しつつ、つまづいている部分だけをサポートするため、生徒様も混乱することなく学習を進められます。
▼全国公開模試の偏差値を上げる対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください
理由②:保護者様の言うことを聞かない子も「憧れの先輩」の言うことなら聞く
中学受験期は、精神的な成長に伴い反抗期が始まりだす時期でもあります。
親子間ではどうしても感情的になりがちで、保護者様の「勉強しなさい」「宿題やったの?」という言葉に反発してしまう生徒様も少なくありません。
しかし、教師という第三者のアドバイスであれば、素直に耳を傾けることはよくあります。
- 「先生も受験生の時はここで苦労したよ」といった実体験や、客観的なアドバイスは、生徒様の心に響きやすく、素直に受け入れられる傾向があります。
■モチベーションの向上
年齢の近い学生教師や、経験豊富なプロ教師との対話を通じて「合格後の学校生活」や「勉強の面白さ」に触れることで、学習へのモチベーションが劇的に変わります。
理由③:わからない箇所だけをピンポイント指導できる
集団塾である日能研では、あらかじめカリキュラムが決まっているため、一人ひとりの「わからない」に合わせて授業を止めることはできません。
一度つまづいてしまうと、そのまま授業が進んでしまい、「わからない」が積み重なってしまいます。
家庭教師を併用することで、以下のメリットが生まれます。
- 日能研の授業で理解しきれなかった箇所や、テストで間違えた単元だけをマンツーマンで解説できます。集団授業では質問しづらい生徒様でも、家庭教師なら気兼ねなく質問できます。
■「クラスアップ」への近道
なんとなく「わかったつもり」で済ませていた部分を、自力で解ける「できる」状態に変えることで、テストの点数は確実にアップします。これがクラスアップ(席順アップ)への最短ルートです。
集団塾の早いペースについていくための「補強」として家庭教師を活用することで、消化不良をなくし、成績向上につなげることができます。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
5. 日能研についていけないあせりから抜け出すために保護者様ができる「環境作り」
成績が伸び悩んでいる時、誰よりも不安で苦しい思いをしているのは生徒様ご本人です。
日能研のカリキュラムは進度が早く、テストによるクラス変動もあるため、精神的なプレッシャーがかかりやすい環境です。
だからこそ、ご家庭を「安らげる場所」にするために、保護者様による環境作りが重要になります。
①保護者様とケンカになるくらいなら「管理」をプロに任せる
宿題の進捗管理や学習スケジュールの作成を保護者様が行うと、どうしても「なんでやらないの!」「この前のテストもダメだったじゃない」といった感情が入り混じり、不毛な親子喧嘩に発展しがちです。
親子関係が悪化すると、家庭の居心地が悪くなり、生徒様の学習意欲(モチベーション)はさらに削がれてしまいます。学習の「管理」と「生活サポート」を明確に分業することをおすすめします。
| 学習管理(家庭教師に任せる領域) | 生活サポート(保護者様が徹する領域) |
|
・日々の宿題の優先順位付け
|
・栄養バランスの取れた食事の用意 ・睡眠時間の確保と体調管理 ・塾への送迎や、リラックスできる空間作り |
「勉強のことはプロの教師に任せているから安心」と割り切り、保護者様は「衣食住のサポーター」に徹してみてください。
家庭内の空気が穏やかになることで、生徒様は余計なストレスを感じることなく、結果として勉強に集中できるようになります。
②点数だけを見ずに頑張った過程をほめる
毎週の学習力育成テストや公開模試の結果を見て、点数・偏差値・席順(列)だけで一喜一憂していませんか?
結果だけを評価されると、生徒様は「良い点数を取らないと愛されない」と感じ、失敗を恐れるようになります。
重要なのは、「結果が出るまでのプロセス(過程)」を具体的に認めてあげることです。
- 1. 姿勢の変化: 机に向かう時間が10分増えた、自分からテキストを開いた
2. ミスの改善: 前回間違えた計算問題を、今回は正解できた
3. 継続力: 毎日の「計算と漢字」をサボらずにこなしている
4. ノートの質: 字が丁寧になった、式や図をしっかり書いている
これらを具体的に言葉にして伝えることで、生徒様は「保護者様は結果だけでなく、私の頑張りをちゃんと見てくれている」という安心感(心理的安全性)を得ます。
この安心感こそが、次回のテストへ向かう自己肯定感とエネルギーの源になるのです。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
6. 日能研についていけないと感じる方によくある質問
Q1. クラス落ちしてしまいましたが、難関校への合格はまだ可能ですか?
-
A:十分に可能です。
クラス落ちは「基礎を見直す絶好のチャンス」と捉えてください。
無理に難しい問題を解くよりも、下のクラスで基礎を徹底的に固め直すことで、結果的に成績が急上昇し、上位クラスへ返り咲いて志望校合格を掴む生徒様はたくさんいらっしゃいます。
焦る必要はありません。まずは今のクラスでトップの成績を取ることを目標に、足元を固めましょう。
Q2. 育成テストの復習が追いつきません。全てやるべきですか?
-
A:全てやる必要はありません。
テスト直しで重要なのは「優先順位」です。 「正答率が高い問題(他の多くの生徒様ができている問題)」で間違えてしまった箇所を最優先に復習してください。
逆に、正答率が極端に低い難問は、基礎を固める今の段階では思い切って捨ててしまっても構いません。
「やるべき問題」と「やらなくていい問題」を分け、効率的に復習することが成績アップの鍵となります。
▼学習力育成テスト(旧カリテ)の対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください
Q3. 算数だけ極端に苦手です。科目別の対策はどうすれば良いですか?
-
A:苦手科目だけ家庭教師を利用するのも一つの手です。
算数は一度つまずくと、自力で挽回するのが非常に難しい科目です。
日能研の授業をベースにしつつ、算数だけは個別の教師をつけて「わからない」を根本から解消する戦略が有効です。
苦手科目を平均点レベルまで引き上げるだけでも、全体の偏差値は大きく安定します。
Q4. 勉強を教えると喧嘩になってしまいます。どうすれば良いですか?
-
A:教えること以外(プリント整理や体調管理)に徹しましょう。
勉強を教えることは、プロである塾や家庭教師にお任せください。 親子で教え合うと、どうしても感情的になりがちです。
保護者様は、膨大なテキストやプリントの整理(ファイリング)、栄養のあるお弁当作り、塾への送迎など、生徒様が勉強に集中できる「環境面のサポート」をお願いいたします。
まとめ|日能研についていけないと思う前に「勉強のやり方」を変えてみよう
「日能研の授業についていけない」と悩む原因のほとんどは、決して生徒様の能力不足ではありません。
単に「学習のやり方」や「取り組むべき問題の優先順位」が、今の生徒様にフィットしていないだけの可能性が高いのです。
-
・スパイラル方式の授業で生じてしまった「過去の穴」をピンポイントで埋める
・膨大な宿題の中から「今やるべき問題」だけを選び抜き、効率化する
・親子喧嘩の原因となる「学習管理」をプロに任せ、家庭を安らげる場所にする
転塾というリスクの大きな決断をする前に、まずは今の環境のままできる「戦略の転換」があります。
日能研という素晴らしいカリキュラムを活かしつつ、足りない部分を個別に補う「併用スタイル」こそが、志望校合格への近道です。
「東大家庭教師友の会」には、自身も中学受験を経験し、難関大に合格した「学習の成功者」である教師が多数在籍しています。
単なる勉強の指導だけでなく、生徒様にとっての「憧れの先輩」として、モチベーションを大きく引き上げ、日能研の成績アップを強力にサポートします。
中学受験塾対策ができる家庭教師をご紹介
SAPIX・日能研・早稲田アカデミー・四谷大塚などの通塾経験や、通塾生の指導経験がある教師が在籍しています。
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
中学受験の合格実績
当会はこれまで、多くの受験生の皆様をサポートしてきました。当会で指導をさせていただいた生徒様の代表的な合格実績をご紹介します。
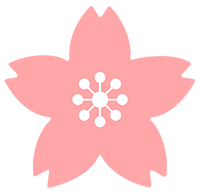 中学受験の合格実績
中学受験の合格実績
■東京都
御三家(麻布・桜蔭・女子学院他) / 新御三家(海城・駒東・鷗友学園他) / 渋渋 / 慶應中等部 / 広尾学園 / 都立小石川 など
■神奈川県
浅野 / 横浜共立 / 慶應普通部 / 洗足学園 / 鎌倉学園 / 逗子開成 / 山手学院 / 中央大学附属横浜 など
■千葉県
渋幕 / 市川 / 東邦大付属東邦 / 昭和学院秀英 / 芝浦工業大柏 / 専修大松戸 など
■埼玉県
栄東 / 開智 / 大宮開成 / 開智所沢 / 淑徳与野 / 浦和明の星女子 など
■その他地域
海陽 / 洛南高校附属 / 東大寺学園 / 西大和学園 / 大阪星光学院 / 同志社女子 / ラ・サール など
中学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会の特徴
当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
東大家庭教師友の会の料金
当会では、「入会金」「指導料」「交通費」「学習サポート費」以外のご料金は、一切ご請求しておりません。指導キャンセル料や教師交代費、解約金等は一切発生いたしませんので、ご安心ください。
ご入会時
体験授業料0円
ご入会金 22,000
体験授業は1ご家庭様につき1人のみ無料でご受講いただけます。2人以上受ける場合、1人につき2,420円(税込)の体験授業料が発生します。
月々のお支払い
交通費は教師が所持する定期区間を除きます。
口座振替でお支払いの場合、手数料385円(税込)が発生します。

東大家庭教師友の会「7つの0円」
ご利用の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
中学受験に強い家庭教師をお探しなら
あわせてチェック|日能研の関連記事