1. 日能研の学習力育成テストとは?

学習力育成テストは授業の復習テストです。
日能研に通室する生徒様が対象で4年生前期から始まります。
保護者様はテストの仕組みをちゃんと把握していますか?まずは概要を解説していきましょう。
①目的
目的は授業内容の理解度を測ることです。
あわせて得意不得意を確認する意味もあります。
②試験回数
・4年生・5年生:2週に1回。
・6年生前期:原則週1回(公開模試の開催週は除く)。
・6年生後期:2週に1回
③開催曜日・試験会場
・4年生・5年生:土曜日に開催
・6年生:日曜日に開催
※試験会場は各教室。開催曜日に都合が悪いときは振替受験の設定があります。
④受験科目
全学年 4科目(国語、算数、社会、理科)、または2科目(国語、算数)での受験ができます。
※志望校によって3科目受験の場合は個別に教室に相談しましょう。
⑤配点・試験時間
【4年生】
・国語・算数(150点満点、40分)
・社会・理科(100点満点、25分)
【5年生・6年生】
・国語・算数(150点満点、50分)
・社会・理科(100点満点、30分)
⑥科目ごとの配点
(1)国語・算数
「共通問題100点」と「基礎問題50点」あるいは「応用問題50点」の計150点で構成されます。
全学年、上位クラスは「共通問題」と「応用問題」を受験。
標準クラスは、「共通問題」と「基礎問題」を受験します。
(2)社会・理科
「共通問題70点」「応用問題30点」の計100点で構成されます。
全学年、クラスにかかわらず同じ問題を解きます。
2. 学習力育成テストの出題範囲と出題傾向、難易度について

学習力育成テストは範囲や傾向がきっちりと決められます。
これは授業内容の定着を確かめて、復習や次の学習機会に活かすためのテストだという大原則があるからです。
範囲や傾向が分かれば対策も自ずと見えます。
①出題範囲
【4年生】
・国語・算数:カリキュラム2回分
・理科・社会:カリキュラム1回分
【5年生】
・国語・算数:カリキュラム2回分
・理科・社会:カリキュラム2回分
【6年生前期】
・国語・算数・理科・社会:カリキュラム1回分(公開模試を挟むときは2回分)
【6年生後期】
・国語・算数・理科・社会:カリキュラム2回分(公開模試、実践テストを挟むため)
②出題傾向と難易度
授業で習った内容の確認が大半を占めます。
ただし共通問題の後半には、授業で扱わなかったテキストに掲載される問題も出題されることがあります。
また応用問題には、授業で習わない入試問題に類似した実力問題、記述式問題も出されます。
同様の復習テストは他の大手塾でも実施されますが、日能研の学習力育成テストの難易度は比較的易しめです。
3. クラスの昇降基準

生徒様の努力や頑張りが反映されるのは、やはりクラスの上がり下がりです。
特に保護者様は志望校合格に近づくためクラスアップを願ってやまないのが正直なところでしょう。
では、その基準はどういったものなのでしょうか?
①クラス替えの頻度・基準は?
クラス替えの頻度は以下の通りです。
・4年生・5年生:約2カ月に1度
・6年生:ほぼ毎月
クラス替えの基準は以下の通りです
・「学習力育成テスト」の共通問題の順位
・「全国公開模試」の順位
・学習力育成テストの基礎問題、応用問題の点数
②テスト後には毎回、席替えがあります!
日能研では合格力育成テストや全国公開模試などのテストを受けた後に毎回、成績順に教室での席順が変わります。
基本的には、最前列の真ん中がクラス1位の席で、その両隣が2位、3位。またその隣が4位、5位という仕組みで、以後、順々に列が後ろになっていきます。
これは日能研の伝統的な取り組みの一つ。
「テストごとに席順が変わるのはリアル過ぎる」と話される保護者様もいらっしゃいますが、あまり深刻には考え過ぎずに「今週はどの席かな?」くらいの気持ちで、
特に低学年のときは席替え程度に思って楽しみながらモチベーションを上げて前向きに取り組んでください。
4. 学習力育成テストの対策方法
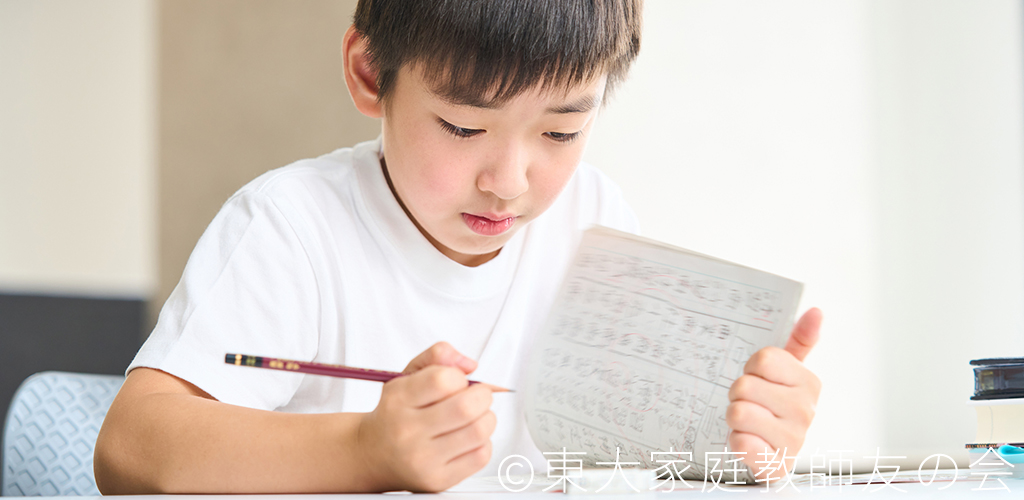
重要なポイントは、日能研のカリキュラムに合わせた学習サイクルを身に付けることにあります。
理想的な学習サイクルとはどのようなものなのでしょう?
ここからは、「理想の学習サイクル」を守りつつ、テストで結果を得る対策法を解説します。
①日能研での理想的な学習サイクルは?
塾には、その塾にあった学習のシステムやサイクルがあるものです。
日能研においては、学習力育成テストに合わせた理想的なサイクルを身に付けることが、ひいては中学受験の勉強を身に付けることにつながります。
その理想のサイクルは、
・授業
→授業で間違った問題の解き直し
→宿題教材『栄冠への道』を解く
→宿題の間違い直し(解き直し)
→学習力育成テスト
→テストの復習(間違いの解き直し)
になります。 日能研では予習は必要なく、解き直しに重きを置くほうが賢明です。
②科目を問わず、大切な勉強法は?
「解き方を丸暗記しない」こと。これにつきます。
学習力育成テストは復習テストですから、解き方を暗記すればある程度の点数を取ることはできます。
ですが、当然ながらそれでは本番の入試には通用しません。
学習は、あくまでも考え方を理解したうえで覚えていくことが大切になります。
③国語のおすすめ対策方法
(1)全学年共通の対策方法
漢字の読み書きは『計算と漢字』を用いて「トメ、ハネ、ハライ」に注意しながら完璧にしましょう 。書き損じが多いときは前学年の教材に戻ってやり直すことも有効です。
基礎問題を受験する生徒様は、基礎問題から解き進めましょう。基礎・応用合計で150点満点中100点が第一目標です。
応用問題を受験する生徒様は、共通問題から解き進めましょう。共通問題のラスト2問、応用問題は(1)だけ解くなど取捨選択をしながら解くことがおすすめです。目標点数は共通と応用合計で100~120点となります。
(2)4年生、5年生前半向け対策方法
授業で扱った文章と、宿題に出た『栄冠への道』の文章を音読し、内容を誰かに語ってみましょう。これは内容を「正しく理解できるようになる」「自分の言葉で正しく記述できるようになる」ためです。
また、テキストの本文、また問題文に線を引くこともおすすめです。これは「聞かれたことに正確に答える」練習です。
「正しいものを1つ選びましょう」「先頭の5字を抜き出しましょう」など多様な問いかけにも慣れていきましょう。
(3)5年生後半・6年生向け対策方法
授業で扱った文章と、宿題に出た『栄冠への道』の文章を黙読し、内容の要約を誰かに語ってみましょう。テスト対策のために、黙読で取り組むことが大切です。
他の読書も並行して行い、語彙力を増やしましょう。
④算数のおすすめ対策方法
(1)全学年共通の対策方法
計算問題は『計算と漢字』教材を用いて、時間を測りながら毎日取り組みましょう。10問を7分から10分間が目安です。1回で正解することを目標に取り組みましょう。
基礎問題を受験する生徒様は、基礎問題から解き進めましょう。基礎・応用合計で150点満点中100点が第一目標です。
応用問題を受験する生徒様は、共通問題から解き進めましょう。共通問題のラスト2問、応用問題は(1)だけ解くなど取捨選択をして解くことがおすすめです。目標点数は共通・応用合計で100~120点です。
(2)4年生向け対策方法
小数などの計算の単元は、確実に高得点を取ってジャンプアップしていきましょう。ここで弾みをつけて、算数そのものを得意科目にしましょう。
また、問われていることに確実正しく答える練習をしましょう。 「カメは何匹ですか?」との問題にツルの数を回答することのないように、普段から問題文にチェックをいれる癖をつけるといいでしょう。
授業と宿題で、間違った問題の解き方を見直して、テストに臨むことが大切です。
(3)5年生向け対策方法
分数、小数の四則混合計算の単元で、確実に高得点を取ってジャンプアップしていきましょう。
5年生は中学受験の単元の基礎部分をすべて学習する一年間です。ここで算数嫌いにならないように気を付けましょう。
授業と宿題で、間違った問題の解き方を見直して、テストに臨むことが大切です。
(4)6年生向け対策方法
まずは自分の得意不得意を理解したうえで授業に臨みましょう。5年生のときの単元の正答率を参考にして授業を受けましょう。
授業と宿題で間違った問題の解き方を見直してテストに臨みましょう。ただし、特訓授業や過去問演習もありますから効率よくすることが大切になります
テストの軸足は徐々に、学習力育成テストから全国公開模試へ移していきましょう。
⑤理科、社会のおすすめ対策方法
(1)4年生向け対策方法
まずは興味付けが第一です。あまり点数や結果にこだわらなくてよろしいかと思います。
授業の内容をしっかり理解できているかを『栄冠への道』で確かめましょう。
(2)5年生前半
授業が週1回となり、テスト範囲が2回分に広がります。
基本姿勢は4年生と変わりませんが、理科の生物や地学、社会の地理や歴史などの暗記分野はしっかりと見直したうえでテストに臨みましょう。
(3)5年生後半・6年生向け対策方法
いよいよ理解を深めて定着させる時期になります。
『栄冠への道』で考え方を整理して、『メモリーチック』で覚えるべきことを繰り返してテストに臨むリズムを身に付けます。
目標とする得点率は75%です。
5. 家庭でできる学習力育成テスト対策のサポートは?

先述の「学習サイクル」や「丸暗記しない勉強法」を身に付けるのは、小学生の生徒様だけでは難しいことです。
そのため、成績アップには保護者様の手助けが必ず大事になります。
ここでは、保護者様にできる学習のサポート内容を解説していきます。
①サポートは丁寧に。ときには助けも借りながら
生徒様へのサポートは主に
・授業の間違い直しの箇所の選定
・宿題の〇付け
・間違い直し問題のチェック
になります。
小学生ですから細かく丁寧にサポートすれば効果はあがります。
ですが、これらすべてをご家庭だけで解決するのは大変な場面もあり、また親子だからこその反抗もありえます。
そのようなときには日能研の教室に相談をしたり、あるいは家庭教師といった第三者に委ねることもあるでしょう。
②計算や漢字の習得は毎日のルーティーンが効果的!
学習力育成テストにかかわらず、本番の入試でも、大半の中学校では計算問題や漢字の書き取りが出題されます。
そこでおすすめなのは、毎朝30分間いっしょに『計算と漢字』という日能研の教材に取り組むというものです。
実践した生徒様は、明らかに単純な計算や書き取り問題の取りこぼしがなくなりました。
ご家庭ごとに事情もあるかと思いますが、特に
①決まった時間に取り組むこと
②生徒様にまかせっきりにせず確認に付き合うこと
の2つを抑えることが結果につながります。
6. テスト結果がおもわしくなかったときは、どう受け止めて次に活かせばいい?

大人も子どもも、誰にでも好き嫌いや得意、不得意はあります。
どれだけ成績優秀な生徒様でもテスト結果がいつも安定していることはまずありません。
テスト結果は得意不得意を表してくれている鏡のようなものです。
ここではそれを上手に利用する方法を解き明かしていきます。
間違った問題の正答率を『本科テキスト』に残しておく!
4教科の間違った問題の正答率を『本科テキスト』の類題に書き写しておくことをおすすめします。
その理由は、生徒様はもちろん、保護者様も一目で得意不得意、これから力を入れるべき単元が分かるからです。
日能研では学年が上がるごとに同じ単元を難度を少しずつ上げながら繰り返し繰り返し学習するため、次回に同じ単元を学習する際に、その正答率を参考にして授業に臨むことができます。
これは本科教室の復習をする春、夏、冬の期間講習でもいえることで、生徒様の苦手な問題を知ってから授業を受けるとスムーズな習得につながります。
生徒様は「苦手だなあ」と嫌な気持ちになるのではなく、「また一から頑張ろう、得意にしよう!」という気持ちで臨むことが大切です。
この場合は、後述するクラスごとの復習すべき「%」も参考にしましょう。
▼日能研についていけない際の対策の詳細は、以下ページも併せてご覧ください。
7. 学習力育成テスト後のおすすめ復習方法

生徒様は、授業がどんどん新しい単元へと進むために次週の勉強をしなければなりません。
そのため学年が上がるにつれて、学習力育成テスト後の復習が十分にできないことも少なくはないでしょう。
しかしながら苦手単元の克服には、テスト後の復習はやはり欠かすことのできないものです。
そんなときの復習方法はこちらです!
①正答率で復習する問題を絞る!
テスト後の復習には正答率表を利用することをおすすめします。
これは復習する問題を絞るという方法になります。
具体的にどのように絞るのかは、現在の所属クラスに応じて正答率表の「%」を参考に決めればいいでしょう。
一例として、
・上位クラス:正答率20%以上で間違っている問題
・中位クラス:正答率40%以上で間違っている問題
・下位クラス:正答率60%以上で間違っている問題
このような形で問題数を絞っていきましょう。
②4・5年生はテスト後の復習を国語・算数だけにするのも一手!
4・5年生のあいだは復習する教科を国語、算数の2科目にして、見直す問題数を絞るのも効果的な方法です。
その理由は、
・入試の主要教科である国語、算数を優先する
・まずは「学習サイクル」の確立が先決であり、テスト後の復習を習慣づける
ことが大切だからです。
またこれにより、勉強を嫌いにならない程度に量を抑えておくこともできます。
最後に
今回は「日能研学習力育成テスト」の概要と対策のポイント、そして教科別の学習方法について解説しました。
毎回のテストでは「良ければ喜び」「悪ければ一憂せず」に生徒様と一緒に取り組んでいきましょう。
テスト結果には「あんなに努力をしたのに」と残念に思うことはつきものです。
そこは感情的にならず継続を心がけてください。
それでも成績の伸びがみられないとき、生徒様とのコミュニケーションが取りづらくなたっときなどは、「日能研の教室に早めに相談をする」また「勉強を見てくれる第三者に任せる」ことも一つの手です。
▼当会では、日能研生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
お問合せ・体験授業はこちら
日能研の関連記事
東大家庭教師友の会をもっと知る




