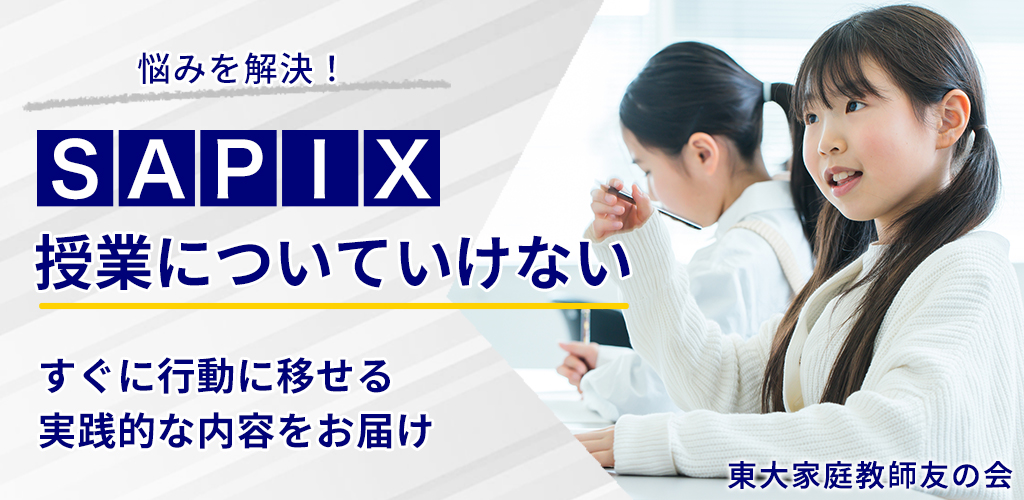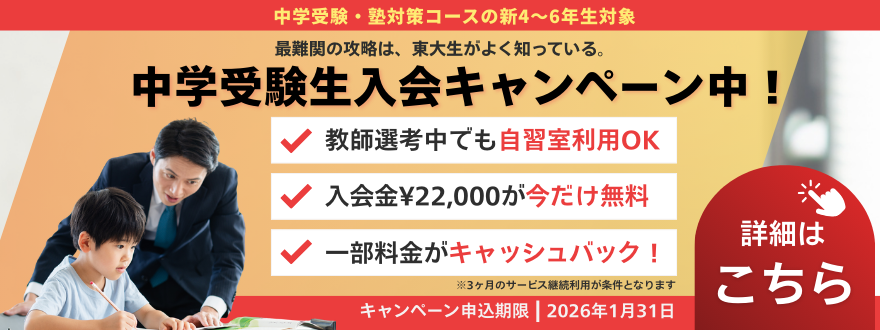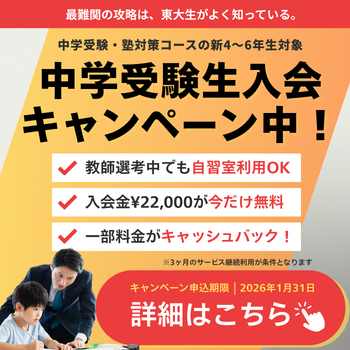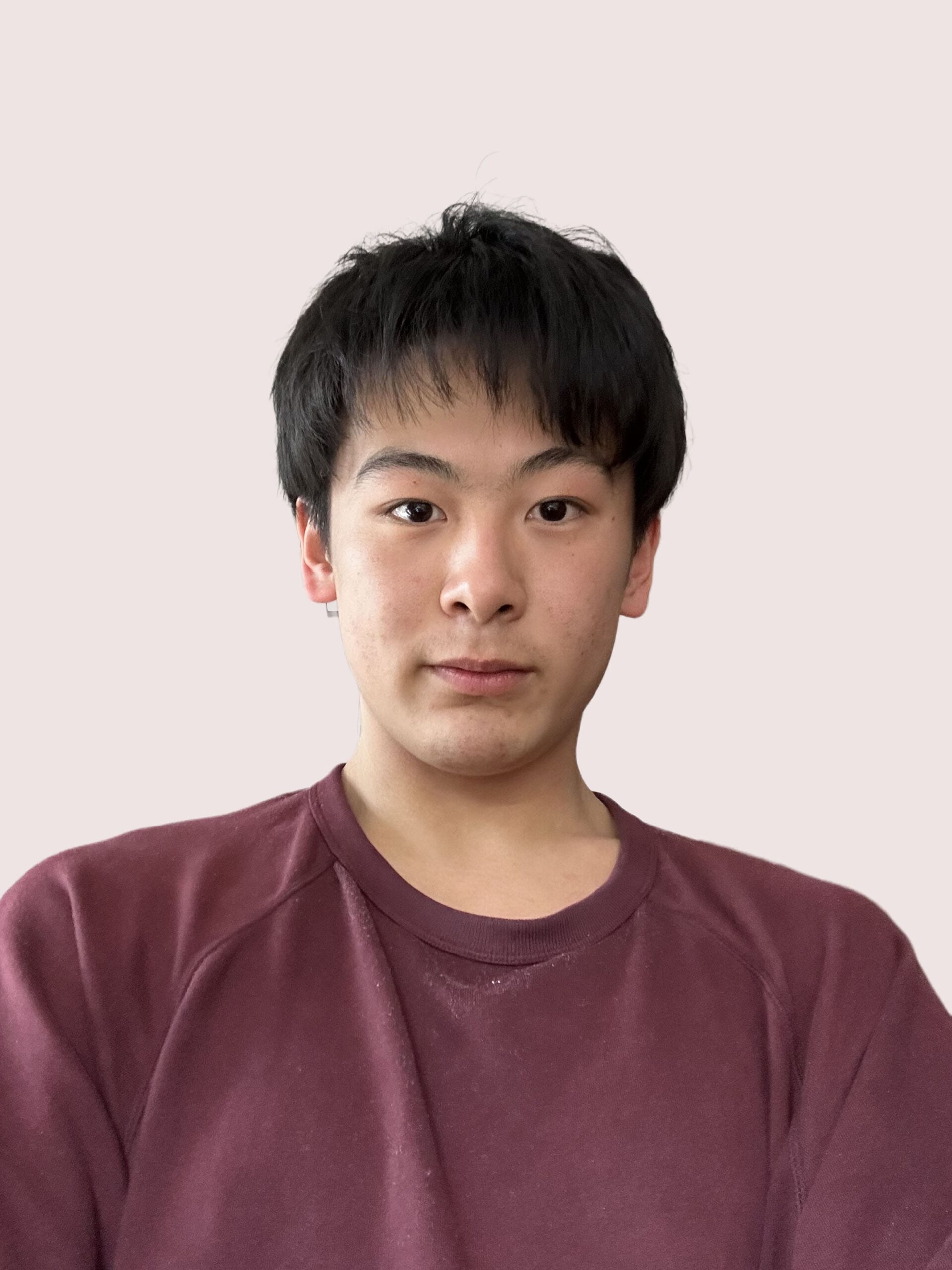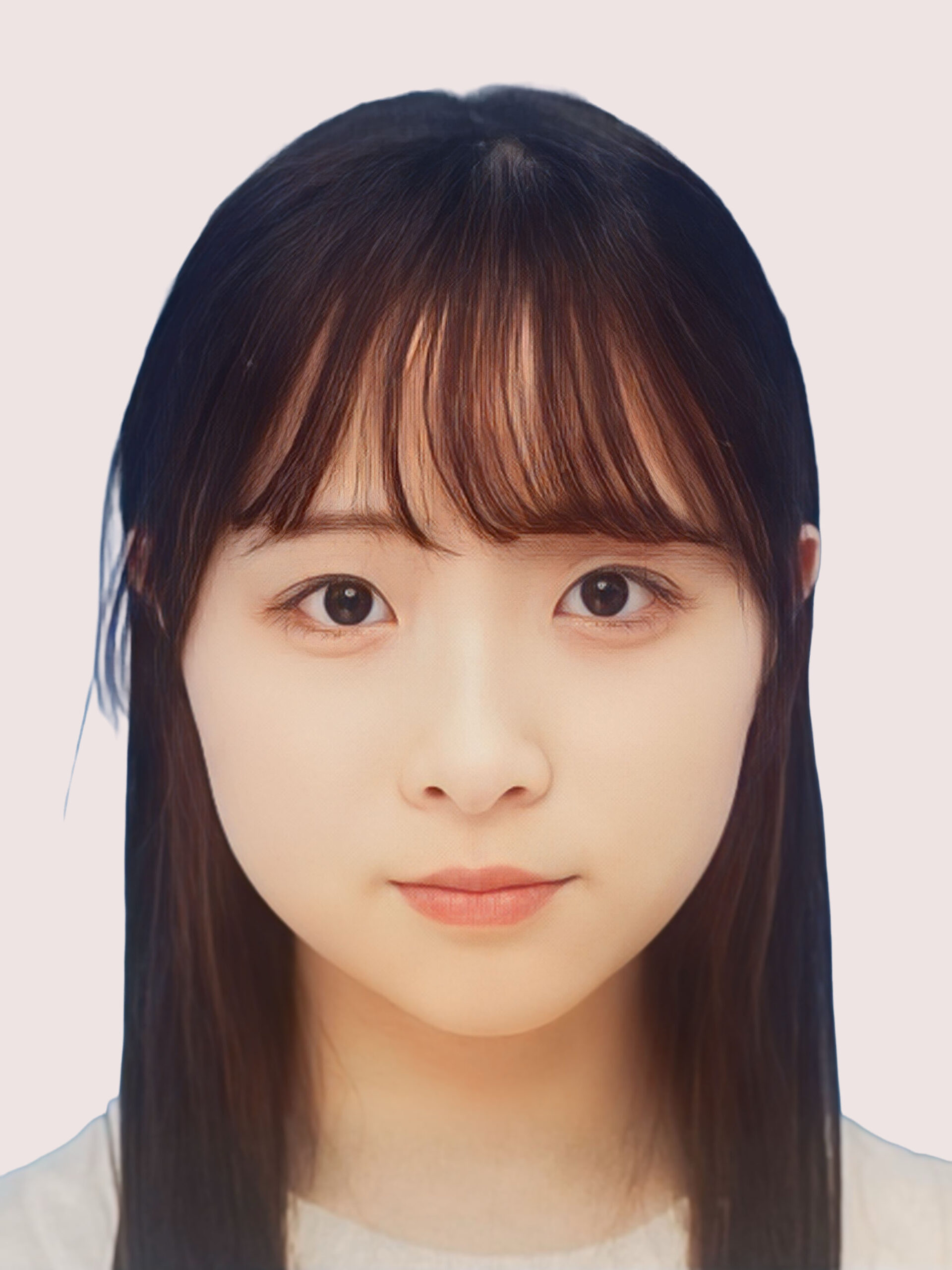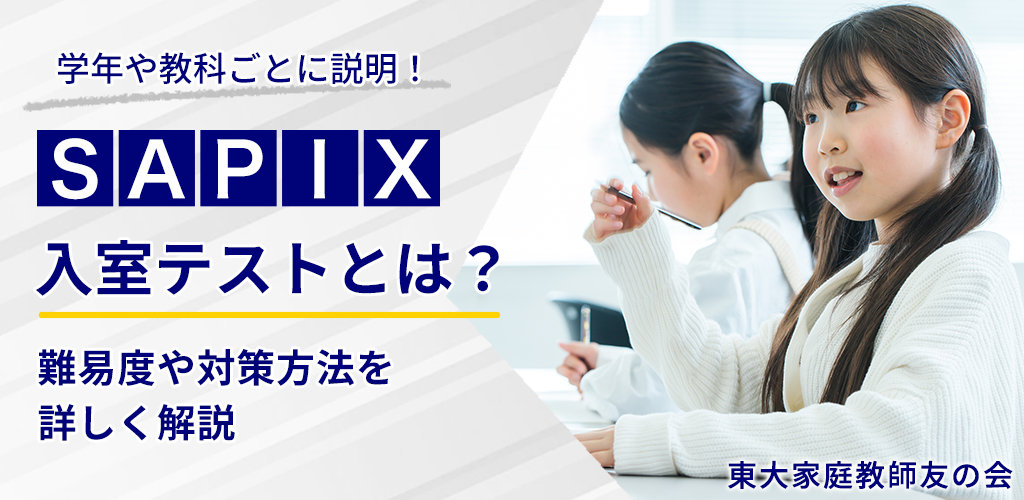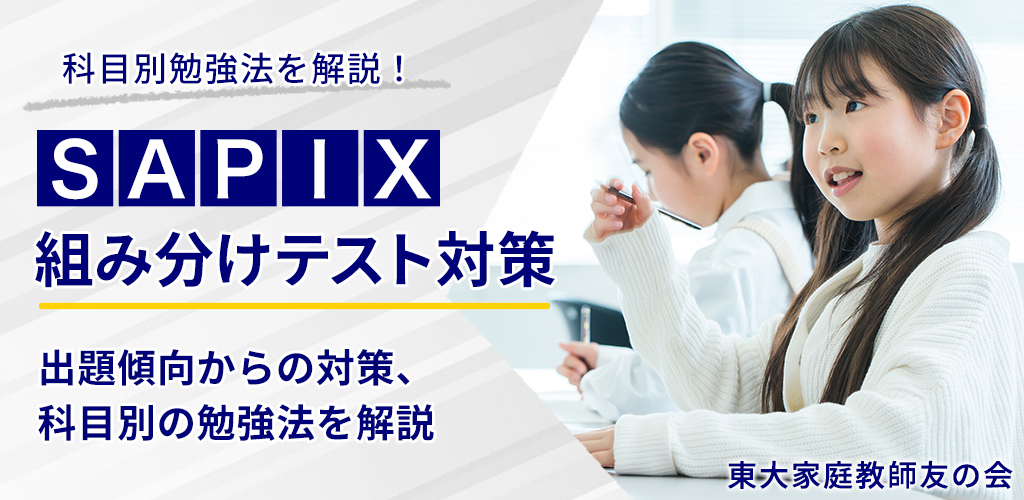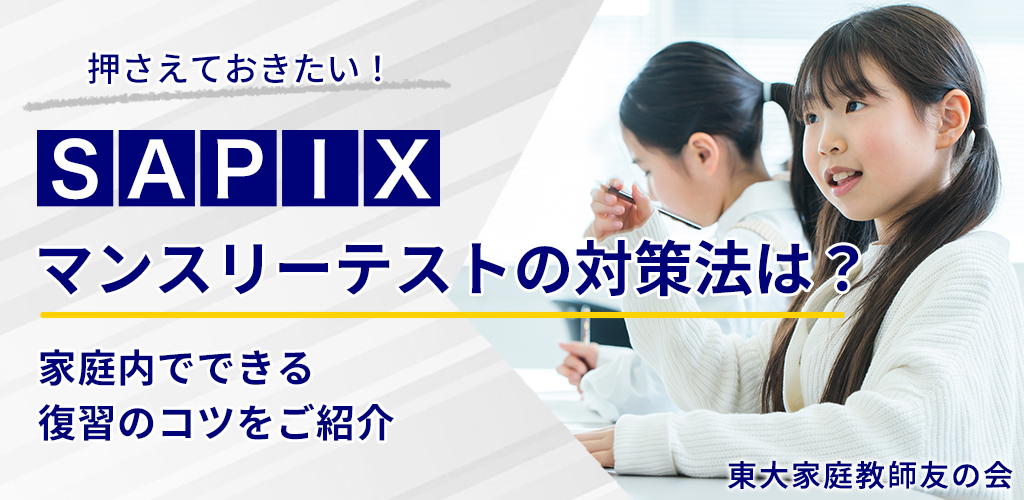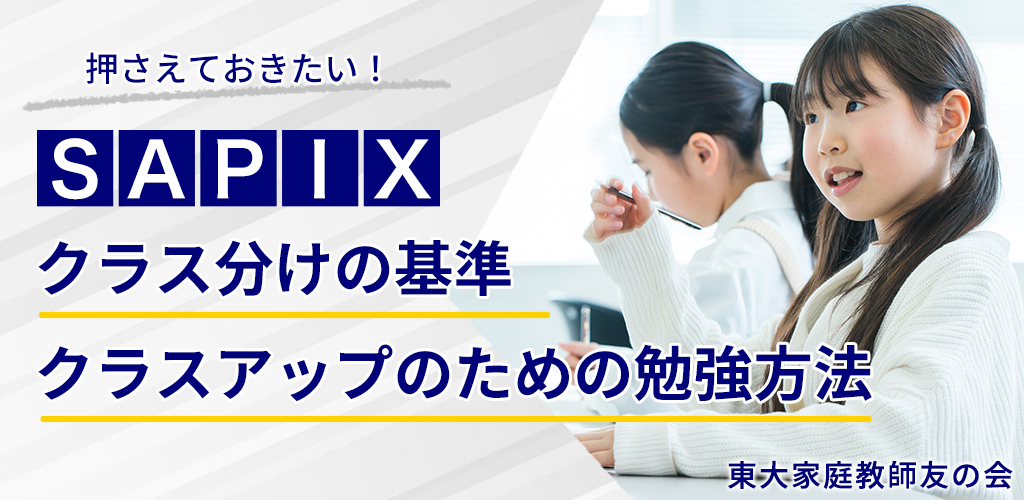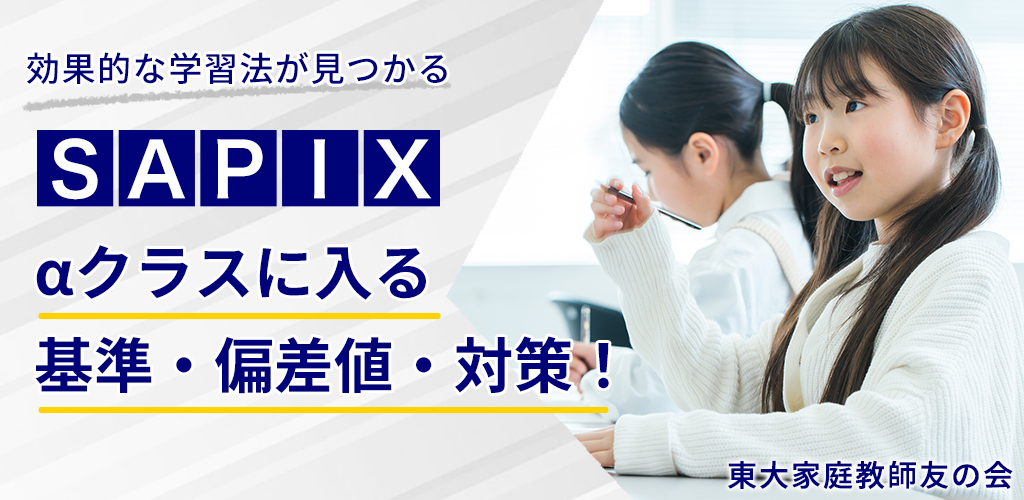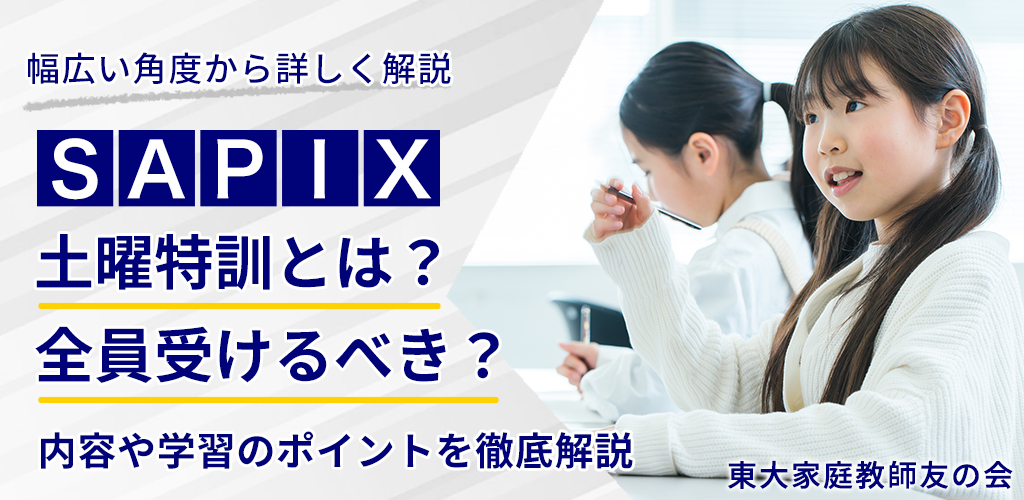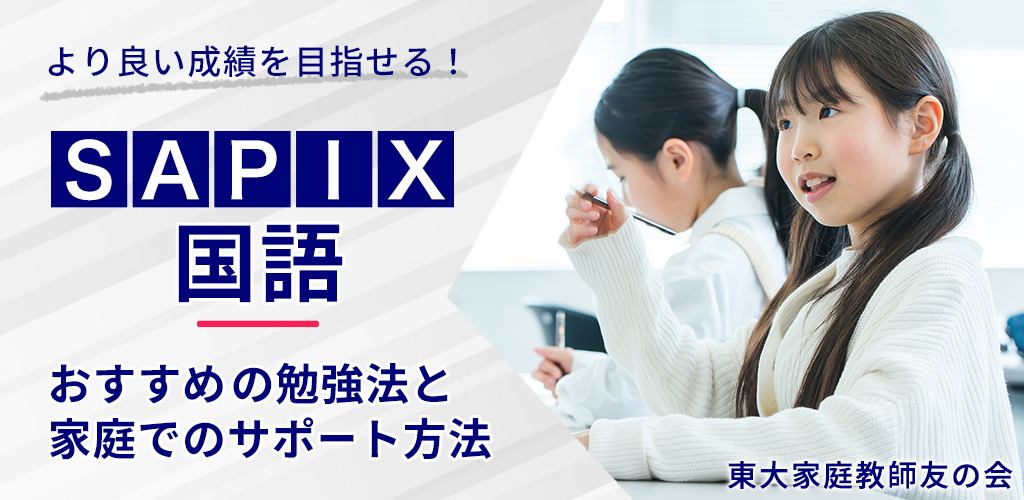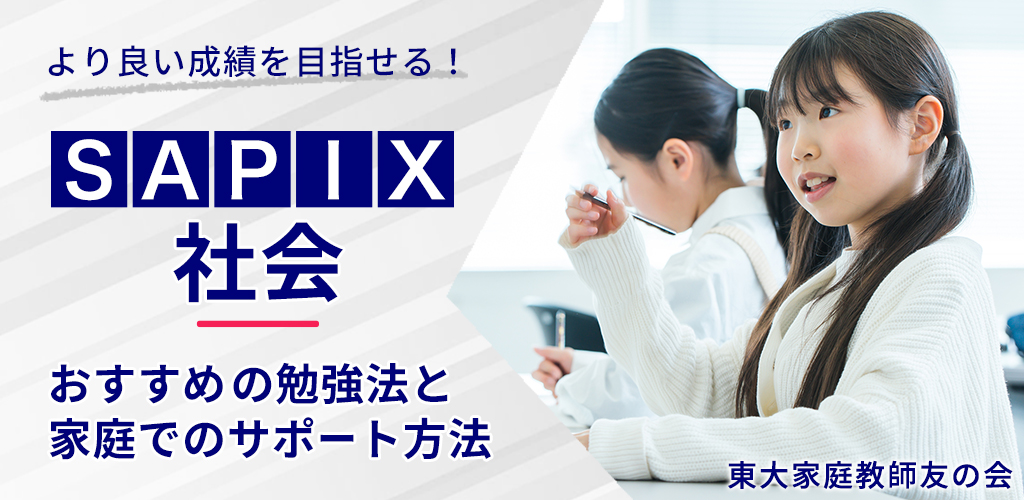1. SAPIX(サピックス)についていけない悩みは多い?授業進度やクラス落ちの現実

SAPIX(サピックス)に通う生徒様の中には、「授業についていけない」と感じる方が少なくありません。
SAPIX(サピックス)は学力別にクラスが細分化されていますが、カリキュラムや教材は全クラス共通で、御三家など最上位校への合格を目的に作成されています。
教材自体が難しいので、多くの生徒様が「難しい、ついていけない」と感じるのも当然だと言えます。
さらに、SAPIX(サピックス)の授業進度は非常に速く、宿題の量も多いため、カリキュラムについていくのが難しく感じる生徒様が多いのが現状です。
また、マンスリーテストや組分けテスト、6年生ではサピックスオープンなど、頻繁に実施されるテストの難易度も高く、これがプレッシャーとなって学習意欲に影響を与えることもあります。
こうした背景から、「SAPIX(サピックス)の授業についていけない」といった声は、多くのご家庭から寄せられることが珍しくないのです。
2. 【学年別】SAPIX(サピックス)についていけない原因|4年・5年の壁とは

SAPIX(サピックス)の授業に「ついていけない」と生徒様が感じる要因は多岐にわたります。中学受験にチャレンジするご家庭の多くが、学習についてお悩みを抱えているものです。
特にSAPIX(サピックス)の教材は非常にレベルが高いため、順調に進んでいるご家庭の方が少ないのではないかと思えるほど、お悩みの声をよく耳にします。
ここでは、実際に私がSAPIX(サピックス)生の保護者様からいただいたご相談内容をもとに、「ついていけない原因」を学年別に紹介します。
|
①【全学年共通】進度の速さと宿題量・テストの難易度 |
①【全学年共通】進度の速さと宿題量・テストの難易度
(1)授業進度の速さ
SAPIX(サピックス)に通う生徒様が授業についていけなくなる主な原因の一つは、授業進度の速さです。
SAPIX(サピックス)のカリキュラムは、同じ単元を別々のタイミングで何度も学習する「スパイラル方式」が採用されています。
短期間で単元やテーマが次々に切り替わるため「スピードが速い」と感じる生徒様が多いようです。
(2)宿題の量や種類の多さ
宿題の量や種類の多さも、ついていけなくなる原因の一つです。
ハイスピードで展開した授業の内容に基づいた宿題をコンスタントにこなす必要があり、時間管理が難しいと感じる生徒様も多いです。
(3)定期的に行われるテスト
SAPIX(サピックス)では定期的にテストが行われます。
最難関中まで含めた志望校判定をおこなうため、必然的に問題の難易度も高くなります。
その結果「テストの点数が思うように取れなかった」とショックを受け、ついていけないと感じる生徒様も少なくありません。
②【低学年】学習習慣と基礎力不足(1〜3年生)
(1)学習習慣が定着していない
低学年の生徒様がSAPIX(サピックス)についていけなくなる主な原因は、学習習慣そのものが定着していないことです。
低学年では、机に向かって勉強をすること自体がまだ訓練期間であり、宿題や復習を自分で計画的に進めることが難しいことも多いです。
(2)基礎学力が不足している
基礎学力の不足が課題となっているケースもあります。
低学年では、四則演算など基本的な内容を習ったばかりで、完全に定着していないことがあります。
そのため、宿題に時間がかかり、集中力が切れてしまって「もう嫌だ」と言い出してしまう生徒様もいます。
低学年のうちは、なるべく保護者様の方も勉強に付き合い、学ぶ楽しさや自分の考えを言葉にするおもしろさを実感させてあげることをおすすめします。
③【高学年】難易度急上昇とクラス変動のプレッシャー(4〜6年生)
(1)学習内容が高度になる
高学年になると、学習内容が高度化します。
難易度の高い問題や複雑な概念を理解する必要があり、これが授業についていけなくなる原因の一つとなります。
特に国語が苦手な生徒様の場合、高学年になって中高生向けの文章に触れるようになってからは、語彙の面で苦戦する傾向が見られます。
(2)クラスのアップダウン・受験へのプレッシャーが大きくなる
高学年になると成績への意識が強くなり、クラスのアップダウンへのプレッシャーも大きくなります。
テストの成績によってクラスが変動するため、常に高い成績を維持しようとするあまり、プレッシャーを感じてしまう生徒様もいます。
中学受験が迫る中、受験に向けた勉強と学校生活の両立が求められ、真面目な生徒様にとっては精神的な負担となるケースが見られます。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
3. 【学年別】SAPIX(サピックス)についていくための対策と勉強法
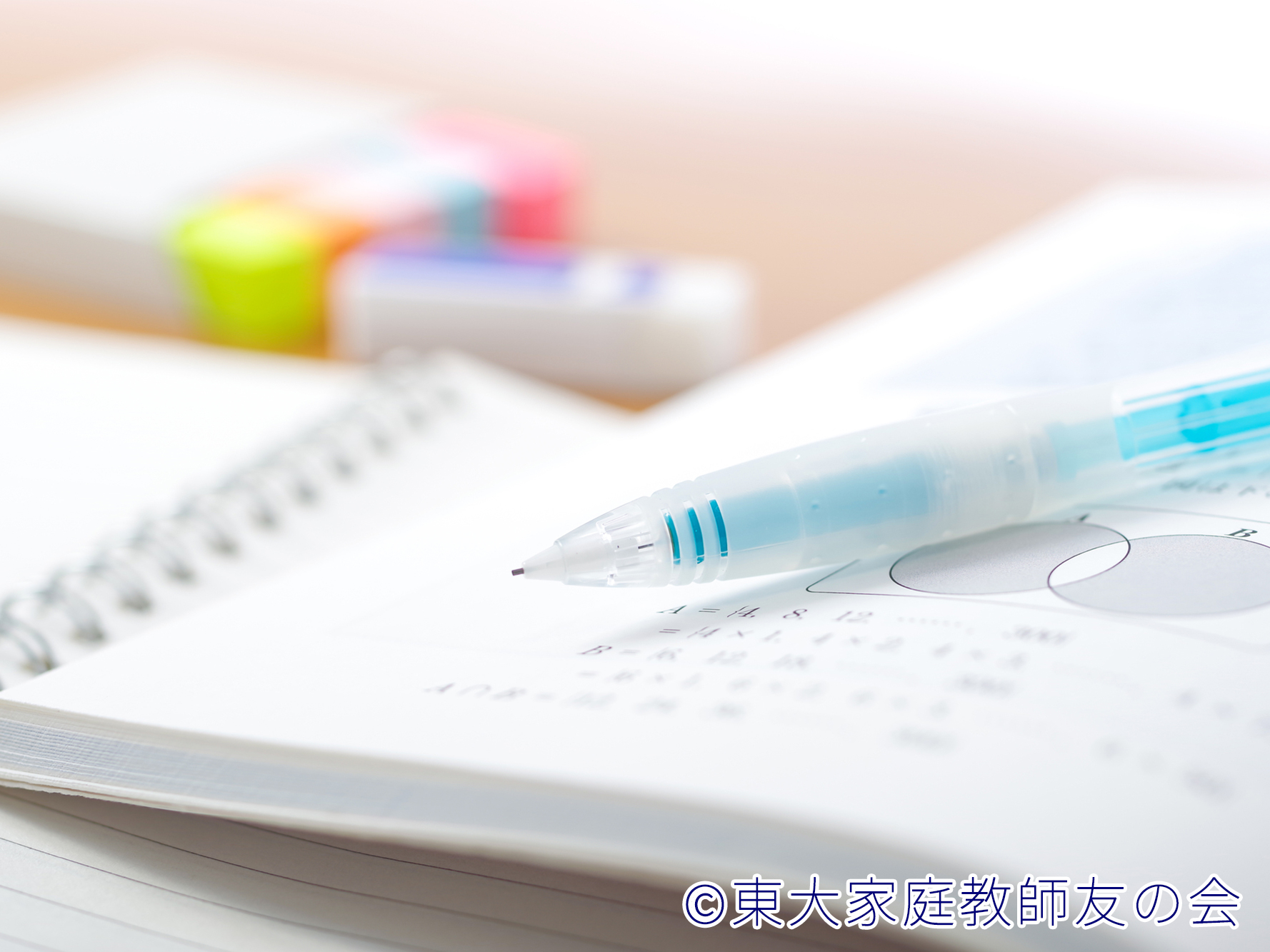
SAPIX(サピックス)の授業についていけない、しんどいと感じる生徒様は少なくありません。その姿を見ている保護者様も「このままで大丈夫だろうか」と心配になりますよね。
しかし、できればSAPIX(サピックス)で最後まで戦い抜きたいというのが、生徒様・保護者様双方の本音ではないでしょうか。
ここでは、SAPIX(サピックス)の授業についていくために参考にしていただきたい学習のコツを紹介します。
|
①【全学年共通】スパイラル方式を活かした復習中心の学習 |
①【全学年共通】スパイラル方式を活かした復習中心の学習
SAPIX(サピックス)のカリキュラムは「復習中心の学習法」を徹底しています。このシステムに従って、正しい復習をおこなうことがまず第一のアプローチとなります。
また、SAPIX(サピックス)のカリキュラムはスパイラル方式を採用しており、同じ単元を複数回にわたって繰り返し学習できる点がメリットです。
しかし、繰り返すたびに難易度はどんどん上がっていきます。そのため、一回一回の学習内容をその都度身につけておかないと、ついていくのが辛いと感じるようになってしまいます。
週間学習スケジュールに復習の時間を作り、基礎をしっかり固めながら学力を積み上げていきましょう。
②【低学年】学習リズムの定着と言語化能力の育成
(1)規則正しい学習のリズムを定着させる
小学校低学年の生徒様は、まず規則正しい学習のリズムを定着させることが重要です。「毎日決まった時間に机に向かって勉強するのが当たり前」という環境作りを意識しましょう。
特に低学年では、親子のコミュニケーションも取れるリビング学習を取り入れるのがおすすめです。
▼リビング学習については、以下ページをご覧ください
(2)「どうしてそう思ったか」を言語化する能力をつける
勉強する際には、単にマルかバツかをつけるだけでなく、「どうしてそう思ったか」を生徒様から説明する形で進めると、論理的思考力や言語化能力を鍛えられます。
何となくこなしていくのではなく「理解できないまま放置するのは落ち着かない」という感覚を養うことが重要です。初めのうちは、生徒様自身で考えを整理したり、答えを導き出したりするのが難しい場面があるかもしれません。
しかし、保護者様が常に先回りして解決してしまうのは避け、できるだけ生徒様自身が考え、理解する経験を積むことを大切にしましょう。
低学年の間は教材自体の難易度はまだそこまで高くはありません。
字を丁寧に書く、計算を素早く正確におこなう、自分の考えを言葉で説明するなど、今後の学習のための土台をこの時期にしっかりと固めておきましょう。
③【高学年】4年・5年からの立て直し|科目別対策と優先順位
(1)授業の復習を丁寧に行う
4年生以上の生徒様は、とにかく授業の復習を丁寧におこない、基本的な内容を身につけることが最優先です。
デイリーチェックで9割以上得点できる状態を目指しましょう。
(2)国語の対策方法
国語の対策としては、まずAテキスト(および漢字の要・言葉ナビ)の漢字や語句、文法を繰り返し練習して覚えましょう。
「読解教室」や「読解力チェック」に丁寧に取り組み、文章の正しい読み方の確認をすることも必須です。
(3)算数の対策方法
算数では、まず基礎力トレーニングでしっかり正解できる状態を目指します。デイリーサポートのA問題、B問題にも対応できるように復習を進めていきましょう。
デイリーサポートはもともと表裏で2回取り組めるように作られていますが、コピーしてさらに演習回数を増やすご家庭も見られます。
マンスリーテストであれば基礎力トレーニングやデイリーサポートからの出題も多いため、ここを完璧に押さえるだけでもそれなりの点数を取ることが期待できます。
正答率の低い問題については一度目をつぶり、正答率7割以上の問題を確実に正解できる状態を目指しましょう。
これがクリアできるようになるころには、生徒様の「ついていけない」という感覚も軽減されている可能性が高いです。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
▼SAPIX(サピックス)の科目ごとのおすすめ勉強方法については、以下ページをご覧ください
「SAPIX(サピックス)国語のおすすめ勉強法!家庭内でのサポート方法も解説!」
「SAPIX(サピックス)算数のおすすめ勉強法!家庭内でのサポート方法も解説!」
4. ご家庭で実践!SAPIX(サピックス)生への学習・生活のサポート方法

SAPIX(サピックス)での学びを支えるには、ご家庭でのサポートが欠かせません。「できることがあるなら何でもしてあげたい」「子どもの負担を少しでも軽くしてあげたい」と考える保護者様の方は多いでしょう。
実際、SAPIX(サピックス)の学習を保護者様の協力なしに生徒様自身の力だけで続けていくのはかなり難しいと言えます。
ここでは、ご家庭での学習面・生活面のサポート方法についてご紹介します。
①学習面のサポート|スケジュール管理と親の関わり方
(1)全学年共通:スケジュール管理
SAPIX(サピックス)の授業やその他の習い事のスケジュールを整理し、家庭学習を「いつ・何を・どこまで」やるかまでを具体的に決め、可視化しましょう。壁掛けカレンダーの形式で掲示する、Excelやスプレッドシートで作成して印刷するなど、生徒様自身がすぐ確認できる状態にするのがおすすめです。
また、学習に前向きに取り組むためには、精神的な支えも大切です。
以下の点を意識して、生徒様が自信を持ち続けられる環境を作りましょう。
・小さな成功にもプラスの声掛けをする
・志望校について魅力や入学後の展望を話し合う
・保護者様自身が努力して苦難を乗り越えた体験を話す
(2)低学年(1~3年生):学ぶ楽しさを育む
低学年の生徒様には、「学ぶことが楽しい」と感じられる経験を積ませることが最優先です。
家庭では、以下のようなサポートを意識してみてください。
・疑問を持ったときに、すぐに答えを与えるのではなく、一緒に考える姿勢を見せる
・「どうしてそう考えたの?」「どんなふうに答えを導いたの?」といった問いかけを通じて、思考のプロセスを言語化する力を育む
・実際に見て触れるような「リアルな体験」(例:植物観察、旅行など)をたくさん取り入れる
こうした学びの積み重ねによって、自己肯定感が高まり、自ら考え、表現する力も養われていきます。
SAPIX(サピックス)は難関中学への合格を目指す塾ですが、決して「がり勉」を推奨しているわけではありません。低学年だからこそできる、のびのびとした学びの機会をたくさんつくってあげましょう。
(3)高学年(4~6年生):学習環境と教材管理
高学年になると学習量が大幅に増えます。家庭では、集中して取り組める学習環境を整えることが大切です。
具体的には、次のようなサポートが効果的です。
・教材やプリントは教科別・単元別にファイリングして整理する
・よく使う教材はコピーしてストックしておく
・文房具や計算用紙など、必要なものをすぐ使えるように準備しておく
また、生徒様によっては反抗期に差し掛かり、親の干渉を嫌がる子も増えてきます。表面上は反抗的に見えても、内心では感謝していることがほとんどです。
生徒様から苛立ちをぶつけられて思わず感情的になってしまうこともあるかもしれませんが、ここはグッとこらえて、合格という目標に向けて、マネージャーのような立場で見守る姿勢を心がけましょう。
②生活面のサポート|睡眠と体調管理の重要性
体調管理は日頃から意識されているご家庭が多いと思いますが、特に「睡眠」には注意を払っていただきたいです。高学年になると学習量が増え、なかには宿題をこなすために睡眠時間を削ってしまう生徒様もいます。また、勉強が終わったあとに趣味の時間を楽しみたくて、つい夜更かし気味になってしまうケースも見られます。
睡眠不足は脳や身体の成長にさまざまな悪影響を及ぼします。学習効率の低下にもつながりかねません。小学生らしい十分な睡眠時間が確保できているか、ご家庭でもぜひ気を配ってあげてください。
5. SAPIX(サピックス)についていけない時は転塾?家庭教師と併用?判断基準を解説

中学受験に向けて頑張っていても、「このままではついていけない」「受験そのものを諦めるしかないかも…」と、追い詰められるご家庭も少なくありません。
そんなとき、転塾するか、家庭教師や個別指導塾を併用するかで悩まれる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、転塾・併用それぞれのメリットや判断のポイントを整理し、どのようなケースに向いているのかを解説します。
|
①【比較】転塾・併用のメリット・デメリットまとめ |
①【比較】転塾・併用のメリット・デメリットまとめ
| 転塾 | 併用(家庭教師・個別指導塾) | |
| メリット |
・環境を変えてリフレッシュできる ・生徒様の学力や性格に合った塾で再スタートできる |
・通い慣れた塾を継続しながら学習を補える |
| デメリット |
・環境の変化によるストレスを感じやすい |
・時間や費用の負担が増える |
| 向いているケース |
・塾のペースや指導方針が根本的に合わない場合 |
・特定の科目や単元に不安がある場合 |
②転塾が向いているケース|成績低迷や本人の意志
以下のような場合には、思い切って転塾を検討することも選択肢のひとつです。
(1)成績が長期間にわたって低迷している場合
偏差値40未満がずっと続いている場合は、SAPIX(サピックス)の学習ペースや難易度が生徒様に合っていない可能性があります。この場合、生徒様が苦しい思いをするだけでなく、志望校判定などでも正確なデータを出せないかもしれません。
SAPIX(サピックス)の偏差値は、受験者層のレベルが高い分、非常に辛口で出ます。偏差値40以下の状態だと、他の受験者データが少なく正確な判定ができなくなってしまうのです。
(2)生徒様本人が「辞めたい」と繰り返し訴える場合
生徒様自身が「もう無理だ」「ついていけない」と強く感じ、何度も「辞めたい」と訴えてくるような場合、無理に続けることが逆効果になることもあります。
SAPIX(サピックス)に通う目的は、あくまで中学受験を乗り越えることにあります。通っている塾がSAPIX(サピックス)であるかどうかは、本質的な問題ではないはずです。
また、人間関係の問題から「辞めたい」と繰り返す場合も、転塾を視野に入れてよいでしょう。悩みを抱えたままSAPIX(サピックス)に通っていても、十分な学習効果が得られにくくなってしまいます。
ただし、学力面で特に問題がない場合は、SAPIX(サピックス)内での別校舎への移動を検討するのもひとつの方法です。
生徒様が前向きに学習に取り組める環境を整えることが最も大切です。
▼中学受験塾の各詳細については、以下ページも併せてご覧ください。
「【中学受験】SAPIXってどんな塾?評判・口コミ、費用等を解説!」
「【中学受験】日能研ってどんな塾?評判・口コミ、費用等を解説!」
「【中学受験】早稲田アカデミーってどんな塾?評判・口コミ、費用等を解説!」
「【中学受験】四谷大塚ってどんな塾?評判・口コミ、費用等を解説!」
「【中学受験】グノーブルってどんな塾?評判・口コミ、費用等を解説!」
「【中学受験】enaってどんな塾?評判・口コミ、費用等を解説!」
③家庭教師や個別指導塾との併用が向いているケース|SAPIX(サピックス)残留で成績アップ
「SAPIX(サピックス)は続けたいけれど、このままでは厳しいかも…」と感じている場合には、併用という選択肢も有効です。
(1)SAPIX(サピックス)の進度に合わせながら、補強が必要な場合
SAPIX(サピックス)のカリキュラムに沿って学びながら、特定の科目や単元だけ補いたい場合には、家庭教師や個別指導塾の併用が効果的です。
家庭教師や個別指導塾では、苦手分野を重点的に指導してもらえるため、SAPIX(サピックス)の授業で理解しきれなかった部分をしっかりと補完できます。
(2) 集団授業ではフォローしきれない部分を個別にサポートしたい場合
SAPIX(サピックス)の集団授業では、全員が同じペースで進んでいくため、個々の進捗に合わせてフォローすることが難しい場合があります。
家庭教師や個別指導塾を併用することで、生徒様一人ひとりの理解度に応じた指導が受けられます。特に、テスト前などに集中的に対策をしたい場合には、効果を実感しやすいでしょう。
(3)学習ペースを自分で調整したい場合
SAPIX(サピックス)では、全体のペースに合わせて授業を進めるため、ペースが合わないと感じることがあります。家庭教師や個別指導塾では、より自分のペースに合わせた指導が受けられるため、学習の進行を自分で調整できます。「苦手な部分をしっかりと習得してから次に進みたい」というお子さまには特におすすめです。
![]() 体験授業を申し込む
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
④東大家庭教師友の会でできるSAPIX(サピックス)生へのサポート
SAPIX(サピックス)の学習内容は高度で進度も速いため、「授業についていけない」「家庭でのフォローが難しい」とお悩みのご家庭も少なくありません。
東大家庭教師友の会では、SAPIX(サピックス)に通う生徒様一人ひとりに寄り添い、学習の悩みに応じたサポートを提供しています。
(1)SAPIX(サピックス)出身・中学受験経験者による実践的なサポート
当会には、SAPIX(サピックス)出身で中学受験を経験し、難関大学に進学した教師が2,000名以上在籍しています。SAPIX(サピックス)ならではの勉強法や宿題の進め方、マンスリー・組分けテストの対策法など、実体験に基づいたアドバイスが可能です。
「自分もSAPIX(サピックス)で頑張っていたからこそ、生徒様の気持ちがわかる」そんな教師が、一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧に指導を行います。
(2)SAPIX(サピックス)のカリキュラムに即した学習フォロー
当会の大きな強みは、SAPIX(サピックス)の授業内容・宿題・テストに完全対応できる点です。
-
・宿題の効率的な進め方
-
・苦手単元のピンポイント解説
-
・マンスリー/組分けテストでの得点力アップ
- ・塾でわからなかったところの質問
-
・授業についていけなくなったときの立て直し
-
といったように、SAPIX(サピックス)のカリキュラムに即したフォローを行い、生徒様の成績アップ・クラスアップを実現します。
(3)中学受験までを見据えた長期的な学習設計
SAPIX(サピックス)の学習だけでなく、中学受験合格までを見据えた総合的な学習サポートが可能です。過去問演習の開始時期や取り組み方の調整、志望校対策の優先順位づけなど、生徒様一人ひとりに最適な学習計画を立てていきます。
学年が上がるごとに難易度が増していくSAPIX(サピックス)のカリキュラムにも、自信と安心をもって取り組めるよう、丁寧にサポートします。
ご希望があれば、無料体験授業も可能ですので、SAPIX(サピックス)でのお悩みがある方はお気軽にご相談ください。
まとめ|SAPIX(サピックス)についていけないときは状況に合ったサポートや学習方法を取り入れよう
SAPIX(サピックス)についていけないと感じる生徒様や保護者様は少なくありません。しかし、生徒様の年齢や状況に合ったサポートや学習方法を取り入れることで、多くのケースは改善が可能です。大切なのは、焦らず粘り強くサポートすることです。
必要に応じて家庭教師や個別指導塾を併用したり、場合によっては転塾を検討することも前向きな選択肢です。
中学受験は長い道のりですが、適切なサポートがあれば、一歩ずつ着実に前に進めます。
▼当会では、SAPIX(サピックス)生への指導に特化した家庭教師をご紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
中学受験塾対策ができる家庭教師をご紹介
SAPIX・日能研・早稲田アカデミー・四谷大塚などの通塾経験や、通塾生の指導経験がある教師が在籍しています。
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
小学生の生徒様の声
中学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会の特徴
当会には、東大生約9,700名、早稲田大学生約8,500名、慶應大生約8,000名をはじめ、現役難関大生が在籍しています。
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
ご利用の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
中学受験に強い家庭教師をお探しなら
あわせてチェック|SAPIX(サピックス)の関連記事
東大家庭教師友の会をもっと知る